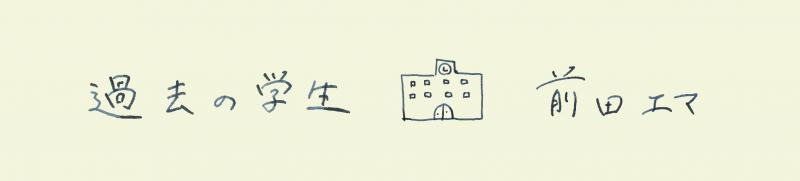松本健一先生に聞く、『海岸線の歴史』
2018.05.07更新
2009年6月に小社から刊行した『海岸線の歴史』。日本人の生活と精神性の変容を、海岸線の変化から解き明かし、日本の歴史観に新たな視点をもたらした一冊としてご好評をいただきました。今回の「本のこぼれ話」では、筆者の松本健一先生に執筆の動機などを語っていただきます。
語られなかった「海岸線」の歴史
―― 『海岸線の歴史』、発売以来たくさんの読者からご好評をいただいています。朝日、読売、日経、週刊文春などにも取り上げられ、NHKの週刊ブックレビューでもご紹介いただくなど、主要なメディアの多くに書評が載りました。
松本 そうですか。それは良かった。
―― そもそも松本先生が、なぜ「海岸線の歴史」について書こうと思われたのか、その執筆の動機について教えていただけますか。
松本 日本は「海岸線」の異常に長い、世界有数の国です。国土面積でいえば日本の25倍近いアメリカの1.5倍、同じく26倍の中国の2倍以上にも達する海岸線を持っています。それにも関わらず「海岸線の歴史」、つまり人間と海が接触する場所の変化を書いた本はこれまでまったくなかった。なければ自分で書くしかない。調べるうちに次々に新しい発見があり、最初の構想から10年以上かかりましたが、ようやく発刊することができました。
直接的な動機は、1998年に『開国・維新』(中央公論社)という本を書いたときのことに起因します。1853年のペリー来航以来、日本がどう開国し、国内の変革をしていったか、その革命の歴史を追った本です。
ただ、それまでの日本の近代史の本は、権力がどう移り変わっていったか、政治体制がどのように変革されたかを調べたものが主流でした。それに対し、『開国・維新』では、もっと「日本人の精神革命」を重視しました。日本人の東洋内にあった精神が、ペリーによる開国によって西洋にも開かれていったのではないかと考えたのです。
開国が日本人の精神をどう変え、国の形や政治体制をどう変えて行ったか。イデオロギー的な意味合いではなくて、もっと文化的、生活的な意味でも変化があっただろうし、その生活の場や風土の形そのものも同時に変わっていったのではないかと、『開国・維新』を書いたすぐ後から、ずっと考え続けていました。
洋船の構造が日本の港を変えた
―― なるほど。開国によって、制度だけではなくて、日本人の文化、生活、精神性が根こそぎ変革を迫られたわけですね。
松本 そうです。ペリー艦隊の来航から、それに続く明治維新によって、日本の政治体制は徳川の幕藩体制から、天皇を中心とする明治政府による国民国家体制に代わりました。その時代に、日本の政治や制度に、非常に大きな変革があったという事実は、歴然としてあります。と同時に、私はこの頃から「日本の海岸線の形態が大きく変わっていったのではないか」と思うようになったのです。
その考えのきっかけとなったのが、ペリーが乗船していた船艦でした。彼らが乗っていた洋船は、排水量が2450トン。当時の日本のもっとも大きな千石船でも、100トンぐらいしかありませんから、25倍もの大きさです。当時、黒船を見た日本人は、船の大きさだけでびっくりしたことでしょう。船の構造も日本の北前船とはまったく違う。外洋航海のためにつくられた洋船は、甲板と竜骨があり、ビヤ樽を横にしたような構造をしています。
それまで日本の北前船が利用していた港は、瀬戸内海の鞆の浦のような、外海と直接は接せず、入り口のせまい、円形の入り江のような浅い港が中心でした。ところがペリー艦隊は、そうした港のなかに入ることができなかった。
実際、彼らは浦賀に来たときも、常に海岸線から2~10キロ離れていたと、船に乗船していた当時の通訳が記録を残しています。それは、射程距離の問題もありますが、彼らの船があまりに大きいので、喫水が深く、岸に近寄ることができなかったからです。水深がわからない港に入ると、座礁する危険性があったのです。
洋船が停泊できる港には、10メートル近くの水深が必要でした。そのときから日本の港は、鞆の浦のようなお椀型の船による国内交易を前提とする時代から、ビヤ樽型の洋船による諸外国との貿易を前提とする時代へと転換があったわけです。
ペリー艦隊は最終的に、徳川幕府に、横浜、神戸、函館、長崎、新潟という5つの港の開港を要求しますが、なぜそのような港が必要だったのかは、今までの歴史書に書かれていなかったんですね。
人口1750倍になった横浜
―― そうだったんですか。しかしこれまで書かれていなかったテーマということで、調査にもご苦労されたのでは?
松本 1995年にアジア太平洋賞を受賞し、200万円の賞金と、研究のためならば海外のどこにでも行ってもいいという副賞をもらいました。それで、インドと中国を旅行しました。その際に、講演を頼まれていたこともあったので、香港にも行きました。ちょうど97年の香港返還の直前です。そこで香港の港湾とビクトリアピークを見たわけですが、するとその港の構造や景観が、山からストンと落ちた神戸や横浜の港に非常によく似ていることに気づきました。
―― ほう、どんなところが?
松本 香港というのは、アヘン戦争で清国に勝利したイギリスが、南京条約を結んだことで手に入れた港です。しかしそのときになぜイギリスが香港を要求したのかは、これまで中国史や東アジア史でも書かれたことはありませんが、私は実際に香港の港を見て、その理由がわかった気がしました。
香港の港の背後には、標高500メートルぐらいのビクトリアピークがあります。そこに登れば港を全部見渡せるようになっている。これは長崎の港と同じです。長崎でも山の上のグラバー邸があるところに立つと、港が全部見渡せます。神戸や横浜もまったく同じです。港を見下ろすように六甲山のような高い山があり、そこからストンと切り落としたように港が広がっている構造です。
要するに当時のイギリスの軍人や貿易商人は、港を全部見渡せるところを必ず軍事的・貿易拠点とし、居を構えるようにしていたのです。それは敵が港に入ってきたらすぐに大砲を撃って撃退するためであり、いち早く貿易船を見つけるためでもありました。紅茶や香辛料を積んだ交易船が港に入ってきたときに、一番に見つけることができれば、最初に駆けつけていち早く交渉をすることができる。軍事防衛のためでもあり、貿易のためでもあった。それで山の上に住んで港を見下ろしていたのです。だから、ビクトリアピークの頂の方は全部イギリス人の居住区となっていました。神戸も横浜もまったく同じく、外人墓地や異人村があるのはだいたい山の中腹以上です。
―― なるほど。たしかにそうですね。非常に大きな発見だと思います。
松本 香港島は当時、島の人口が2000人、九竜半島も足して8000人しかいません。それがいまは800万人の巨大都市になっています。同様に、ペリー来航当時の横浜村は、人口わずか800人。対岸の戸部村を合わせても2000人しかいなかった。それが今では、横浜市の人口は350万人。1750倍に跳ね上がり、日本第二の巨大都市となっています。つまり現在の世界的な港湾都市である香港も横浜も、その時代を境に人口が急増しているという現実にも気づいたわけです。
古い地図を見ると、現在の横浜駅は海のなかですし、その先の「税関の内側(内陸側)」を意味する「関内」という京浜東北線の駅も海中にありました。税関があったところはまさに埋立地で、葦が生えている湿地帯だったんですね。江戸時代まではまったく使われることのなかった湿地の土地が、急に外国に向かって開かれることになり、どんどん埋め立てていって海岸線を海に押し出していったのです。
このように、ペリー来航の衝撃というのは、西洋文明に接触するという意味でのウェスタンインパクトであると同時に、日本の港湾にも劇的な変革を迫るものでした。そして港、ひいては海岸線の変化はその後、日本人の暮らしや生活意識をも大きく変えていったのです。
「海山のあひだ」に生きてきた日本人
―― 日本人にとって、海岸線というものはどんな意味があるのでしょうか。
松本 日本の海岸線をあらためて数字で見ると「諸外国にくらべてこんなに長いのか」とびっくりします。中国もアメリカも大陸国家なんですね。とくに中国は海に接しているのが、東シナ海に面したところだけですから、国境線の1/10しかありません。また中国の場合は、海岸から1万キロほど内陸に入らなければ山がありません。
日本は沢山の島からできていて、岩手の三陸のようなギザギザのリアス式海岸も持っているし、海に接するように山がある土地が、あちこちにあります。隣の村に行くのにも険しい山を越えねばならないような場所では、海から船で行ったほうが楽なため、そのような交通形態をとっていた地域も少なくありませんでした。そういう地形が、中国にはありません。つまり中国のほとんどの人には、その精神風土のなかに海がないんですね。アメリカも同じです。
中華料理も考えて見ますと、上海や香港の料理以外は、海のものは入っていません。干しあわびや干しなまこなど、全部乾燥したものです。日常生活のなかに海があるという感覚は日本人に独特なものなのです。
神代の時代につくられた出雲大社のご神体というのは、1メートルぐらいある大あわびです。ふだんは見ることができませんが、昔は外国人が来ると見せてしまっていたんですね。ラフカディオ・ハーンが、それを見たときのことを書いています。
大昔、出雲大社に辿りついた海洋民族は、海のなかで一番美味な大あわびを豊穣のしるしのご神体として拝んだのでしょう。祈りによって豊漁を祈願し、海の民族だからこそ、海のなかで見つけた大きな不思議なものを崇拝したわけです。昔から日本人にはそういう感覚が備わっていたわけですね。
基本的に日本人は、古代に海を渡ってきた人々が、日本列島に住みついた民族です。だから自分達の祖先も海の彼方にあると考えます。神様も海の向こうにいる。これはギリシャと同じなんです。ギリシャも島がいっぱいある国で、エーゲ海に浮かぶ島を渡って辿りついた人々がつくった国ですから、神殿はほとんど海の方向を向いています。自分達が渡ってきたもともとの故郷の方を向いているのでしょうね。
―― 日本人が海と切っても切れない関係にあることがよくわかりました。しかし現代の日本人にはその感覚が薄れつつあるような気がします。
松本 その通りです。本書を通じて、日本が中国やアメリカに比べて2倍以上の海岸線を持っている、島嶼国家であることを改めて認識してもらえれば嬉しい。二千年来、海岸線とともに生きてきたにも関わらず、その民族の知恵や感情というものを、わずか150年ほどで失いつつあります。
私はむかし、釜山から福岡に戻るときに、ある無人島を船で通りかかりました。白い浜があって、緑の山があって、その美しい風土を見たときに、「こういう土地ならば、死んだ後でも私の魂は安んじて戻ってきたいな」と思ったことがあるんです。人間の人生というのは、長く見ても100年です。日本人が生まれ、住み、死んでいく場所であるこの土地が、どういう場所であってほしいか、どういう美しい光景であってほしいか。それがどのように変化してきたかを、『海岸線の歴史』を通して考えてもらえれば嬉しいですね。