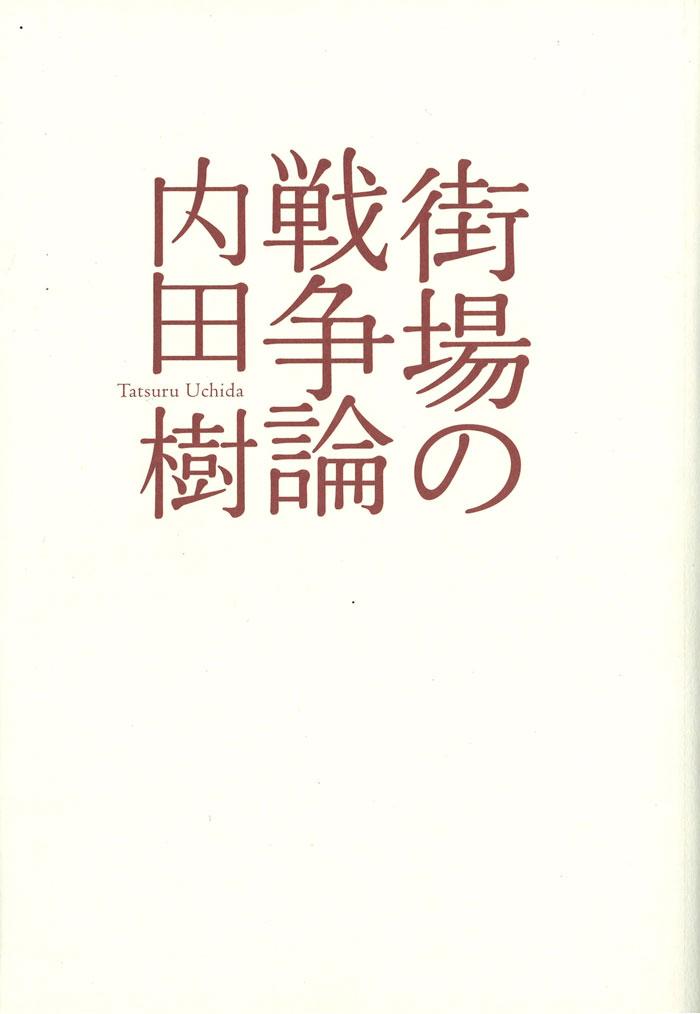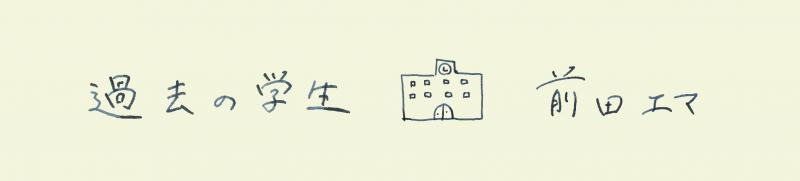教えて! 内田先生「日本のいま、そして行く末を」
2018.05.07更新
『街場の戦争論』発刊を記念して、2014年11月22日、紀伊國屋書店梅田本店・グランフロント店共同開催による内田樹先生のトークイベントがおこなわれました。
トークイベントのお題は、「日本が二度と戦争をしないために」。でしたが、先生のお口からは、その話題にとどまらない、「これからの国家」を考えるにあたりとても示唆に富んだお話でした。
今月の特集では、総選挙前に、国民として知っておきたい、そのお話の核となったところを中心にお伝えします。会場に来られた方も来られなかった方もどうぞ!
(構成:三島邦弘、写真:中谷利明)
もっとも弱い人間が集団のパフォーマンスを高める
僕は神戸女学院大学で、2011年まで教鞭をとっていました。教師をしていて思うのですが、集団のパフォーマンスを高めるためには、成員ひとりひとりに多様性が必要であるということを痛感しました。教員というのは個人技でつとまるものではありません。他の多くの教員たちの共同作業ではじめて教育事業は成立する。
教育の主体は「教師団」という集団です。だから、教育のアウトカムを高めようと思ったら、どうすれば集団のパフォーマンスが向上するのか、どういう個性を組み合わせる最高の力を発揮するようになるのかについての技術的知見が必要になります。
黒澤明の『七人の侍』という映画を僕はすぐれた組織論として観てきました。集団を効率的に機能させる最小数がだいたい6人か7人です。これは「グループで仕事をする」映画に共通しています。『荒野の七人』も『黄金の七人』も『ナバロンの要塞』も、だいたいそれくらいです。『七人の侍』の中で、僕が最も注目する登場人物は、ひとりは千秋実演じる平八という侍、ひとりは木村功演じる勝四郎という若侍です。平八をリクルートした五郎兵衛は彼をこう紹介します。
「腕はまず、中の下。しかし、正直な面白い男でな。その男と話していると気が開ける。苦しい時には重宝な男と思うが」
これは卓見だと思います。五郎兵衛は「苦しいとき」を想定して人事を起こしています。長期戦や後退戦を想定して、そのときに生き延びるために何が必要かを考えている。
勢いに乗じて勝つことは難しいことではありません。勝機に恵まれれば、小才のある人間なら誰でも勝てる。でも、敗退局面で適切な判断を下して、破局的崩壊を食い止め、生き延びることのできるものを生き延びさせ、救うべきものを救い出す仕事はむずかしい。平八採用はそのような経験的な知見を踏まえたものでした。そして、実際に彼はその負託によく応えます。
勝四郎がなぜ組織に必要なのか、これは説明が要ります。この青侍は戦闘力としてはほとんど頼りにならない。けれども、彼が加わることによって組織力は高まります。なぜなら、残りの6人が「この若者だけは死なせてはならない」とひそかに黙契を交わしているからです。自分たちはここで野武士と戦って死ぬかもしれない。たぶん死ぬだろう。けれども、自分たちがどんなふうに戦い、どんなふうに死んだかを誰かに語り伝えてもらいたい。六人はそう考えています。
「自分たちの戦いの物語を語り継いでくれる人」というのは組織のパフォーマンスの鍵です。未来の世界のどこかで自分の名前が冒険譚の中で言及されると想像しただけで、個人のパフォーマンスは爆発的に向上する。そういうものです。
尾田栄一郎さんのマンガ『ワンピース』にもウソップ君という「語り部」が登場します。彼は戦闘要員ではありません。彼の使命は海賊の仲間たちがすべて死んだあとにも生き延びて、その武勲を語り伝えることです。自分たちの冒険の物語がウソップ君の語りを通じて、いまから半世紀、一世紀語り継がれるだろうという空想が海賊たちの戦闘力を一気に高める。
集団は「彼らの経験を次世代に語り継ぐメンバー」を含んでいるか、いないかで戦闘力に大きな差が出ます。それは集団というものが本質的に「時間の中の存在」だからです。今ここでの具体的な業績や成果ではなく、それが歴史的時間の中で持つ意義によって、組織のパフォーマンスは賦活される。無時間的な集団と、歴史的な物語の中に位置づけられる集団では今ここにおける力強さが違う。
ですから、組織において幼いもの、弱いものを支援しなければならないというのは、組織論としてきわめて合理的な判断なのです。それは守るべき弱い者を含む集団の方がしばしば強者だけで組織された集団よりも強いことを人間は知っているからです。

立つべき場所、やるべき場所がわかる人間
沢庵禅師の『太阿記』の冒頭に、「けだし兵法者は勝負を争わず、強弱にこだわらず・・・」という有名な言葉がありますが、武道の修業の場では、集団構成メンバー個人の相対的な強弱や優劣を論じることは禁じられています。
もちろん、競技武道は別です。本来の武道は競技ではありません。どうやって集団が生き延びられるか、どうすれば集団のパフォーマンスが最も高くなるのか、その経験知に基づいて体系化された「戦技」です。集団が生き残るためには、集団内で成員間の個人的能力の優劣を論じてはならない。これは自明のことです。
もし、集団の中で、人々が競争的なマインドを持って、自他の優劣強弱を比べるようになると何が起きるか。自分を強める努力と同じだけの努力を他人を弱めるために注ぐようになる。相対的な優劣競争においては、自分が強いと他人が弱いは同義だからです。そして、明らかに周囲の同胞たちの生きる力を「弱める」方が自分の生きる力を「強める」よりも圧倒的に費用対効果がよい。
ですから、競争にかまける人たちは自分と同じ集団を形成している仲間たちが、自分より弱く、自分より愚鈍で、自分より無能であることを願うようになる。集団構成員たちがお互いに同胞が「弱い」ことを願い合うようなれば、そのような集団全体の生きる力が衰えるのは自明のことです。
だから兵法者は、勝敗を争い、強弱にこだわってはならないとされるのです。兵法者とは自己利益の増大よりも集団が生き延びることを優先的に配慮する人間のことだからです。競技武道者はアスリートではあっても兵法者ではありません。そして、武道修業がめざしているのは高い身体能力を持ったアスリートの養成ではなく、兵法者の養成です。
兵法者とは、「いるべきときに、いるべきところにいて、なすべきことをなす」ことのできる人のことです。自分が属している集団の中で、自分が立つべき場所がわかる。なすべきことがわかる。状況が変化しても、臨機応変に、誰の指示がなくても、集団のためにしなければならないことが瞬時にわかる。それが兵法者です。
そういう個体を多く含んだ集団は、個人的能力は高いが、ひとりひとりが自分のことだけ考えている集団よりも強いということは誰でもわかります。
平和な時代が終わって
今の日本は集団として弱いと僕は思います。人々は集団全体のパフォーマンスを高めるためには自分は何をなすべきかではなく、自己利益を最大化するために自分は何をなすべきかを優先的に考えている。
なぜそんなことができるかと言えば、それは戦後日本が例外的に平和で豊かな社会だったからです。兵法者がいなくても存続できるほどに安全だった。誰も集団全体のことを配慮しなくても、社会システムがきちんと機能するほどに制度設計がしっかりしていた。これはある意味ではすばらしい達成です。それは歴史的成功として誇ってよい。
でも、全員が自己利益の増大だけを追求している集団は、危機的状況を生き延びることはできません。あまりに長く続いた平和と繁栄のせいで、日本人はどうすれば日本という集団の力は高まるのか、日本人ひとりひとりがその個性と能力を最大化できるのかという問いを考えなくなった。それより、自分以外の日本人ができるだけ無能で非力であることを願うようになってきた。そうすれば自分の「パイの取り分」が増えると思っているからです。
そうやって日本人全員がお互いの個性と才能の開花を妨害し合うというゲームをここ30年ほど夢中になってやってきた。同胞の市民的成熟をどうやって支援するかということを誰も考えなかった。でも、そんなことにかまけられるほど平和で豊かな時代はもう終わりつつあります。
対米従属によるふたつの成功体験
日本の国家戦略は戦後一貫しています。それは「対米従属を通じての対米自立」というものです。「対米従属を通じての対米自立」は、敗戦後の日本においては「それしかない選択肢」であり、政策判断としては合理的なものでした。
実際に1945年から6年間GHQの支配に全面的に服従した結果、わが国は51年のサンフランシスコ講和条約で主権を回復しました。講和条約は歴史上珍しいほど敗戦国に対して寛大な講和条約でした。対米従属によって戦後日本はまずかたちの上では主権を回復した。これが最初の成功事例でした。
成功はさらに続きます。朝鮮戦争、ベトナム戦争においてアメリカの後方支援に徹したことによって、72年には沖縄の施政権が返還されました。国土の一部が回復したわけです。
つまり、45年からの対米従属は、51年の講和条約と72年の沖縄返還という二つの成功体験を日本人にもたらしたのです。主権の回復と国土の回復という二つの成功体験は、日本人の中に「対米従属をしてさえいれば、いいことがある」という信憑を刷り込みました。それがそれからあと42年続いているのです。
対米従属戦略は「待ちぼうけ」
敗戦後の日本の政治家たちはアメリカに対してアンビバレントな構えをしていました。直近の敵ですから、むろん日米の国益は相反する。でも、対米従属以外に日本が生き延びる選択肢はない。それゆえ「対米従属を通じての対米自立」は面従腹背の戦術として採用されたのです。顔は笑顔だけれど、腹の中には「はやくアメリカを追いだして、自分たちの手で国を作り直そう」という下心があった。
けれども、二度の成功体験のせいで、日本人はこの面従腹背が国益確保のための戦術的迂回であるということをいつのまに忘れてしまった。沖縄返還からあと42年経ちました。でも、その後はどれほど対米従属を強めても、日本は主権的にも、国土の上でも、アメリカから何の「リターン」も受け取っていない。沖縄の基地は返還されないし、横田基地も返ってこない。けれども、対米従属がこの42年間何一つ日本に「いいこと」をもたらしていないという歴史的事実を誰も指摘しない。
「まちぼうけ」という童謡があります。もとは韓非子の「株を守って、兎を待つ」という故事です。農夫が畑を耕していると、兎がやってきて、切り株にぶつかって首を折って死んでしまう。それを持ち帰って食べた。その成功体験に居着いた農夫は、それからあと畑を耕すことを止めて、日長一日切り株の前に座って兎がやってきて首を折るのを待っていた。畑は荒れ果て、農夫は国中の笑いものになった。そういう話です。
僕にはいまの日本の「対米従属」戦略は「まちぼうけ」のようなものに見えます。二度の成功体験があったせいで、「対米従属」という「切り株」の前に座り込んで「次にまたいいことがある日」をずっと待っている。42年間待っている。でも、もう「うさぎ」は来ない。そして、日本は畑を耕す仕方を忘れてしまった。
1980年代、せめて90年代までは対米従属によってリターンを期待するのは合理的な国家戦略だったかも知れません。しかし、2010年代になってなおそれにしがみついているのはもう病的信憑というしかない。どう考えても、あと10年や20年のうちにアメリカが沖縄から立ち去り、国内の基地がなくなり、日本の安全保障戦略についてフリーハンドを獲得して、日米同盟以外の同盟関係を構想するという可能性はありません。
つまり、対米従属はするけれど、対米自立はできないという「まちぼうけ」状態がこのあと、50年も100年も続く可能性がある。にもかかわらず、それについて危機感を持っている政治家も官僚も知識人もいない。少なくとも日本の指導層にはひとりもいない。
いまの日本では対米従属そのものが自己目的化しています。ですから、政界でも官界でも財界でも、対米従属を効率的に進めることのできる人間だけが出世できるような仕組みになっている。自分たちが何のために対米従属しているのか、その理由さえもう考えていません。
ただ、対米従属を効率的に進めると出世するし、年収も増えるし、ポストも約束されるし、社会的威信も増すという仕組みだけが自己運動している。かつては主権の回復・国土の回復のための迂回的戦術であった対米従属がいまや国家目的となってしまった。日本の国益よりアメリカの国益を優先する人たちしか国内で指導層になれなくなってしまった。
映画監督のオリバー・ストーンは、(2013年8月6日に)広島での講演で「日本はアメリカの従属国であり、衛星国である。日本は国際社会に発信すべきいかなる政治的主張を持っていない。日本は何も代表していない」と言い切りました。これがアメリカのリベラル派の常識だろうと思います。アメリカから見て日本は同盟国ではない、属国だと当のアメリカ人が言明した。
けれども、日本のメディアはひとつもこの発言を報道しませんでした。属国だと言われたのですよ。そうではないと思っているなら取り上げて反論すべきでしょう。でも、黙っていた。それはそれがほんとうのことだと日本人はみんな気づいているのだけれど、それに気づいていないふりをすることが国民的な合意事項だからです。

植民地の買弁資本
日本は最近植民地宗主国であるアメリカにさらに擦り寄っています。特定秘密保護法は、アメリカの軍機を守るために日本人の言論の自由を抑制するという政策でした。「アメリカの軍機を守るために自国民の基本的人権を犠牲にすることにしました」と言われたら、アメリカも「ああ、そうかい。そりゃすまないね」としか言いようがない。ずいぶんひどいことをすると思っても「アメリカのためです」と言われたら断るロジックはない。
そのあとは集団的自衛権の行使容認です。アメリカがやってる戦争を自衛隊が肩代わりしようと言ってきた。アメリカからしてみれば「ああ、そうかい。そりゃすまないね」としか言いようがない。
けれども、この提案はどちらもアメリカからみたらかなり「気持ちが悪い」ものだと思います。僕がもしアメリカの国務省の役人であったら、日本のこの二つの政策は気持ちが悪い。
その見返りに日本政府が「日本の国益」を増大するような譲歩をアメリカに求めるというのなら話はわかります。たとえば、沖縄の基地を返還してくれとか、TPP交渉で日本の言い分を大幅に聴き入れるとかいうのであれば、わかる。
でも、この二つの政策はいずれも「アメリカの国益を増大させる」という以外に何の目的もない。リターンとして要求されているのは「そのようにしてアメリカに忠義立てをする『私たち』をこれからも支援してください」ということだけです。安倍政権が長期化すればするほどアメリカにとって「いいこと」が続きますから、安倍政権を支持してくださいということだけです。日本国民の基本的人権も、自衛隊員の命も、海外派兵の結果日本人が抱え込むかもしれないテロのリスクもすべて「自分たちの政権を支持してくれるなら、支払っても構わない」代償として差し出されている。
僕が国務省の役人だったら、こんな気持ちの悪い提案をしてくる政治家を同盟者としては受け容れたくない。利用できるだけ利用はしたいけれど、信頼できるパートナーだとはとても思えない。自国の国益を犠牲にして、自分の政治的延命や自己利益の増大を諮っているような政治家をどうして信用することができるでしょう。
彼らからは、今の日本の指導層は「植民地の買弁」に見えるでしょう。「買弁」というのは、清朝末期において植民地の支配者である英仏米独におもねって、宗主国の便宜をはかる代償に自己利益を増やした人々のことです。
ホワイトハウスからは官邸は「買弁」の巣窟のように見えていると思います。国益を代表している人となら外交交渉もできるでしょうが、私的利益しか代表していない人間とは交渉できない。いまのアメリカの日本に対する距離感は彼らが感じている日本の指導層に対する「気持ちの悪さ」の表われだろうと僕は思っています。
先日の上海の国際会議で、習近平が安倍首相と「嫌そうな顔」をして握手をしていましたが、あれは非常にわかりやすい政治的ジェスチャーだったと思います。あなたは日本の代表ではなく、自己利益の代表者にすぎないのではないか、自分とは立場が違うという感情を表現したのだと思います。自分と同格の政治家として扱っていない。そういう政治家と外交儀礼上握手しなければいけないことに対する嫌悪感だと思います。
韓国首脳もアメリカ首脳も、みんな「同じ表情」を浮かべます。あれは自国と国益が相反する隣国の政治家に対する顔ではありません。自国の国益を代表することを止めてしまった政治家に対する嫌悪の表情だと僕は見ています。
国の強さとは人間の強さ
国が強いということは、人間が強いということです。はっきり言って、法律や税制なんて副次的なことなんです。国民がちゃんとしていれば、十分な市民的成熟に達した人たちが一定数要所要所にいるならば、それはちゃんとした国なんです。だから、どうやって「ちゃんとした大人」を育てるのか、それが国策の基本になる。
そして、最初の話に戻りますが、別に「理想の日本人」というようなモデルがあるわけじゃない。組織の力が最大化するのはそれが多様なメンバーを含んでおり、それぞれが「いるべきときに、いるべきところにいて、なすべきことをなす」ということです。そのような集団を形成することです。
『街場の戦争論』にも書きましたが、非常事態に関する法律なんてどうだっていいんです。いまの日本の指導層は非常事態になったら「指示待ち」でフリーズするような人たちばかりです。だから、非常時のための法整備なんてしても仕方ない。非常時に何をすべきか、上からの指示がなくてもわかる人を育成するしかないんです。
ドゴールがいたおかげでフランスは戦勝国になったわけですけれど、ドイツに降伏した時点で、ドゴールは国防次官に過ぎませんでした。ロンドンに亡命して、対独徹底抗戦を訴えて、ヴィシー政権から死刑宣告を受ける。自国の政府から死刑宣告を受けるような人間が、結果的にフランスを救うわけです。
というか、そういう人間でないと国難のときに国を救うというような大事業はできない。非常時に備えて法整備なんかしても意味がないんです。そうではなくて、「ドゴールのような人間」をどうやって作り出すのか、どういう教育制度や組織論によって、そういう救国の英雄になれるような人間を一定数確保できるのか、それを考えるべきなのです。
エリートというのは、なすべきことについての自己判断と国家的の政策判断が一致する人間のことです。別に上からの指示がなくても、国益のために何をなすべきかがわかる。それがエリートです。
先の大戦のときにイギリスの人類学者ラドクリフ=ブラウンはスーダンで人類学のフィールドワークをしているときに開戦の報を受けました。彼はただちに研究を止めて、現地民たちを集め、彼らを自分の部下に編成して、ジャングルを超えてエチオピアのイタリア軍にゲリラ戦を仕掛けた。これがエリートです。何をなすべきかについて自己判断できる。それはそこまで深く国家目的が内面化していたということです。ケンブリッジとかオックスフォードという大学からはこういう人間が生まれるんです。
第一次世界大戦のときアラビア半島で軍司令部から独断で「アラブの反乱」を指揮したT・E・ロレンスもそうです。彼もオックスフォード出身のエリートでした。自分がなにをなすべきか教えられなくてもわかる人間、そういう人間が集団の中に一定数いなければならない。イギリスやフランスではそういう考え方が定着している。
ひるがえって、わが国には、そのような人材育成の制度的基盤がありません。非常時に対応できる人間というのは、いま与えられているルールを長期的利益のために平然と無視できる人間。上からの指令が間違っていると思ったら「間違っている」と抗命できる人間です。そういう人間だけが非常時に対応できる。でも、いまの教育システムがそのような人間を育てようとしているようには思えない。そんな人間は絶対に出世できないように社会の仕組みができている。
ですから、日本は近いうちに制度的にがたがたになるだろうと僕は思っています。そのときに今の社会で指導的地位にいない人たちの中からあるいは非常時対応人材が出てくるかも知れません。とても、楽観的にはなれませんけれど、そういう「意外な人物」の出現に期待するしかないだろうと思っています。
ここからは、総選挙前にどうしても読んでほしい一冊『街場の戦争論』のまえがきを特別に公開。内田先生がどうして『街場の戦争論』を書こうと思ったのか。ぜひご一読ください。
***
みなさん、こんにちは。内田樹です。
今回ミシマ社から刊行いたしますのは『街場の戦争論』です。
この本、最初は『街場の二十二世紀論』という仮題で進められておりました。三島君はじめとするミシマ社の人たちがやってきて、「日本は次の世紀にどのようになっているか」についてSF的な想像をしてみるという、風通しのよい、スケール感のある企画です。
そこで僕が思いつき的に話したことを逐一録音し、それをテープ起こしして、ゲラに「ちょいちょい」と手を入れて活字化して、「一丁あがり」・・・そういう見通しでした。でも、実際に出てきたゲラを読んでみると、どうもいけません。
それは他の本と同じ話の繰り返しが多いということです。僕は2013年の暮れから2014年の夏にかけて、半年ほどの間に10冊以上の本を出しました。これは明らかに異常なペースです。僕だってこんなペースで本を出したいわけじゃありません。単行本なんて、2年に1冊、せめて1年に1冊くらいのペースでていねいに書き上げるものであって、月刊ペースで出すものじゃない。それくらいの常識は僕にだってあります。
でも、とにかく編集者たちが殺気立っている。「以前送ったあのゲラ、どうなったでしょう?」という問い合わせが、苛立ちから怒り、さらには絶望というグラデーションを伴って定期的に訪れる。営業会議で上司から「あの本はどうなったんだ!」と毎度叱責されていると聞かされると申し訳なさで身が縮む。
僕だってそれほど非情な人間ではありません。なんとかみなさんに機嫌を直していただきたい。しかたがないので、本も読まず、映画も見ず、旅行も行かず、あれこれの楽しみを断念して、ひたすらゲラを直しては戻すという日々を送っていたら、こんな冊数になってしまったのです。気の毒な話だと思いませんか。
なにしろそんなペースで本を書いていたわけですから、どの本も中身が似てくるのはしかたがありません。この本だって、原稿を書いている最中に三島君が来て、そこ で仕事の手を止めてインタビューが始まるわけですから、「今書いてたこと」をついしゃべってしまうことは避けがたい。
ですから、ゲラを読み返してみたら「どこかで読んだ話」がたいへん多かった。たいへん多かったどころか、6割くらいが「どこかで読んだ話」でした。それではとても「書き下ろしです」と言って出版社に託すわけにはゆきません。それでもかまわないという方もおられるかもしれませんけれど、僕の職業的良心(というものがあるのです)がそれを許さない。
しかたがないので、「どこかで読んだ話」は、話のつながりで残しておかないと筋 道がわからなくなる部分(「国民国家の株式会社化」とか「憲法が空語でいいじゃないか」とかいう トピック)だけを残して、あとはばっさり切りました。
すると残ったのは意外なことに「戦争の話」と「危機的状況を生き延びる話」だけになりました。読んでみて僕自身驚きました。
これはいずれも2011年の東日本大震災と福島第一原発事故後になってから次第に僕にとって緊急性の高まったトピックでした。でも、それはカタストロフを経験したから、その反省を通じて緊急性を持つようになった主題というのではなく、むしろ次に訪れる、もっと大きなカタストロフの前兆を感じたからこそ前景化した主題のように僕には思われます。
僕たちが今いるのは、二つの戦争つまり「負けた先の戦争」と「これから起こる次の戦争」にはさまれた戦争間期ではないか。これが僕の偽らざる実感です。
今の時代の空気は「戦争間期」に固有のものではないのか。その軽薄さも、その無力感の深さも、その無責任さも、その暴力性も、いずれも二つの戦争の間に宙づりになった日本という枠組みの中に置いてみると、なんとなく納得できるような気がする。
この本を書いている間にも、僕よりはるかに若い書き手たち、中島岳志、片山杜秀、赤坂真理、白井聡といったそれぞれ専門を異にする知性がまるで申し合わせたように「先の戦争の負け方」について深い独特の省察を始めました。おそらく彼らもまた何か「禍々しいもの」の切迫を直感したのではないかと僕は思います。
そして、それを回避するためには、せめてそれが「何であるか」を予測するためには、どうして先の戦争に日本はあんな負け方をしたのか、敗戦を日本人は戦後七十年間かけてどう総括したのか、それについての自分なりの回答をださなければならないということをひしひしと感じ始めたのだと僕は思います。
僕自身もそういう焦燥感を実際に感じています。そんなこと、僕は生まれてから今日まで一度も感じたことがありませんでした。でも、今は感じている。気がつくと毎日戦争のことばかり考えている。戦争に関する本ばかり読んでいる。戦争映画ばかり見ている。
この「まえがき」を書いている日の前日は山本薩夫監督の『真空地帯』を見ていました。見ながら、「召集された場合に、陸軍内務班のような場所で僕は生き 延びられるだろうか」ということをずっと考えていました。首尾よく三年兵くらいまでたどりつけた場合に、今度は初年兵をことあるごとに殴り飛ばしたり、「員数」のためにと他人の軍装を盗んだりする「要領」のよい古参兵になったりするのだろうか。年齢的に僕が召集されることはありえないわけだし、旧軍の内務班のような制度 はもう存在しないだろうとは思いますが、それでもそんな想像をしていることに気づいて驚いています。
戦争についてもっと知っておきたいと急に思うようになったのは、それを忘れないためではなく、「次の戦争」が接近していることを肌に感じるからでしょう。
そういう生々しい不安と焦りがこの本にははっきりと伏流しています。そのせいで、あまり読み易い本にはなっていないと思います。読者の中には読んでいて「何か異物が喉につかえたような気がする」という方もいるかもしれません。それが素材を十分に消化しないまま本にしてしまったからだとすればお詫びしなければなりません。あらかじめ謝っておきます。ごめんなさい。
それに三島君はもっと希望に満ちた書物を期待していたのでしょうけれども、期待に応えられず申し訳ないと思います。でも、これこそ2011年の夏に僕がずっと考えていたことです。できれば最後までお読みください。
『街場の戦争論』は、全国の書店さんで発売中!書店の店頭にない場合も、店員さんにおっしゃっていただければ、ご注文いただけます。選挙後、これからの日本がどうなっていくのか、『街場の戦争論』を読んで、ともに考えましょう。