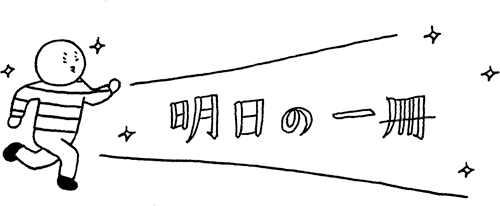2021年7月
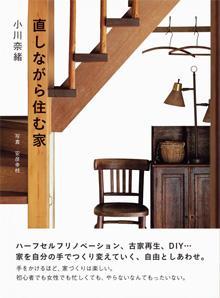 パイ・インターナショナル
パイ・インターナショナル-
『直しながら住む家 』
郊外の中古物件を直して住むという選択をした著者。本の前半では、建築家とともにリノベをした家の全容や、リノベにあたって考えたことが写真とともに綴られます。この和モダンなお家がすばらしく、写真をみているだけでうっとり。本の後半では、手つかずのままだった2階部分をハーフセルフリノベする様子が記録されています。そんな選択肢もあるのか!と驚いたし、自分たちの手で家がつくられていく姿は愉快です。
『愛と欲望の雑談』で、岸政彦さんが「家を建てるのは『自分がこの世界でどうやって生きていくか』という宣言だったなと思います」と話されてるんですが、ああ、ほんまにそうなんやなあと感じた本でした。2021.07.30
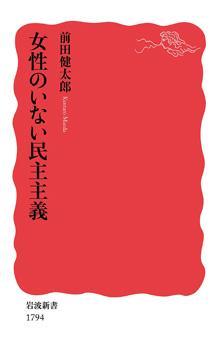 岩波新書
岩波新書-
『女性のいない民主主義 』
日本は民主主義の国だというけれど、その「民主主義」は、誰にとっての民主主義なのか? 政治学の教科書に取り上げられてきた主流派の学説を、ジェンダーの視点を導入して論じていく。はじめて本書を読んだとき、今までなんとなく抱いていた「なんっかなぁ」というもやもやがボカンとふっとび、目から鱗どころかワカメでも出てくるんでは?というくらい何かがにゅるりとこぼれ落ちた。折に触れて読み返していて、この本の内容が全部自分にしみこんだらいいのにと思う。本当にいい本なので、もっともっと広く読まれてほしいです。
2021.07.28
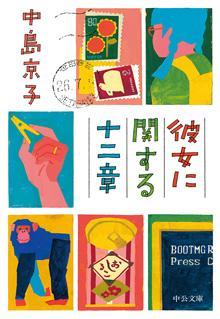 中公文庫
中公文庫-
『彼女に関する十二章 』
中島京子さんの小説が本当にすごいと思うのは、生活を描きながら、そこにかかわっている社会を、強調するでもなくそのまま自然に入れ込んで、読み手は話を追っていくなかでふと「あれ、これはよく考えると自分の暮らしでも問題なのかもしれない」と感じるところです。そんな良さがしみじみと詰まっているのが本書。なんだか50歳も楽しそう、とにこやかな気持ちになりました。
2021.07.26
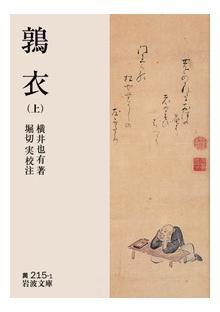 岩波文庫
岩波文庫-
『鶉衣(上) 』
『三流のすすめ』の中でも紹介した江戸時代の俳人・横井也有の書いた『鶉衣(うずらごろも)』。漢詩も作るし、和歌も読む。文章も書くし、絵も描く。俳諧だってする。でも、全てへたくそだと言う横井也有翁は、この世の中をユーモアと和で読み替えてしまおうと提案します。古文ですが、江戸後期のものなのでまあまあ読めます。また、いまは(下)を書店で買うことはできませんが、続きものではないので(上)だけでも充分楽しむことができます。
2021.07.23
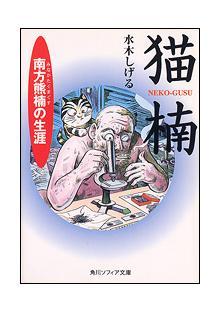 角川ソフィア文庫
角川ソフィア文庫-
『猫楠 南方熊楠の生涯 』
三流人の大巨人といえば南方熊楠(みなかた・くまぐす)。柳田國男から「日本人の可能性の極限」と称される南方熊楠は、どの本を読んでも蒙を啓かれるし、そして面白い。ぜひ御家庭に1セットは南方熊楠全集を揃えていただきたいのですが、「え、南方熊楠って誰?」という方は、まずは南方熊楠の生涯を水木しげる氏の漫画で読んじゃってください。自由な生き方に勇気づけられます。
2021.07.21
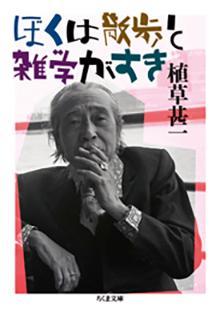 ちくま文庫
ちくま文庫-
『ぼくは散歩と雑学がすき 』
ジャズもミステリーも洋書の買い方・読み方も、すべて植草甚一氏の本から学びました。ものの見方、暮らし方、生き方すらも氏から学んだといっていいかも知れません。ぼくが「三流こそがすばらしい」と胸を張って言えるのは、植草甚一氏のおかげです。どれを読んでもわくわくしますが、まずはこの2冊からはいかがでしょう。お手に取ってご覧ください。
2021.07.19
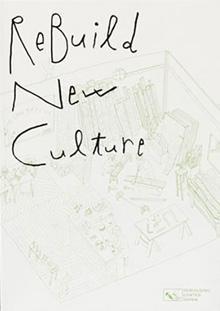 ReBuilding Center Japan
ReBuilding Center Japan-
『ReBuild New Culture 』
長野県諏訪市で、建築古材のリサイクルショップを営む〈ReBuilding Center Japan(通称リビセン)〉。手をかけて古いものを残すより、どんどん新しいものに入れ替えていく方が効率的とされてきた社会。でも、本当に未来に残したい景色って何なのか?楽しくたくましく、新たな文化を作り出すリビセンの姿に、胸打たれます。
2021.07.17
 真鶴出版
真鶴出版-
『日常 vol.1 』
〈日本まちやど協会〉が刊行する雑誌。「まちやど」とは、まち全体を一つの宿と見立て、ゲストとまちの日常をつなげていく宿泊施設のこと。どのまちにも、それぞれの「日常」があって、泊まる宿の選択によって、まちの見え方が大きく変わってくるのが面白いです。まちやどに向かう道中で、電車に揺られながら読みたい一冊です。
2021.07.16
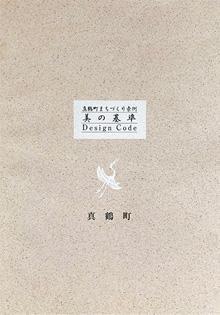
-
『美の基準-Design Code- 』
神奈川県真鶴町で、今から約30年前に制定されたまちづくり条例。日本各地でリゾート開発が進むなか、港町の風景を残すために、まちの経済成長をとめることを選んだ町が、30年経った今、どこよりも未来をみていたことに気づかされます。町の条例の冊子とは思えない、ポエミックな表現やユルいイラストも魅力的です。
2021.07.14
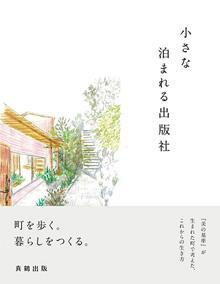 真鶴出版
真鶴出版-
『小さな泊まれる出版社 』
神奈川県の西の端にある町で、泊まれる出版社〈真鶴出版〉を立ち上げた夫婦の記録。出版とゲストハウスという、一見、全く異業種の2つを組み合わせることによって生まれる相乗効果が面白い!小さなことからひとつずつ、夫婦2人で考え取り組んでいく過程が丁寧に記されていて、読んでいてとても勇気づけられる一冊です。
2021.07.12
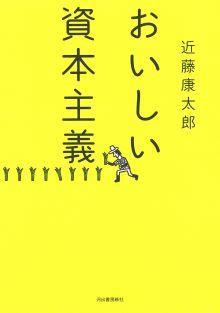 河出書房新社
河出書房新社-
『おいしい資本主義 』
コロナ初期に読んだ一冊。誰かがさかしらに声高に述べる資本主義とは違う、いわば本当に地に足をつけ自分の中から生まれる、循環していく資本主義とでも言えばよいのでしょうか・・・。
(ミシマ社サポーターさん)
2021.07.09
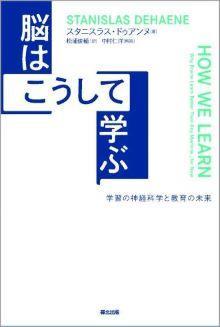 森北出版
森北出版-
『脳はこうして学ぶ 』
森田真生さんが「学びの未来」の中でも話していた、神経学者が学びを能の能力から説明している本です。「学ぶ」そのものを考えさせてくれる、とても示唆に富んだ内容です。
(ミシマ社サポーター 上原隼さん)
2021.07.07
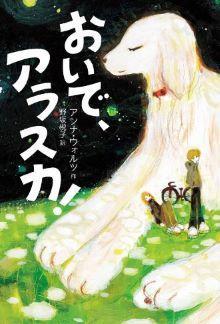 フレーベル館
フレーベル館-
『おいで、アラスカ! 』
えっ! この本なんなの? 児童書だからと気軽に借りた私。読み始めて、ドキドキ。てんかんの少年と強盗を見てしまった少女。でも気持ちは二人のこともわかるような気も。
(ミシマ社サポーター りんごジュースさん)
2021.07.05
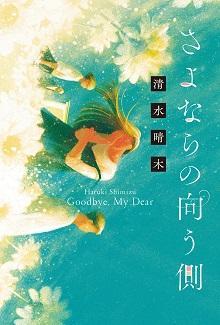 マイクロマガジン社
マイクロマガジン社-
『さよならの向う側 』
地元作家。それだけで応援したくなる。作品に地元が出てきたら尚更だ。頭の中で、見知った地名のそこで...登場人物が動き出すのである。本作もそのあたりは健在し、ニンマリ。
読む前に《号泣する》《涙が止まらない》という感想を見てしまい、構えて読みはじめた。が、しかし。結局、1章目から泣いて、ほぼ全章泣くなんて誰が予想しただろうか。
文字数の関係で詳しく書けないので、とりあえず読んでいただきたい!涙活におすすめ。2021.07.02