第2回
遠い曲を勤める
2025.10.09更新
能楽師はどんな演目でもすぐさま勤めることができると、思われているのか思われていないのかわからないが、だいたいは、記憶と経験を身にたぐり寄せて舞台に臨んでいる。
記憶と経験がない場合は、新しくそれらをこしらえることになる。
なかなか演じられることのない曲を、遠い曲という。
反対に、よく演じられて馴染みのある曲を、近い曲という。
私のような生半可な能楽師でさえ、近い曲というものはあって、そのまま舞台に引きずり上げられても勤められる演目はある。江戸時代、幕府公認の儀式用芸能となった能楽は、じっさい貴人のお召しで急の演能が命じられたこともあったと聞いている。台詞が飛んだり失態を演じたら失職とか切腹という世界だから、平和な現代では、失敗して鉄拳が飛んでくるくらい何でもないということになろうか。
遠い曲、とりわけ初めて勤める遠い曲ともなると、かなり用心して本番を迎えることになる。
能楽の教育システムはよくできていて、若い子弟は、師匠の鞄持ちで楽屋までくっついてきて、暇を盗んで先生たちの舞台を垣間見たり、演者のすぐ後ろで後見として控えたり、あるいはツレ役として板に立つことでその曲が内包する匂いや芯のようなものを身体で覚える。
だから、勤めたことのない御役を頂いたとしても、以前に先生がこうしていたとか、こんなイメージで舞台が進行していたとか、なんとなくの前提が自分にあるので、そこに具体的な稽古を上乗せすれば、スムーズに曲が出来上がっていきやすい。
このなんとなくの前提、記憶というものは侮れない。いったん見聞きしたことというのは、頭や身体に染み付き、そうちょうど真新への染みのようなもので、容易に消えないのだ。当該の内容まで自在にアクセスできる人は、記憶の達人と呼ばれる類いの人たちだが、どんな人にも、あらゆる記憶の染みは深に浅に残っている。本人が覚えていないだけで。
我々でいえば、具体的な所作や楽譜を覚えていなくても、たとえモニター越しの目撃だったとしても、その曲の空気を吸ったという事実を負うことは、当人にとってかけがえのない財産となる。0と1は決定的に違うということだ。
同じ本を二冊買ったことのある健忘のお仲間にはわかっていただけるかもしれないが、初めての役を承ったと思っていたら謡本やノートに自分の詳細な勤め書きが残されていた、という笑い話を、実は楽屋内で意外と耳にする。覚えのはっきりした人間であるに越したことはないし、忙しすぎるのか頼りないのかこの笑えない話を、私は、ある種の胆力を感じて聞く。つまり細かい記憶はどちらでもよい、根っこでさまざまな曲の芯を身体に蔵してきているから、少々のことには動じまい、という自信がそこにそこはかとなく香る。
舞台を経験したり背中を見るということは、具体的な行動はできなくとも、深層心理に確かな芽を植え付けるということだと思う。
その意味で、年の功を積んだ先輩長老が身近にいたり、親や代々の経験則が積み重ねられた家というのは、大小の逸話や教えが日常生活にぴったり貼り付いているわけだから、普通の職業役者よりも一日の長たりえると言いなすことができるだろう。
もしかしたら、具体的な所作や楽譜を知っていることよりも、この苗の芽を植え付けられている方が、舞台人には大事であるのかもしれない。
具象も重要だが、抽象はもっと再現の難しいものだからだ。
駆け出しの役者は、タダ働きでも野次馬でもなんでもいいから、とにかく舞台や楽屋に出入りして少しでも演者たちの横顔を焼き付けろというのは、理に適った精神論である。顔馴染みになってオファーの売り込みをしよう、なんていうのは副次的な問題にさえならない。
遠い曲という認定を下してよいのかどうか、能《知章》の御役を頂いた。
げにげに遠国の人にてましませば、知ろし召さぬは御理。
知章とは相国の三男、新中納言知盛の御子息にて候。
如月七日の合戦に、この一の谷にて討たれさせ給ひて候。
能《知章》
《知章》は、前場に出てきた男が、実は名のある平家公達の亡霊で、後場で修羅の世界に浮沈する苦しみを僧に訴える物語である。武士は相手の命を奪うのが職業なので、死後に修羅道へ堕ちるのは運命づけられている。こういった武士がシテとなる曲を修羅能という。
旅僧が須磨を訪ねて卒都婆を見つけ、板に「知章」と書いてあった。平家一門のどなたかな、と思う。すると不思議な趣の若者が話しかけてくる。遠国の人ならば仕方がない、知章というのはあの有名な知盛の息子で、一の谷の合戦で討たれたのだ、と教える。
僧は、当時の知識人に相当する。お坊さんは漢字が読めないと御経を上げられないし、教養がなければ人びとを諭せない。だからこそ能では、土地にゆかりのある神霊が、ワキの旅僧に話しかけるという話の流れになる。神霊も、せっかく旅人に話しかけた結果が、おうちどちらさんどす、では浮かぶ瀬がない。
この能が少し面白いのは、その旅僧にも、知章とは誰かと訊かれ、前シテが詳しい素性の説明を余儀なくされるところにあると思う。
平知章は、平知盛の息子。父親は平家の軍事総司令官にもなった勇将で、とみに名高い。彼が後シテの能《船弁慶》は屈指の人気曲だ。
でもその息子の曲となると、上演されることも少ない。遠い曲である。
私はこの《知章》に今まで縁がなくて、学生だった観客時代も、楽屋側に回ってからも、テレビや映像でも、まったく見たことがなかった。
やったことも見たこともない曲。怖いので、よくよく稽古する。しかしかなり稽古を進めても、謡が浮気しそうというか、実体が?めない感じがいつまでも拭えなかった。これが遠い曲の恐ろしさだ。
本番の感覚を掘り起こして身体に馴染ませるというより、いつまで経っても練習現場に居合わせるようなもどかしさ。
手がかりが薄く仕方がないので、このシーンは《箙》と同じだとか、この部分は《田村》の雰囲気があるとか、親しみのある曲の本当の舞台感覚の欠片を繋ぎ合わせて、せいぜいパッチワークのように作って臨んだ。
迷宮入りの稽古のせいか、申合と称するリハーサルでは、「ワキに言いようのない具合悪さがある」と指導されてしまった。確かにシテとの会話の流れとか、一曲の添いということが手薄になってしまったと思う。
《知章》は若武者なので、前シテも直面だし、しぜん、若い能楽師が勤めやすい。直面は、自分という顔の能面をかけたつもりで勤める、という心得がある。
シテの視線がまっすぐで、中心の黒目に信念が、肚がすわっているように感じた。若い役者だとまず舞台に緊張するし、あれこれの指導を直すべく気が散りやすいが、脇座で太い視線を食らって直球の清々しさを思った。稽古と、生来の環境か。血だろうか。
それにしても一曲のヒーローが、知章というのは誰だと言われ、語リで懇切に説明するも、僧の夢枕で再び、やんごとない公達ながら貴方はどなたと尋ねられるのは、戯曲上の構造とはいえ、ちょっとかわいそうだ。「誰とはなどや愚かなり」と後シテが謡うのも同情する。
しかし、「さも花やかなる御姿」と公達らしさは確と旅僧に感知され、華麗に武家の御曹司らしく戦場で散る、しかもそれが肉親を助けるためという可憐な戦いぶりは、健気で、そのひたむきな姿勢は、遠い曲の主人公ながら、何か必死にメッセージを送り届けようとしているように思える。
偉大な父を持つ青年武将。彼はどんなことを思っていたのだろう。
知章と会うことがあったら、ちょっと飲みに誘ってみたくなった。平家の貴公子はつまらない一役者なんて興味がないかもしれないけれど、彼の人生と孤独は、どうしてか友達になれそうな、淡い親しみを感じる。
なるほど観客も、この遠い曲は、こうやって意外と自分を投影して見るということなのかもしれない。人はみな無名で、みな孤独だから。


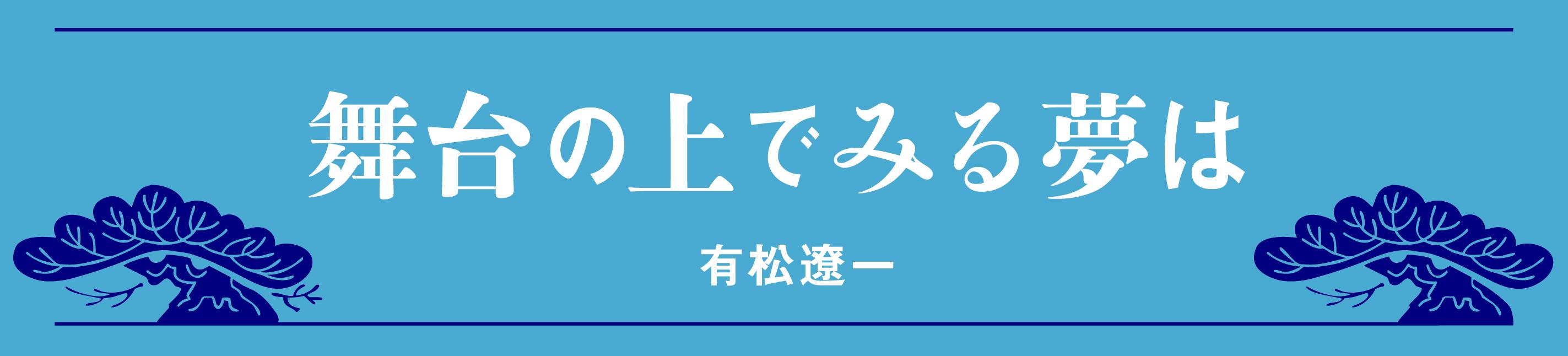

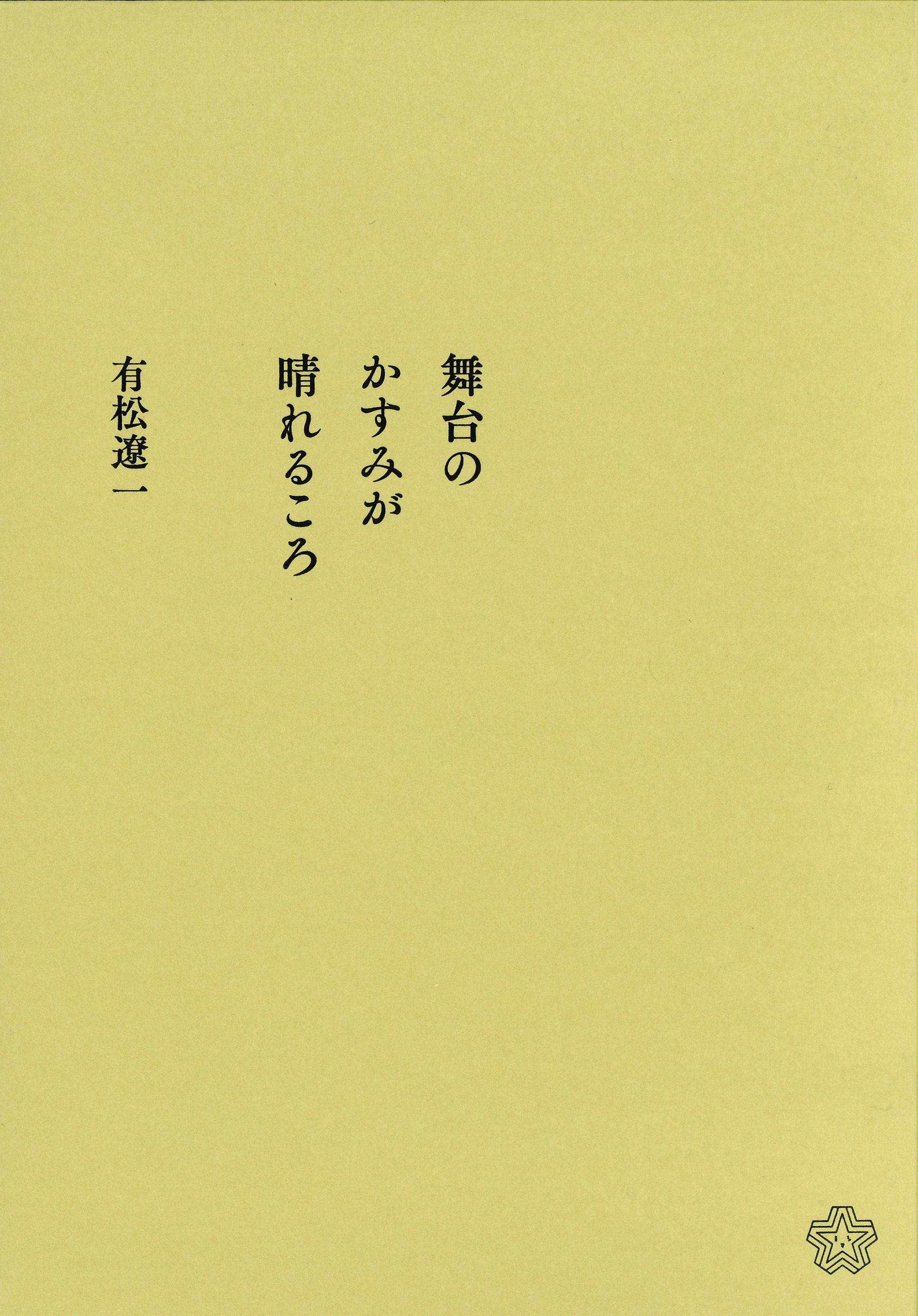


-thumb-800xauto-15803.jpg)


