第3回
息子があかんと言う日
2025.11.26更新
私は東京生まれなので、身体の脇をくすぐられると、「くすぐったい!」と口走ってしまう。
これはどうしようもないのだ。京都に住んで二十余年、京都の女性と結婚し、京都に家を構え、私をよく知らない方にはなんとなく京都の人と思ってもらえるらしいが、それでも、大脳を介さない無条件反射には、すぐに化けの皮が剥がれてしまう。
何の話をしているのかというと、ここは本当は、「こしょばい!」と口走らなければいけないのである。「こそばい」でもよろしい。
自分なりに身体をかなり京都に馴染ませてきたつもりだが、このことだけは自己改造できずにいる。できずじまいかもしれない。
妻は、ときどき私をくすぐって面白がっている。
ちなみに、どの地域を「京都生まれ」と称し、どのエリアの住まいが「京都在住」に値するのかは、うんざりするような面白い議論が他にあるので、それはそちらに譲っておく。
関西弁、京言葉、言語の学習は好きな人間だ。
学生の時に、四条高倉の食事処でアルバイトをして、女将さんにいろいろ口ぶりを直された。教えてもらったとおりに真似するのだが、女将は「有ちゃんちょっとちゃうねんな~」と眉を曇らせる。言葉のシャワーをもっと浴びないといけないと思った。私はバイト代より、美味しい賄いとこのレッスンがむしろ楽しみだった。
大学院生の時には、現代まで続く和歌の家、冷泉家時雨亭文庫の事務局へ伺うようになり、藤原俊成卿・定家卿からの都人である冷泉さんや、事務局のおばさまたち(いやお姉様方)に一から十まで教えてもらった。京都でも知る人ぞ知る、冷泉家は始祖の阿仏尼以来、女性がしっかりとした家なのである。
この局(つぼね)に十八年間愉快に所属させてもらったので、妻は「あなた中身はおばちゃんやな」と評する。
耳がいい、とも言われたことがある。耳が早いわけではなく、そこは鈍臭いのだが、言葉の習得には耳の良さが一役買う。
人よりも耳が利けば、それは能楽の仕事でも役立つ。たとえば謡の稽古なら、師匠が謡うさまを、どれだけ受け止めてその骨法を自分の中に移し取るかが勝負なのだから、音の感覚に秀でることは有利だ。手本の機微をこぼれ落とすほどもったいないことはない。
芸談も、耳がダンボの者こそ面白いエピソードを蓄積させていく。
そういえば、私は鼻も利くほうである。比喩的な意味ではなく、そこも鈍臭いのだが、実際の嗅覚がすぐれているらしい。妻は「さすが戌年生まれね」と評する。
昔はそんなに鼻を意識したことはなかったのに、趣味のコーヒーやウイスキーを嗜むうち、香りの嗅ぎ分けに勤しみ鼻が進化してしまったらしい。能楽師なら花を深化させよと叱られそうだ。
食べ物の匂い、草木の匂い、建物の匂い。知覚する印象のうち、人よりも匂いの要素が強いかもしれない。
妻が飲み会から帰ってくると、どんな居酒屋でどんな飲み食いをしたか、けっこう当ててしまうので気味悪がられている。
よく耳にする絶対音感は、世の中の音、音という音が、ぜんぶドレミで聞こえてしまう聴覚能力だ。雑音までがドレミで聞こえたら、さぞかし日常がうっとうしいだろうと想像しているが、自分はさながら絶対嗅覚の不自由さをまとっているというところか。
大人になって、趣味を持って、後天的に育ててきたアビリティの一方で、先天的な、環境から自然に身につけたアビリティの発揚を目撃すると、まるで手品を見るような、不思議な心持ちになる。
外国人の子どもが、たどたどしく英語をしゃべっているのを見ると、名にし負う天使よ、と思う。こんな幼少期から英語をしゃべるのかと、間抜けな感想を電車や公園などで抱いていた。
同じような感懐を、京都に移り住んでから、関西の子どもたちにも認めてきた。なるほど、この子は小さい時から関西弁をしゃべるのだな、と今でも思ってしまう。口にすれば、何を当たり前のことをとツッコミは免れない。
子方 やあ我こそ房前の大臣よ。
あら懐かしの海士人や、なほなほ語り候へ。
シテ 今まではよそ事とこそ思ひしに、
まさしき御身の上を申しけるぞや。あらかたじけなや候。
能《海士》
藤原不比等の息子・房前大臣は、実は讃岐国の志度の浦の、海士の子だった。「面向不背の珠」という秘宝を命と引き換えに龍宮から奪い返した房前の母(シテ)は、土地の物語としてよそ事に語るうち、房前が身を明かすことで、みるみる正体がとけだし母子の邂逅へと入っていく。
能はこのように、事件の当事者の雰囲気をまとった人物が、前場のシテとして現れ出で、語りのうちにその正体が露わとなって後場へ繋がっていく曲が多い。
この「今まではよそ事とこそ思ひしに」というフレーズは、日常生活の大小の出来事でたびたび頭をかすめる。
一歳半になる息子が、言葉の、まずは単語を口にするようになった。にゃんにゃん、わんわん、の初級をはじめとして、アンパンマン、バイキンマン、の中級に入り込んだ。名詞のほかに、おおきい、ちいさい、と形容詞も言う。
実は感情表現をいつ言うか、ちょっと楽しみにしていた。うれしい、楽しい、というのは身体を躍らせるのが表現の第一だから、それよりも、来たるイヤイヤ期と重なって、自分の意に沿わない事象への拒絶表現がそろそろやってくるのではと期待していた。もちろんその初手は泣くということなのだが、言葉としての拒みを、どのように表出するか。
そう、「いや」と言うか、「いやや」と言うか。関東と関西の差はこの一文字で決まる。
ある日、ついに口にした。よく聴取したが、残念ながら末尾の平仮名が一つか二つか、微妙な音のなびきで、確と判定することはできなかった。
それよりも、「あかん」と言うようになった。
正確に書き記せば、「あっか~ん」と呟くように言う。まるで旅館の女将が休憩時間に愚痴をこぼすよう。洩れ出るような嘆息。「あーかーん!」と叫ぶならまだ子どもらしいと思ったが、このはんなりとした仕様はどこから来たのか。
自分の幼少期には絶対に「あかん」とは言わなかったから、これは妻由来だろう。私のいないところで妻が「あかん」を連発しているのだろうか。しかし妻ははんなり女将の血筋ではないし、このマイルドな言い回しは、彼独特のものであると思われる。
今までは外国人やよその子どもで抱いてきた感慨を、いよいよわが子で受け止める段になった。
よくよく聞けば、形容詞も、おっきい、ちっさい、と言っている気がする。ちっさ、とも言い捨てているか。この促音「っ」は確かに存在していたのに、わが良き耳が、それを自己願望的に曇らせていた恐れが浮上した。
このいけずな拒絶、まだ数は少ない。大好きな葡萄を柿に代替してよいかと尋ねて「あっか~ん」、オモチャも潮時に寝る時間ですよと言上して「あっか~ん」、くらいか。これが濫発されるようになると、もっと歯切れの良い、さざ波の乱打になって、いけずがずっと先鋭的になっていくのだろう。
子どもは、自分の分身であるが、一個体として独立した人間でもある。親子はその距離感をさまざまな出来事で伸び縮みさせてお互いに成長していく。その「派出所」が、「あっか~ん」と天然に話すことへ、親は後天的学習を積みこの地に暮らす者として、しみじみと言葉にできないものがあった。
そもそもながら、彼は「やだ」とも言わなかったな。今度脇をこちょこちょして、耳元で「くすぐったい」と囁いてみようか。




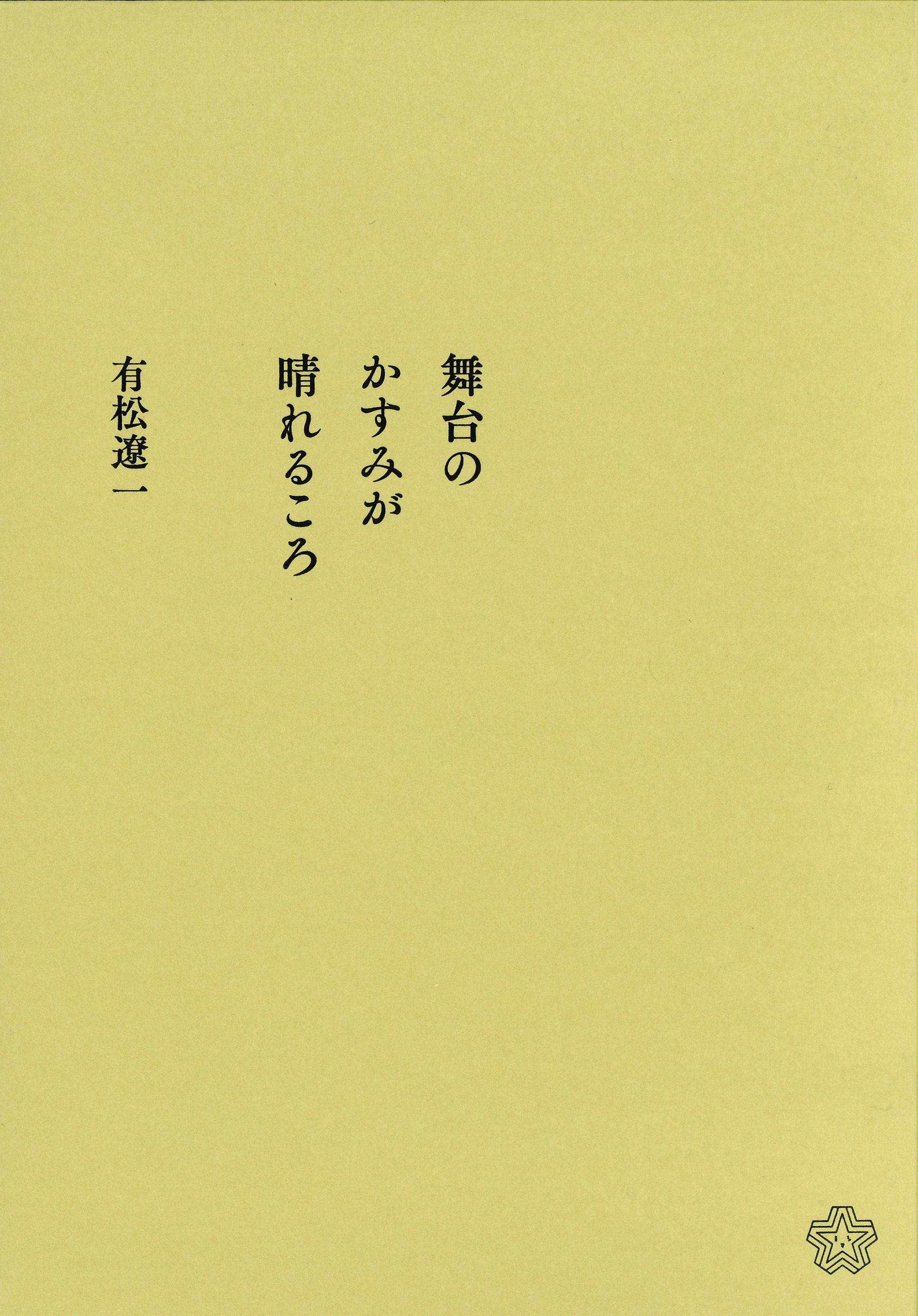




-thumb-800xauto-15803.jpg)
