第5回
二つの鐘
2026.01.23更新
能、《道成寺》。
「ドウジョウジ」という音の響きだけで、心がずしりと重くなる。
能楽師にとってこの曲は、そういう曲である。
能舞台をよく見ると、本舞台の天井に滑車が一つ付いている。
また、舞台に向かって右奥の柱(笛柱)の下腹に、輪っかが、やはり一つ垂れている。
能のレパートリーがおよそ二〇〇曲あるとしたら、一九九曲では、この装置は使わない。たった一曲、《道成寺》のためだけに、能舞台はこの設えを備える。《道成寺》の滑車と環を持つ舞台のみを本式の能舞台と称することができる。
《道成寺》は、「能楽師の卒業論文」といわれる。
シテと小鼓を筆頭に、各役とも重い習い事がたくさんあり、大事な曲として扱われている。
今まで培ってきた土壌の上に、この曲の教えや決まり事を一つひとつ、きちんと積み重ねて、無事に幕へと帰ってくる。そのミッションを果たすのが《道成寺》だ。
「無事に幕へ帰る」と書いた。
これは誇張でもなんでもない。
「披キ」(初演)では、無事の帰還ならひとまず、まずまず、と評される。
戦争へ行くわけではないのだから、無事に帰還するなんて当たり前のことではないか、とも思われるだろう。
しかし、舞台というのは、いったい非日常のオンパレードであり、普段には一度も起こらなかった事が、あとで不思議なくらいに、魔の差す、何が起こるかわからない方域である。
そういう空間で、例えばシテの鐘入リなら、一〇〇キロ近い鐘の落下に合わせてその中に飛び込む。もちろん視界の狭い能面をして。教えを踏み外せば、死が隣にいる。
さらに奥には、表現の根本として、《道成寺》はどれだけ肉体と精神を突き詰められるかという苛烈な主題が待っている。
そもそも能とは、アクセルとブレーキを全開で踏み込み、そこに生じた火花を表現の種とするような芸能である。
その矛盾した力の相剋、面白さを極限まで煮詰めてしまった最たるものが《道成寺》といえる。
鍋で具材を三〇〇年間煮込んだスープをイメージをしてもらったよいだろうか。
あらすじは、紀州道成寺の鐘供養に参詣した白拍子が、女人禁制の境内に入り込み、舞を舞いつつ重鎮する鐘を落下させる。この寺には、昔、山伏を付き慕った娘の執念が蛇体となり、鐘ごと男を溶かし殺したという謂われがあった。ワキの住僧たちに祈られ鐘から現れた大蛇は、日高川に飛び入ってその姿を消す。
江戸時代以降の諸芸能では、安珍と清姫の物語として発展していく。
《道成寺》ワキの名ノリは、舞台中央、正中で名乗る。名ノリの立ち位置は、普通は橋掛から舞台に入ってすぐの常座だ。
正中は、舞台で一番目立つ場所、軸であり、シテならばともかくそう易々と立ち入っていいエリアではない。しかしこの《道成寺》は、そこに立ち入る代償を払ってもなお、曲の格、位を示すため、名ノリ笛であえて正中に進む決まりになっている。
観客たちも、いつもと違う域へぐいと進む姿に、尋常ならざる空気を読む。板の上では、常座くらいから空間が重く、まるでプライベートゾーンに搔き分け入るようなストレスを感じる。
《道成寺》の住僧、水衣の色は紫と決まっている。これも約束事。高僧にしか許されない色で、それだけの器、居住まいが、お前にあるかという問いの衣を身にまとう。
名ノリの謡は、一曲の重みを否応なしに感じさせる、深く、大きな気格を示す。「ああ、大曲が始まるのだ」という事実を観客と共有する。
自分の身体が暴走するのか、名ノリを謡う間、共鳴が収まりきらず耳が利かなくなる。特に右耳。角帽子を着けているせいもあるか。耳圧の爆風を受けて耳がツーンとする。龍が躍り出ていく。多少この身の垣を壊してもよい、思うがままに空間へ飛び出ていけ。
ワキにとっては鐘入リ後の、語リも重要な場面だ。言葉や節もようよう盛り上がり、正しく謡えば後場への期待がふくらむように設計されている。
難しいのは、この住侶は、蛇体となった荘司の娘をそこで見ていた人ではないことだ。寺に伝わる縁起をあくまで口承するのみ。役者が身体に切羽詰まっても、どこか伝聞で冷静な立場を忘れてはいけない。事件当事者の熱演になってはいけない。
これがなかなかできない。アクセルを踏み切らぬ上手じみた能ほど、腐臭に満ちた下手物はない。ついアスリートのような汗をかいてしまう。日高川の深淵ではない、別の淵がちょっと見えたりする。舞台の事故は迷惑をかける。最後は自分が積み上げてきたものを恃むしかない。ええい、ままよ。
周りの演者をここまでの気持ちにさせるのは、やはりシテの登場の、次第ではないだろうか。習ノ次第というこれまた特別な囃子に乗り、多くの約束事を負い、白拍子の女が橋掛を進む。常座でおもむろに背に回り、怪しい心中を謡う。
作りし罪も消えぬべき、作りし罪も消えぬべき、
鐘のお供養を拝まん。
能《道成寺》
披キのシテたちを見てきた。悲痛なまでに、全霊で、虚心に、初手にそんなに出し尽くして大丈夫かと心配になってきた。
《道成寺》の勤めが許されるレベルの演者は、上手風の小手先でこの曲が成立しないことをよく知っている。乱拍子という大関門もこれからなのに、初っ端の次第で体力を使い果たすかの気概と覚悟。フルマラソンなら、あとの四一キロをどうやって走り抜く気だろうと途方なくなってしまう。
そうしないと《道成寺》ではないなんて、能はなんという芸能だろう。
《道成寺》の舞台前は、このシテの密度に照準を合わせる。
自分自身の披キは誰だってがむしゃらになる。問題なのは二度目以降、あの緊張感を再び自分の中に築くのは、厄介な人間の慣れが頭をもたげてなかなかに難しい。
自分ではそのつもりでいても、どこか足りなかったり、気持ちが甘かったり。
緊張をよそおったとても仕方がない。
あの気密を求めるため、精進潔斎、暮らしの中に禊ぎを設ける人もいる。スピリチュアルとか迷信というより、生活節制を通じて心身を高める知恵だと理解している。
そんな束縛をわざわざ潜り抜けなくても、《道成寺》のひと通りは、技術的にやってのけることはできるだろう。
しかしどんなに枝葉が繁って見えても、幹が、いやその根が深くなければ、《道成寺》という能からは悲しく遠ざかる。
「道成寺にならない」という表現も会話でしばしば聞く。
《道成寺》に参加する他の役の演者とも、舞台で同じくすると、すぐにそれに気がつく。「あ」と符合の声が出そうになるものだ。「そうですよね」とも口走ればよいか。
この真贋を、目ある観客は必ず知っている。
煮詰め、研ぎ澄まし、肉迫にもがいて初めて、《道成寺》の出場切符は得られるのだと思う。
その精神の葛藤は、何時間稽古したとか、いくら費やしたとかの指標のものでもない。外見には見えない闘いだ。正味は《道成寺》の舞台を呼吸した人しかわからない。
応援してくれる人の感謝を背負っても、支援者は舞台を作ってくれない。作るのは自分。人間は一人の存在なのだと思い知る。
表現者は孤独なのだ。自分のことは誰もわかってくれないし、誰も助けてくれない。
同業の仲間でさえ、初役にも初役の、ベテランにはベテランの、その人だけの重荷があって、年齢とか、芸歴とか、環境とか、家族とか、後援者とか、お金とか名誉とか、さまざまな条件で、その人にしかわからない闇の中で舞台と対峙している。
その闇の色はそれぞれの唯一で、結局は自分で立ち向かうしかない。全く同じ立場の人間など一人とて存在はしない。
《道成寺》は、表現者の覚悟を問う能でもある。
近日、同じ月に、二度《道成寺》を勤めることがあった。
秋だった。月の初めと終わりの、それぞれ別の公演からの依頼だった。どちらのシテも披キだった。
大曲の指名を頂戴するありがたさは何にも比しがたい。しかし、きちんと勤められないのであればお断り申し上げなければならない。
月に鐘を二つ釣り下げたのは、私は初めてのことだった。
師匠と相談して、どちらも勉強させていただいたが、今も心の中にあの《道成寺》の大きな鐘が、暗がりの中でぶら下がり続けている。
白拍子の蛇体は、僧たちに祈り退けられるものの、遂に日高川の深みへ飛び入るだけで、「成仏した」とは謡われない。
またあの白拍子が現れるかもしれない、束の間の暮らしに戻るだけかもしれないと、芸人の宿命を思いもした。




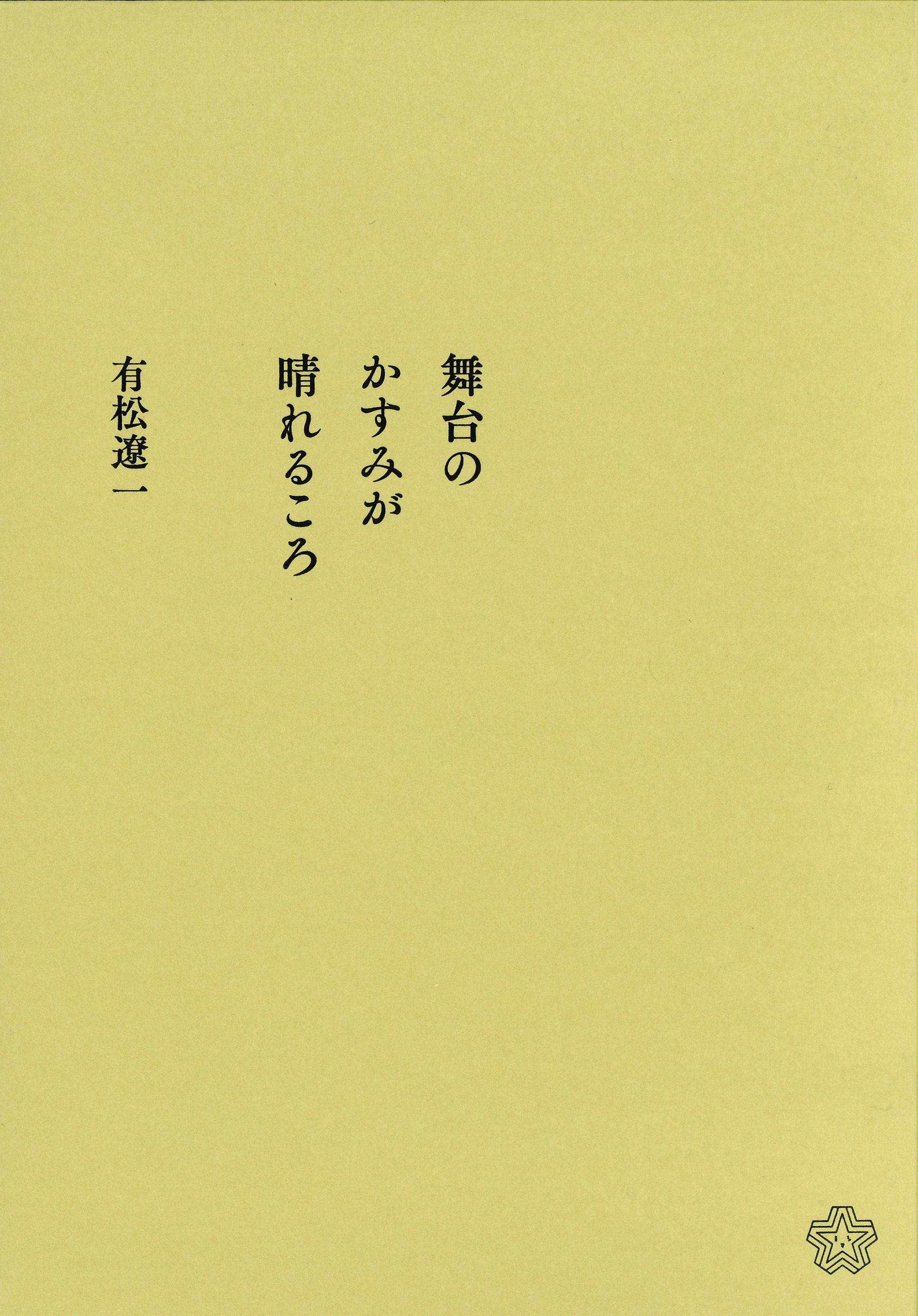




-thumb-800xauto-15803.jpg)
