第1回
自分の書く文章の価値
2025.09.16更新
自分の書く文章には価値があるのだろうか。
こういう疑問や心配は、もっと最初に感じるべきだったかもしれない。
新聞の連載や、エッセイの寄稿、書評、新作能の執筆、脚本のリメイクなど、これまで依頼があれば頼まれるまま、やすやすと筆を執ってきた。この度も、いま書かねばならないことを書きましょう、という音頭に乗って、その気になってすぐに承ったものの、はたと、これでいいのかと、身体の横をいやな電気が走りはじめた。
不惑に入ってやってきた思春期のようだった。
文章は誰にでも書ける。万人に開かれたものだ。だからこそ、人様に読んでもらうためには、そこに特別な何かがなくてはならない。
自分は、匿名の筆で名乗りを上げ、世間に知られたわけではない。
能楽師という、ちょっと風変わりな職業に携わっているおかげで、下駄を履かせてもらって、読み手の目に耐えてきた。
令和四年三月に出した『舞台のかすみが晴れるころ』という初めての本も、舞台人のコロナ禍の生活という特殊な内容と、特異なご縁で、披露の好機を得ただけである。
だから、その技術かその素材か、社会に貢献できる何かがないまま、世に文章の表現など許されないだろう、世の中はそんなに甘くはないだろうと、たちまち筆が止まってしまった。
困った。とりあえず腹が減っては戦ができぬと、昼にうどんを湯搔いた。麺をすすりながら、しかしこのつゆも、鰹節がうまいダシのために身を削っているのだと思った。箸が止まった。いわんや人間の文章において、私は何を削ったらいいのだろうか。頭を抱えた。
誰でも、自分の仕事の意義、ひいては生きる意味、これをやっていていったい何になるのだろうという疑義を抱くことは、あると思う。
それと闘いながら、社会や家庭と対面してもがき、折り合いを見出しながら人は生きてゆく。そういうものだと古今説かれている。でもそれは、本業で格闘している人びとへの讃歌であって、ましてやこの自分の筆は、わざわざ染める必要のないものとも見える。
ちなみに、能楽の仕事ではなぜその疑念を感じずにいられるのかといえば、それは師匠と、先人たちの残してくれた型や教えに助けられるからである。もちろん芸の山は高く頂が見えないし、山登りはひどく苦しいし、自身の不甲斐なさを感じることばかりだが、それでも先達や道しるべが、こっちだがんばれ我も登ろうと励ましてくれる。その山の高さを確かに信ずることができる。道の途中、木の間から遠く広がる山下の野辺を眺めることができる。私は、ありがたい仕事に奉じている。
隣からスポーツ選手のインタビューが流れてきた。試合の意気込みを訊かれて、「あとは楽しんでやれたら」と若く溌剌と答えていた。
近年こういう受け答えが増えた。真剣勝負に「楽しむ」とは何事だ、と初めはお叱りを受けていたのかもしれない。時代が、指導法の大勢が、こういうスタイルに馴染んできたのだろうか。
楽しんでやるだけなんて、何とうらやましいことかと思うおめでたい人は、さすがにいないだろう。実際、制約から解放されたパフォーマンスは実力以上の発揮が科学的にも認められるのだろうが、この「楽しむ」にはむしろ、千載一遇の一事に向けてコツコツと準備を重ね、努力してきた花をどうにか咲かせたいという切実な願いと、スポーツの残酷めいた宿命を思う。人事を尽くして天命を待つ孤独が、若者の笑顔の向こうから流れてくる。
「あとは」の三文字の重みを感じる。
最近私がよほど陰鬱な顔をしているのか、普段から応援してくださる方が、「巧拙よりも、あなたの文章を読みたい人がいて、書く人がいて、それだけで関係は十分に成立しているのではないですか」と持ち上げてくれた。行きつけの喫茶店だった。優しさが身に沁みた。
よその店でも、同じようなことを言われたことがある。市場経済の理屈で考えるなら、それはビジネスモデルとして基本形なのだろう。でもこの山は、その種の山ではないと思うのだ。そういうのは家でやればいい。ファンミーティングでやればいい。一端にも文章の表現者を標榜するのなら、提供者と享受者の関係を超えて、真善美の摂理で、読み手や社会を否応なく高みに引き上げるような、まわりの精神を浄化するような霊性が少しでもなくては、意味がないと思ってしまう。
つまりはスポーツなら、隣の選手より一秒早くゴールインすることが目的ではなくて、これまでの自分の中の最速、世界のどの競技選手よりも、あるいは歴史上の全人類よりも、早いタイムに手を伸ばす勝負をしなくてはいけないような気がするのだ。
打てばその声妙にして、
聞く人感を催し、喜びの声満ち満てり。
能《天鼓》
この能は、中国の物語である。天から鼓が降り母の胎内に宿る夢を受けて生まれた少年・天鼓は、天から本当に授かった天の鼓を打つと、妙音が人びとの感を動かし、喜びの声が満ち満ちたという。楽器を召し上げる皇帝の意に反した天鼓は処刑されてしまうが、誰が打ってもその鼓は鳴らず、代わりに天鼓の老父が宮廷に呼び出されることになる。
能が始まる、最初の名ノリでワキの勅使がその事情を語る。
打つだけで音色が人の心を震わせる。打つだけで。私は想像するのだが、それは大汗したたる力演とか、超絶技巧の熱演とか、そういう類いではないと思う。一音で、心を摑まれるような澄んだ音色をイメージする。岩間の一粒の滴りでハッと我に返るような。
能の演技でも、前シテの老父が「老いの歩みも足弱く」「薄氷を踏むごとくにて」作リ物の鼓にとぼとぼと近寄り、「打てば不思議やその声の」と一つ撥で打つだけで、「心意を澄ます声出づる」その妙音が響き渡り、思わずとろとろと後ろに退る型をする。
ただ撥で打つと、ただ音が響く。どこまでも自然で心に沁みる。天然に実直で、感動の作意はない。
聴衆も、何にこれほど感動しているのかわからない、と極言できるかもしれない。
おとぎ話のようだが、舞台に出てくるだけで空気を動かせる役者を目撃してきた身としては、この天鼓も現実に存在し得る話であろうと思う。
天才といえば簡単だし、何よりこれは「天鼓」という名前なのだが、舞台人も、美術家も、文筆家も、そういうものを目指して心血を注ぎながら自分の言葉を紡いでいる。
一つ救いがあるとすれば、どんな名手も、最初から名人であったわけではないことだろうか。必ず稽古という修練の段階があって、天上の境地に至っている。天鼓少年も、撥の持ち方くらいは誰かに教わっていてほしい。
それが、山を登る者としては一摑みの救いである。その淡い期待を抱きながら、進んでいくしかない。文筆の片端に傍するうえは、自分の何事かを削ってでも、価値あるものを書き残したい。
せめて、ダシの風味だけでも出せればうれしいのだが。すっかりうどんが伸びてしまった。


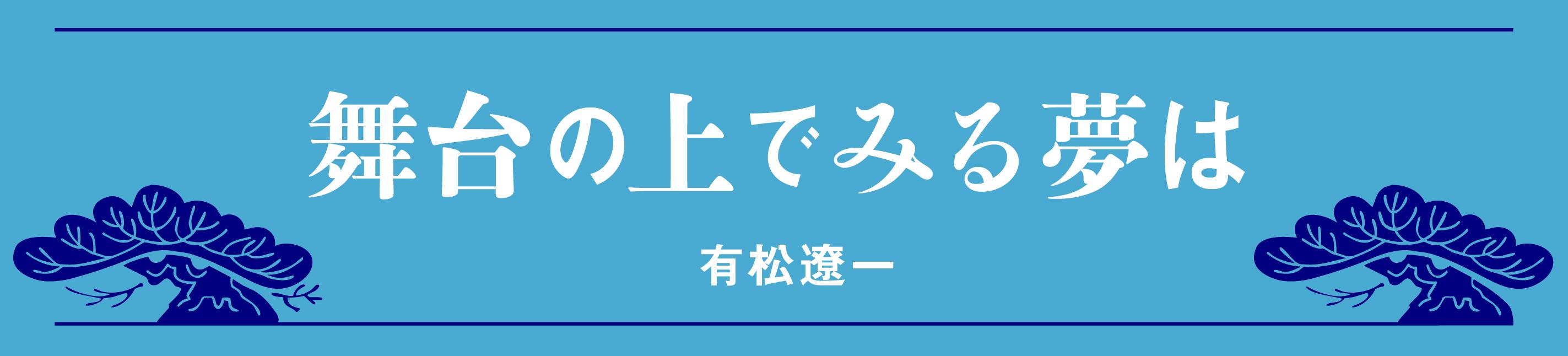

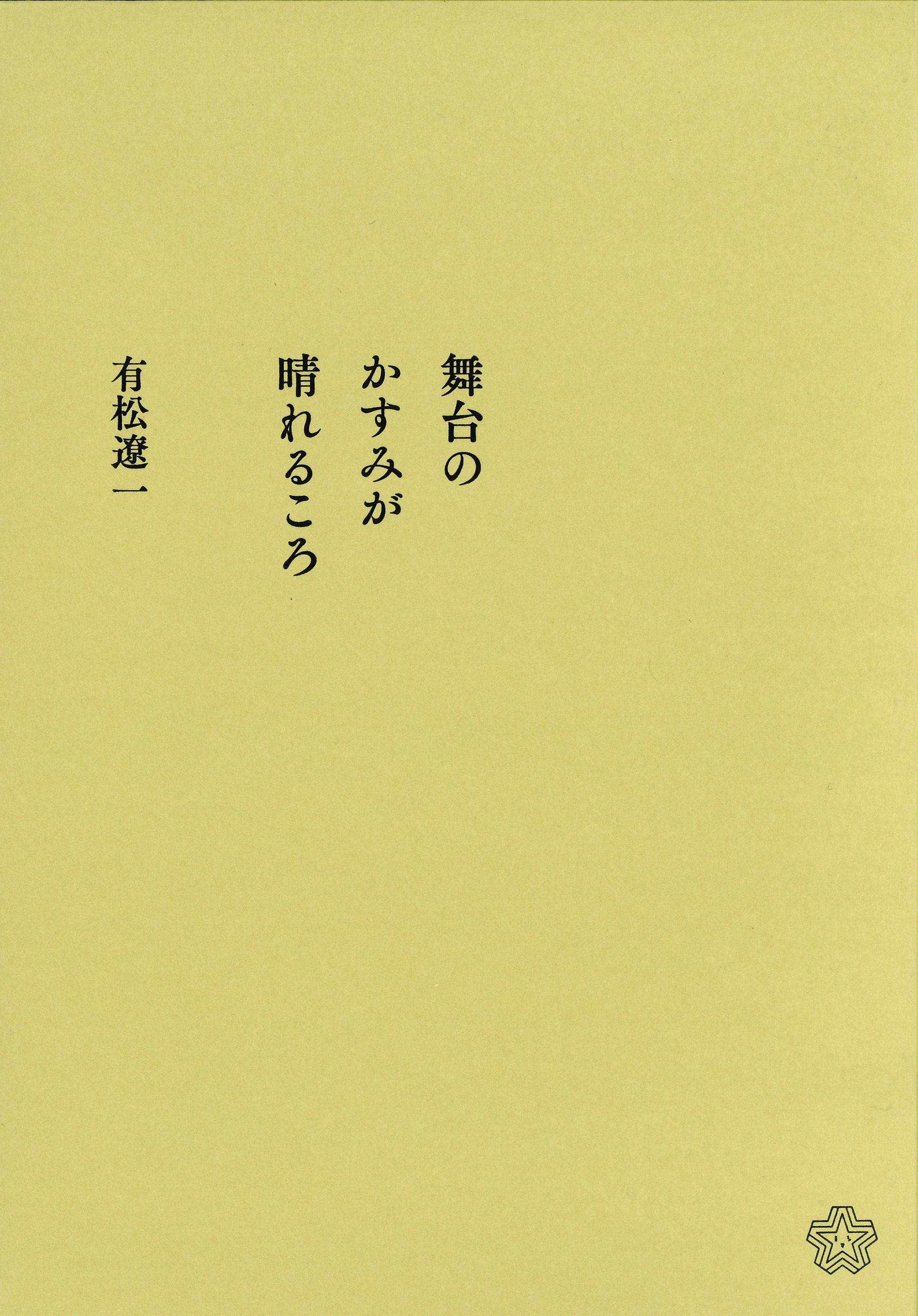


-thumb-800xauto-15803.jpg)


