第6回
ふつうが一番いい
2026.02.16更新
鼻をかんだことがなかった。
京都で一人暮らしをするようになった頃、大学生の時か、ティッシュで鼻をかんだと覚える。その記憶が正しければ、高校生くらいまでは鼻をかんでいなかったことになる。
そんなバカな、嘘をつけ、どこの世界に鼻をかんだことのない奴がいるのだと諸賢のお叱りを受けそうである。
しかし、世界は広いのだった。
これを身内にこぼした時、「風呂に入ったことがない」とか、「服を自分で買ったことがない」とか、「選挙に行ったことがない」という、そういう人間を見る目の視線を浴びた。蔑視という透明の二文字が浮かんだ。鼻をかむのがふつうのこととは知っていたが、それでも、この種の蔑みが日常の生活から急に顔をのぞかせるとは思わなかった。ふつうという斉一性に、ただただ口を結ぶしかなかった。
鼻汁を、鼻孔から出る粘液を、では今までどうしていたのだと思われよう。
紙面を割くのに尾籠で申し訳ないかぎりだが、子どもの頃から、いつも痰にして吐き出していた。
多くの子どもは、いつ、鼻をかむのを習うのだろう。子どもの自分には、家族や周りに花粉症の人がいなかった。鼻を四六時中かんでいる人と居合わせる景色がなかった。風邪の鼻かみはどうか。家族は鼻をかんでいたのだろう。でも私は鼻をチーンとはしていなかった。とめどない鼻汁にティッシュで防波するくらいのことだった。
いま一歳半を過ぎたわが子が、ふと鼻を垂らしていると、ティッシュで摘まんでグイと拭う。鼻から勢いをつけて空気を噴き付けるという文明を教えるには至っていない。もう少し会話が通じるようになったら、きちんと鼻のかみ方を、手取り鼻取り伝授する日も来るだろう。その日が来なかった私の反面として。
私とて、ティッシュを当ててえいやと鼻息を噴出させたこともあるのだ。しかし、律儀な性格が禍となり、紙を余さぬよう隙間なく鼻の両孔を覆って、密閉し、そこへ内腔の空気を噴き付けてしまった。
当然、鼻腔の空気は出口を失い、逃げ場のない激しい気流は耳孔の方へと吹き荒れた。鼓膜を強く震わせた。
とても痛かった。鼓膜が破れてしまうのではないかと思った。鼻をかむのは恐ろしい行動だと合点した。
鼻水を取り除きたいのなら、カーッ、ペッ! と、鼻内部のルートを頼りにして痰で吐き出せばよい。よほど鼻から垂れて困るのなら、ティッシュを穴に突っ込んでやはりテトラポッドを築けばよい。
こうして私の半生では、鼻をかむという行為が日の目を見なかった。少しティッシュを加減すれば空気を抜きつつ鼻水を放出できるという素朴なことに気がつくまで、二十年を要してしまったのである。
落ち着いて考えてみると、二十年間は仮にもそれで無事に過ごしてきたのだから、この先五十年、鼻をかまずに生きていく人生というのもあったように思われる。だが、その生き様を貫くためには、あの蔑視よ、社会の多数派による指弾から逃れ続けなければならない。秘匿すること五十年。それはなかなか堪える。やっぱりふつうがいい。医学も鼻かみを推していそうだし、他の皆もそうしているし、多くの人が選んできた蓄積があるからこそ、そのふつうが、道として踏み固められてきたのだから。
此方へ入らせ給へとて、
夫婦の者は先に立ち、かの旅人を伴ひつつ。
能《錦木》
能《錦木》は、諸国を旅する僧が、陸奥の狭布の里で土地の男女に出会い、由緒のある塚を案内してもらう。錦木の人の塚だ。昔から奥州では、恋のアプローチに色美しく彩った錦木を意中の人の家に立て置くのだという。和歌の世界でも知られる陸奥の雅びな風習だった。
この謡で、シテとツレの男女は立ち上がり、ワキの旅僧を塚へ誘う型をする。観世流では、ツレの謡「此方へ入らせ給へとて」で二人とも先に立ってしまい、「夫婦の者は先に立ち」で先導する態をとり、「かの旅人を伴ひつつ」とワキに一足詰め寄ることが多い。
ワキのこちらは、「夫婦の者は」で立ち、「かの旅人」でシテへ相応の一足を詰める。つまりワキが立ち上がるのは、謡としては一つタイミングを遅らせている。ちょうど、先立って案内する男女に引き続くような態が取れ、詞章の内容とよく添う。細かい工夫だ。
しかし、金剛流の舞台で、「夫婦の者は」でシテもツレもじっくり立たれたことがあった。しかもその後、「狭布の細道分け暮らして、錦塚はいづくぞ」とシテはワキの手を取り、舞台を対角線に斜めに出て、《田村》や《融》の名所教えのように二人並んで案内する動きを伴った。実写的で、積極的だった。異なる流儀のシテと相手をすると、同じ曲でもこういう考えの違いに触れられて面白い。
この「夫婦の者は」が向こうの立つきっかけになると、ワキが立つタイミングと同じになる。「シテと共に立つ」という型は他にもよくあるパターンだから、難しいことは考えず一緒に立てばよいのだが、謡の「先に立ち」というニュアンスが何やら惜しまれて、悩み出した。
台本や所作のレシピである型付には、大まかな動きの流れや心得が書かれている。微に入り細を穿つ指示内容が書き記されていることはむしろ少ない。不親切なのではなくて、空白は師匠に習いなさいということであり、自分の持てるものの総動員で悩み埋めていけ、という深慮である。
実際、細かく指示を書き残し過ぎると、かえって金科玉条の縛りとなって、流儀や各家で異なる型に対応できなくなってしまったり、枝葉に惑わされ根本の意図が見えにくくなってしまう。
型付や勤め書きが勝手に独り歩きしうるというのは、一般的なテキスト論と同じことだ。その危険をよくわかっている、昔の人はえらい。
《錦木》は、夫婦のシテとツレが立つタイミングから一呼吸遅く立ったほうが、道案内される感じが出るかもしれない。「シテと共に立つ」という型の範疇は守る。でも、一呼吸、わずか〇・五秒動きをずらすだけでも、意味が生まれたり演出が利いたりする。シテと相談して、申合(リハーサル)ではそのようなタイミングで試してみた。
終えて、手応えを確かめる。もやもやとした感覚が残った。やっぱりちょっと、どうだろうな、しかし意図的な感じがする。どこか作為が臭う。
結局、本番の舞台ではその工夫を捨てた。シテとツレと同じタイミングで立った。「夫婦の者は先に立ち」と謡っているのだから、変に手を加えなくてもよい、そのままシンプルに、すっきりと勤められた。シテとも舞台後に同じ感想を確認し合った。
やっぱり、ふつうが一番いいのだ。
ふつう、というのは強い。
鼻をかむふつうも、本当は私もそれが良かった。この原稿だって、そもそも「洟をかむ」と書きたいと思っている。でも読みやすさや、一般的なふつうに目配せして、「鼻をかむ」と自ら書いているのだ。
みんなと同じ、人はふつうに結構やられやすい。
では、「ふつう」とは何か。この問いは職業柄よく考える。なかなかややこしい。舞台業の人間は、堅気の仕事ではなく、生活の基準や考えが世間と馴染みにくいところで回っている。少しでも芸能史を繙けばわかることだ。人と違うがゆえの特性を、奇異の目で見られたり、文化芸術の徒として持ち上げられたり、二面性があって、ふつうを希求しながら、ふつうから外れる面白さを求められる。そういう矛盾した存在なのだ。人と同じだったら誰も振り向かないのだから。
芸人にとって、ふつうに関する問題はふつうには解決しない。この矛盾を生涯背負うのが宿命ということか。いけない、考え詰めていたら思わず鼻水が垂れてきた。
あなたは、洟をかんだことはありますか。




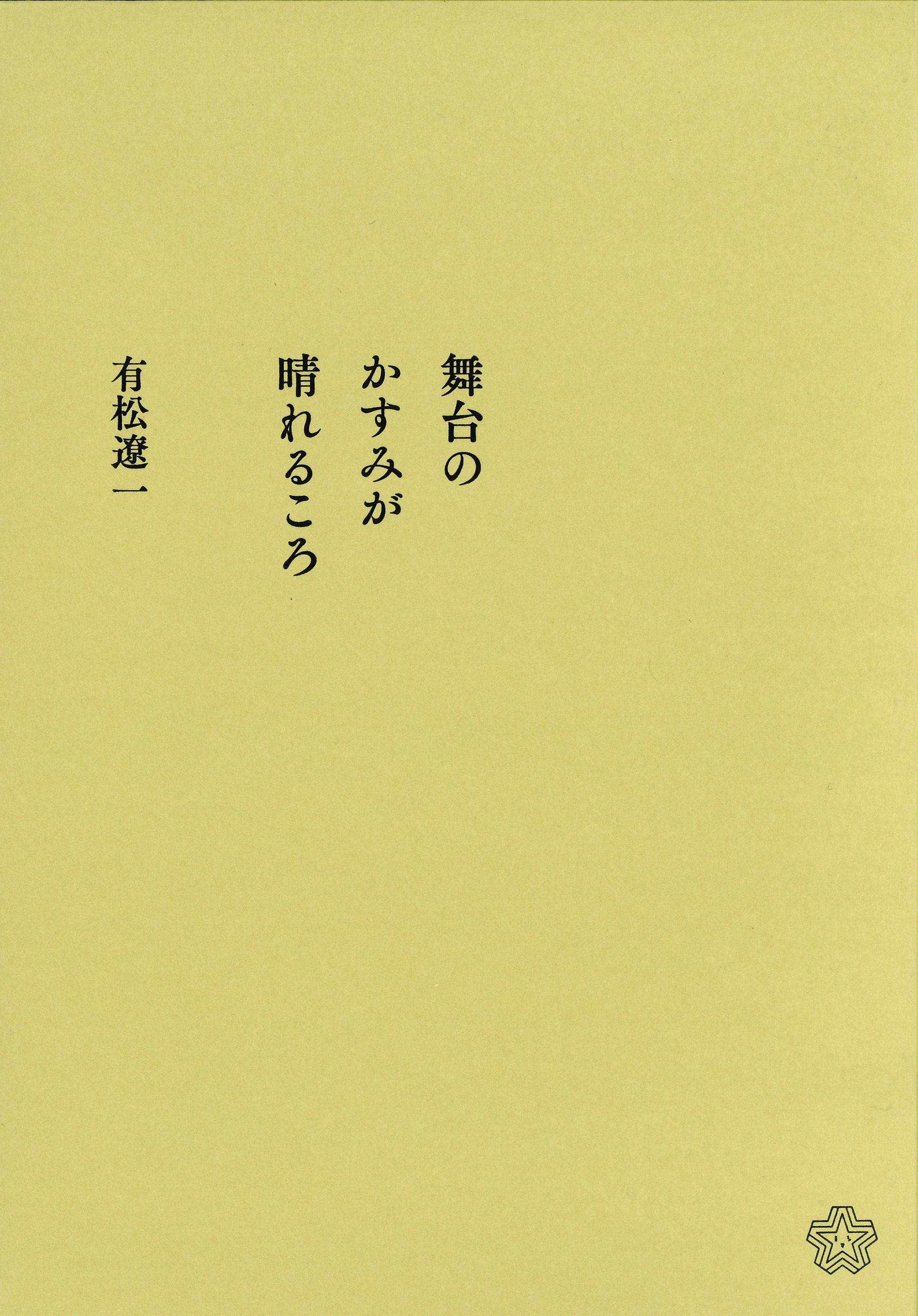


-thumb-800xauto-15803.jpg)


