第4回
視る世界
2025.12.23更新
初めて能楽堂に入ったときの印象はどうだったろうと思い返していて、記憶を手繰り寄せるのだが、どうして鮮烈な体験も何も出てこず、少し焦っている。
だいたい能楽師は、代々にそれを家業とする「家の子」が多く、物心つく前から舞台が遊び場であり、楽屋を走り回り、初舞台も三歳やそこらで勤めてしまうので、初めての能楽堂という名の記憶は薄いものだ。私は大学で初めて能を知ったので、せっかくのその原体験を奇貨としようと、思い立ったのに意外な空振りで胸が騒ぐ。
不穏だが、最初は、能に興味がなかったのかもしれない。
こんなに特徴のある劇場へ足を踏み入れておいて、と自分でも思う。
能舞台は、三間(約六メートル)四方の本舞台が客席に大きく迫り出し、四本の柱が室内ながら屋根を天に戴いている。背景の板には老松の絵。そこから左の下手へ橋掛という廊下がずうっと伸び、その先には五色の揚幕が垂れて、演者は幕の向こう、鏡の間から本舞台へと歩いて登場する。
演劇ホールのような緞帳はない。客席はL字型に広がっている。花道かと思えば橋掛は客席のエリアを貫くわけでもなし、むしろ、舞台は軽々に近寄りがたい寺社仏閣のようなオーラをまとっている。
この不思議な空間を、初見にはどのように思っていたのだろう。およそ二十年前の記憶を、丁寧に淹れたコーヒーを啜りながら辿っているのだが、一向に、コーヒーが苦いことしかわからない。
初観能の覚えは辛うじてある。能楽サークルの先輩たちに連れられて、梅田の大阪能楽会館に行った。京都ではなかった。主な対象が学生だったか親子だったかの初心者入門鑑賞教室で、半能の《船弁慶》を観た。
そういう企画だったのか、観能後に、ロビーのようなところで演者との小さな交流会があった。出演の大倉源次郎先生が交じっておられた。小鼓方大倉流十六世宗家で、能楽界の第一線で活躍されている先生だが、当時の私は、なんだかえらい先生が下界に降りてこられ、舞台で見たのと同じ顔をしているな、くらいの貧しい感想しかなかった。先生は、今はいわゆる人間国宝である。
あまりにも残念な自分の記憶を恨む。
能楽サークルも、大学のクラスメートに誘われるまま入ったし、この観能イベントも断ることができないまま、思うに、週末ここへ連れてこられたのだろう。
他の能楽師たちが持ち得ない奇貨どころか、暗雲が立ち込めた。
人生の現実は全然かっこよくない。小説や映画のように、たとえば雷に打たれたような衝撃で斯道を志すドラマは、私にはなかった。
苦渋してコーヒーを二杯お替わりしたところで、その能楽堂の二階席から観た、妙な、能舞台の立体感覚を思い出した。印象や感想はない、無着色の記憶だが、でも二階席からの眺めは、本舞台が箱庭のような、小宇宙のような、そんな景色の味わいだった。ただただその立体感だけが、何のラベルも貼られることなく、記憶の箱に無造作に放られていた。
視覚は、改めて、人間の感覚のかなりの部分を占めると思った。
能舞台に上がる側に回っては、舞台上の景色というものは、それほど具体的ではない。
舞台では、あまり目を使っていないのだ。
いや、視界は入るし、その位置情報を自らの動きにもちろん使う。ただ、面遣いはするが目遣いはしない。視覚情報は普段の生活のものとは異なる。舞台用の目を作る。
まず、よそ目をしない。画角は広い。舞台全体を捉えるような視野を保つ。興味のある点と点をそそくさと移動させてはいけない。角膜の周りの組織を緊張させて、顔全体の表情にパーツを没入させる。
ワキは直面なので、平然の顔を作っている。
能は仮面劇であり、どんな役者も能面をかける。現実の人間の役のシテや、ワキは、能面をしないではないかと思われるかもしれないが、そうではなく、「自分という顔」の能面をかけて演じる決まりになっている。かの世阿弥も、直面は難しいと言う。
直面では、まばたきをしない。当たり前だが、能面はまばたきをしないからだ。瞼の開閉は生理現象なので止めようがないものの、まばたきをしていないと思わせることはできる。実際、お客さんに「さすがワキの方はまばたきをしませんね」とよくお褒めにあずかる。内心そんなこともないけれどと謝りつつ、でもそのように見えるのは自然だとも思っている。
ワキに多い僧侶役のときは、頭に角帽子をしていて、眉を隠すように帽子の縁を当てるので、布生地に押さえられて瞼に張りが出る。顔も緊張すると、目の見え方が日常と変わる。生身の現実世界は見ていない。夢幻能、まさに夢の中で目視するよう。対象は見えるけれども、具体的な把握はあいまいなままで、常に景色として捉える感じがある。
対象物を捕獲するような視線は、一点を見つめる目になる。直線的で広がりがなく、何を見ているのだろう、と観客に思わせる目つきである。生成りの、素に戻った目、という言い方ができようか。
ワキがシテと相対するときは、広い視野のほうがいい。シテが常座に現れ、ワキが脇座から対角線に向いて会話を始める。視線をシテの顔に当ててもいいが、ごく一点に絞ると、シテが演技で少し動いただけで焦点が外れてしまう。サーチライトのようにちょこまかちょこまか動くわけにはいかない。ワキは扇の要さながら、能舞台の軸となる存在だから、脇座から常座へ斜め四十五度に向いた姿で、広く大きな視線を舞台全体に行き届かせ、まんべんなく、シテの演技を包み込む必要がある。
うまいワキだと、その姿が、シテが舞台のどこを動いても、いずれも見守っているような横顔になる。ちょっとした身体の使い方だ。日の浅いワキは、気張って一点を凝視しているように映る。シテが大小前から正面に数歩迫り出ただけで、あらぬ方向へ見損じている態になってしまう。
この辺りが、物言わぬワキの、腕の見せどころなのだが、その要素の一つに目の作り方があるように思う。
能《大会》で、やったことのない目の使い方を実験してみた。
おとぎ話のような能である。比叡山の僧のもとに山伏姿の天狗が現れ、以前命を助けてくれたお礼に、望みを何でも叶えようと言う。僧はお釈迦さまが霊鷲山で行った有名な説法の光景を願い、希望どおり天狗の魔術によってその法会が再現されるが、敬虔な僧をイミテーションでたぶらかすなと帝釈天が降臨し、散々に天狗を懲らしめる。
「大会」は仏教語で、「だいえ」と読む。大きな法会のことで、能はこの天狗が見せたイリュージョンが山場になっている。
不思議や虚空に音楽響き、仏の御声あらたに聞こゆ。
両眼を開き辺りを見れば、山はすなはち霊山となって。
能《大会》
いつもの見慣れた山々の景色が、古代インドの釈迦の聖地へとみるみる変化していく。床几という椅子に掛けたまま、ワキは客席の表側へ斜めに向いて、辺り一面を眺める型をする。
このところで、演能中保ち続けていた直面の目を、一旦ほどいてみた。半眼ではなく、角膜を開き、眉の皺や眼輪筋をゆるめ、普段の目遣いで客席を眺めた。表情は変えない。
能舞台では、非日常の視覚をもって、能の日常の時空を生きる。これは、天狗が見せる幻惑という非日常を、かえって日常の視覚でもって眺める。そういう試みだ。面白い逆転だと思った。
具体的な把握をめぐらす視線など、なかなか飛ばす機会はない。目を本来の視界に開き、見所を見回すと、会場の客席、観客の顔、服装、緑色に灯る非常灯、赤いカーペット、この世の存在物がいろいろ見えた。
霊鷲山の雄大なスケールを意識して、少し視線を上に向ける。二階席に視線が届いた。ちらほらと若者の学生のような姿も見られた。
二階は学生券の座席も多くて、自分もこの安い席に、開場前の早くから並んで手すりの最前列でよく観ていた。もしかしてあの若者は、先輩に連れられて観能に来た学生だったろうか。その子は、これから能が好きになってくれるだろうか。自分は、思いもかけず今この板の上にいるけれど、二階席の温かい観能経験はたくさんある。よかったら、またこの能楽堂へ気軽に来てほしい。
私はあの二階席を、しばらくそのまま眺めていた。




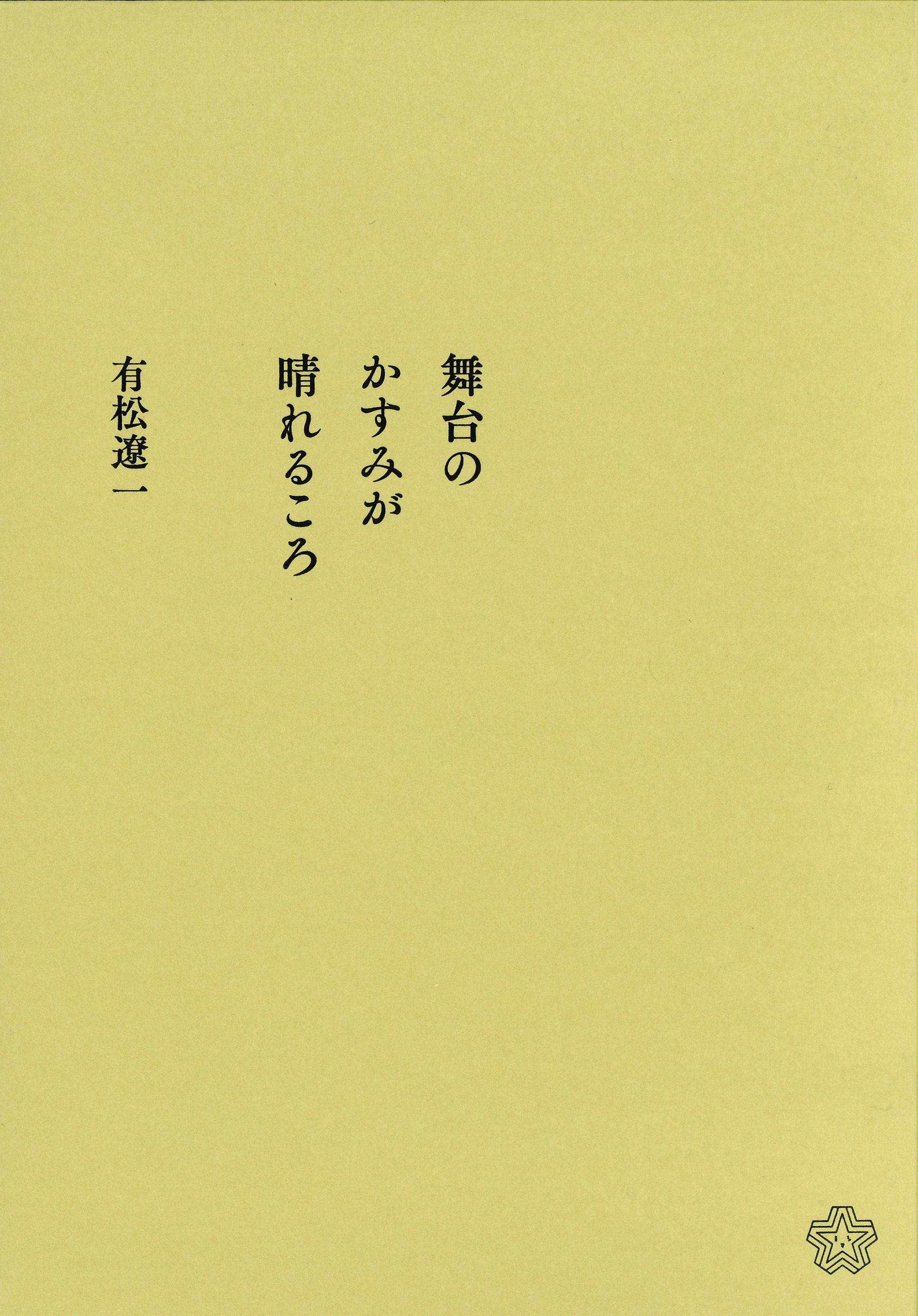


-thumb-800xauto-15803.jpg)


