『等身の棋士』発刊記念 北野新太さんインタビュー ~歴史的な瞬間に立ち会っていることを伝えたい
2018.05.08更新
2017年12月16日(土)、今年のミシマ社最後の一冊『等身の棋士』が満を持して発売となりました。藤井聡太四段の歴代最多連勝記録、加藤一二三九段の引退と人気、そして羽生善治永世七冠の誕生、国民栄誉賞検討・・・2017年はこれまでにないほど、日本中が将棋に沸き、注目した1年でした。
著者の北野新太さんは、ミシマガジン「いささか私的すぎる取材後記」にて、たびたび将棋の記事を寄稿くださり、その記事には多くのファンが。2年半前に発刊されたシリーズコーヒーと一冊『透明の棋士』は4刷まで増刷を重ね、次作を待ちわびる多くの声にお応えして、このたび新著『等身の棋士』が完成しました。
これまで、ミシマガにご本人が登場されることはほとんどありませんでしたが、今回は、初の単行本を書き終えたばかりの北野さんにインタビュー。言葉への感覚、ノンフィクションについて考えていること、そして将棋への熱い熱い想いを、語っていただきました。
(聞き手、構成、写真:星野友里、構成補助:野崎敬乃)
せっかくだから、好きな言葉だけで書きたい
―― いわゆる一般書としては初めての著書ができあがりました。普段、新聞記者として記事を書かれている感覚との違いはありましたか?
北野 おおいにありました。よく言うことなんですけど、記事と文章は似て非なるものなんですよね。立ち位置というか、公的なものと私的なものとで顔立ちのようなものが根本的に違います。ただ、僕は・・・新聞記者として言っていいことかどうかわからないんですけど、文章というものが元来好きなので、記事を書くときも、いわゆる文章的なものを記事に落とし込むように書いてきた感じがあるんです。最近ではとりわけそうです。
長いものは基本的に書き慣れていないので、文章を書くのは毎回相当に消耗しますけど、構築する過程でのスピード感も違って、ゲラ直しで「こことここを入れ替える」とか「この句点はこっちじゃないほうがいい」とかいうのを延々とやる作業は本当に面白いですね。野球のナイターの後に書く記事で「この句点は取ってください」なんて言ったらデスクに叱られます(笑)。
―― 本書の原稿のやりとりでも、「ここは平仮名にしませんか?」という提案に対して「ここは漢字なんです」とか、細かなところまで明確な意図を持たれている、という印象でした。
北野 そうですね。本書の中でも書きましたけど、僕は好きな言葉と嫌いな言葉というのがけっこうあるんです。新聞記事も、できるだけ好きな言葉によって書いているつもりではあるんですけど、さすがに新聞的な用語というのもありますし、老若男女にわかりやすい言葉を書かなくちゃいけないという意識もあります。それが本に書くとなると、制約がやや取り払われるので、解き放たれた感動があるんですよね。だったらせっかくだから、できるだけ好きな言葉だけで書きたい、というのはありますね。
あと文章の感覚について言うと、作家の横山秀夫さんにお話を伺ったときに、なるほどと思ったことがあるんです。横山さんも新聞記者出身で、一気にグイグイ読める文章を書かれる作家さんであることは皆さんご承知の通りだと思いますけど、彼は、自分の本のゲラを見るときに、まず開かれた2ページを絵というかビジュアルとして捉えて、バランスを見るそうです。
で、改行によって生まれるスペースがどうとか、ここは一文が長すぎるぞ、といったようなことを考える。すごいのは、重要な文章がページをまたがっていたりしたら、全部修正するらしいんですよ。そこまでリーダビリティーや効果のようなものを考えていると伺ってすごい! と思いました。あと点を打つ位置とかも、文章的にはココに点を打ったほうが正しいというときも、自分が打つべきと思うところに打つという考え方でいらっしゃる。とにかくスッと読めることが何よりも大事だと。横山哲学に倣いたいなと思いつつ、頑張ってみたところはありますが、さすがにページのまたがりまで考えるのは不可能でした。
―― 本書に、若い頃から、誰かを取材して文章を書くような仕事をしたいと思っていた、という話が出てきます。
北野 中学2、3年生の頃に、沢木耕太郎さんの『一瞬の夏』を読んで、「うわっ!」って衝撃を受けたんですよ。そのときに「ああ、こういう体験をして、こういうものを書きたい」という理想像を抱いたのかもしれません。あの時に抱いた憧れのまま、だらだらと生きてきてしまった、というような感じはあります。
手の届くところに誰かがいる、という距離感を書く
―― 今回の作品は、ノンフィクションにしては、著者=取材者のシンパシーを積極的に伝える書き方だと思います。自分のスタイルについて意識していることはありますか?
北野 こうやって書こうと意識しているというよりも、こうしないと書けないという面のほうが強いかもしれません。でも、いくつか理由のようなものはあります。まず、日々書いている新聞記事では、98%くらいは「私」という主語の視点が入ってこないので、書籍ではそれとは違うものを表現したいというのが、まあ・・・これは第三ぐらいの理由です。
第一の理由としては、ノンフィクションは徹底して客観的に、第三者的で、禁欲的でなくてはならないという価値観自体がそんなに常に正しいことなのかどうかがわからないということがあります。
ノンフィクションにもいろいろな種類がありますけど、それぞれに適した書き方はあります。文献を徹底的に読み込んで書くものもあるし、30年前の出来事を、当時の関係者にたくさん話を聞いて書くっていうものもある。こういう文章に書こうとするときに「私は」ってなかなか書けないですよね。でも、少なくとも僕がこの2冊(『透明の棋士』と『等身の棋士』)でやってきたことは、同時代を生きる人々のことをライブで書いていくことです。こういうことを、自分なりに人に伝わるようにして書こうと思ったときに、自分という人間を通して書くことしか僕にはできませんでした。ある意味、技術的にも、心情的にも。
「等身の」というタイトルにもつながるところですけど、実はこの本の中でも結構出てくるのは「目の前の」という表現です。藤井聡太四段が29連勝して将棋連盟の特別対局室でインタビューに答えているとき、僕と藤井君は20センチぐらいしか離れていなかったです。本当は前から写真を撮りたかったけど、背中側にいたから仕方なく「後頭部と報道陣」的な写真しか撮れなかったぐらいで(笑)。
その、目の前にいて、手の届くところに誰かがいるという距離感が将棋界にはあるんです。人と人との関係という意味合いとしての距離感も含め、それは他のスポーツなどよりも圧倒的に近いです。それを取材できて、話を聞けて、書くところがあって、自分がどう伝えられるかなと思ったときに、やっぱりそのスタイルになっちゃうんです。
―― なるほど。
北野 ノンフィクションの禁欲性みたいなものは「恥ずかしいだろ、そんなに書き手が前に出てきたら」という既存の価値観によるものである気がしていて。それはおそらく正しい指摘なんですけど、時にはそうじゃないものもあっていいんじゃないかなーというのが僕の考え方です。
それこそ僕は出発点が沢木さんの『一瞬の夏』なので、あれはもう自分が登場人物ですからね。短編でいうと、沢木さんの『敗れざる者たち』の中にボクシングの輪島功一さんを描いた『ドランカー 酔いどれ』という傑作があるんですけど、あの書き方が常に僕の理想像のような思いが今でも強くあります。実は本書の中に、あの作品に強く影響されて書いた一編もあるくらいで。
―― 第二の理由もありますか?
北野 そうですね、今はSNSとかブログとか一億総マスコミ、メディアと言われていて、誰だって書こうと思ったらいくらでも文章は書けます。将棋だって「この対局はこんなふうに進行し、こういうふうに終わりました。この2人はこんな人たちです」といったところまでは、ある意味では誰でも書けるし、発信もできるんですよね。
でも、お金を払って買ってもらう媒体に書くとき、やはり普通の人と同じように書くわけにはいかないです。取材者じゃないと絶対に書けないものを書かないと、商品にはなりません。僕は棋力が低いので盤上のことは腕自慢のアマチュアの方が書いたもののほうが確実に上、という悲しい一面もありますので(笑)、現場の空気感であるとか、ふと聞こえた言葉とかを伝えないといけない使命感はあります。
僕はそれこそ中学生の頃からノンフィクションというジャンルがメチャクチャ面白いと思ってきましたし、今でも思いは変わりません。なんでミリオンセラーとかが生まれないのか不思議なくらいで(笑)。
沢木さんは・・・また沢木さんの話をしてしまいますけど、常に「どのように書くか」と模索して書かれてこられました。いろんな人がいろんなノンフィクションを書いていけば面白いと思いますし、自分も、まあ自分が書いているものが「ノンフィクション」だと上段に構えるつもりはないですけど、あるレポートみたいなものを、自分なりの思いで書いていきたいなという思いはあります。
そろそろ、一冊の中に一度も「私」という単語が出てこないものも書きたいな、とも思います。でも、同時代のライブレポートのようなものについては、いつまでも今のように書いていくかもしれないです。

初恋の『透明の棋士』から、生身に一歩踏み込んだ『等身の棋士』
―― 今年は、藤井聡太四段とか加藤一二三九段が大ブームになりました。フィーバーの渦中にいて、どんなことを思っていたんですか?
北野 それはそれはすごい、すさまじい日々だったわけですけど、連勝の記録のすごさとか、キャラクターの面白さみたいなものだけでこんなに日本中の人が沸く国民行事みたいになるかなって考えたときに、それだけではないんじゃないかと思うんです。そこにはたぶん、勝負に生きる人とか、自分たちとは全然違う世界に生きている人々の特殊性への羨望みたいなものもあるんじゃないかなという気もして。だから今、そういう人たちの将棋とか棋士に対する思いは、もっと広がる可能性がまだ開けている気がするんです。
―― 今回の『等身の棋士』というタイトルは、その可能性にもつながっている気がしますが、タイトルに込めた思いをうかがえたら。
北野 お恥ずかしい表現で言えば、出会って恋をした、初恋のような感情を表したのが前著『透明の棋士』なんです。今もたぶん、恋に落ちているような思いは変わらないんですけど、今回は、そういう対象になる人々の生身の姿というか、時には、僕らとも同じような思いを抱えたり、苦悩を抱えたりするんだな、という部分に一歩踏み込んでみた部分はあるような気がします。
―― そうですね。
北野 あと言葉としては「等身の」というのは、実はそのままではあんまり意味が無い言葉なんです。「等身大」ならポピュラーですけど。僕は、ある単語から一部分を切り取って使うのが好きなんです。本書でも、普通なら「快進撃」と書くところを「進撃」にしたりもしました。
―― 校正の方からは確認の鉛筆が入っていましたね。
北野 でも快進撃より進撃のほうが快く進撃している感じがしませんか? なぜかと考えると「快進撃」は紋切り型だから、どうしても読んだ時の印象が薄くなる。
―― ちょっと手垢が付いてしまっている。
北野 だから国語学者に言わせたら、このタイトルは赤字ですね、って言われる可能性もあるかもしれないですけど、まあいいじゃないですか、許してくださいっていう感じですね。
現場にいた人が感じたものを、そのまま「こうだ」と書きたい
北野 前著の『透明の棋士』と大きく変わっているところとして、今回は棋士の肉声がたくさん入っている、という点があると思います。その言葉ひとつひとつが彼らの等身というか、彼らの在りのままの姿であると思いながら書きました。前著もそうなんですけど、こういう思いを吐露しながら書いたようなスタイルの本だと「誇張しちゃってさ」とか「神格化しないで」という読まれ方もすると思うんですけど、正直言って、誇張しようとか、10のものを50とか100として強く伝えようという気持ちは一切ないです。本来あるものをそのまま伝えようとしたから「等身」ということになったのかもしれないです。
さっきのノンフィクション論にもつながりますけど、ものすごく魅力的な人がいたり、ものすごく劇的なことが起きていても、あえて抑えて書く、みたいなことが今までのノンフィクションにはあったと思うんですけど、その劇的性とか魅力とか、現場にいた人が感じたものっていうのを、そのまま「こうだ」っていうふうに書きたいなと思ったんです。
だから「等身」というのは文字通りに等しいサイズ、そのままなんです。僕が飛躍させたとかデコレートしたものではなくて、本当にこのままだからすごいんですよ。将棋という世界や棋士というものは。
―― 棋士たち自身の等身と、筆者や読者と棋士たちが等身であるというのと、筆者の書いている文章と棋士たちのすごさが等身であるということ・・・三重くらいの等身ですね。
モーツァルトのライブを最前列で見ているようなもの
北野 本書の中で、羽生善治さんが目の前で汗をかいている、という話も書きましたけど、これ、考えてみるとものすごいことなんです。30年も前にトップに立った人が未だ戦っていて、永世七冠をかけるような真剣勝負の場にいることのすごさがあって、で、自分がその場に居合わせる幸福みたいなものがものすごくあるんです。
モーツァルトがそのへんのライブハウスかなんかのコンサートをしていて「これが僕の新しい曲です」って言ってメロディーを奏でているのを最前列で見ているようなものなんですよ。また大げさな、と言われると思うんですけど、意外と大げさすぎることもないとも思っていて。
将棋の今のルールや制度みたいなものが原型的に始まったのが400年くらいなんです。モーツァルトが生きていたのは200何十年か前ですよね。将棋の400年間の歴史の中で、羽生さんくらいに、その時代において屹立した人、長きにわたって活躍した人、後世に影響を与えた人っておそらくいないんです。
そういう人がまだ現役でいて、それを目の前で見られるってことはモーツァルトの新曲を聴くようなものなんですよね。で、この曲にどんな気持ちを込めたのか、とかを尋ねることができてしまう。たぶん羽生さんならば、丁寧に語ってくれる。だから書ける。書けば「へえ、羽生さんはそんなことを考えていたのか」って興味を持って読む人もいるはずで。その、ものすごさのようなものが伝わればいいなと思います。
―― 皆さんに知ってほしいですよね。今すごいことが起きているって。
北野 起きてるんです。特に2017年は、加藤九段がいて、藤井四段がいて、羽生さんがまだトップでいてっていうことが奇跡的に重なった、輝ける時なんですよね。
それこそ、本書にも書いたことですけど、マリリン・モンローとジョー・ディマジオが結婚して離婚した1953年に加藤先生は学ランを着て実戦を指しているんです。その人が64年後の今年、まだ現役で、目の前にいる若い棋士を「俺のほうが強いんだ」と倒そうとしていて、その数日前には、14歳の藤井さんが新記録を懸けて戦っている、という、これを歴史と言わずしてなんと言おうか、なんですよね。
―― 読者の皆さんにも、ぜひその歴史を堪能していただけたらと思います。
北野 僕がその役割の一端を担うべきなのかどうなのかとかは、実は今もわからないままです。僕は将棋界における取材歴も浅いですし、棋力も圧倒的に低い。将棋の取材をしながら芸能の取材までしているような人間です。だから「将棋界ってこんな世界です、棋士ってこんな人たちです」と書く資格があるかどうかはわからないんですけど、勇気を持って一手を指さないと前には進めません。だから、新聞記者なんぞがトークショーをやる、みたいなこともぜひあたたかい目でお許しいただけたら幸いであります。
―― ありがとうございました(笑)。



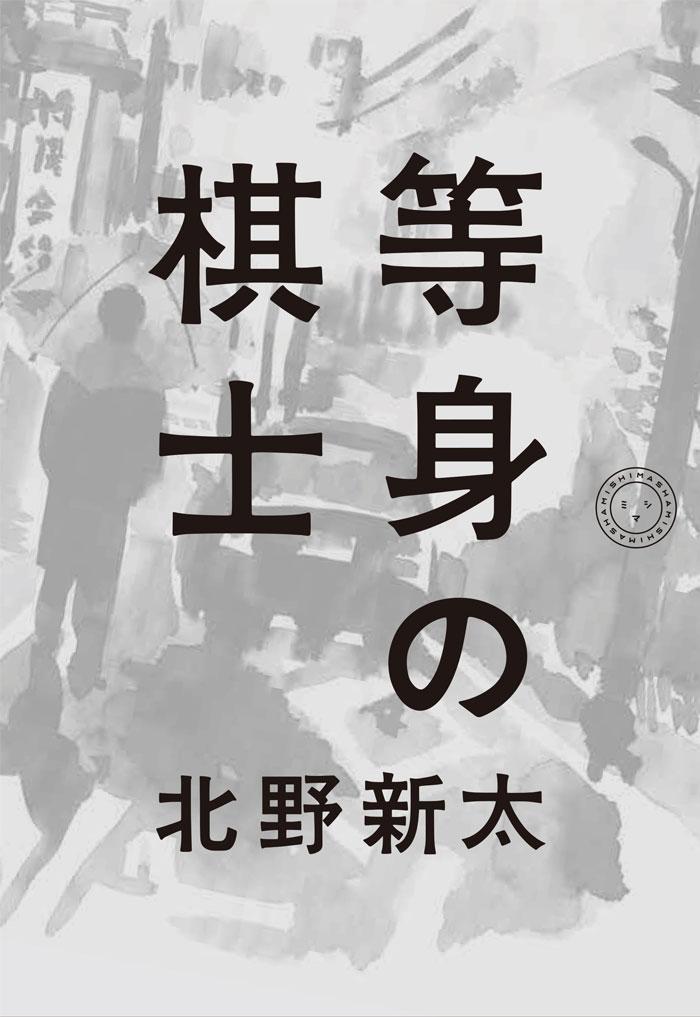

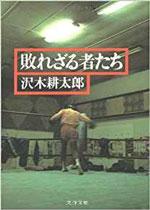
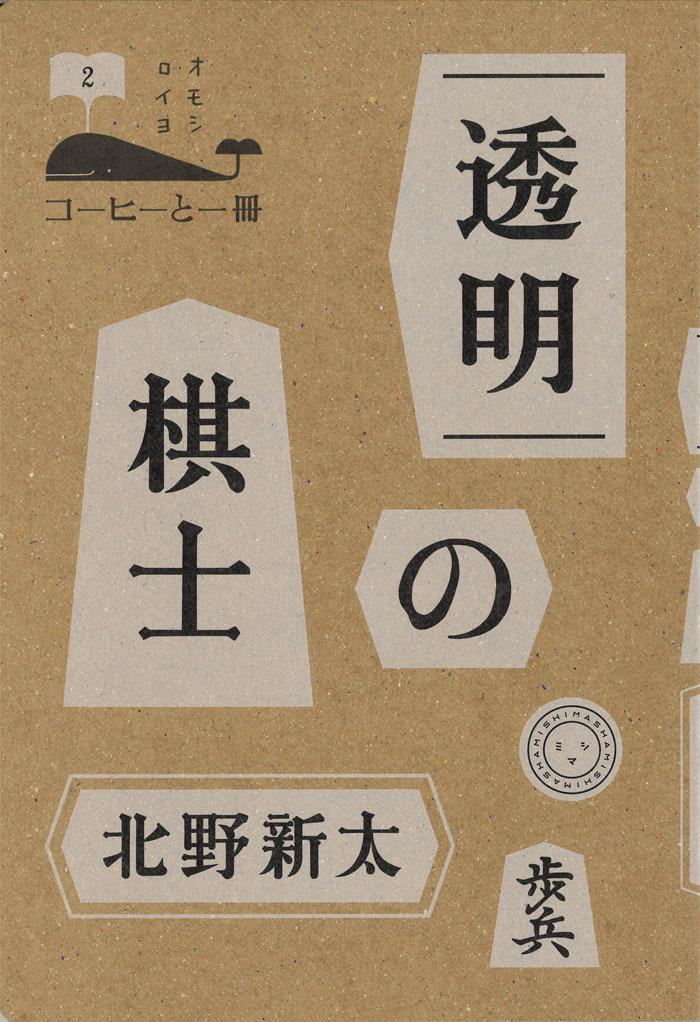


-thumb-800xauto-15803.jpg)


