第13回
戦争のさなかに踊ること─ヘミングウェイ『蝶々と戦車』
2024.05.16更新
海の向こうで戦争が起きている。
インターネットはドローンの爆撃を手のひらに映し、避難する難民たちを羊の群れのように俯瞰する。ウクライナではロシアの侵攻から2年も経過しながら未だに戦争終結の物語が見えず、ガザでは非道な爆弾が市民たちを追い立てている。
イスラエルのガザ侵攻は、西欧世界に深く根付く差別主義的な思想と植民地的な領土変更の変奏であって、帝国主義を彷彿とさせる非人道的な虐殺が行われていることは言うまでもない。そもそもロシアのウクライナ侵攻も、領土変更を目論んだ二十世紀的な戦争の復古であることの衝撃を世界に与えたものだった。ロシア国内の反発に対するプーチン政権の権力は凄まじく、批判者の子どもを含めた家族ごと消息がつかめなくなる事案も報告されている。
「平和」な日本に住みながら、世界ではかくも残酷な戦争が今まさに起こっている。いったい僕たちに何ができるのだろうか。
「戦争だって?・・・そんなものはとっくに始まっているさ。」
押井守は映画《機動警察パトレイバー 2 the Movie》(1993)で、荒川というどこか胡乱な諜報員の男にこんなセリフを語らせている。それは、主人公の警部補が国内で起こったテロに対してこぼした「戦争でもおっぱじめようってのか?」という言葉への返答だった。
「戦争だって?・・・そんなものはとっくに始まっているさ。」
「この国のこの街の平和とは一体なんだ?〔・・・〕今も世界の大半で繰り返されている内戦、民族衝突、武力紛争。そういった無数の戦争によって構成され支えられてきた、血まみれの経済的繁栄。それが俺たちの平和の中身だ。戦争への恐怖にもとづくなりふりかまわぬ平和。正当な代価を、よその国の戦争で支払い、そのことから目を反らし続ける不正義の平和。」
「その成果だけはしっかりと受け取っていながら、モニターの向こうに戦争を押し込める。ここが戦線の単なる後方にすぎないことを忘れ、いや忘れたフリをし続ける。・・・」
《機動警察パトレイバー 2 the Movie》
戦争はいま始まったことではない。第二次世界大戦という人類最大級の戦争の後に「冷戦」という戦わない戦争のイメージが流布したせいで、僕たちはしばしばそれを「戦後」と呼び、あたかも戦争が一時停止したように思ってしまうが、実際はそうではない。
「ヨーロッパの外側」では、常に戦争が起こっていた。60年代から70年代には激しいベトナム戦争やナイジェリア内戦があった。70年代にはやカンボジア内戦があり、80年代のスーダン内戦やモザンビーク内戦があった。これらの内戦はいずれも死者100万人を越えている。90年代には湾岸戦争がはじまって、中東地域の不安定性や日本の軍事出兵が話題になった。
僕たちはずっと戦争をしていて、その距離感だけが常に変わっている。押井守の言葉を借りれば、戦争がなかったのではなく、僕たちは戦争の「後方」にいたにすぎない。
イスラエル・パレスチナ紛争において、今年だけで既に3万人近くの死者が出たという報道もあった。私たちはこの空虚な数字をどのように悲しめばよいのだろうか。イスラエルという欧米の思想的関心が非常に高い問題に起因する中東地域の紛争は世界中で話題となり、日本でもそれにならって報道されるが、逆にアフリカの紛争などは大きく報じられることは少ない。
アフリカの紛争は凄まじい。およそ100万人が犠牲者となった1994年のルワンダの虐殺については知る人も多いが、たとえばベルギーの植民地支配にあったコンゴ民主共和国では独立後に内戦が勃発し、驚くべきことに1998年以降で500万人以上の死者を出している(第二次世界大戦以降の紛争による最多死者数だ)。言うまでもなく、アフリカ諸国における紛争の大きな原因はヨーロッパの植民地支配と領土分割による民族分裂だ。宗主国は民族を勝手に分割し、自国に都合のよい特定の民族や組織に武器を与え、無法状態を利用して統治した。
当然のように独立後も紛争が続く。荒れ果てた国家において国内難民となる子どもたちは貧困にあえぎ、低賃金重労働で搾取されるか、生き残るために武装組織に所属して生を送ることになる。イギリス(とエジプト)の南北分割統治を遠因とする南スーダンでの紛争は昨年2023年にも激化して現在なお続いている。国内人口の約半数にあたる2400万人が人道支援を必要としており、2024年の現在でも、少なく見積もって600万人が国内難民となった上に亡命もできていない。
ヨーロッパの繁栄、あるいはアメリカの繁栄、そしてそれを十分に享受した日本の繁栄は、少し歴史を拡大して眺めると、アフリカ諸国や東南アジア地域への植民地主義による搾取によって成り立っている。そしてその後遺症による傷は、いまだに現地で血を流し続けている。たしかにそれは「血まみれの経済的繁栄」と呼ばれるべきものかもしれない。
見えにくいかたちで常に生じている世界の悲劇。現実の過酷さとしての戦争を考える時、そしてその無力を思う時、僕はいつもある小説を思い出す。アメリカの作家アーネスト・ヘミングウェイの短編『蝶々と戦車』だ。
肉体よ越えていけ
ヘミングウェイの『老人と海』を読んだときに驚いたのは、そのタイトルのイメージとはかけ離れた肉体的な存在感だった。高校生の頃になんとなくタイトルから想像していた『老人と海』は、老齢の穏やかな老人が静かな海で悠々と釣りをしている、というものだった。しかし実際に読めば分かるように、『老人と海』は筋肉隆々の力漲るタフな老人が、腕に血を滾らせながら巨大なカジキやサメと対決する激烈な小説だった。
僕は冗談交じりにこの小説を「筋肉小説」と言うこともあるのだが、実際にヘミングウェイその人もタフで闘争的なイメージの強い作家だ。ウディ・アレンの映画『ミッドナイト・イン・パリ』は1920年代のパリにタイムスリップした作家を夢見る青年が、華やかなるパリの夜に文学のスターたちに出会っていく物語だが、そこに登場するヘミングウェイは、文学について語り合おうと興奮する青年に、真顔で「お前はボクシングをするのか」と言い出すのには笑ってしまう。
ヨーロッパが近代に確立したのが自律した強き精神=自我だったのに対して、アメリカが近代に頼ったのは、肉体による自然の克服だった。千年王国を建設するのだというプロテスタントの新たなる宗教的な使命を抱えて新大陸に乗り込んだピューリタンたちは、神の崇高なる使命を仰ぎ見ながら、実際には未開拓の過酷な自然をその肉体労働によって耕して開拓するという力技によってその国のアイデンティを形成していった。
自然の象徴たる海や魚と、一人の人間が腕っぷしで対峙する『老人と海』がアメリカ文学を代表する作品になっているのは、こうしたタフネスの象徴こそアメリカ精神だという国民性の現れでもある。
スペイン内戦と水鉄砲
一八歳で第一次世界大戦に参加したヘミングウェイは、生涯を通じてさまざまな戦線の取材に赴く。過酷で激しい戦争の物語を多く書いたヘミングウェイは、たしかに肉体の力強さ、意志の強さ、物質的な力の強固さを描き続けてもいたが、その裏側では常に人間の脆さを理解する繊細さを持っていた。
『蝶々と戦車』という短編小説は、ヘミングウェイが内戦中のスペインにいた際、自分で経験したのか現地の人に聞いたのかは定かではないが、実際に起こったらしい事件をもとにした小説だ。
内戦が続くある日、男がバーに寄って酒を飲んでいると、酔っ払った一人の男がふざけながらウェイターや客に水鉄砲を撃っている(その水鉄砲には、香水がつめられていた。男は皆に香水をかけていたのだ)。はじめのうちは笑っていた者もいたが、ある別の男は苛立ちが募り、水鉄砲の男にやめろと警告するが、男は止めない。数人の男たちがついに本気で怒り出し、水鉄砲の男を裏手に連れて行く。ガツンと物音がすると、顔から血を垂れ流した水鉄砲の男が出てくる。シャツも引きちぎられてボロボロになり、顔面を殴られた男は、それでも水鉄砲で水をかけることをやめなかった。そしてついに一発の銃声が聞こえる。水鉄砲の男は本物の銃に撃たれ、死んでしまうのだ。
スペインでの戦争は二年目に入ったところで、街は敵の包囲下にあった。人々は酒を飲んで楽しんでいたが、本当は誰もが緊張していた。水鉄砲の男は、この緊張に穴を空けようとしていて、その硬質な空気に打ち返されたのだった。ヘミングウェイはこの情景に「蝶々と戦車」という言葉をあてた。
「彼の陽気さが、戦争の深刻さとぶつかったんです。さながら蝶々みたいに──」
「ああ、たしかに蝶々みたいだったな。」私は言った。「蝶々に似すぎてたよ」
「これは冗談で言ってるんじゃありません」支配人は言った。「おわかりですか?あれはちょうど、蝶々と戦車みたいなものだったんです」
『蝶々と戦車』、一五三頁。
極度の緊張とストレスのなかで、すべてが戦争の空気に包まれている。深刻な世界の状況に自らも深刻になるのではなく、それに反論するのでもなく、ただふわふわと蝶々のように浮遊して踊ること。それが水鉄砲の男がしたことだった。この話の肝は、緊張する空気のなかで男がただふざけたことではない。その凄みは、水鉄砲の男がいちど殴られてもなお水鉄砲をやめなかったところにある。つまり彼のふざけた態度は、単なる思いつきやその場の気分で行われたのではなく、顔面から血を流してでもやめなかった「決死の踊り」だったということだ。
はたから見ると、ふざけているように見える蝶々のような酔っ払いのダンスは、命がけのダンスだったかもしれない。本来は同じ国に生きる仲間であるはずの男たちに殴られ、血だらけになりながら水鉄砲で香水を撒き散らせていた男の心の中は分からない。彼は死にたいほど不安だったかもしれないし、誰かを殺したいほど緊張していたのかもしれない。それでも男は、暴力という戦車に向かって、蝶々のように踊り、そして撃たれて死んでいった。
本当に恐れるべきは、権力でも反乱でもない。僕たちが真に恐れなければならないのは、思考や振る舞いの単純化と硬直化である。戦争を引き起こすのは、誰もが一つの方向しか見なくなるという一様化であることは歴史が証明している。水鉄砲の男はまさにその一様なる力に殺された。
誰もが同じ方向を見ているときに、一人ただ別の風景を見ようとすること。それこそが真なる抵抗ではないか。賛成であれ反対であれ、一様なる振る舞いほど権力にとって利用しやすいものはない。不安と、矛盾を許せない心は不可避的に単純化する。僕たちは、それがいかに脆弱なものであろうと、逡巡を抱えた複雑な心、その結果として生まれる、わけのわからないふざけた行為、愚行、逸脱。これを許容して維持していくことが必要だ。真面目だからといって真摯であるとは限らず、愚行だからといって真剣でないとは限らない。水鉄砲の男は本気で愚かなダンスを踊ったのだから。
ヘミングウェイの目
この小説を読む上で、もうひとつ重要なことがある。それは、この小説が全くの創作(フィクション)ではなく、実際の出来事をモデルにした物語だという点にかかわる。つまりヘミングウェイは、実際にスペイン内戦やこの物語そのものの内部にいる「当事者」であると同時に、それを作品として書く外部の「観察者」でもある、という二重性をもった微妙な立場にいるということだ。
ヘミングウェイの偉大なところは、この水鉄砲の男を見つけ出す冷静な目を持っていたことではないか。現実の緊張に取り込まれた酒場の人々、またそこに穴を空けようとした水鉄砲の男、その関係性の全体を捉える繊細で冷静な目をヘミングウェイは持っていた。彼は取材のためにスペイン内戦に関わったが、記者だったから冷静だったのではない。むしろ彼は戦争という現実に実存的にコミットしていた。
ヘミングウェイはファシズムに対抗するという決意が強く、1944年の連合軍ノルマンディー上陸作戦に随行した後、パリでは自らフランス軍自由パルチザンの兵士らを率いて指揮している。スペイン内戦にも通算で八ヶ月もの間滞在したヘミングウェイにとって、戦争ははじめから記者として観察する客観的な対象ではなく、スペイン人民を守るという正義感を持つ、自分にとってリアルな問題だった。つまり彼にとっての「敵」や「味方」が明確に存在していたし、その意味で十分に政治的意志を持っていた。それにもかかわらず、現場の空気に飲み込まれなかった。そして彼は、敵でも味方でもない、政治的でも反政治的でもなく、ただそれらからすべて離れて踊る水鉄砲の男を見つめることができた。
その意味で『蝶々と戦車』という小説の仕掛けとしての面白さは、このタイトル「蝶々と戦車」はこの事件の顛末を語った酒場の支配人が考え、作家であるヘミングウェイにそのタイトルで作品にしてくれと頼むというところにもある。しかもヘミングウェイはそれを、気に入らないがしょうがない、といった面持ちで受け入れる。おそらくヘミングウェイは、自分でこの事件を表現するイメージ豊かなタイトルを思いついたのだが、それを真っ直ぐに書くことを躊躇い、その躊躇いそのものを作品のなかに書きつけた。
ヘミングウェイが躊躇ったこと、それは「象徴化」だろう。現実の複雑で表現しがたい空気を、イメージによって固着させてしまうこと。その功罪を彼はよく知っていたのだと思う。それは、すべての表現者が抱える矛盾でもある。この眼の前に存在し、現象するこの世界をなんとか表現したい、しかし表現することによってそのリアリティが象徴化されて失われてしまう。すべての作家はそのパラドックスを抱えている。
かつてヘミングウェイは、『老人と海』の老人が三日三晩の魚との戦いを終えた後に、マストを抱えて丘を上るシーンをイエス・キリストの受難と重ねる寓意的解釈を含んだ批評に対して「海は海、老人は老人。〔・・・〕世間で言うシンボリズムなどはゴミです」と答えている。彼は安易な象徴化・シンボル化を拒みながら、それでも世界を自分の目というフレームで捉え続けた。
パラシュートとアサガオの花
同じくスペイン内戦を描いた『戦いの前夜』という小説は、主人公が映画監督で、戦争の現場を撮影する話だ。主人公の男は凄惨な戦争の場面を俯瞰したカメラでショットに収める。「小説にしてくれ」と頼まれた作家と同じように、リアルな現場をひとつの冷静な画面に切り抜くことが求められる。
爆音と共に爆撃機が飛来すると同時に、丘の頂にもくもくとたちのぼる硝煙や土煙をとらえるのにも、遠すぎはしなかった。けれども、八百メートルから千メートル離れた地点から眺める戦車は、せかせかと林の中を動きまわって小さな閃光を吐く、泥のこびりついたカブトムシのようにしか見えない。その背後に従う兵士たちは、さながら玩具の兵隊で、それが地面にぴたっと伏せては起きあがってしては走り出し、また地面に伏せては走り出すのだ。
『戦いの前夜』、一六一頁。
カブトムシのような戦車と玩具のような兵隊。距離をとって眺める戦争の現場は、まるでゲームのように映る。そこでは人が撃たれ、死んでいるのに。興味深いのは、一方では象徴化は現実を貧しくしてしまう効果も持つのと同様に、他方では現実を美化してしまう効果も持っている。『戦いの前夜』では、被弾して燃え上がる戦闘機の中から脱出する仲間たちを見た兵士の語る言葉が印象的だ。
あれはまるで、溶鉱炉の中を覗いているような感じだったな。それから搭乗員たちが脱出しはじめたんだ。おれは半ば横転しながら急降下してから、また機首をもちあげた。そして背後を見下ろすと、あの溶鉱炉の扉から、彼らが次々に飛びだしてきた。なんとか、燃える機体から離れようとしてな。それからパラシュートがひらきはじめたんだが、あれは巨大なアサガオの花が空にひらくみたいな感じだったな。
『戦いの前夜』、二〇六頁。
溶鉱炉さながらの炎と噴煙が墜落していくさなか、突如として空に巨大なアサガオの花が咲く。鮮烈なイメージだ。戦争がゲームのように陳腐に見えること。戦争が花のように美しく見えること。それは同じ象徴化の裏表でもある。
いずれにせよ、戦争という圧倒的な非日常の出来事は、私たちから現実を現実のまま受け取らせるという冷静な心を奪うのだろう。過剰にそれを陳腐化してしまうか、過剰にそれを劇化してしまうか。それは、どこか現実の拒絶による幻想化なのかもしれない。戦争は現実感をなくすということをヘミングウェイはよく知っていた。数々の戦争に随行した彼は、それゆえにその空虚さとリアリティをどのように表現するかということをいつも考えていただろう。
「半−当事者」の芸術
僕たちは、あらゆる悲劇の当事者になれない。しかし、純粋な当事者ではないからこそできることもあるだろう。当事者は常に現実を生きることに必死だ。酒場で水鉄砲の男を殴り、殺した者も必死だった。当事者でありながら、苦しみを蝶々のダンスに変えることができた水鉄砲の男は奇跡的だったかもしれない。
戦地に生きる人々は誰もが必死だった。その現場のどうしようもない残酷さを、記憶し、伝え残したのが、純粋な当事者ではない人間、すなわち「当事者/観察者」の二重性を抱えた、いわば「半−当事者」であるヘミングウェイの冷静な目だった。彼の文学というフレームだった。フレームを与えることに躊躇いながらも、名付けようとすることの暴力性を自覚しながらも、それでもそれを象徴化する距離感に敏感であることによって、文章と表現の技術によって、当事者にはできない別の現実の引き受け方をしたのだと思う。
戦争のさなかに踊ること。その滑稽だが勇気ある人間の生を僕たちが記憶できるのは、ヘミングウェイがいたからだ。歴史は意味ある大きな出来事をしか記録しない。酔っ払って蝶々のように踊って死んでいった男など、歴史の網にはかすりもしない。しかし歴史が見逃すその些細さ、無意味さにこそ、人間にとって決定的に重要な何かがある。
すべてが現象として流れ去っていくからこそ、象徴化、フレーム化、イメージ化の力が必要なのだ。それこそが芸術・文学というものが試されている力だ。現実を損なわず、いかにその現実を再生させるのか。象徴化やイメージ化には功罪があるからこそ、その技術と意志と責任が問われてくる。
拡張された想像力のなかで
今・ここに生きる僕たちにとって重要なのは、戦争そのものであるというよりも、戦争の受け止め方ではないか。戦争の「後方」にいながら、戦争の「前線」をイメージすることはどのようなことだろうか。現在のメディア環境において、僕たちの「想像力」はいわば「強制的に拡張」されている。あらゆる真偽不明の情報から、感情に訴えかける物語、情動を揺らすセンセーショナルな映像が、24時間途切れることなく入ってくる。
世界のあらゆる悲劇が、ある意味ではすべて「等価な情報」として入ってくる。すべての距離がつめられているからこそ、いったい何がリアルで何がヴァーチャルなのか分からない。何が陳腐で何が鮮烈なのかが分からない。僕たちのフレームは自らのリアリティによってではなく、ソーシャルメディアのアルゴリズムによって与えられる。そこではただ巨大な悲劇の物語が誰もを一様に包もうとする。そこにヘミングウェイがぎりぎりの目線で捉えたような繊細な現象は存在しない。
意識に流入し続ける情報と、無限に拡張され続ける想像力に対して、この身体は有限な行動しか取ることができない。いまメディア環境は、僕たちの「眼の前」ということの条件を変えた。今や世界中の出来事があたかも「眼の前」で起こっているように降りかかってくる。しかし真に今ここに存在するこの有限な身体の「眼の前」には何が存在しているのか。本当の身近な、僕たちにとって、いやそれぞれのあなたにとって、切実な問題とは何だろうか。
あらゆる出来事が連関しているならば、この身体のすぐ隣にも、遠い場所の途方もなく巨大な悲劇の一端が確実に存在しているはずだ。巨視的で複雑な世界のパワーゲームを観測しながら、微視的で繊細な眼の前のディティールを見失わないこと。巨大な悲劇のまわりまわって生じている幽かなる悲しみの兆候を引き受けること。それこそが僕たちが応えられる真摯さではないか。
意識は原理を求める。意識は言語というデジタルな道具を媒介に思考するからだ。言語は僕たちに、賛成か反対か、敵か味方か、白か黒かを問い詰める。しかし身体は原理に対応しない。すべてが曖昧でグラジュアルで、どこか一箇所に明確な線を引くことはできない。時に風に吹かれ、大地に揺れる。あるいは逆走し、逸脱する。そのような自由と不自由の曖昧な境界を漂う感性が、言語に埋め尽くされたこの世界において守られなければならない感性であるような気がする。
戦争という巨大な物語の端っこで、たった一発の凶弾に倒れた蝶々。それを見つめたヘミングウェイ。あまりに些細な出来事にこそ宿る、小さな真理を見つめて僕は生きたい。
参考文献
ヘミングウェイ,高見浩(訳)1966.『蝶々と戦車・何を見ても何かを思い出す(ヘミングウェイ全短編3)』,新潮文庫.


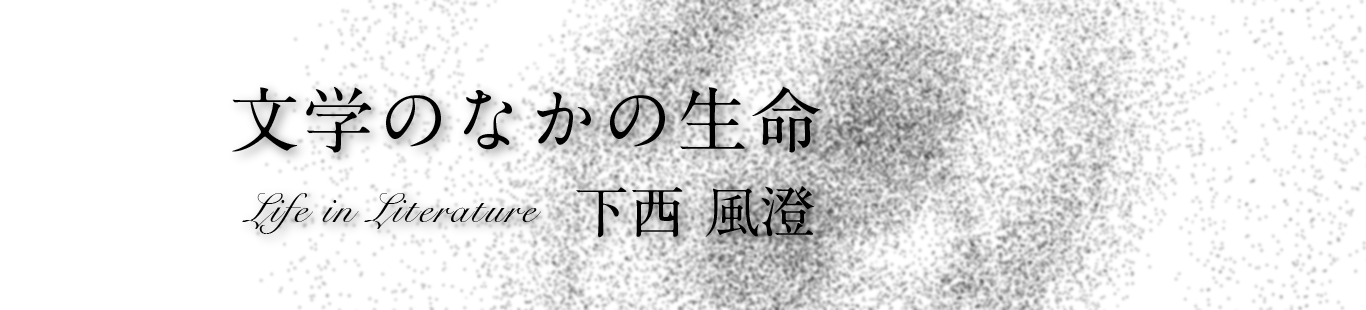






-thumb-800xauto-15803.jpg)
