第1回
私のアバロン
2025.07.25更新
「変な人についていったらいかんよ」
昭和生まれの私だって、一応そう言われて育った。というのも、登下校がかなりの山道だったので、リアルに変質者にしょっちゅう遭遇していたのだ。
「変」にもいろいろな変がありますからね。43歳になった今、甥っ子たちから見ると、私もかなり変な人らしいのです。ある種「変」というのは褒め言葉でもあるよね。
「高橋さんの人生において、東京に出たことが大きかったですか?」と聞かれることが多いが、思い返すに18歳までに出会った地元の大人たちの個性豊かだったことよ。私がついていった人たちは、大分風変わりだった。
バンドに熱を注いだ20代。チャットモンチーでのデビューをきっかけに上京し、大学の頃に作った曲も多くの人に聴かれるようになった。その一つに、高校時代の塾を舞台にした「湯気」という曲があった。作詞者は私。
「いやいや、平成にこんな雨漏りする塾ないでしょ! リアリティさなすぎだよー」
と、プロデューサーに笑われ、そうかあの塾はやっぱり特別だったんだなと思った。
雨の日は金だらいやバケツが何個も並べられ、トイレまでの廊下を歩けばベコンとへこんで、〈雨漏りの音ポツリポツリ響く部屋で先生はうたた寝〉な塾。
先生は80代のおじいさんで、高校の数学の先生を退職したあとに自宅の離れで塾を開いていた、というのは小説なんかでもよくある設定だが、先生は高校教師をしながら副業で塾の先生を始めたそうだ。近所の人から「息子が数学ができんから教えてほしい」とお願いされたことがきっかけで始まった塾だとか。公務員が副業、やはり昭和は寛容だったのだ。そして、できない子を放っておけない先生の優しさも想像できる。
建付けの悪い木のドアを開け、土間で靴をぬぐ。小上がりの畳の部屋に入ると、ストーブでお湯がちんちん沸いていた。それを囲むようにロの字型に長座卓が並んで、学校帰りの高校生がぽつぽつと座っている。ストーブといっしょに鎮座しているのがおじいさん先生だった。
鼻の頭の赤い、まるっこくて小さな先生は、テストの点など聞かないし興味もなさそう。がんばれとか、こんな点数でどうするんだとか言われたことがなかった。
「久美子ちゃんは国語ができるんだから、数学はもう諦めなさい」
にこにこしながらそう言う。ここは数学の塾です。
なんというか、先生は人生三周目くらいの解脱感に包まれていた。受験なんて目先のことでなく、もっと遠くを眺めていればいいんだというふうに。
私は数学が苦手だった。苦手というレベルを超えて吐き気のするくらい嫌だった。不真面目でできないならまだ納得できるが、まじめに頑張ったって、どうにもこうにも数学だけは無理だった。
今思うに、高校時代は頑張りが闇雲よな。例えば、吹奏楽部で打楽器をしていたのだが、シンバルを一日200発叩くとか、ひたすら教則本を見て練習台を叩くとか、効率とかでなくただスパルタだった。今ならYou Tubeでいくらでも効率的な練習方法を紹介しているが、ネットがない時代、吹奏楽も高校野球も優秀な指導者が回ってきた高校が大会で優勝した。その先生が別の学校に移動になるとその学校が優勝した。つまり実力はほぼ一緒。ただ、限られた時間をどう使うかにかかっていた。これも闇雲に練習したからこそ分かったこと。今、私が多少器用に生きられるようになったのは、あの闇雲時代で気づいたからだ。
勉強も同じで、努力の方向を指し示してくれるのが、いわゆる予備校とか進学塾の先生だったのだろう。私の塾はあらゆる方面で雨漏りをしていた。もちろん私の数学の成績は一向に伸びない。でも嫌いでなく、むしろ好きだったから通っていた。
どういうわけか賢い人ばかりがその塾に行っていて(いや、賢いからこそ、進学塾でなくても事足りたのだろう)、わからないところが出てきて先生に聞くと、「◯◯君に聞いてみるで?」と、ほとんど話したことのない先輩が教えてくれた。
その先輩たちも、さすがこのゆるやかな塾を選ぶだけあって、高校生とは思えぬ解脱感が漂っていた。受験生感が全くない。かといってヤンキーでも、熱心に部活に励むでもなく、精神的におじいさん先生を師事して通っているように見えた。
受験と部活一色の学校生活を送っていた私にとって、ここはフジロックでいうならアバロンステージだった。LOVE&PEACE。愛に溢れていた。いや、溢れすぎていた。
近くの食堂(こちらは「サラバ青春」という曲になった食堂)で、人数分の大判焼きを買ってきてくれる太っ腹の先輩がいて、そうすると別の先輩が、
「先生、お茶入れましょうか」
「はいはい、お願いします」
となり、奥の部屋から湯呑や急須をもってきて石油ストーブの上に乗っている金色のやかんを持ち上げてお茶タイムがはじまった。みんな笑顔だった。
私たちは〈湯気でメガネ曇る人を笑って〉また〈ちんぷんかんぷんの数学〉と向き合う。謎のメロウな一体感があり、それは受験戦争とは真逆の光景だった。ここは塾と言う名のアバロン。シェルターであり、天国だった。
先生はときどき、「僕は、でもしか先生じゃけんなあ」
と言った。母に聞くと、先生「でも」なるか。先生「しか」なれなかった。という意味らしかった。私はその後教育大に進み、採用率約20倍の時代に愛媛で先生を目指したので、時代による採用率の偏りに腹立たしさを感じたりもしたが、父母の子供時代は戦後のベビーブームで教師が不足していたので、教員が大量に必要だった。戦地から戻ってきた元兵士の教師も多かったそうで授業の途中でよく戦地での話をし、恐さにリアリティがあったと聞いた。戦争を体験していない母世代と体験している教師世代で、決定的な価値観の違いがあったのだろうと思う。
ある日、私は先生に尋ねた。
「先生は、本当はどんな仕事をしたかったんですか?」
いつも静かな先生が口を開いた。
「僕はね、若い頃は、中島飛行機におったんよ」
「中島飛行機・・・確か零戦を作っていた会社ですよね」
驚いた。いつも仏のように鎮座し、うたた寝をしているおじいさん先生が、歴史の教科書にも載っている中島飛行機にいたと言うのだ。
「零戦に関わる仕事をしていたんよ」
俯き、わら半紙を切る小刀を出したり入れたりしながら、時間にしたら数分だったろう、若い頃の話をしてくれた。群馬などいろいろな場所を転属しながら戦闘機の新しいエンジンの開発にも携わっていたと言った。数学が好きで、機械工学の道に進んでいた先生にとって、飛行機に携わっていた時間は、充実したものだったのだとその表情から見てとれた。
「軍需工場なんかは空爆を受けたと習いましたけど、大丈夫だったんですか」
「ほうじゃなあ。何回か空襲を受けてな。かなりやられたよ」
それ以上のことを話そうとはしなかったし、私も聞けなかった。
ご子息の話によると、先生は高校卒業後、広島高専(のちの広島大学工学部)に進み、中島飛行機に就職していたそうだ。戦争中は海軍中尉として技官をしていたそうで、白い軍服を着ている写真も残っている。工員たちのよき上司だったに違いない。
先生は、私にはよくわからない飛行機のエンジンの話や、数学的なおもしろさを話してくれた。若かりし日、純粋に機械工学に憧れた少年だったのだ。
それだけに、敗戦後の絶望感は高校生の私にも想像できた。先生から漂う解脱感の理由がわかった気がした。ご子息によると、長男だったので農地を継ぐために地元に帰らざるを得なかったということだった。夢をおしまいにして、地元で日中は農家、そして夜間高校の先生として働く第二章が始まったのだ(そのうちに昼間学校の先生になる)。祖父母が亡くなったときにも痛感したが、人には歴史がある。先生の長い長い人生の終わりの何年かに私は出会ったのだった。
「久美子ちゃん、数学はもうええじゃないの。国語で行けるとこ行ったらええよ」
「いや、私はセンター試験受けて国立行くしかないんで、全教科いるんです」
何十回と繰り返した先生とのコント。
がんばれと言われる方が楽だった。私は、まだ諦めることに慣れていなかったのだ。
今なら、いろんな道があると知っているけれど、その頃の私には諦めた先は闇しかなかった。闇ではなくて、その先にも道があるんだよと教えてくれる人はいなかった。
夏でようやく部活が終わり、残り3ヶ月の奇跡を信じて進学塾へも行ってみた。他の教科は伸びたが、数学はやっぱり伸びなかった。それでも、なんとか受かった教育大に進んで、それなのに教師にならずにバンドに邁進した。そして今は作家をしている。まだ先生の半分ほどしか生きていないのに、生きていれば勝手に歴史ができると知った。
大学生になったある日、先生が事故にあったと聞きお見舞いに行った。賢い先輩が質問するどんな難しい数学の問題も酔拳のように、ひょいひょいと解いていたのに、先生はにこにこ笑うだけで、本当に解脱してしまっていた。悔しかった。私達はみんな先生のことが大好きだった。
デビューしたあと、お仏壇に「湯気」が入ったCDをお供えした。
東京に行ってすごい人にいっぱい会ったし、本当にフジロックのアバロンステージにも立った。でも、自然派生したアバロンは後にも先にもあの塾だけだ。
先生が言いたかったのは、諦めるということでなくて、一番好きな道を極めるほうがいいということだったのだと今ならわかる。諦めた先にも希望は絶対にあるんだから、胸を張って進めばいいのだと。きっと、そうやって逞しく生き抜いてきた人生の、最後の生徒として、私は出会ったのだ。




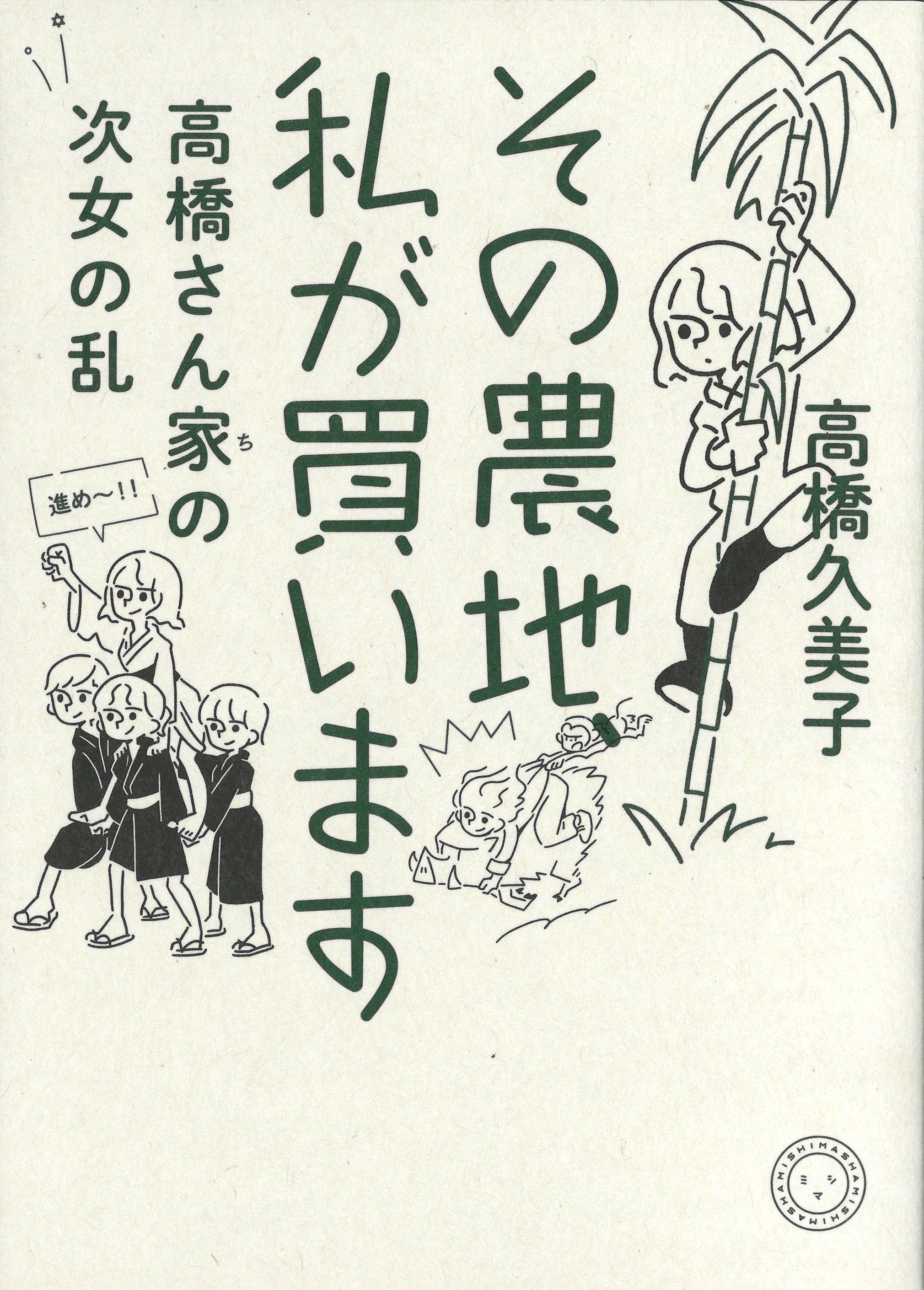
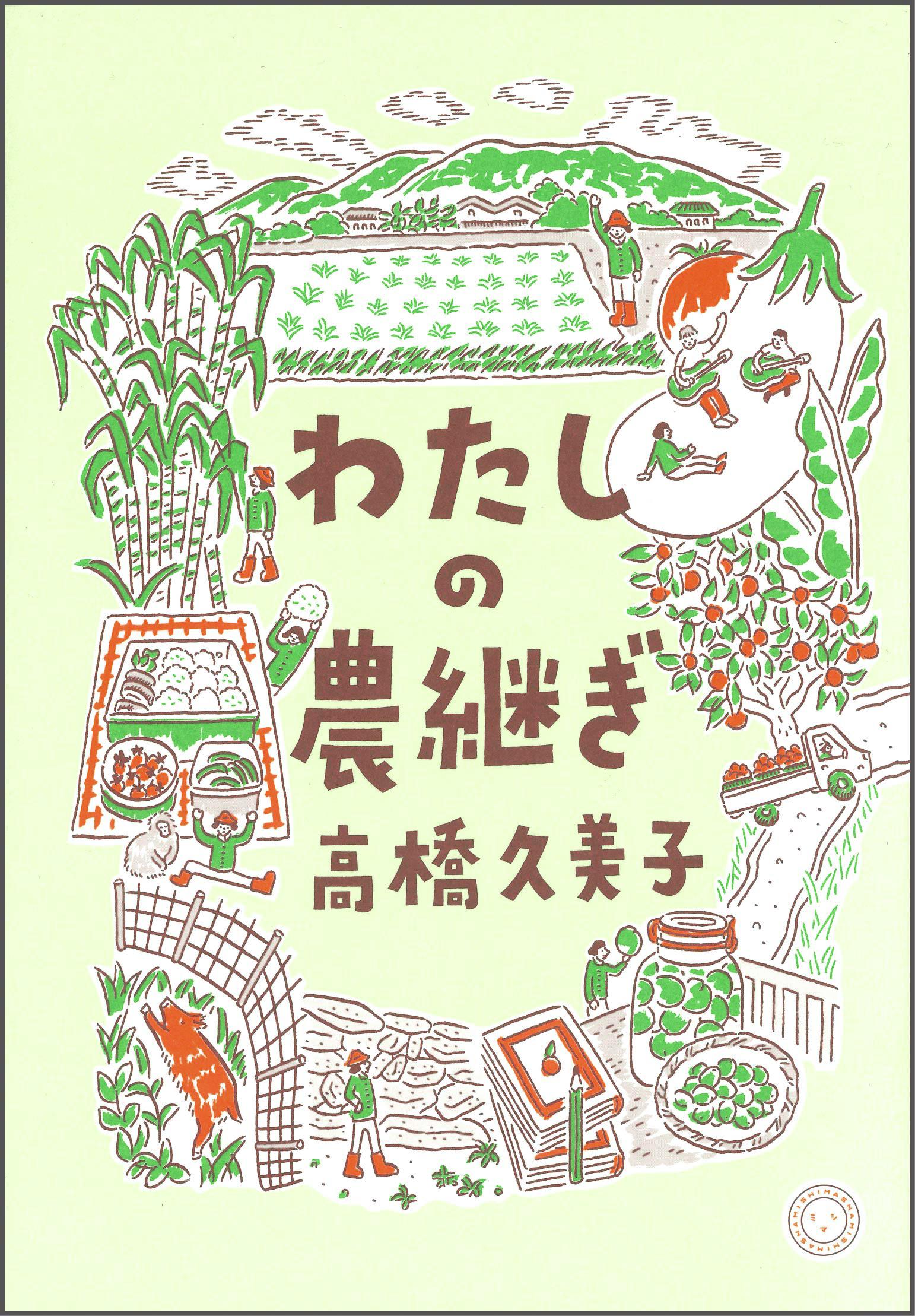


-thumb-800xauto-15803.jpg)


