第3回
それは魂の叫びなのさ
2025.09.29更新
43歳、人生も半分終わったんやなと回想してみるに、大学卒業後〜ここまで、音楽、そして文筆と、かなりエッジの効いた人々の中に身を置いてきたんだなということに気づく。
変な人について書く連載にはうってつけの業界だが、みんな、変ながらまとも、というか、まともに変というか、本やCDを出せるわけだから、やはり真面目で誠実だった。鬼才の多くが表向きはシャイで優しく、心の奥に燃えているものは作品でしか見せないというのもこの世界に入って分かったことだった。
編集や、デザイナー、校正、音楽ディレクター、プロデューサー、エンジニア、作曲家、編曲家・・・バンド時代は置いておくとして、お互いに、既に何者かになって出会った人たち。それぞれに、3つくらいトンネルを突破した先で繋ごうとしている手だった。ついていく、というか、ともに歩んでいこうと思える共通言語の備わっている人達だ。
泳いで泳いで泳いで、たどり着いた今、と書きたいが、泳いでいる途中にある今という方がしっくりくる。しのぎを削ってきた人たちと、一冊入魂で作る本は私にとって何よりのご褒美だ。自分の思いのままに作れるZINEやリトルプレスももちろん好きだけど、プロ集団が集まって一寸の隙も見逃さずに一張羅を仕上げる出版や音楽の世界の隅っこに、踏ん張っていたいと思う。
今私の周りにいる人たちは、変で当たり前だ。変、またの名をこだわりや偏り。
だから、ここで書くのはどうしてもそれ以前の出会いになる。
例えば、中高時代なら同じ吹奏楽部でも、県大会優勝を目指している人もいれば、ちょっと楽器が楽しめたらという人もいたし、全国を目指している人もいた。部員の中で目標が定まらないことが悩みの大半だったように思う。
限られた地域の限られた年齢の中でチームを組み、同じ目標を持つということは、今の私が歌詞や本を作るよりずっと大変なことだ。
楽しければいいじゃないのという人が大半の吹奏楽部の中で、一人全国を目指していたなら、変な子だねとなる。今から50年前の愛媛で、30歳を超えても女性がロックミュージシャンを目指していたら、それも変な人になる。いつだって変な人は少数派。飴の中の空気でふいに舌を切ってしまうくらいに、ひりりと痛く、気づかれにくい。
40年前のこと。
ある日、母とバスを降りて家まで歩いていると、ピアノの音が聴こえてきたそうで、3歳になったばかりの私は「くみちゃんもピアノを習う」と言ったそうな。それが私と音楽の出会いだ。家から徒歩2分のところに、音大を卒業したお嬢さんが帰ってらして、ピアノの先生をするぞと張り切っていたところだったようなのだ。
歩いて通えるところにピアノ教室、こんな奇跡あるんかいなと母も喜び、私は、まずはカスタネットでリズムを、それから赤バイエル、黄バイエルと順当にピアノ道を進んでいく。
ちょど6年ほどたったところで、先生の子育てが忙しくなって、ピアノ教室を閉めることになった。
さあ、どうしましょう。せっかくここまでやってきたしね、学校の帰りに歩いて通えるところに変わることになった。
新しい先生は、私や姉と同じ年頃の子供がいるお母さん先生で、いつもパリッと美しく、サバサバしているので、子供にも大人にも人気があった。私はめきめき腕を上げそうだったが・・・。小学校のうちは、普通にピアノバイエルや聴音の練習をしていたが、だんだんとピアノの練習をしなくなっていった。
これは誰のせいという訳ではなく、どんな道も次第に険しくなっていき、ふるいにかけられるのは当然のことである。習い事とて甘いもんではない。実際、多くの子が、中学でピアノをやめてしまう。
先生は見抜いていた。
「バイエル、おもしろくないんでしょう?」
「・・・」
「そうなんよ。この曲も、この曲も、全然おもしろくないのよ。弾いてても全然楽しくない」
そう言うと、ぺらぺらーっと教則本をとばして
「ハノン(運指練習の本)はせんといかんけど、これからは、おもしろい曲だけやろう」
と、ソナチネ(教則本)とは別に、知っている曲ばかりが入っている楽譜集を買うことになった。
そのあたりから、先生の仮面はぺりぺりと剥がれていく。そのうち、
「久美子ちゃん、ピアノ向いてないわ。ギターやってみたら?」
と言い出した。3歳からやってきたものを、一言「向いてないわ」で一蹴するの。でも、全く嫌味ではなく、むしろその目はいつも希望を放っている。
瓶底眼鏡に、制服のスカート膝丈で、生徒会役員をしている、見るからに暗めのくみこちゃんに、先生はギターを渡した。
「これからは、ギターしよ!」
「え・・・。ギターですか。やったことないけど」
「ギター弾けたらかっこええやん!」
先生は母を説得し、母もまじめ一徹なもんで、YAMAHAのごっついハードケースに入ったクラシックギターを言われるがままに買ったのだった。
今思えば、そこでアコギじゃないんかい! と突っ込みたい。中学生女子の手にクラシックギターは、ネックも太いし弦も分厚いし、弾きこなせんやろ。
そう、やっぱり、Fでつまずくし、「禁じられた遊び」は転調する前で止まるし、一向に上達しないわけなんです。
高校生になっても、私はしぶとくギターもピアノも続けていた。
「くみこちゃん、ギターも向いてないわ。大学行ったらドラムしなよ。ドラムなら絶対向いてると思うよ!」
こうして、消去法で私はドラムへと導かれたのだった。
先生は、普通の主婦の仮面をかぶった、ロックンローラーだった、ということに私はこの頃になってようやく気づき始めたのだった。先生は、ときどき、ピアノ教室をお休みにして、東京ドームへ海外アーティストを見に行っていた。深夜に、道玄坂やスクランブル交差点を歩いて、若者に話しかけて、娘に止められたみたいなことも言っていた。
特に、BONJOVIとU2がお気に入りで、アルバムも全部貸してくれた。私が洋楽を聞き出したのは、ピアノの先生からの影響なのである。
先生の仮面は勢いよく二枚も三枚も破れて、ある日、ついに別の部屋からカラフルなギターが出てきた。小さな箱も一緒に。その箱・・・またの名をギターアンプに線を繋ぎスイッチをONにすると、赤くライトが点滅する。カラフルなギターを肩からかけて、かき鳴らす先生の手、ギュアーーーーーン!!!!と、すさまじい音がした。
初めてエレキギターの音を聞いた瞬間だった。かっこよい。何もかもだ。体を突き抜ける音も、四角い箱についた英語のロゴも、そんな危なげなギターを、こっそりど田舎で弾いている先生も。自分を囲っていた壁がバラバラと音を立てて崩れていった。
「私はね、本当はこんな田舎でピアノなんて教えていたくなかったんよ」
「え・・・?」
「本当はね、東京に出てロックミュージシャンになって、エレキギターをガンガン弾いてステージで光を浴びているはずだった。男に生まれていればなあ」
先生は悔しそうに言った。
「どうして行かなかったんですか・・・」
「今ならいってるよ。でも、私達の頃に、こんな田舎で女じゃ、だれも東京行きなんて許してくれなかったんよ。それに、そんな道へ行って幸せになれる時代じゃなかった。でも、ためしてみたかったって、今でも思うときがあるのよ」
ピアノの先生である前に、先生は母親でもある。子供をもって、今がとても幸せそうでも、それでも、夢を叶えられなかったと悔やむことってあるのか。というか、今まで教えてもらったことはなんだったんじゃいと思った。
この田舎で夫や生徒のいぬ間に、ピアノの隣で、このギターを掻き鳴らしているのかと思うと、かっこいいけど切なかった。せめてピアノ発表会で弾いたらええのにと思った。
ふとあの日の先生や母を思い出すとき、二人とも今の私よりも若かったのかと、なんとも言えぬ気持ちになる。
母はどうだったろう。寿退社して家に入って、子供を育てて家を守ることだけをやり通してきた。妻、母という箱の中に入ったまんまで。自分のアンプをフルテンにして、鳴らしたい日が何日も何百日もあったんじゃないかと思うよ。本当は。
数年後、私がバンドでデビューしたとき、誰より喜んだのは、ピアノの先生だった。ロックからほど遠いところにいた私が、ロックバンドでデビューしたのは、本物のロックを間近で見ていたからかもしれない。田舎の片隅で、かき鳴らさずにいられないから、一人エレキを鳴らしてた女性がいた。「それは魂の叫びなのさ」って、どっかのロックンローラーが言ってた気がするよ。久々に教室に行くと、BONJOVIのポスターの隣に私達三人のポスターが貼られていた。
そして、私が脱退したときに誰より惜しがったのも先生だった。叶わなかった夢は、いつまでも頭上でキラキラしていて、実はそれが一番美しいのだろうなと思った。




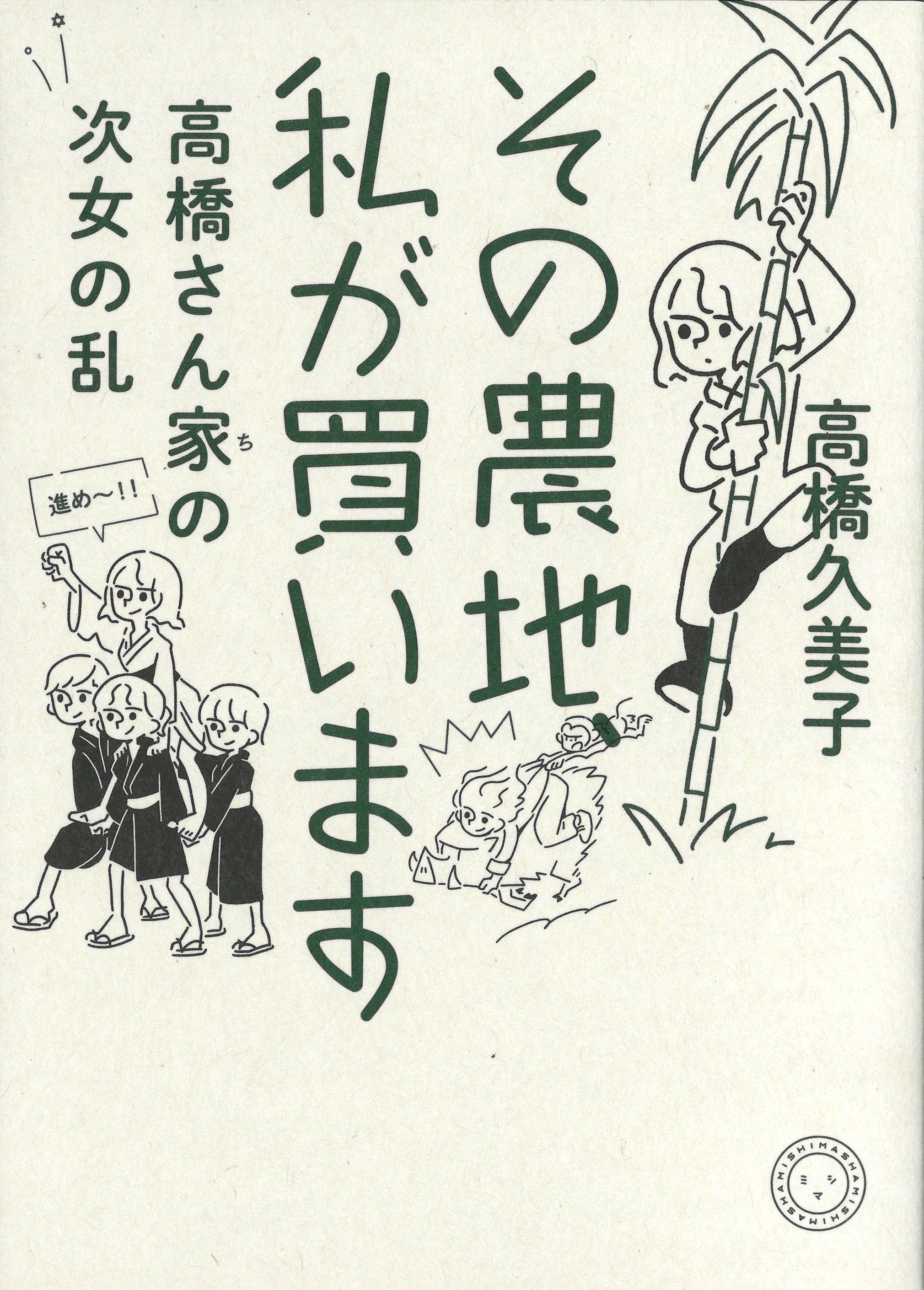
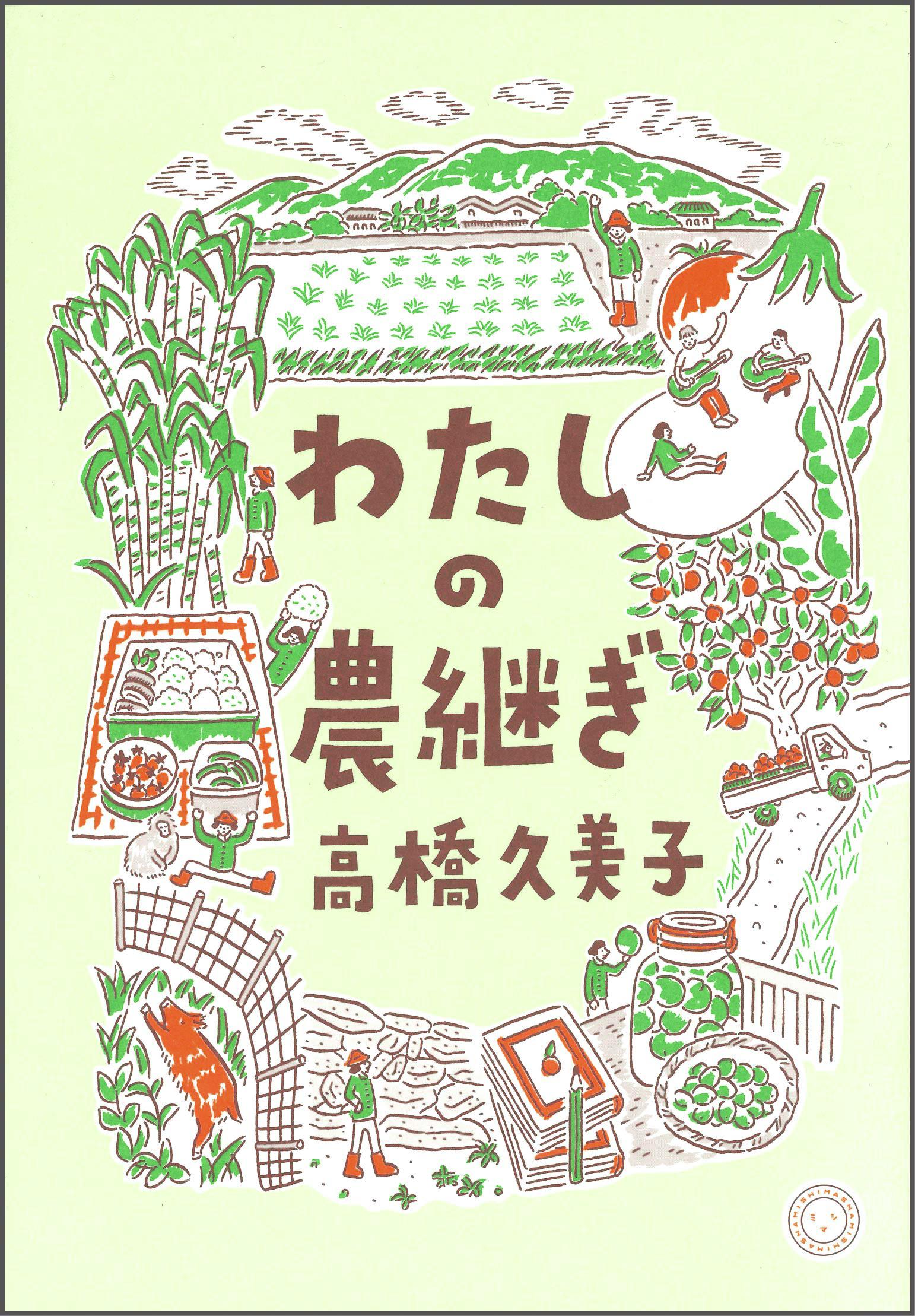


-thumb-800xauto-15803.jpg)


