第2回
黒糖BOYZふぉーえばー
2025.08.29更新
サトウキビを育て、自分たちのラインで黒糖を販売しはじめて3年が経つ。この11月には、長年温めてきた黒糖の絵本も発売されることになった(絵は加藤休ミさん!)。
いつのまに高橋は黒糖屋さんになったんじゃ。という事の始まりは、ミシマ社から出版された『その農地、私が買います』と、続編の『わたしの農継ぎ』を読んでいただけたらと思うのだが、その二部作の主要人物として出てくるのが黒糖BOYZ、私の師匠たちである。
この黒糖BOYZについていかなければ、私は黒糖作りとも、サトウキビ栽培とも出会っていなかった。
先日、今後のことを相談したいとBOYZの裏ボスから連絡があった。ついにこの時がきたんだなと思った。師匠たちの引退だった。
問題は今後、製糖場を誰が管理、維持するかということだった。「あのスーパーマンたちのあとを継ぐというのは、私には土台無理ですよ」。でも、誰かがやらなきゃ終わってしまう・・・。
今から7年前のこと。
山奥で何やら怪しい集団が、怪しそうなものを作っていると、近所で噂になっていた。昼夜煙が立ち上っているとも耳にした。妹と山を登って確かめに行くと、本当に煙突から煙が出ていた。ババババババーーーー!!! 爆音を立てて、何かが粉砕され機械から吐き出されて山積みになっていた。
「あのう、何をしているんですか?」
粉砕させているおじさんに尋ねてみた。
「ああ、黒糖を作ってるんですよ。これは絞りかすを裁断してるんです」
これが、始まりだった。BOYZと言いたくなるような、少年のままのおじさんたちが、山奥のアジトで黒糖を作っていた。
15年ほど前、おじさんたちは、かつて地域の産業だった黒糖を復活させようと町中の耕作放棄地を借りてサトウキビを作り、製糖工場を手作りで作ってしまったのだった。山奥というのが、また魅力的だった。
それから私は、山を登って製糖場にお手伝いに行くようになった。
サトウキビの甘い香り。大きな鉄釜の中で6時間かけて煮詰められたサトウキビの汁は、おいしいおいしい黒糖になった。
特に魅力的だったのは、かまどに薪をくべて製糖していることだった。
冬、凍てつくような寒さの中で、赤い炎がごうごうと薪を燃やし、釜からは湯気が上っている。いいなあ、私も自分の黒糖作ってみたいな。
お手伝いをはじめて数年後、私も自分のサトウキビ畑を持つことになった。
「火を操れるようにならんと一人前とは言えん」
とBOYZの山ぴーさんはよく言った。火が強すぎれば吹きこぼれ、弱ければアクが出きらず良い黒糖にならなかった。また、火をかきだすタイミングも非常に難しかった。たった30秒、遅れると焦げ付き、早いと固まらなかった。
「薪じゃって頭使ってくべんかったら無駄になるんよ」
それもその通り、木材集めも薪割りも、全て山ぴーさんがやっていた。一年放置してアクや水分を抜いた木を、油圧器で割っていく。薪は外の壁際に石積みのように美しく積まれていた。1釜分を製糖するにも一日燃やし続けるわけだから、20キロ以上の薪が使われた。黒糖工場を立ち上げた当初は、燃やす木が工面できず苦労したそうだ。最近では、廃材を持ってきてくれるトラックも増えた。
かまどが壊れたら耐火煉瓦を積んで直し、巨大な木桶が壊れたら当て木をし、山ぴーさんは何でも直すことができた。もしくは「あの人に頼んだらええわ」という、凄腕の仲間がたくさんいた。工場内を見渡しても、殆どのものが手作りだ。自給自足が当たり前の幼少期を過ごしてきているので、どんなこともお茶の子さいさいなのだった。
70代後半だというのに、何馬力あるんだろうと思うほど働いた。一人でサトウキビの収穫に行き軽トラに積んで工場へ帰ってきて、ノンストップで製糖の手伝いをした。石積み学校に通って技を習得し、山道の石積みをほぼ一人で直してしまったという。図書館に通って、雑草の種類を勉強し、抜くべきもの、置いても大丈夫なものの見分けもできるようになったと言っていた。ただでさえ知識と体験が豊富なのに、アップデートし続ける姿勢はまさにスーパーマンだった。
私がサトウキビ畑をはじめると、季節ごとに指導に入ってくれた。「草刈りせんと大変ですよ」と、草ボーボーの写真がメールで送られてきた。豚糞の発酵堆肥を作るおばあさんも紹介してくれたし、根切の時期は畝間にトラクターを走らせてくれた。
草刈りの日程を伝えたらいつも応援に来てくれ、サトウキビの間を高速で手刈りをしてくれた。そうして、数年間、私が一人前になるまで助けてくれた。
私は、やっと、やっと、火を操れるようになった・・・と思う。トラクターはないが、借りている耕運機で、根切もなんとかできるようになった・・・と思う。去年は、BOYZたちが不在の中、自分たちだけで製糖することができた。
できることも増えるが、年々農業が体にこたえてくるようになった。先日は草刈りでぎっくり腰になってしまったし、昨年も夏の農作業の疲れから帯状疱疹になった。BOYZたちは父より年上なのだから、重労働をするには当然タイムリミットがある。
水のタンクを持ち上げるとき、糖蜜を運ぶとき、これまでなら簡単にひょいっと持ち上げたが、しんどそうだ。「ほら、若い子が行って!」と自分のチームの男性に手伝いを呼びかける。気づけ。気づけ。しゃんしゃん気づけ。
BOYZたちは、若い衆の3歩先が読めているので、その動きの予測を立て、かつ自分の作業もしながら気を配ることは、簡単なようで難しい。というか、現代人はいろんな場面で勘が鈍っていると痛感する。
ある日、用事で製糖場へ行くと、一人で作業している山ぴーさんがいた。耐火煉瓦を切り、壊れたかまどを組み直していた。その粉塵で頭が真っ白だった。
「手伝いましょうか」と声をかけて、しまったと思った。「大丈夫。一人でやるから帰りなさい」と言うに決まっているからだ。「教えてもらっていいですか」と言うべきだった。
また別の日に行くと、今度は高い梯子をかけて、屋根に登り煙突に笹を入れて煤払いをしていた。もし転げ落ちてもこんな山奥に一人じゃ誰も気づかんよ。そんな心配こそ、しゃらくさいと思うのが山ぴーさんだった。手伝いを申し出たが、「いや、かまんかまん。自分らのことだけやっといたらええから」と。その言葉が冷たく刺さった。若者は、お金でないと動かないと思っている人も多いのだ。何か予定にないことをさせるとハラスメントになるとも、扱いにくいとも・・・とにかく一人でやる方が早くて気楽でいいと先輩たちは思っていた。
チームを作って数年が経ち、私もだんだんその気持ちが分かるようになってきた。頼むより自分でやるほうが煩わしさがない。お願いするのが億劫だった。嫌そうな顔をされると傷つく。それなら一人でやる。そうやって、また体を壊すわけだが。
気づけ。気づけ。よう目を開いて見ろ。自分自身に対しても思うことだ。よく見て、想像し、分からなければ聞く。信頼はそこからしか生まれようがない。苦労の先にたどり着く本当の面白さを見ずに終わるのはもったいなくないかい? とも思う。
誰かがやらねば終わっていく。気づく人、気づかない人、気づいても気づかないふりをする人。山ぴーさんは、殆どのことに誰より早く気づいて、一人動いて、そうして静かに消えていくのだろう。残された私たちはそこから新しくスタートするしかないのだ。
人一人がいなくなるだけで、簡単に組織は終わる。人を育てることが最も難しいと思う。自分のチームとてそうだ。
BOYZたちと出会って、人の手は何でもできることを見せつけられた。同じ手であるのに、私のは、生きていく上で必要なことが何もできない手だと思った。私の黒糖作りは、それが一つずつできるようなる道だった。辛いこともたくさんあったけど、道になるまで突き詰めてやれて本当によかった。
毎日忙しく動き回っている山ぴーさんは、大勢で集まってわいわいだらだらするのが苦手だ。自分のやるべきことを終えたらさっさと帰っていく。私たちのような集団を、痛々しく、そして少し懐かしく、見ている。
一年目の製糖が終わったあと、山ぴーさんはこう言った。
「一年目は祭りじゃから。珍しいからみんな集まってくるんよ。問題は来年、再来年、祭りが終わってからじゃ」
案の定、翌年からは手伝ってくれる人が減っていった。収穫や製糖は人が集まったが、真夏の草取りは大半を私と母で行った。山ぴーさんの言葉が身にしみた。
黒糖BOYZも立ち上げ時は10名以上がいたのに、人が減り、私が手伝いに入ったときには4人になっていた。そして2名の方が辞めていき、最後は山ぴーさんと、Oさんだけになっていた。二人は特にプライベートで仲が良いわけでもないし、飲みにいったりもしない。たまたま最後まで残った二人だった。
都会で就職し定年退職後に地元に帰ってきたOさんは、山ぴーさんとはタイプが違って畑には行かず、製糖やラム酒作りに熱をそそいでいた。煙突の掃除とか、薪割りや石積みをしたりもしない。営業や広報、内部のいろいろを切り盛りするリーダーだった。二人はこの工場を何とか残していきたいという思いだけで繋がっていたと思う。
同じ物を見ても、見えるものは違う。そう思うと、やめてしまったBOYZたちには、見えてないことも、逆に見えすぎていたこともあったんだろう。
先日、父が帰ってきて「おい、山ぴーさんから間違ってワシに電話あったぞ。『こっちが娘さんの電話でないん?』と言いよった」と。父も別ルートで山ぴーさんと知り合いである。
妹からも、「Oさんから私にメールあったよ。久美ちゃんと間違ってるよな」と連絡があった。えー。去年までは電話かけてくれよったのに、二人とも急激に老いが来ていて心配になるわ。
山ぴーさんに電話をかけ直した。これからのことだった。先日相談を受けた裏ボスのKさんと言うことがまた違う。
「え、Kさんそんな事言いよった?」「へー、Oさん、そんなことがあったん?」
知らんのかい! おじさんたちは、連携がとても下手なのだった。
電話でもそれぞれに違うことを言う。私は伝書鳩のように仲介する。そのあたり昭和の男らしいなと思ったりするが、歳の離れた私にだから気を許して話せるのかもしれない。
電話はやがて雑談になっていく。雑談こそが大事だった。最近は仕出し屋が少なくなって、祭りのときに大量に頼めるのが「ほか弁」しかないとか、NHKBSの低名山に高橋さん出とったの見たぞな。とか、サトウキビの話も。
「綺麗に草刈りできとったやね。上等、上等」
今もこっそりと見てくれているんだな。
「でも、今年小さいんですよね。堆肥もう一回入れた方が良かったですかね」
「いやいや、辞めておいた方がいい。残り三ヶ月で大きくなるでしょうからね、そのままでええでしょう」
そう言ってもらえると、とても安心する。
今年はチーム内に黒糖だけの班を作り、早朝の草刈りも月一、全員集合することでクリアできた。逆に野菜畑の方に人が来なくて、結局そっちの草刈りを一人でやり続けてぎっくり腰になったので、朝三暮四ではあるのだが。私の課題は、一人で頑張りすぎずに仲間に相談することだ。それも信頼の形の一つだよなあ。
夏が終わる。私にはもう冬が見える。今年みんなで育てたサトウキビの、一年の恵を形にする、実力の試される冬。工場の神棚の火の神様に手を合わす意味が今はよく分かる。
「とにかくこの暑さじゃから、体にはくれぐれも気をつけて」
と、電話の最後に山ぴーさんが言った。ああ、先を越されたと思った。みなさんこそ、体に気をつけて、ゆっくりしてくださいよ。あとは任せたと言ってもらえるにはまだ時間がかかりそうですが。




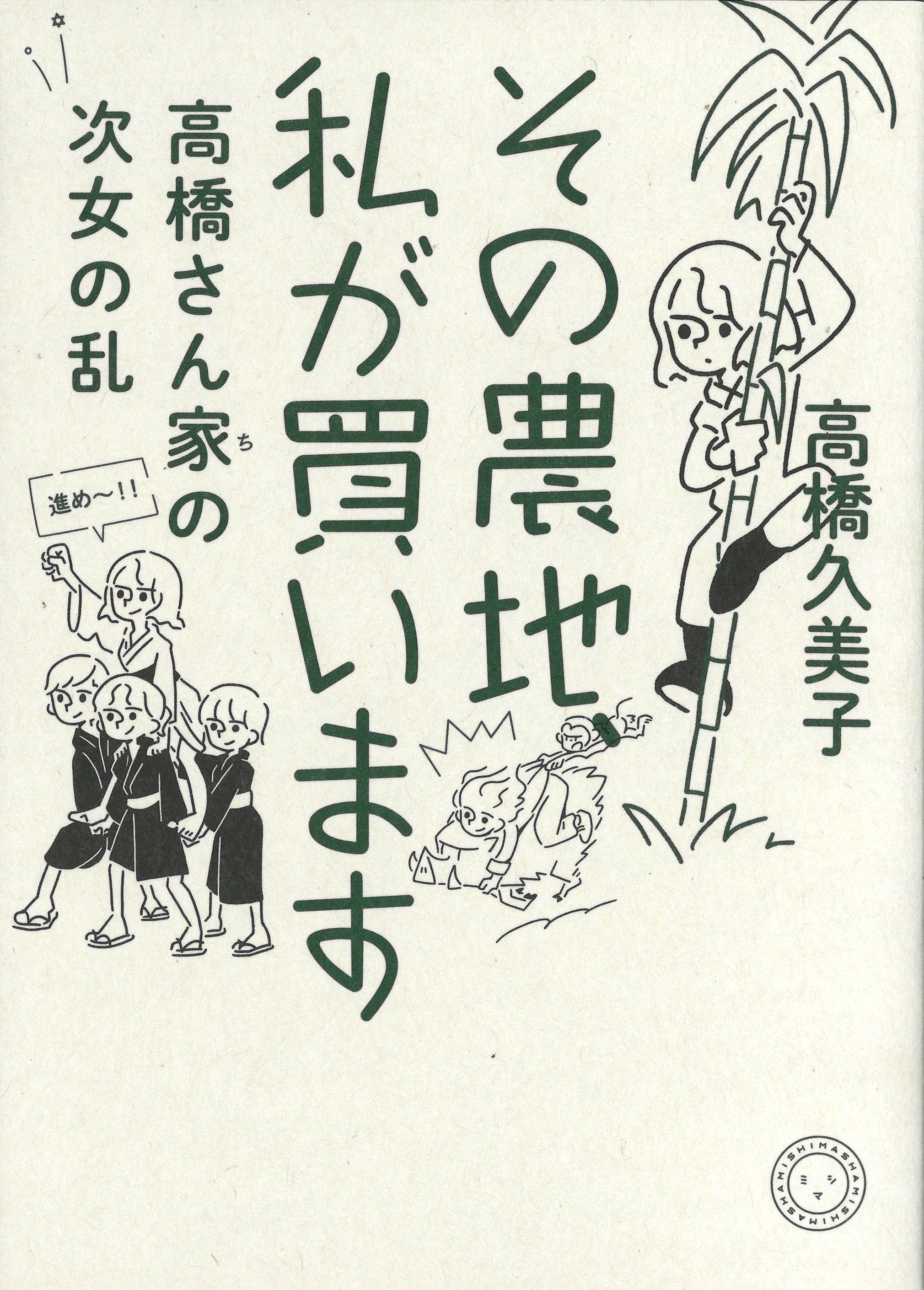
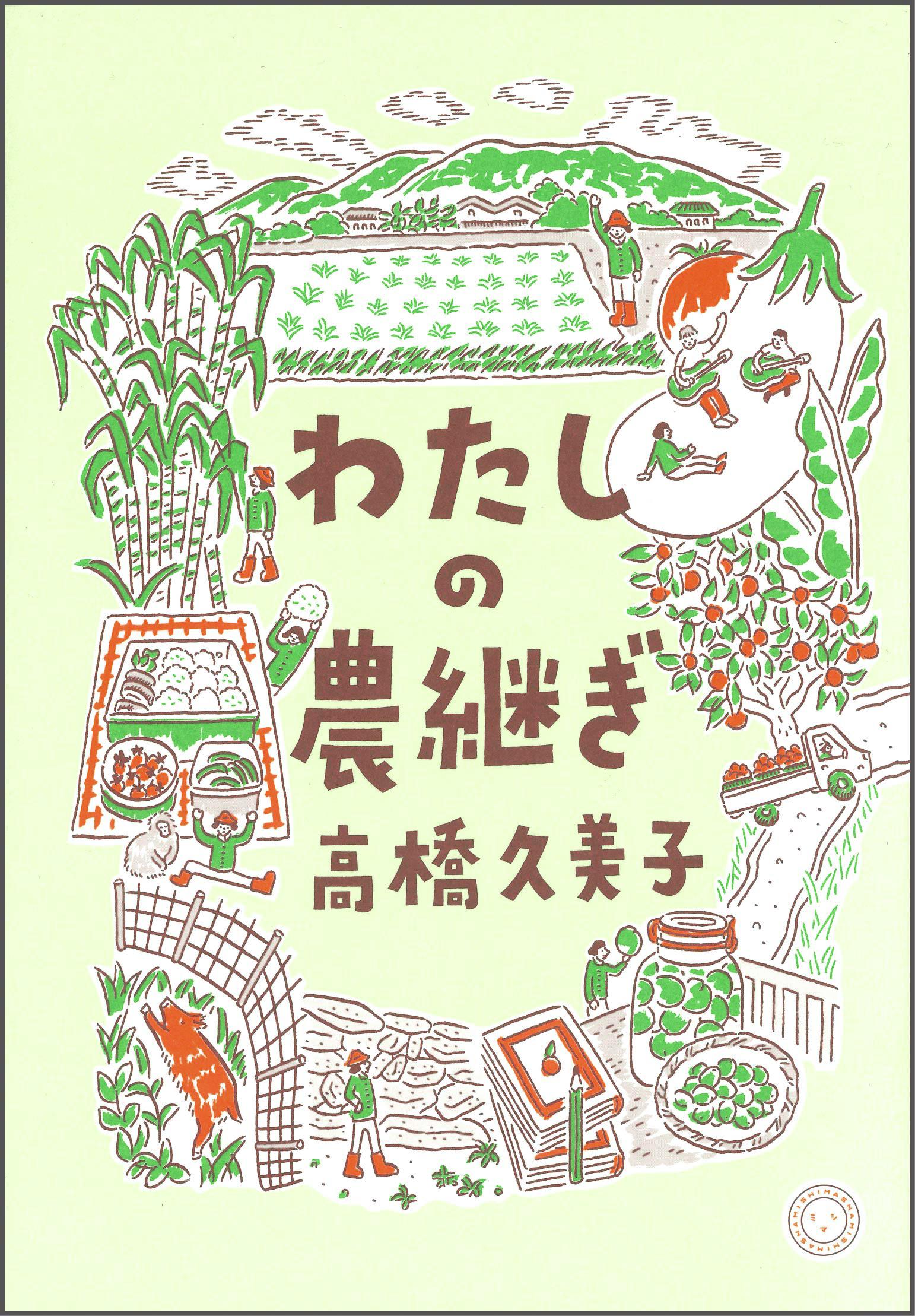




-thumb-800xauto-15803.jpg)
