第3回
万策尽きて立ち上がる「巻き込まれる力」(村瀨孝生)
2020.10.06更新
アナーキーな相互扶助。
全盲の女性を支える盲導犬。片足を切断した男性を支える義足。お年寄りの生活を支える僕。立ち位置的には僕は盲導犬であり、義足なのだと思いました。ママ友の会のお話しは、それぐらい感情移入してしまいます。そして盲導犬が彼女に、義足が彼に抗うように、僕もお年寄りに抗っているなあと思います。
それでも、そんな抗いに対して、女性は盲導犬が「これでよかったなあ」と思えるように考える。片足を切断した男性は「義足がどういう歴史を背負っていまここに来ているのか、ということを理解しようとしてあげないと、使いこなせない気がした」と思える。
盲導犬であり、義足でもある僕が「これでよかった」と思えるように。「信頼関係を結ぶ」ために僕の出自や生い立ちを理解しようと努力してくれるのですね。そう考えると実に感慨深くなりました。彼女、彼にお年寄りたちがかぶります。
あるお爺さんを思いだします。
ことごとく、次の行為に移れないお爺さんです。迎えに行っても、椅子から立たない。立っても玄関に行かない。玄関に行っても靴を履かない。やっと靴を履いて送迎車にたどり着いても乗らない。お爺さんとしては、よりあいに行く理由がないのですから当然です。だから、ひとつひとつ生じる抗いを尊重しないとお爺さんから信頼が得られないと思いました。
さらに、このお爺さんが面白いのは送迎するとき「車に乗りましょう」では伝わらないことでした。「そろそろ船がでますよ」と伝えると「ああ、そうか」と言って車に乗ってくれるのです。それには理由らしき過去があったのです。
お爺さんは太平洋戦争の敗北を北朝鮮で迎えました。すでにソ連軍の配下にあった港には、日本の船が邦人救出のために寄港することができませんでした。当時、若かりしお爺さんは同朋と闇舟を手配して命からがら脱出してきたのです。
ぼけを抱えて生じる危機感と当時の危機感がシンクロして「車」が「船」になったと思われる節があるのです。介助を通してお爺さんの背負った歴史を知り、その重さを感じることになります。
介助者からすればケアすることでお年寄りから抗いを受け振り回されているように感じてしまいますが、お年寄りからすればケアされることで介助者に抗われ振り回されている。互いが互いの「抗い」を「ケアし合っている」かのようにも思えます。ママ友の会に僕も参加していれば「やんちゃな子(おやじ)でスミマセン、でもね・・・」と夜遅くまで話が尽きなかったかも(笑)。
そして、
この話のポイントはやはり、「思える」というところだと思います。抗いがあるからこそ「相手を尊重できる」のではなく、「相手を尊重したと思える」と村瀨さんが書いているところ。この盲導犬がたまたま自分のもとにやってきた偶然性に向き合うことや、この義足が作られるまでの長い歴史を知ろうとすることも、自分の思惑を超えた「抗い」の要素を自ら探し求めている点で、「思える」と同じこころの動きだと思います。
という伊藤さんの指摘は深く考えさせられました。
介護の世界には過剰な「思える」ではなく、過剰な「思い」を持っている人が少なくありません。僕はかねがね「思い」という言葉に違和感がありました。それは伊藤さんの言う善行、相手を自分にとって都合のいい道具に仕立てて、支配しているだけと似通っていると思い当たります。過剰な「思い」に警戒してきたことが腑に落ちます。
そして、伊藤さんの言葉から改めて考えました。介助される人、する人になぜ過剰な「思える」が生じてくるのかと。そこには、場を介してひとつの行為をふたりで行うという待ったなしの抜きさしならぬ状況があるからではないかと思います。
お年寄りに関わって感じるのですが、これまで自分でできたことを他者の手を借りて行うことは簡単ではないと。さんざん抗って、葛藤し、万策尽きて、仕方なく自分の体を他者に委ねる(多くのお年寄は大なり小なり、そのようなプロセスを経ていると思います)。介護者もまた、喜んで介護する人はいないのではないか。できなくなっていく人を前に手を貸さざるを得なくなる。手を貸して実感します。自分の無力さを。介護は両者にとって仕方なく始まっていくものと感じています。しかし「仕方なさ」を悲観的にとらえていません。むしろ、救いがあると思うのです。
「場」を共にする介護される人、する人が互いに万策尽きた状態になったとき「思える」が立ち上がりアナーキーな世界を帯び始めるのかもしれません。これは英国のブライトンで生まれた相互扶助にもつながるのではないかと感じます(あとで、改めて書きますね)。
そもそもお年寄り、特にぼけを抱えた人はアナーキーな存在かもしれません。加齢によって時間と空間の見当が覚束なくなる。言葉を失い始め、記憶がおぼろげになる。そこには、概念から外れていく面があります。これまで縛られていた規範やルールからの解放ともいえるでしょう(当事者はそのことによってまた苦しむのですが・・・ここでは触れません)。概念から社会をとらえるのではなく、生身の実感から世界をとらえるようになると感じます。おそらく、そのように転じざるを得ないのです。
「待っても、待っても来ないのよ」。お婆さんはいてもたってもいられない様相で言いました。「誰が来んと?」と尋ねると「犬の注射の日」と答えます。保健所が公民館を巡回して行う狂犬病予防注射があるのですが、せっかちで記憶に不安のあるお婆さんはその日を逃すであろうことが心配でしょうがない。まるで、人を待つかのようにその日を待っているのでした。いくら待っても、人のようにはやって来ません。「どうして来ないのか」と問われてもお婆さんの腑に落ちる答えを持ち合わせていませんでした。これは母の話です。
あるお婆さんは、湯飲みを持ちながら「モシモシ、モシモシ」と言い出します。お茶を飲もうと湯飲みを口元に運んでいるのですが、唇で受け止める寸前で湯飲みが電話の受話器に変換してしまうのです。お婆さんは「モシモシ、モシモシ」を3回繰り返したのち、4回目でお茶を飲み干します。4回目は湯飲みが湯飲みのままでいられたのです。僕から笑いが漏れ出てくる。そして、お茶が飲めた瞬間、「よかった~」と思う。笑わせるつもりのないお年寄りが笑うつもりのない僕を笑わせる。ここには目論見がありません。
このような出来事は枚挙にいとまがないのです。だから僕の既成概念はずいぶんと解体されたように思います。それはとてもアナーキーなことです。本来、私たちは概念によって共通の認識を得ることができていると思います。では、ぼけを抱えた人たちの世界では概念に依ることなく共同性や相互扶助のようなものが生まれるのだろうかという謎が出てきますよね。
結論めいたことを言えば、80年、90年かけて育んできた自分らしさをいかんなく発揮して、ズレまくりながら調和している感じなんです。その様子はある意味、相互扶助的に見えます。
いくつかの看取りのエピソードから。
今にも息を引き取りそうなお爺さんの呼吸をみんなで見守っていました。すると、キリスト教徒のお爺さんがまだ息のあるお爺さんにむけて「南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏」と、お経をあげ始めました。つられて、ほかのお年寄も念仏を唱えるので、「みなさん、まだちょっと早いです」とさりげなくお知らせしました。
不思議なことがあります。看取りがいよいよ佳境に入ると、みなさん水を打ったように静かな夜を迎えることが多いのです。職員は死にゆくお年寄りに集中することができます。朝の申し送りで「昨夜はみなさんが看取りに協力してくださった感じです」といった夜勤者の声を聞くことが多いですし、僕もまた実感するところです。
看取るために家族が泊まりこむことがあります。ある家族は6日間泊まりました。そこで暮らすお年寄りたちと寝食を共にすることになります。看取りを終えたとき、お年寄りたちに支えられたと言うのです。
ちょっと前の出来事を憶えていないお婆さんが「ちゃんとご飯を食べたね?体がもたんよ」と気にかけてくれたそうです。ただ、記憶が続かないので激しいときは5分、10分おきに「ご飯を食べたね?」と心配する。それを見ていたお婆さんが「あんた、何回それを言えばいいとね」と怒り出す。すると「まあ、まあ、そげん怒らんと」とたしなめる3人目のお婆さんが現れる。
最初のお婆さんが「ご飯食べたね」と発すると「何回、言うとね」、「まあ、まあ、怒らんと」がワンセットで繰り返されるのでした。家族はあれがあったから頑張れたと言いました。
家族の希望によってはよりあいでお葬式をすることもあります。日蓮宗のお坊さんがお二人でシンバルやドラのようなものを盛大に鳴らしてお経をあげていました。
するとひとりのお婆ちゃんがリズムに乗ってきました。元気よく、しかも楽し気に手拍子を打ち始めてしまいます。ひとりが楽しくなると後に続く人が出てきます。結局、手拍子ができるすべてのお年寄りが手を打ち出したのです。それはまるでお坊さん(演者)とお年寄り(ファン)が一体となったコンサートホールでした。
面白いのは喪主である家族や親類縁者をはじめ、式に参列した地域住民が「とてもよかった」と言うのです。お坊さんにいたっては「感動した」と泣いておられました。
お年寄りたちは思想信条に依らないアナキズムと人格や宗教に依らない許し(今回は触れていませんが)を発揮し、場をつくり始めると言えるでしょう。そのように時折シンクロします。大方は揉めながらバラバラのままに一緒にいる。いるしかない。なんか、まじめで滑稽でしょ。好きなんです。
共通していることは目論見がないことなんです。誰かの強い意思と提案によって始まった感じがしない。巻き込まれていくといった感じでしょうか。
「巻き込む」には目的と計画の匂いがします。しかし「巻き込まれる」には「仕方なさ」や「思える」が漂っています。伊藤さんが考えているように、結果が想定されないままに動かされているように思えます。
ブライトンの相互扶助も万策尽きた人の存在に、「場」を共にする人たちが仕方なく巻き込まれていった側面があるのではないか。「巻き込む力」ではなく「巻き込まれる力」が作用したのではと想像しています。
ヒントというより感じるままに書きました。介護の現場に33年いますが未だに介護(ケア)とは何かよくわからないんです。人の行為は偶然性や一回限りで再現性のない営みで成り立つことが多いからでしょうか。お便り楽しみにお持ちしています。


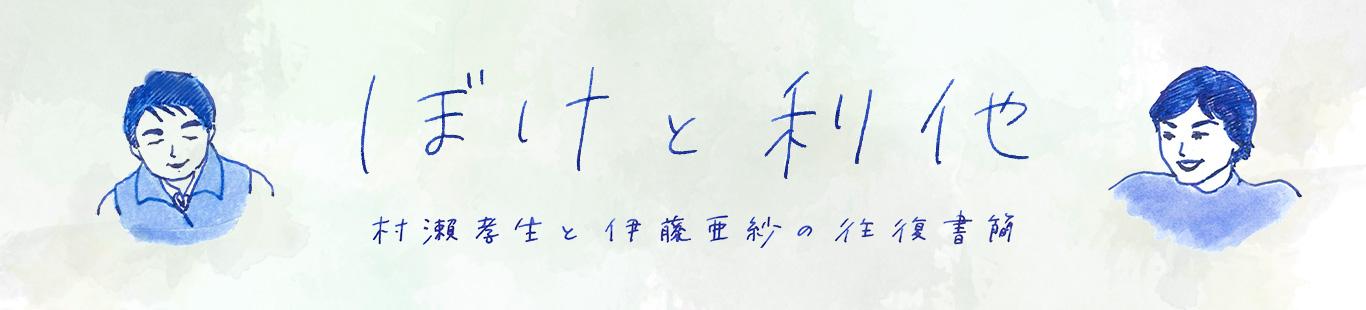



-thumb-800xauto-15803.jpg)


