第16回
羅針盤の10の象限。(前編)
2025.05.15更新
自分のことを語るよりは、やった仕事を記録していく航海日誌であろう。そのほうが具体的で面白いだろうし、どうせその中に自分語りも出てくるだろう。
そんな風に考えてこの連載を進めようとしているけど、やはり散らかって見えるなあ、とも思う。直近2回は、乃木坂46・久保史緒里さんの青春文化祭と、芸人さん4組によるコント番組のことだし、他にも演劇だけじゃなく、自分たちでバラエティ番組「暗い旅」もやっていたり、脚本家としてはドラマやアニメもやっている。劇団でゲームだって作っているから、ヨーロッパ企画を「へっぽこな実写ゲームを作る奴ら」として認知している人たちもいる。最近だと映画も作る。
羅針盤ぶっこわれてんのか。劇団なのに、エンタメ海の荒波にもまれてオールが流されたんだな。そうではない。羅針盤はめちゃくちゃちゃんとあるし手入れもしている。波は荒いけどオールは手放さない。潮目をできるだけ読もうとしているし、ユニークでアイデア溢れるラインをいつだって取ろうとしている。
演劇人として、真に往くべき海路だけを、薄暗い風雨の中でじっと見据えるようなやり方もあるだろう。そんな船長の目はかっこいいし、インタビューへの口ぶりも確かだ。しかしうっかりすると乗っていた船員はいつのまにかガイコツだ。なんなら船長もガイコツだし、船はサルガッソーを漂う幽霊船だ。
そうならないために、なるべく匂いに敏感にいる。潮の匂いに、果物や動物の、そして人の匂いに。追い潮に乗って、獲れるものを獲り、交易をし、知見を得ながら、太く面白く、アドリブ的に航海を進めていく。
劇団ごと舵を切ることもあれば、ひとりで小さなボートを漕ぎ出すようなこともある。とにかく匂いのする方へ、何か起こりそうな方へ。それでいて、他の船がまだ見つけてなさげなルートへ。
もともと演劇だけをやりたい人ではなかった。
中学高校時代はパソコンでゲームや音楽を作っていたし、その前はワープロで豆本を作っていた。お笑いも、劇場へ観にいくくらいには好きだった。ドラマや映画はほどほど。ファミコンゲームの攻略ビデオを2台のビデオデッキで編集していたのも高校のころ。あとはギター。そしてSFが好きだった。スポーツは嫌い、モノを作るのが好き。
高校2年で演劇と出会い、クラス劇を任され、やりたいし向いてるのはこれだ、となった。演劇をやるために大学に入り、ヨーロッパ企画を始めてからは、劇団と本公演をベースに活動しつづけ、今年で結成27年目、次が第44回公演。業界だと長いほうだ。
ヨーロッパ企画という船に乗ってはいるが、僕の羅針盤が差す方向は、演劇だけじゃなく色々だ。スポーツ以外のあらゆる方角に興味があるけど、大きくは10の象限に分かれる。
①演劇
針は基本的にこっちを指している。あるいはこっちを含む方角を。僕が往くべきメインルートだと思っているし、得意でもある。
年に一度の本公演ツアーと、最近では外部舞台もあって、だいたい一年に2本作る。主に新作をやるけど、再演もときどきやる。
ヨーロッパ企画を始めたときからずっと、SFやファンタジーの要素を含んだ群像コメディをやってきて、それは今後も変わらなさそう。
劇場のサイズが大きくなったり、本公演以外では原作ものをやることもあったりと、少しずつ変化はあるし幅は広がっている。ホラーやミステリ、音楽劇など、笑い以外の調味料も扱いはじめた。毎回作品の趣向は変えるけど、演劇って基本的に過去作は観れないので、過去やってきたこともなるべく最新作に含むようにしている。過去はもうなく、今作しかない、というイメージ。
初期はとにかく書けなかったし、初期はなんて言いながら15年くらいは思うように書けず、筆が遅くてみんなに迷惑かけたけど、最近やっと書けるようになって、ここ10年くらいは調子いい。演劇はきっと要素が多いから、一人前に作れるようになるのに時間がかかるのだろう。そしてそこまで続けると、あとはあまり年月を裏切らない。そこがいい。
いずれは笑いの勘が衰えるだろうし、コメディを書く体力も落ちてくるだろう。ミステリや音楽劇を始めているのは、そのころに備えてでもある。笑いに頼らないエンタメの形。とにかく行けるところまで、エンタメ演劇を切り拓きたいし盛り上げたい。とくに本公演は、チームの経験値も相まって、近作の仕上がりはちょっと凄いことになっているので、この感じをできるだけ保ちたい。
演劇で培ったことは、あらゆる象限で役に立つし、前に書いた青春文化祭のような場所に出ていくことだってできる。25周年には久しぶりにコント公演もやった。演劇以外の人を演劇に巻き込むのも楽しい。逆によその海での経験が、演劇にフィードバックされもする。演劇は本業すぎてキリがないのでこの辺で。
②映画
僕の映画のキャリアは偶然始まった。
劇団3年目にやった「サマータイムマシン・ブルース」という劇が、本広克行監督に見初められ、映画化してもらえた。そのときに脚本を担当したのが始まり。
なんかいい流れでラッキー、と思ってたけど、本当にラッキーそのもので、その後いくつも映画脚本をやったけれど、最初のこれが一番スムーズにいったと思う。
自分たちで主催する本公演と違って、映画はたくさんの思惑が絡むし、なおかつ僕は映画では監督ではなく脚本家なので、思うように事が進まず、書いたものが全然形にならなくて、一時期は相当へこたれた。シナリオまで書き終えたけど、撮影に至ってないものが片手じゃきかない。
脚本を作ってから予算やキャストを集めることが多いからやむなしだけど(そして僕が関わる企画はチャレンジングなものが多く、頓挫することもしばしば)、この打率で映画に関わり続けるのはしんどいな、と思った。けど映画はやりたい。作品が独り歩きする楽しさや、残る嬉しさは、演劇だとちょっと味わえない。
それで辿りついたのが、自分たちで映画を作るということ。
下北沢の映画館・トリウッドさんからお誘いをいただき、2020年に「ドロステのはてで僕ら」という70分の映画を作った。
脚本は僕で、監督は劇団の映像スタッフ・山口淳太。せっかく自分たちでやるのならと、よその映画じゃできないような、劇団の特性を生かした長回しによる時間ギミック映画にした。出演はヨーロッパ企画メンバーと朝倉あきさん。ご近所のカフェパランさんをお借りして、夜から朝まで撮影した。劇団にしか作れないような映画になった。
コロナ禍で思うように公開できなかったけど、海外の映画祭で思いもよらない好成績を振るい、23冠を獲得(国内では無冠)。さらに配信もされ、演劇ではありえない広がりが出たし、何より映画を自分たちで作っている実感があった。
2023年には第2弾「リバー、流れないでよ」を、京都・貴船で撮影。これまた長回しを多用した時間映画で、大寒波による撮影延期は悪夢のようだったけど、奇跡的にできた映画は、「ドロステ~」よりもさらに広がりを見せた。
演劇と違って、映画は身軽に海を渡れる(逆に向こうの映画も海を渡ってくる)。ならば映画の中で映しとる風景は、むしろドメスティックな、地元でしか撮れない景色がいい。演劇では逆に、香港やロンドンを舞台にした劇を節操なくやる。
また「時間もの」というジャンルも、僕が映画をやるのに合っている。「サマー~」から連なる系譜だし、パズルやギミックを織り込みやすい。低予算でもアイデアや作りこみで勝負できる。そして「構造」は言語をこえて伝わる。そもそも時間操作って映画の特権だし。
あくまで自分の本領は演劇なので、映画のすべてはやれない。ならば「時間映画」という一点突破でやっていこう、と考えている。それ以外の脚本もやるけれど、人のご縁があれば、という感じで、基本的には時間映画やギミック映画にしか興味がない。
監督はまだ長編映画ではやったことがない。短編ではある。監督までやると自分の人生が足りなそうだ、という危惧と、やりたい思いが、日々自分のなかで会議を繰り広げている。
③ドラマ
テレビドラマには正直、乗り遅れている。
遅れているも何も、本業は劇作家だし、テレビドラマをやらない作家人生だってある。
僕の場合は、やりたい。テレビドラマを書きたいし、願わくばテレビを自分のフィールドにしたい。自分にしか書けないドラマで席巻したい。そんな野心を持っていて、そして縄跳びに引っかかり続けている。
初めてシリーズ脚本を手掛けたのは、短いのやローカルのを除けば、2014年の「ドラゴン青年団」。東京タワーにドラゴンが出現し、それを倒すべく、静岡の若者たちがクリスタルを集め旅に出る冒険ファンタジー。ご存じないでしょう。知ってる人は知ってますかね。
こんな面白い設定ないだろと今でも思っているし、熱烈に好きでいてくれる人もいる。実際面白かったと思う。そして面白いことと、ドラマの成功はまた違う。
失敗したわけではないけれど、大概のドラマは何となく終わっていく。そして一握りの作品だけが、そのクールで特別なドラマとして輝き、閾値をこえて話題をさらう。視聴率や再生回数という形で現れたり、タイムラインを熱狂的に賑わせたり。
「ドラゴン青年団」ではそういうことは起きず(当時まだ配信はなかったけど)、これはやっぱり悔しいことだった。
僕にとってドラマは難しい。演劇や映画と違って、圧倒的多数の人たちの心を掴み、夢中になってもらうのが難しい。見たことないものが作りたく、風変わりな設定や物語が好きだけど、ドラマではそれが仇になっているのかもしれない。見たことあるものが安心を生んだりする。けど見たことない面白さで、世間を夢中にさせているドラマだってある。
「浦安鉄筋家族」「グラップラー刃牙はBLではないかと考え続けた乙女の記録ッッ」「全っっっっっ然知らない街を歩いてみたものの」「あいつが上手で下手が僕で」「魔法のリノベ」「時をかけるな、恋人たち」。
僕が今まで書いてきた連続ドラマ。どれも全力を尽くしたし面白い。他にはないドラマだなあ、と思うし、ちょっとずつだけどコツも掴めてきた気がする。まだまだ経験値が足りない。ドラマのレジェンドたちが、日々新しい発明や発見をし続けてるような世界なのだ。「テレビドラマ」と書いているけれど、配信プラットフォームも増えてきて、情勢も刻一刻と変わってきている。
去年は10件くらいドラマのお誘いをもらい、プロットを書いて、大体ぜんぶ落ちました。まじですかと言われるけどそんな感じです。プロデューサーさんは全力で向き合ってくれ、これはという企画書がいつもできる。それが通らなかったり、塩漬けになったり。
企画が通ってからオファーをもらうパターンもあるし、原作ものも面白い。だけどやっぱりオリジナル企画をいちから開発したい。そうするとこういう険しい戦いになる。ちょっと賞レースみたいな気持ちかもしれません。へこたれない限りは挑んでいきます。うちのメンバーにだって出てほしいし。
④アニメ
アニメについては運がよくて、2010年に「四畳半神話大系」というテレビアニメシリーズの脚本をやったのが最初。湯浅政明監督のぶっとび方にはたまげたし、森見登美彦さんの原作は樹海のようだった。
僕はものごとを整理して考えるのが好きで、原作ものをやるときは、原作を分解するように読み解き、デザインしなおすような気分で脚本へと移し替える。四章からなる豊饒な原作小説を、湯浅監督の自在なイメージを交えながら、テレビアニメサイズの11話へと落とし込む作業は、自分にとって適職だった。
それがなかなかうまく行き、同じ湯浅監督と、アニメ映画「夜は短し歩けよ乙女」、さらには石田祐康監督と「ペンギン・ハイウェイ」、夏目真悟監督と「四畳半タイムマシンブルース」。森見作品ばかりをアニメ脚本にする専門家、みたいなポジションにありつけた。
アニメをたくさん観るほうではないけど、アニメの世界に足りない言葉が文芸にはある、と直感していて、森見作品のシリーズでは「森見さんの言葉や文芸を、アニメの世界にインストールする」というのが僕のテーマ。アニメの表現はアニメの人たちにお任せで、いろんな監督と組むたび、得意技が違ってて面白い。
そして文芸とアニメは、じつは相性がいい。どちらも実写と違って、現実に引っ張られずに変幻自在のものが作れる。幻想文学のような森見さんの小説は、特にアニメと響きあう。そして演劇も実はそう。どれも白いキャンバスにいちから絵を描くようなこと。
2023年には、映画「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」の日本語脚本をさせてもらった。ゲーム少年だった自分としては光栄すぎる仕事だったし、ここでもやったことは、劇作で培った言葉をマリオに持ち込むこと。非言語のスーパーヒーローに、いわゆるアニメ的でない、肌触りのある言葉をしゃべってもらう。英語版に負けない、リズミカルでユーモアに富んだ日本語版を作ろうと腐心した。
実写でなくアニメ吹き替えなら、リップを合わせればかなりのところまで戦える。「スーパー日本語版」という誉れ高い称号をいただいた。
去年は「ドラえもん」の誕生日スペシャルの脚本も担当した。これはセリフというよりは、プロットでの戦い。タイムマシンものばかりやっていた僕に、本家から白羽の矢が立った。子供向けのアニメだけど、子供だましではいけない。古代ギリシアの、バースデイケーキの起源をめぐるハードな歴史介入プロットを、手加減なく組み上げた。
あまり深く考えてなかったけど、自分の作風はどうやらアニメに向いている。たしかにSFやファンタジーは、実写よりもアニメと相性がよさそう。アニメを通ってこなかったし、自分がまさかアニメに関わるなんて、思ってもみなかったけど。演劇もそういえばそうだった。
あとアニメの世界には、モノを作るのが本質的に好きな人が多い。芸能界ってそうでもなく、クラスの一軍の人たちとやりあうような面白さがあるけど、アニメの人たちとは多分、クラスにいたら仲良くなってただろうなーって感じで肌が合う(失礼)。
ただし悩みがあって、「アニメって劇団とあんまり関係ないな」ってこと。僕は脚本家であるまえに、劇団の座付き作家で、だから劇団の役者が出られることを大事に考える。実写だとそれができるけど(できないこともあるけど)、アニメは劇団員がちょっと関わりにくい。声優さんの世界って、俳優の世界とはまたちょっと違うんです。
そう思ってたけど、こないだ「舞台俳優さんは、誇張的な演技もやり慣れてるから、アニメの声もうまいんです」っていう話をアニメのスタッフさんから聞いた。実写映像と違って、声ですべてを表現しなくてはいけないアニメは、実写のようにやると「足りない」のだそう。
確かにそうかもしれない、と目から鱗だった。演劇とアニメの、思わぬ接点が見つかった気分。遠いようで近い、演劇とアニメ。演劇人としてアニメにできること、まだまだありそう。
⑤ヨーロッパ企画
ここはちょっとあやふやな分類だけど、いうなれば「本公演以外の劇団活動」ってことです。
これがけっこうある。イベント、生配信、動画、Blu-rayやDVDのリリース、グッズ、劇団で受ける案件のような仕事、劇団運営。
僕らのメインの劇団活動は、年に一度の本公演ツアー。これはでっかくて、数か月かけて十数都市を巡る、劇団と会社をあげての大プロジェクトだ。最近は映画も大きめ。
だけど他にも色々やりたいし、本公演へ向けての盛り上げや、作った公演のパッケージ化、よその仕事を受けるようなこともしたい。
新しい表現へ向けての実験や種まきも、日常的にやっていたい。お金を稼ぐことや、アテンションを集めることだって考えないとだし。お客さんとのコミュニケーションも面白くやっていきたい。そういうことの積み重ねの上に、本公演という大きな祭りができあがるイメージ。
ヨーロッパ企画は京都を拠点にしていて、「ヨーロッパハウス」と呼ばれる仕事場が二条にある。何を隠そう僕の実家で、元々は焼き菓子工場だった。両親の代で廃業してから、今は建物の趣をそのままに(築100年らしい)、中身を少しずつ作り変えて、劇団の事務所として利用している。
役者メンバーは半分くらい東京に住んでいるけど、スタッフはほとんど京都にいて、ヨーロッパハウスで仕事をしている。社員もいれば、作家たちや映像スタッフもいて、会議室や映像編集室、機材置き場、グッズ倉庫などがある。
僕の書斎もあって、京都にいるときはここで仕事をしている(昼間は喫茶店に行くことも多いけど)。演劇の稽古はしないけど、ちょっとした撮影もよく行われる。
元々が工場だったからか、ここはずいぶんモノが作りやすい場所だな、と思っている。ヨーロッパ企画自体もここから生まれたし、いろんな企画や作品がここから生まれた。ヨーロッパ企画とヨーロッパハウスは、ちょっと切っても切れない関係にある。
この「ヨーロッパハウスから、どんどんモノが生まれていく感じ」を、僕は大事にしたい。生まれたころから、工場に職人さんやパートさんが集まって、焼き菓子を作るところを見ているから、そういう「工場が動いてる感じ」が安心するのかもしれない。作家なら別に一人でもできるけど、集まって作ることが、やっぱり劇団の醍醐味だし、それをしてるときが楽しい。
作りたい作品はもちろんあるけど、実はなんだっていい、と思っているところもある。劇団で何かを作っていることや、手を動かしていること、それ自体が楽しいというか。作家って結局ひとりの作業だし、ストレスフルだからその反動もあると思う。この象限以外では僕は基本的に「作家」だけど、ここでは僕は色んな顔になる。
イベントの構成をやることもあれば、生配信の出演者になることも、映像企画の案だしをすることもある。グッズについて冴えない意見を出したり、映像チェックが遅れて迷惑をかけてしまったりも。後輩作家の相談に乗ったり、逆に相談に乗ってもらったり。決裁もするけど、まあ頼りないので、みんな勝手に進めてくれている。年々よい工場になってきていると思う。
役者メンバーの多くが東京に行ってしまったのは、正直、淋しい。劇団の醍醐味は「集まって作ること」で、それが年々メンバーとはやりにくくなっている。
活動や拠点を縛るつもりはないし、俳優の現場は東京にあることが多い。メンバーが東京に住むことは自然な流れだと思うし、東京での活躍を応援している。応援しているも何も、東京にもマネージャーがいて、東京での仕事をマネジメントしてくれている。ヨーロッパ企画はだから、今や京都と東京の二拠点劇団で、僕も行ったり来たり。脚本を書くのは京都だけど、仕事や取引先の多くは東京だ。
それでもやっぱり、集まって作りたくて劇団をやっている。
去年から、旗揚げメンバーの諏訪さんと永野さんとは、会えるときに会って話すことにした。ふたりとも去年から東京に住みはじめ、仕事は充実してるけど会うことは少なくなった。会わなくても仕事はできるけど、会うから話せることがある。そこからアイデアや次の動きが生まれる。昔は当たり前にそうだった。だから頑張ってそうすることにした。
同じように、他のメンバーともチャンスを見つけてはご飯を食べたり、東京と京都のスタッフで合宿したり。もちろんリモートも使う。だけどなるべくなら集まる。二拠点劇団としてのありかたを模索しているところ。
そして京都にいるメンバースタッフとの活動を、ますます充実させたい思いにもなっている。新しい劇や公演を立ちあげたりしたいし、出会いも増やしたい。新劇団員の金丸も京都に住むという。嬉しいし、何か始まりそうでわくわくする。
あとに書くけれど、KBS京都での番組「暗い旅」も、京都チームで企画やグッズを作ったり、いろんなコラボをするプラットフォームみたいになってきている。映像チームにもらえる仕事も増えてきた。総じて、京都でする仕事は楽しい。
27年目だけど、新しくヨーロッパ企画を始めるような心持ちです。劇団をまだまだ面白くしたい。春めいたオファーや出会い、待ってます。
(後編につづく)
*後編は2025年5月17日(土)公開予定です。
編集部からのお知らせ
上田誠さんの新作「リプリー、あいにくの宇宙ね」
上田誠さんが脚本・演出を務める舞台「リプリー、あいにくの宇宙ね」が、東京にて上演中! 6月は、高知・大阪公演もあります。
「リプリー、あいにくの宇宙ね」
<イントロダクション>
スクランブル発生! 今度は何が起きている? 宇宙はつねに変化に満ちているし、いつだって射撃訓練所の中だ。たえず11人目がいるようなものだし、スタービーストは暗黒の森林で息をひそめている。それにしてもひどすぎないか、と二等航海士・ユーリは思う。量。このトラブルの量はなんだ。マザーCOMはなぜ答えない。船長はなぜ判断しない。ロボ、三原則いまはいいから。アーム、そんなポッド拾わなくていい。漂流詩人乗ってこなくていい! これどこからのスライム? 石板、いまは進化させていらない! ユーリは白目で歌う。リプリー、あいにくの宇宙ね。ってハモんのやめて。
<公演スケジュール>
●東京 本多劇場
2025年5月4日(日・祝)〜5月25日(日)
●高知 高知県立県民文化ホール オレンジホール
2025年6月3日(火)
●大阪 森ノ宮ピロティホール
2025年6月6日(金)〜6月8日(日)
『ちゃぶ台13』に上田誠さんのエッセイ掲載!
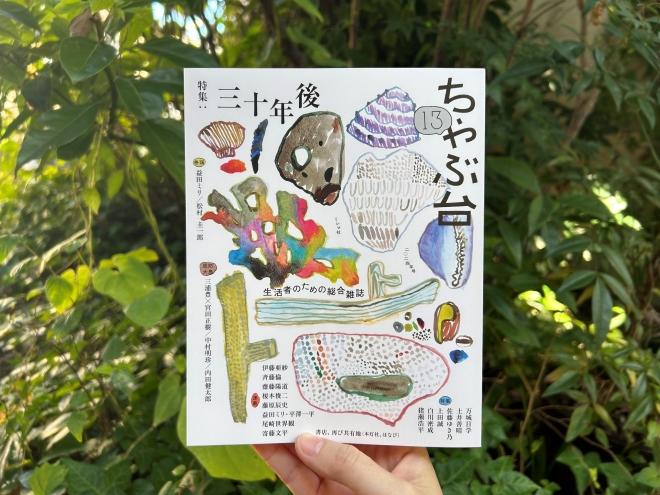
2024年10月刊の雑誌『ちゃぶ台13 特集:三十年後』に、上田誠さんがエッセイ「劇団と劇の残しかた ~時をかけるか、劇団」を寄稿されています。ぜひ、本連載とあわせてお楽しみください。
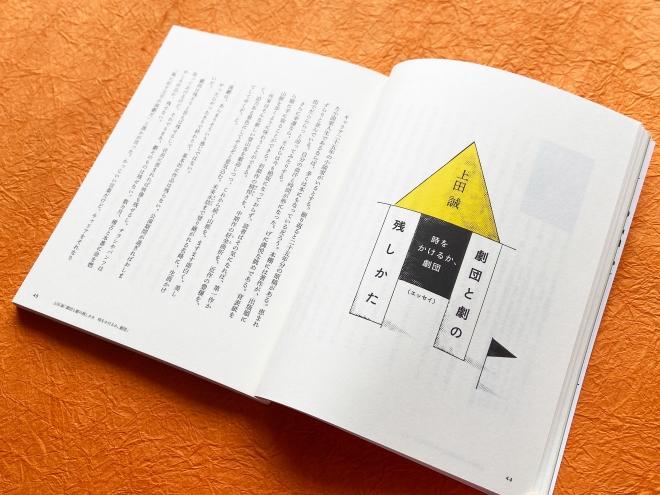
上田誠さん、ミシマ社通信に寄稿!
万城目学さん著『新版 ザ・万字固め』(2025年1月17日発刊)にはさみこまれている「ミシマ社通信」に、上田誠さんが熱い原稿を寄せてくださいました。タイトルは「万城目文学の恐ろしさ――脚本化を許さぬ文章の完成度について」。こちらから一部お読みいただけます!
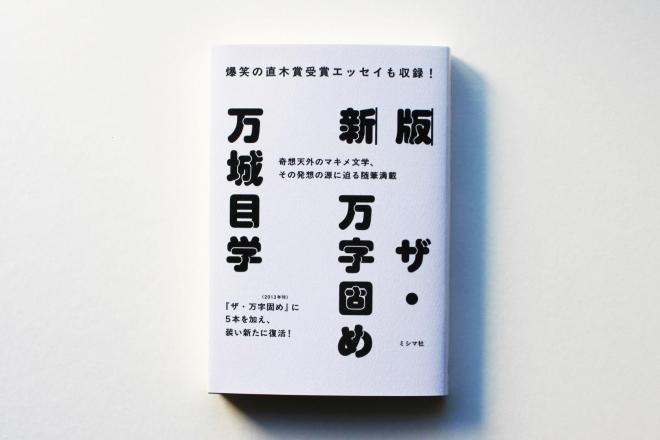


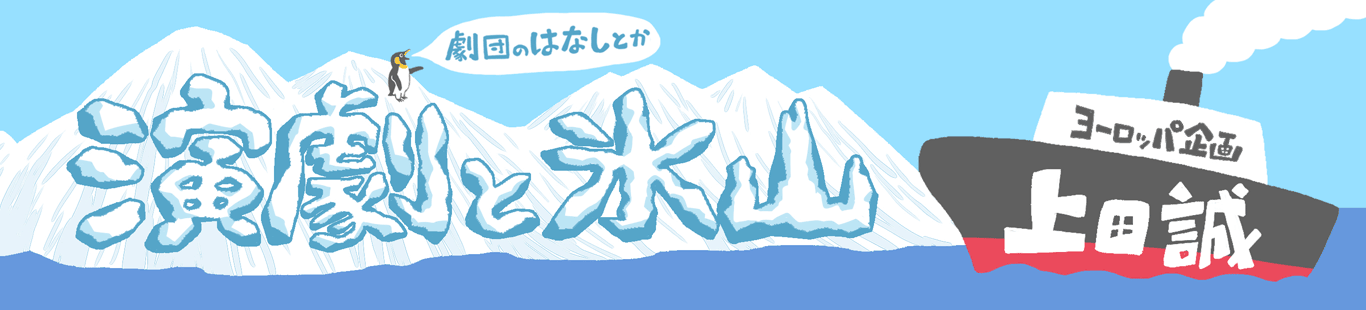
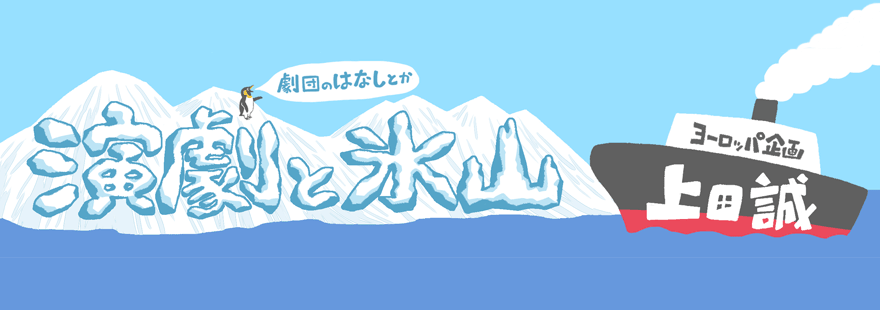

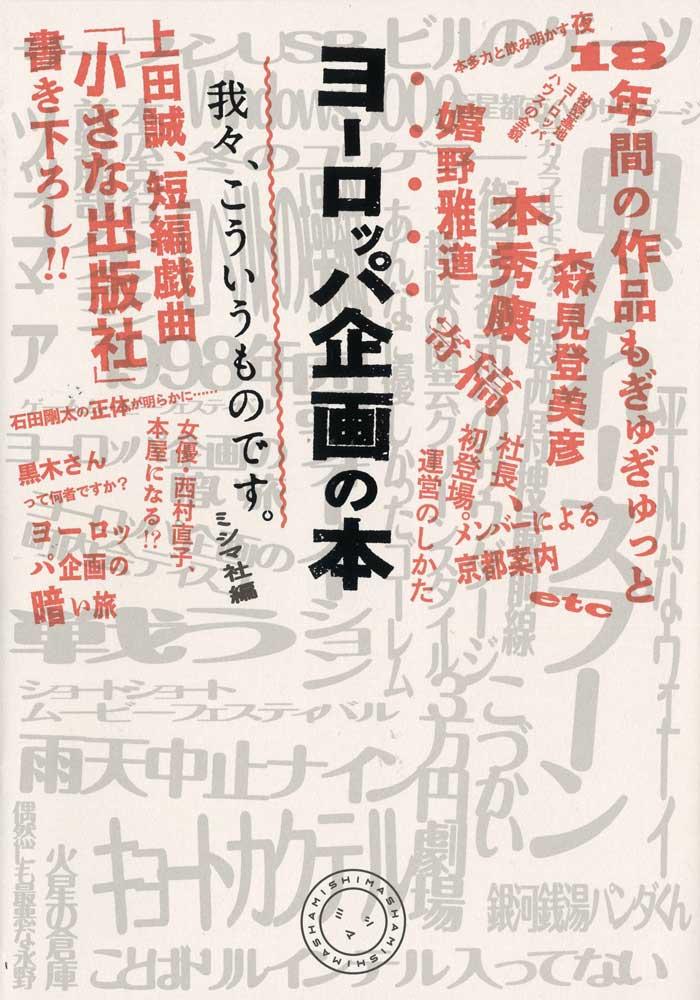


-thumb-800xauto-15803.jpg)


