第17回
リプリー、あいにくのコメディね。
2025.08.14更新
ある動画をふと見た。
たまたまネットの海から打ち寄せたもの。それはアメリカの高校生たちの演劇発表会。
やっていたのは、映画「エイリアン」の演劇版アレンジ。というかコピー。コピーバンドをやるようなもんなのかな。アメリカの高校生たちはコピー演劇をやる。知らないけど。
往年のあのいかついエイリアン(成体のやつ。ゼノモーフって言うんですね)が、たいへんなクオリティで舞台に現れ、観客は「ヒュー!」と熱狂していた。宇宙船を愚直に再現しようとしたセットは、段ボールや廃材で作ったそう。映画中の名シーンが、さながら仮装大賞のような創意工夫で演じられるたび、動画を覆うような拍手喝采が起こっていた。
羨ましかったし、負けてると思った。「演劇ってこういうことじゃん!」って目が覚めた。そして、プロの俺たちが本気を出せば、もっと凄いのが作れるし高校生たちよりも熱狂させられる、って大人気なく思った。
演劇ってそう、総合エンタメだ。お客さんを沸かせ、驚かせ、フィーバーさせることができる。だけど演劇はなぜか、そのことをよく忘れちゃう。頭でっかちになってしまったり、周りの目を気にしてしまったり、真面目になりすぎたり、芸術っぽくなりすぎたり。
もちろんどんな演劇だってあっていい。だから、エイリアンみたいな演劇だってあっていい。お客さんもきっと楽しいはず。あの動画の中の観客みたいに。
次の劇はエイリアンをやる。そう決めた。比喩ではなく、文字通り、エイリアンをやる。魂だけを受け取って違うことをやるのでもなく、まっすぐエイリアンものをやってお客さんを沸かせる。それを今やるべきだと直感した。そして今ならできるとも。
本公演とは別に、最近はニッポン放送さんとも毎年、劇をしている。
これまでは原作ものをやってきた。「続・時をかける少女」「たけしの挑戦状ビヨンド」「たぶんこれ銀河鉄道の夜」「鴨川ホルモー、ワンスモア」。そして次が5回目。
劇場は、東京公演はうちの本公演と同じ、下北沢本多劇場。密度感ある空間の中で、いよいよシリーズ初のオリジナル作品をやりませんか、とのオファー。
だったらエイリアンだ、と矛盾してるけど閃いた。動画で見たアメリカの高校生のあれ。あれをプロの力で大人気なく超える感じのやつ。
本多劇場を、逃げ場のない宇宙船に見立てる。そこへ強靭なキャストたちを乗せ、宇宙生物をはじめとする、宇宙で起こるトラブル全部乗せのスペースオペラにする。
宇宙ものってきっと難易度が高い。少なくとも地上ものよりは。だけどチームワークが練れてきた、今のタイミングならチャレンジしてもいいはず。事故らずに重力圏を突破できるのではないか。
重力圏。なんかそういうものがあるんです。業界にうっすらと。
演劇業界に限らず、たぶんどこでも。閉塞感かもしれないし、固定観念なのかな。シンプルに物理的な限界かも。集団でこの辺までならいけるよね、っていう常識的な合意。おおよそ合理的な作り方で、まともに作ったら、このあたりに収斂する、っていう。僕らの中にあるのかも。
しかしそこらへんをたまに突破できるのが人類だし、そういうエクソダスな集団が時おり組み合わせの妙で現れるし、原始スープから多細胞生物がにょきっと出てきたのも、人が重力を振り切って宇宙へ出れちゃったのもそういうことで。
なんだかそういうロケットみたいな劇をそろそろ待ってたし、タイミング間違えたらプロジェクトごと笑われちゃうけど、今いけそうかもって。雰囲気の話でごめんなさいね。
映画「翼よ!あれが巴里の灯だ」で、リンドバーグが太平洋横断するときに、直前に飛行機につける小さな鏡がいるってなって、少女に借りてガムで計器の横にくっつけて、飛んでった。あれ「今いけそう」って思ったんでしょうねえ。
映画の話ふたつになっちゃった。エイリアンでした。
エイリアンを観かえしたら面白かった。1979年の「1」。まったくこれは舞台でやるとコメディになるな、って思った。そして実写じゃハリウッド映画ぐらいの巨大な構えがいりますけど、演劇だとできちゃったりするんです。
時期的にも幸い、今は冷戦時代の宇宙開発にかわり、先進企業が宇宙へ乗り出そうとしていてタイムリー。宇宙資源のことや、地球外生命体の可能性も、まあまあ真面目に議論されている。演劇ってこういう世相の風に乗るのも大事で。
そして、言ってもまだまだ宇宙はフロンティア。あんまり分かってないのをいいことに、起業家たちは夢を好きなように描いているし、嘘もつき放題。僕もその作法に倣うことにした。医療もので嘘つくわけにいきませんから。
それっぽい言葉で「それらしさ」だけを纏いつつ、コールドスリープあり、光線銃もあり、アンドロイドも吟遊詩人も宇宙海賊もあり、無重力はなし、みたいなワガママ宇宙をでっち上げていった。コメディと僕の都合に優しい、甘やかな宇宙。
ちなみに僕がハリウッド映画で好きなのはそういうところ。皆さんほんとフィクションを好きなようにでっち上げて、言葉と演技で「それらしく」している。脚本力と演技力の悪用がすごい。ハリウッドの宇宙は「それらしさ」でできている。
タイトルは「リプリー、あいにくの宇宙ね」に決めた。「リプリー」はエイリアンの主人公から拝借。劇の主人公も、リプリーと同じく女性にしたかった。エイリアンのリプリーみたいに、あり得ない量のトラブルに見舞われ、どうにかこなしていくようなイメージ。そして「あいにくの宇宙ね」とぼやくような。
そのぼやき、せっかくならポエトリーラップにしたい。ベースはトラブルトラブルまたトラブル、のエンドレストラブルコメディなんだけど、音楽劇の要素をいれることで、たぶん良いクッションになりそう。天体用語を使ったラップも作ってみたいし。
伊藤万理華さんしか主演思いつかないなこれ、と思ってオファーしたらOKいただけた。理不尽なほどのタスク処理をして、ぼやきラップを歌い踊る、受難系ポップヒロイン。そこからは伊藤さん演じる航海士・ユーリを困らせるやっかいなクルーたち、という観点からキャスティングを進めていった。
井之脇海さんは、ユーリのバディで宇宙ガチ勢のキリト。ここじゃないだろってタイミングでユーリに恋心を伝えて困らせる。宇宙パイロット絶対似合うだろって思ってた。
シシド・カフカさんは、漂流吟遊詩人のニルダ。演劇はやったことないって仰るのを口説いて出てもらった。シシドさんみたいな地球外生命体に出会えるなら最高の宇宙だ。
かもめんたるのおふたり。う大さんは他責的なキャプテン。槙尾さんは不当な扱いにむくれる作業用ロイド・ボグ。男性ブランコのおふたり。平井さんは好奇心に殺されそうな科学主任。浦井さんはジェントルな作業用ロイド・ロビィ。辣腕のコント芸人さんが2組いるというのが、この座組のストロングスタイルを象徴してると思います。セリフ書くの僕だって怖いほどの笑いのリング。
演劇兵器・野口かおるさんには、自分が主人公だと思って騒ぎまくるリプリーみたいな通信士を演じてもらったら、ほんとに宇宙船が壊れるかと思うほどのインパクトでした。
そしてヨーロッパ企画から、石田剛太、中川晴樹、金丸慎太郎。やはり僕のやり口の一番の理解者であり、これまで数多のコメディを潜り抜けてきた猛者たちなので、この宇宙船にも欠かせない。石田さんはすぐ暴徒化するオペレーター、中川さんはすぐエイリアンにやられる機関士、金丸さんは厚かましい密航者。
とにかくトラブルにつぐトラブル、状況につぐ状況。それだけで劇を構成したかった。
僕らの日々だってそうだし、よく分からないまま状況の中にいて、何とかやっているうちに次の状況がまた来る。宇宙ものなんて限りなくフィクションだけど、リアルはその「トラブルの密度」に宿ると思った。
宇宙資源の開発のため、宇宙船ブリコロモ号に乗り込んだ11人のクルー。資源は見つからず、帰りの宇宙船から劇がはじまる。コールドスリープから目覚めると、宇宙船内に大量のエイリアンの卵。そこから騒動はやまず、卵は孵り、指示を仰ごうとしたマザーコンピューターは暴走し、メテオロイド(流星群)と遭遇し、船体に穴が開き、内部ハッチからは密航者が出てきて、成体のエイリアンも出てきて、船外作業中のロイドは外宇宙へ飛ばされ、船内の酸素がなくなり、氷隕石を拾おうとしたら謎のポッドを拾って、そこから漂流吟遊詩人が出てきて歌い、モノリスみたいな高次元パトロールも現れ、地球からは自決命令が出て、宇宙海賊にも襲われ、UFOを手に入れたり人体改造されたりしながら、戻ってきたロイドは機械帝国に取り込まれて闇落ちしており、帝国の起源である捨てられたトースターの記憶を呼び覚ますべく、ワープして霧の惑星へ。そしてさらに王位継承争いへと物語はつづく。
今書いててもどこで息継ぎするんだこれって思うほどの、クライマックスだけで構成されたような過剰な展開量。これに終始、クルー全員で対応していく、どフィジカルどコメディ。
その中でユーリの過去がほどかれてゆき、ポエトリーラップと共に、地球に残してきたクズゲーマー彼氏との記憶が紡がれる。地元と宇宙。引力と外心力。人類はどうしてハビタブルな世界を抜け、ストレスフルな宇宙へとはみ出していくのか。スペースデブリはあいつの食べてたセブンティーンアイスの棒みたい。そんなリリカルなところもあって。
脚本作業はハードだった。密度がありすぎて、一行がなかなか進まない。酸欠になり、ガムをボトルで消費しながら、夜ごとスクワットしつつ、全身筋肉痛でどうにか書き上げた。運動量すごそうだから100分に収めようとしたら、全然2時間を超えていた。
初稿をプロデューサーチームに提出したら、笑ってもらえながらも「ハイブロウだねえ」と玉虫色の反応が返ってきた。確かに普通のつくりではない。けどある突破を果たすためには、極端なフォルムをしている必要があるし、特にこの宇宙船は、キャスト・スタッフ全員が体重をかけないと大気圏で爆発する、ピーキーな仕様になっているのだった。
11人のクルーは宇宙飛行士のように逞しかった。シーン1で早くも汗だくになって息切れし、そんなシーンが12ある。水を飲みに引っ込むタイミングもないほどで、どうしてもという場合には申告してもらって、宇宙船が揺れるリアクションに乗じて数秒ハケてもらい、そこで水分補給してもらったりした。
舞台上でこっそりタブレットだけでも舐めれたら唾液の出がぜんぜん違う、というアスリートみたいな裏技も開発された。人類はこうして進化を続け、宇宙へ出たのだな、と思った。
体力をもたせて走り切るだけではもちろんなくて、演技をして笑いを取りつづけなくてはならない。何このスポーツ、ってみんな思ってたと思う。
金丸は本番初日でノドがやられかけた。平井さんは劇の前半で汗をかきすぎて、後半は震えるぐらい冷えてきて風邪をひきそうになった。浦井さんが衣装の下に仕込んでいた保冷剤には、冷気を求めて役者たちが劇中しばしば触りにきた。井之脇さんはシンプルに4キロやせた。
中でもユーリを演じる伊藤万理華さんは、劇中は一度もハケずにエンドレスでリアクションをし続け、さらに振りつきのポエトリーラップを何曲もこなす、名門の部活の夏合宿よりしんどいことを、汗ひとつかいてない風情でやってのけた。無限のエネルギーを秘めたクエーサーみたいな演劇天体だぜ、と惚れ惚れしていたけど、まともに大変だったらしく、「詐欺です」「聞いてません」と何度か言われた。
シシドさんのセリフ量もおかしくて(僕がそうしたんですけど)、ミステリアスな漂流吟遊詩人として登場したかと思いきや、そこからの30分くらいはのべつ喋りつづける、という魔構成。ダメージがまず頬にきて、つぎは舌にきてる、って言ってた。それにしたって初舞台ウソでしょって感じの、すべてを掌握する立ち振る舞い。
ここでは書ききれないけど、スタッフの皆さんも全力でプロの演劇発表会に加担してくださいました。曲線をたたえた宇宙船の美術はこれこれってなったし、映像も衣装ヘアメイクも、レトロフューチャーみのツボをピンポイントで押してた。SF小道具や造形物はすべてが抱きしめたいクオリティ。大小エイリアン、光線銃、各種ロボ、ぐっとくるあれこれ。台本に書かれたすべてを実現してくださった、ニッポン放送チームと制作部演出部の顔つきはほとんどJAXAだった。
仕掛けもあちこち多すぎて、天井のバトンは吊りものでパンパンになってた。宇宙船のあちこちを光らせてくれた照明チーム、アラート音や爆発音のバリエーションが底知れなかった音響チーム。そして僕が弾き語りした野太いデモ音源を、スぺかわいい(スペーシーでかわいい)トラックに精錬してくれた、音楽の伊藤忠之さん。おかげでスペースオペラが本来の意味のオペラに接近遭遇しました。
宇宙船は爆発しなかった。全員がもれなく体重を乗せてくれたからだ。
予算に対してホンを書きすぎた感じはあるし、あの玉虫色の反応はそういうことだったかもしれないけれど、我々はたしかに重力圏を突破し、宇宙を見た。そこでは見たことない地球外生命たちが、ようこそ、やっと来たねと笑ってた。先に着いてたアメリカの高校生たちとハイタッチした。まったくあいにくの宇宙。
セブンディーンアイスの棒を胸に、次は機械帝国の逆襲編と、宇宙遺跡編が待っている。
編集部からのお知らせ
「リプリー、あいにくの宇宙ね」円盤化決定!

「リプリー、あいにくの宇宙ね」のBlu-ray&DVD化が決定しました! 2025年12月13日(土)発売です。9月12日(金)23:59までの先行予約には、伊藤万理華さんのオリジナル音声コンテンツが聴ける「直筆イラストカード」が特典として付いてきます。
上田誠さん脚本の映画『リライト』が上映中!
上田さんが脚本を務めた映画『リライト』が、6月13日より上映中です!
次回「演劇と氷山」(8月28日公開予定)では、本作が生まれた背景と制作の過程を上田さんがたっぷり綴られます。ぜひ映画とあわせてお楽しみください。
<イントロダクション>
監督:松居大悟、脚本:上田 誠のタッグが贈る!
史上最悪のパラドックス <タイムリープ×青春ミステリ>
この青春は、分解される―
数々の青春映画で若い世代から圧倒的な支持を集める松居大悟と、“時間もの”で高い評価を獲得している上田 誠(ヨーロッパ企画)。
“師弟関係”にある両者が初めてタッグを組んだ。原作は、「これを映画にしたい。やるなら松居大悟監督と!」と上田が熱望した、法条 遥の「リライト」(ハヤカワ文庫)だ。“SF史上最悪のパラドックス”として評判を呼んだ衝撃作を、上田脚本史上“最高に緻密な時間のパズル”で再構築し、松居監督が青春のもがき、輝き、そして感傷と希望で色鮮やかに綴ってみせた。
(映画『リライト』公式ページより)


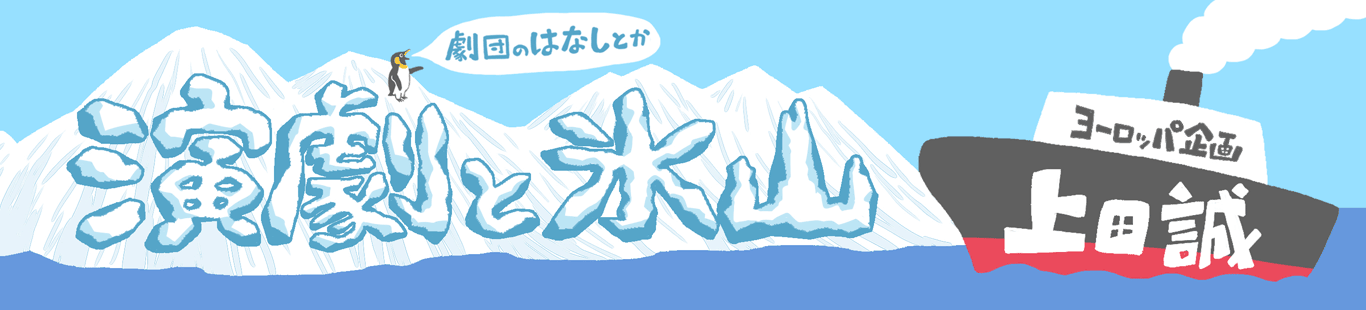
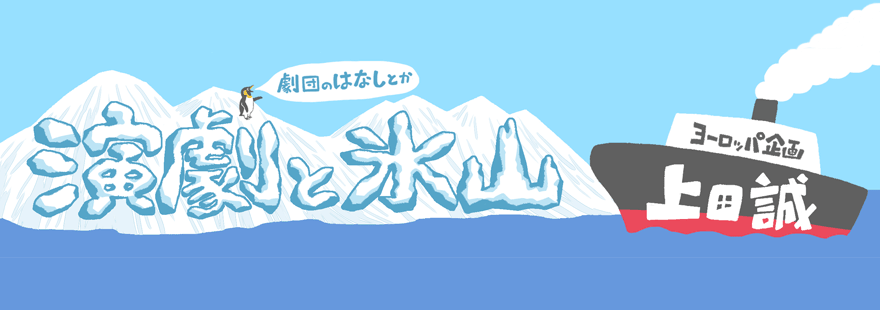

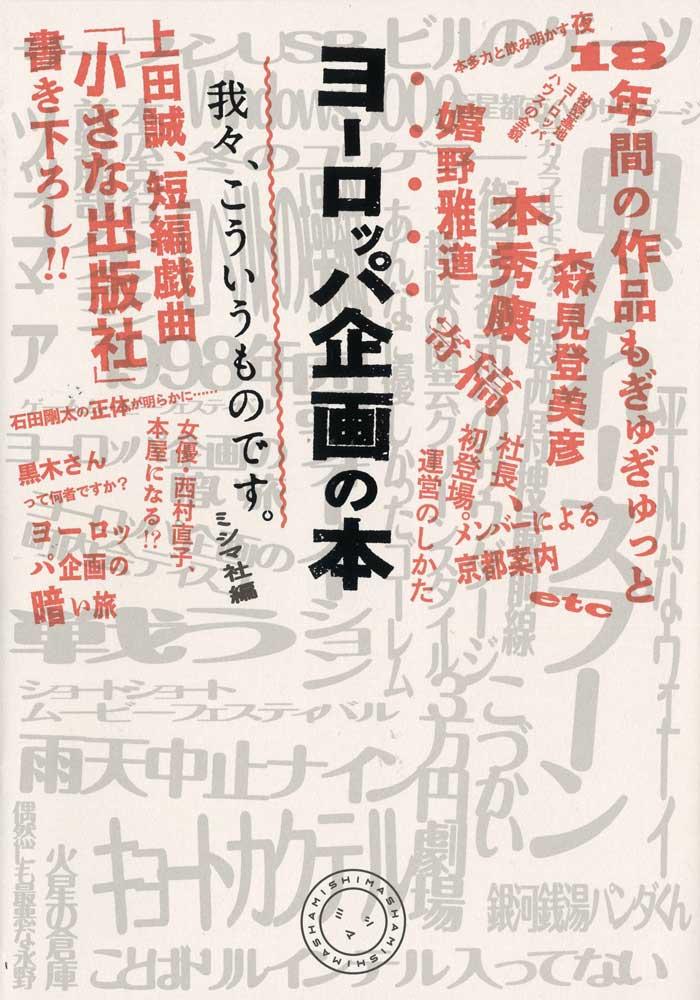


-thumb-800xauto-15803.jpg)


