第16回
羅針盤の10の象限。(後編)
2025.05.17更新
(前編はこちら)
⑥暗い旅
これは⑤の「ヨーロッパ企画」の象限に含まれるかもしれない。しかしそうするには、僕の魂を占める割合が大きすぎるので、もはやひとつの独立した象限として捉えている。
「ヨーロッパ企画の暗い旅」という、ローカルテレビ番組をやっている。2011年にKBS京都で始めて、今年で15年目になる。
始めたときからそういうコンセプトだったんだけど、自分たちで何もかも作る番組。企画も撮影も出演も、編集も納品も自分たち。2週間に1本、30分番組を作る(実尺23分)ということを、15年続けている。放送回は現時点で360回を超える。
YouTubeみたいなもの、といえば分かりやすいかもしれない。それをYouTubeが隆盛する前から、KBS京都という地上波で始めた。予算はかかりません、と企画を持っていったら、OKをもらえた。言ってみるもんだなと思う。
MCは、メンバーの石田剛太と酒井善史。企画構成は僕で、ディレクターやスタッフは少しずつ入れ替わりながら、今は8人のチームでやっている。
元々バラエティ番組に興味があり、自分たちの番組を作りたかった。
他局で冠番組をやらせてもらえたりもしたけど、単発で終わったりして、どうにか継続的にやる方法はないものか、と考えた。生意気な話だ。
「水曜どうでしょう」を見て、これだ、と思った。地方発のドキュメンタリーバラエティ。これなら最小のチームで作れそう。
偶然そのころ、作り手の藤村さん・嬉野さんに出会い、手ほどきしてもらった。画面に隠されたクリエイティビティの数々に感銘を受けたけど、何よりいいなと思ったのは、「自分たちで何もかも一から考えて、番組を作ることの、面白そうさ」だった。それをやっている人たちが北海道にいる。君らも来いよ、と言われてるみたいだった。
始めるにあたって、カメラは1カメ、テロップも1種類、と決めた。SEやBGMも入れない。初期は照明もマイクもなく、ロケはMC2人と、ディレクター兼カメラマンの西垣君、そして作家の僕の4人。バンドみたいだなと思った。続けるうちに充実していけばいい。
1回目を作ったら面白くできたし、作るたび面白くなっていった。第8回放送で「SAKEKE完全攻略の旅」をやったとき、こんな面白いのが撮れちゃってどうしよう、一躍有名になっちゃう、と思った。ならなかった。まあこんなことばっかりだ。
暗い旅のコンセプトは「まだ見ぬ面白さを探し歩くドキュメンタリーバラエティ」。旅番組ではないけれど、日常を離れて「魂の旅」をする。バンド・我々さんが提供してくださった、テーマ曲にある一節「ぼくしかできない すべてを生きるつもり」が信条だ。
普通のテレビでは見たことない面白さばっかりをやろうとした。怪談テロップ。区民運動会。闇鍋。ジグソーパズル。バスタブでんぐり返し選手権。木彫りの熊を彫る。
どれも面白く、そしてハードコアだった。見るたびやってることが違う、非常にレコメンドしにくい番組になった。面白さの本質はついていたし、本当に面白かった。そして面白いことと、バラエティ番組の成功はまた違う。
そんなことを15年やっている。やめてないの、と驚かれるむきもあろうが、やっぱり面白いことは面白い、という確信のもと、ライフワークのようにしつこく続けている。行き詰まることもしょっちゅうだけど、その都度いいことがあったり、出会いや光明があり、旅をもう少し続けようか、という気持ちになる。
去年、暗い旅を大きくリニューアルした。番組のYouTubeチャンネルを新設して、そこに過去作品を集めつつ、新作もフルで公開するようにした。ショートの新作も旺盛に作り、生配信も定期的にしはじめた。
ローカルテレビからYouTubeへと間口を広げた感じ。だけどKBS京都で深夜にやってるエッジの立ったローカル番組、という始まりは忘れない。ふとテレビで出会った人にびっくりしてほしい。
内容も初期からはずいぶん変わった。YouTubeが流行るにしたがって、企画系のコンテンツやVlogみたいなのが、動画の世界に溢れた。初期の暗い旅みたいなものを、高校生でも一般人でも、誰もが作れるような時代になった。それは端的に凄いことだと思うし、だったら僕らはそこに埋もれてちゃいけない。
そう考えて、最近は「モキュメンタリーコント」をやるようになった。「デスゲームの作家をやってるらしい旅」「先祖が恋に臆病な旅」「包丁男が机の下にいる旅」。ドキュメンタリーバラエティを模した、もはや完全台本による映像コント。準備のカロリーは半端じゃないし、台本が1本のドラマくらいの分量になる。小道具や準備物にも追われる。
だけどこれは誰もやってない面白さだし、劇団がやるバラエティとしての正解でもあると思う。やっと辿り着いた。見るのに体力もいるからYouTubeに向いてるとは言い難いけど、劇をひとつ作るような気持ちで作っている。一度見てみてください。
あとは「コラボ旅」も増やした。ヨーロッパ企画や暗い旅が受けた、いろんな仕事の現場に潜りこんだり、コラボを持ちかける。「トニセンコンサートに酒井ロボを納品する旅」「久保史緒里さんの青春文化祭に潜りこむ旅」。東映京都撮影所、京都競馬場、パン屋さん、眼科。普通じゃ見れない景色が見れる。これも暗い旅のフィロソフィーに沿っていると思う。
夏にはグッズを出し、「暗い旅キャンプ」というイベントをKBSホールでやる。過去もっとも賑わうイベントになると思う。暗い旅は、15年経った今がいちばん命を燃やしているし、面白い。
⑦文芸
この象限を掲げることもおこがましいけれど、確実に僕の中に存在するので、書く。この領海においては、僕はおみそであり、学童のような心持ちでいる。
たとえばこんな風に、エッセイを書かせてもらうことがある。それとか、原稿を頼まれたり、小説を依頼されるようなことも。
基本的にそういう仕事を、僕は避けがちに生きてきた。必要があれば書くが、なるべくなら書かない。なぜなら僕は劇作家であり座付き作家で、文章を書くことは「一人でもできる」からだ。
劇団というのは特別な季節だと思っている。一度手放せば、簡単に手に入るものではない。だから劇団でいられる間は、できるだけ座付き作家としての仕事を優先しよう。エッセイや小説を書くことは、いずれ劇団を辞めたときの楽しみにとっておこう。
そう考えて、小説などは断ってきたし、エッセイの連載なども極力、引き受けないようにしてきた。自信がなかったこともある。小説や文章を読むのは好きだし、それだけに、半可な気持ちでやっても太刀打ちできない。元々人のセリフを書くのは得意だけど、自分の言葉は持ってないし、って。
その思いは今でも変わらない。だから小説や書きおろしの仕事は、たぶん受けない。だけどこのごろは、文章を書くことはジョギングのようなものかもしれない、って思うようになった。あるいは包丁を研ぐようなことかもしれない、って。
2015年に「TOKYOHEAD」という劇で、初めてモノローグを書いた。それまでは会話劇しか書いたことなかったけど、原作が冗談みたいにキザな地の文で構成されていて、これをセリフにも生かさない手はないと考えた。だったらモノローグだ。やってみると思ったよりうまく行った。
翌年の「来てけつかるべき新世界」で、より意識的にモノローグを取り入れてみた。新世界の串カツ屋を切り盛りする「マナツ」の、じゃりン子チエみたいな一人語り。これも思いのほかよく書けた。誰かのセリフとしてならモノローグも書けるんだ、と分かった。その作品で戯曲賞ももらい、自信がついた。モノローグは使える武器のひとつになった。自分の言葉もたゆまず磨いた方がいい、と思うようになった。
元々がゲームデザイナー志望だったし、文芸をしたくて演劇を始めたわけではないから、文芸以外の方法で演劇をハックしよう、と思っていた。でも文芸の力が借りれるなら、劇作の幅はもっと広がる。言葉の力を使って、もっと遠くへ、あるいは深いところへ行ける。
何より幸運なことに、身に余るような先達にも恵まれた。
文筆家のせきしろさん。こんなユーモアを湛えた特殊な文芸が存在していいのだ、ということを教わったし、自著の解説やコントなど、たくさん書く場をくださった。
森見さんには、お会いするたび文章の秘密そのものを、ご自身の悩みを吐露するような形で教えてもらっている。森見さんに相談したおかげで書けたエッセイもある。
万城目学さんも、創作の秘密を飄々と語ってくださるばかりか、去年は森見さんとともに、シャーロックホームズ同人誌の執筆にまで声をかけてくださった。翻案とはいえ小説を書くのは初めてだったが、引き受けた。締め切りをすぎ、万城目さんに原稿を取り立てられるという贅沢を味わった。
そして三島さん。この連載もそうだし、筆の重い僕にじつに根気よくつき合ってくださる。僕の新作をご覧になっては、全身に歓びが湧くような言葉をいつもくださる。錚々たるミシマ社の執筆陣に混ぜてもらえていることは僕の誇りであるし、呆れられないようにこれからも書き続ける所存である。
⑧テック
ここはまだ霧がかった海。全容が見えず、おぼつかない。だけどきっとルートはあるし、劇作家として航路を進めてみたい。地図を作りたい。メンバーや身内もあまり知らない、自分だけがおぼろげに見えている海。そんな海のことも書いておく。
劇団でゲームを作ったと書いた。実写ムービーを使ったFlashゲーム。初めて作ったのは2004年。Flashという規格がかつてあったんです。
僕は理系で、ヨーロッパ企画を立ち上げた諏訪さんも理系。メンバーやスタッフも、なんとなくデジタルに強かった。
Flashはゲームが作れて、ムービーも扱える。ならば実写を使ったインタラクティブなゲームが作れるんじゃないか。そう考えて「ゲームムービー」というシリーズをHPで展開してみた。
コマンドでムービーの行く末を選択する「偶然にも最悪な永野」「名探偵スワー」。動画のおかしなところにツッコミを入れる「ツッコマニア」。メンバー酒井にカーソルが触れると爆死する「電流イライラ酒」。
新しい面白さだったし「発明」だった。数十本作ったし大会までやり、それなりに盛り上がったけど、見返りもなく、そのうちに冷めた。
10年ほど経ち、僕らのゲームムービーが「ゲーム実況者」によって発掘され、イジられているのを知った。動画はどれも数十万回再生。SNSには「ヨーロッパ企画草」という言葉が散見された。ヨーロッパ企画はトンチキゲーム制作集団だと思われているようだった。
悪い気は全然しなかったし、10年早かったのだと思った。実況者は潤い、我々には実入りがないな、とは少し思った。その後スマホでもリリースしたが、ゲーム自体はやはりダウンロードが伸びず、それをイジる実況者たちが潤った。
あるいは2013年。「前田建設ファンタジー営業部」という舞台をやった。今となっては珍しくないけど、劇中にリアルタイムモーションキャプチャーを採り入れ、役者と連動して映像中のCGキャラクターが動く、目新しい演出を試みた。マジンガーZの格納庫に、アバター的に入ってみる、というシーン。小規模な劇に似つかわしくないテックフルな感じで、異様だったし面白かった。
同じシステムで、翌々年には格闘ゲーム「バーチャファイター」のキャラクターを役者と連動させ、ゲーセンの劇を作った。先ほど書いた「TOKYOHEAD」。その劇ではまた、本物のゲーム筐体を使って、実際に役者同士がゲームで対戦し、勝敗によってストーリーが変わる、というギミックもやった。なかなか画期的だったと思う。劇場がゲーム会場みたいになった。
2020年。コロナ禍において、ムロツヨシさんと真鍋大度さんと「非同期テック部」というユニットを結成した。真鍋さんはライゾマティクスの代表であり、プログラマー。インスタライブやYoutubeの生配信で、テックを駆使したサプライズのような作品を上映した。
真鍋さんとのご縁はその後も続き、虎ノ門ヒルズでのライゾマティクス×ELEVENPLAYのダンス公演に、ストーリーで参加した。テックとダンスの競演に、物語を付与していくような作業。こういうメディアアートの領域にも、劇作家の関わりしろはあるのだ、と鼻を膨らませた。
これらは僕の中で繋がり、うっすらと航路をなしている。「来てけつかるべき新世界」でドローンやロボットを登場させたことや、映像でギミック撮影を好むこと、ゲーム関係のオファーをしばしばもらうことなんかも。
去年はリアル脱出ゲームのSCRAPさんとコラボして、スマホを片手に会場を散策して謎を解く「学校の77不思議からの脱出」というゲームを作った。スマホでヨーロッパ企画メンバー扮する「霊」と会話できる、という仕掛け。
暗い旅では、東京にいる石田のアバターロボットを京都に作り、東京からロボットアームを操作してもらった。京都にいる石田ロボがウィィィンとひどくゆっくり手を上げた。バカバカしく感動的だった。
テックをエンタメにしたいし、物語で補完したい。劇にテックを採り入れもしたい。自分はそういうことが得意だと思う。
この海の名前は、まだない。何と呼んでいいのか分からない。しかしとんでもない財宝が眠っていそうである。
⑨お笑い
お笑い。バラエティ。芸人。
昔から好きだった。関西で育ったから余計にか。バラエティ番組は一通り見ていたし、中学や高校の頃には、吉本の若手芸人のライブを観に行っていた。千原兄弟さん時代の二丁目劇場が好きで、憧れていた。
演劇と出会い、三谷幸喜さんが好きになり、コメディ劇団を始めた。
しかし自分の中で、コメディはどこかお行儀が良くて、芸人さんのやるお笑いは獰猛に思えた。コメディ的な笑いと、芸人さん的な笑いの、融合ってできないものか、と漠然と考えていた。
日本では「笑い」が異常発達していて、ステージパフォーマンスから「お笑い」が独立している。テレビでの笑いと結びつき、「お笑い芸人界」として、独自の発達を遂げている。演劇における「コメディ」とは何だか相容れず、というか笑いに関して「コメディ」が置いていかれている印象がある。僕らは演劇界でコメディをやっているけど、本当に笑いを目指すなら、芸人界を無視するわけにはいかないぞ。
そんな風に思っていたから、芸人さんのことは絶えず意識してきたし、何より好きだったし、今でも見ているのは、ドラマや映画よりバラエティばかりだ。
「ヨーロッパ企画」が、芸人さんに勝てる方法をずっと考えていた。
僕らに芸人さんのような筋肉はない。だけど構造を作る力や、役を演じ抜く力はある。2時間それをやり抜けば、芸人さんが作る瞬発的な笑いより、遠いところへ行けるんじゃないか。壊すことより構築すること。より大きなバカバカしさを創造すること。そういう笑いに、芸人さんも巻き込みたい、といつしか思うようになった。
2005年、小籔千豊さんとコントライブをした。「ゴルフ」というタイトルの、すべてが一つの物語に収斂するような、テーマを持ったコント集。
当時から小籔さんは辣腕だったし、出たとこ勝負でやりたいから立ち稽古はなるべくしません、というスタイルだった。僕らは僕らだけで稽古した。僕らが世界を作るから小籔さんには壊してもらえばいい、と思っていた。
その目論見はうまくいって、当日の小籔さんのアドリブは凄まじかったし、コントライブ全体のまとまりも見事だったと思う。小籔さんの凄さは「小籔ショック」として語り継がれ、その後のご活躍もむべなるかなだ。小籔さんとやってから、あまり怖いものはなくなった。
他にも色んな芸人さんたちと、番組をやったりイベントをご一緒したりした。
野性爆弾、ザ・プラン9、友近さん、なるみさん、東京03、ピース、おぎやはぎ、かもめんたる、チョコレートプラネット、ジャルジャル、劇団ひとりさん。
たぶん僕らが芸人から始めていたら、全然手が届かない人たちばっかり。だけど僕らは劇団で、場所や企画から作れたから、そこに乗っかってもらうような形でご一緒できたし、飛び級で超人たちと組手しているうちに、僕らもずいぶん太くなった。
自分の転換点としては、大喜利イベント「ダイナマイト関西」が大きい。
大喜利は昔から興味があったし、やるなら若いうちにやっておかないと、キャリアを重ねたらやれなくなるな、って思ってた。
2006年に「D関」主宰のバッファロー吾郎・A先生に誘ってもらい、初めて出場した。そのときは、相手は芸人さんでなく、放送作家さんや一般の方と戦う「ノンジャンル予選」。2回戦で負けて、優勝したのがせきしろさん。圧巻の大優勝だった。面白いことは正義だと思ったし、自分も勝ちたい、できれば芸人さんと戦いたい、と厚かましく思った。
2010年に優勝した。芸人さんたちに混じっての戦い。これは途轍もない勲章になった。コメディ作家として、これでもう舐められないぞ、と誰も舐めてないのに思った。芸人さんたちにコントやセリフを書くことに、気後れがなくなった。
大喜利を発展させたようなイベント「企画ナイト」を、せきしろさんとA先生と、あと劇団の酒井善史と僕とで、長らくやっている。
大喜利って相手の答えのラインを潰しながら答えるようなところがあって、少し「破壊」を伴うけど、創造していくような大喜利だってある。その可能性を教えてくれたのが、せきしろさんとA先生だ。ニッチなイベントだけど、相当ラディカルなことをやっていると思う。暗い旅もそう。
大喜利的な考え方は、脚本にも役立っていて、ひとセリフごとに、大喜利するような心持ちでセリフを書いている。
かつてはバラエティ番組を作ることに興味があったけど、今はなくなった。それよりドラマや物語に興味があるし、なんなら笑いのない作品もアリになってきている。世界が作りたいんだと思う。
それでもやっぱりお笑い芸人さんへの興味が尽きることはない。お笑いはまだまだ日進月歩だし、みんなクリエイティブだからだ。
面白い人たちが集まりやすい。その中で活躍している人たちは、やっぱり半端なく凄い。お芝居をしたってモノを作ったって、何をしたってすごい。
西野亮廣さんや板尾創路さんに、自分の劇に出てもらった。今の劇にはかもめんたるさんと男性ブランコさん。皆さん、役者としてもコメディリリーフとしても凄腕だ。
コント芸人さんと僕の劇は、とくに相性いい感じがする。前に書いた「S区の奇妙な人々」もそうだし。
僕の劇世界で、芸人さんが輝き、笑いを作ってくださること。芸人さんの世界を、僕が物語や劇作の力で、なんらか拡張すること。そういう関係であれたらいいと思っている。芸人さんとコメディを作りたい。あとは見て笑って楽しむだけだ。
⑩音楽
これはちょっと気恥ずかしい。けど自分の中で年々、大事な要素になってきている。恥ずかしさの正体も、節度も少しずつ分かってきた。
小学生の頃から音楽が好きになり、中学でギターを始め、パソコンでの作曲に目覚めた。高校になるとギターを歌を習い、好きなミュージシャンのコピーを弾き語りする日々だった。恥ずかしながらオリジナル曲も作った。
ヨーロッパ企画を始めて、どんどん音楽から遠のいていった。特に、自分で作ったり弾いたりすることから遠のいた。メンバーがあまり音楽をやらない人たちだった、というのもあるし、僕は演者じゃないから、歌や演奏を披露するのも違う。
僕の音楽は、ヨーロッパ企画にいらない要素だった。そんなことで出しゃばらないほうが、うまくいきそうだった。人はやりたいことよりも、求められることをする方がいい。プライベートで気晴らしにギターを弾くことはあっても、人前で演奏したり、自分の音楽を披露することは「封印」した。
劇中音楽を、敬愛するミュージシャンの方々にお願いするようになってからは、ますます僕が音楽でなにかする必要もなくなった。
封印を解いたのは、つい最近。2021年にフジテレビさんでやった劇「夜は短し歩けよ乙女」で、ポエトリーラップを取り入れた。
「~乙女」の原作は、魅力的な情景描写に満ちていて、しかしこれを会話にすることはできないし、モノローグにするのも飽きてしまいそう。
ならばポエトリーラップにしよう、と思いついた。「森見節」を、可愛らしいラップに落とし込む。乙女役の久保史緒里さんは歌や踊りが上手だし、「夜は短し歩けよ乙女」というタイトルからして七七調だし。
ラップなら、ミュージカルのように本格的に歌う必要はなく、セリフからしれっとポエトリーラップに入れる。そればかりか、ミュージカルでありがちな問題「セリフから急に歌へ移行することのしらじらしさ」さえも、ラップを挟むことで緩和するのではないか!
そんなふうに大発明した気分になって、「~乙女」の劇全体をポエトリーラップでくるんだ。これは大正解だったし、久保さんのラップはとてもキュートだった。
「~乙女」では他にも、音楽的な演出や演奏をキャストにやってもらい、たいへん良い感じに劇を彩った。自分で歌いさえしなければ、演者さんに自分の音楽をあてがうことは悪くないのか、と、長年眠らせていた音楽心に火がついた。音楽を、音楽劇を、もっと作りたい。
2023年には「たぶんこれ銀河鉄道の夜」という劇をやった。宮沢賢治の物語世界を下敷きにした、デスゲーム音楽コメディ。
「銀河鉄道の夜」にもまた風景描写が多く、これらを音楽に乗せない手はなかった。「~乙女」とは趣向を変えて、宮沢賢治の原文を一字一句変えず、それにメロディを付ける、ということをした。
ずいぶん持って回った文体だから苦労したけど、「銀河鉄道の夜」に新味を吹き込むことができたと思う。「~乙女」の時と同じく、僕が弾き語りでデモテープを作って、それを音楽の伊藤忠之さんが楽曲に仕上げる、というやりかたが定着した。
2024年「鴨川ホルモー、ワンスモア」では音楽要素は鳴りを潜めたが(さだまさしの替え歌などはあったけど)、今年の「リプリー、あいにくの宇宙ね」では、6曲のオリジナル曲を伊藤さんと作った。宇宙用語やSF用語を散りばめた、スペイシーなラップや歌たち。主演の伊藤万理華さんがぼやくように舞って歌う。チャーミングが爆発している。演劇で新しい表現を見つけたような気分でいる。
他にも、リアル脱出ゲームの主題歌を作ったり、トニセンのコンサートで替え歌の歌詞を書いたり、青春文化祭でちゃっかり劇中曲を2曲作ったり。
やりたさが先行してはいるけど、物語の中での音楽の活かし方が分かってきたし、自分は音楽じゃなく「劇中歌」が得意なんだ、とも気付いた。
物語に必要な音楽を、劇作家として適切に作る。言葉を音楽に乗せてよりよく響かせる。そして間違っても自分では歌わない。
ーーーー
自分の仕事の総覧のようになった。
この①から⑩までが、いまの僕の羅針盤の象限であり、進むべき海域だ。
僕の手帳には、この10象限がマトリックスのように書いてあって、新しい仕事が決まったら、付箋に書いて、それをマトリックスのふさわしいところに貼る。そんな風にして自分の海路を眺めている。ロックマンのボスキャラを選ぶみたいに、次はどこへ行こうか、って。
こっちはいま追い風だなあ、とか、こっちは中々進まなそうだぞ、とか。こっちから迂回したほうが遠くへ行けそうだ、とかもある。10象限あるから大変だけど、景色が変わるから飽きないし、あるところでの経験が別のところでの土産話になったりもする。
どの海域にもゴールはなく、果てしない。そもそもゴールを目指しているような航海でもない。匂いを頼りに、往けるだけ往く。航跡が面白いといい。
(了)
編集部からのお知らせ
上田誠さんの新作「リプリー、あいにくの宇宙ね」
上田誠さんが脚本・演出を務める舞台「リプリー、あいにくの宇宙ね」が、東京にて上演中! 6月は、高知・大阪公演もあります。
「リプリー、あいにくの宇宙ね」
<イントロダクション>
スクランブル発生! 今度は何が起きている? 宇宙はつねに変化に満ちているし、いつだって射撃訓練所の中だ。たえず11人目がいるようなものだし、スタービーストは暗黒の森林で息をひそめている。それにしてもひどすぎないか、と二等航海士・ユーリは思う。量。このトラブルの量はなんだ。マザーCOMはなぜ答えない。船長はなぜ判断しない。ロボ、三原則いまはいいから。アーム、そんなポッド拾わなくていい。漂流詩人乗ってこなくていい! これどこからのスライム? 石板、いまは進化させていらない! ユーリは白目で歌う。リプリー、あいにくの宇宙ね。ってハモんのやめて。
<公演スケジュール>
●東京 本多劇場
2025年5月4日(日・祝)〜5月25日(日)
●高知 高知県立県民文化ホール オレンジホール
2025年6月3日(火)
●大阪 森ノ宮ピロティホール
2025年6月6日(金)〜6月8日(日)
『ちゃぶ台13』に上田誠さんのエッセイ掲載!
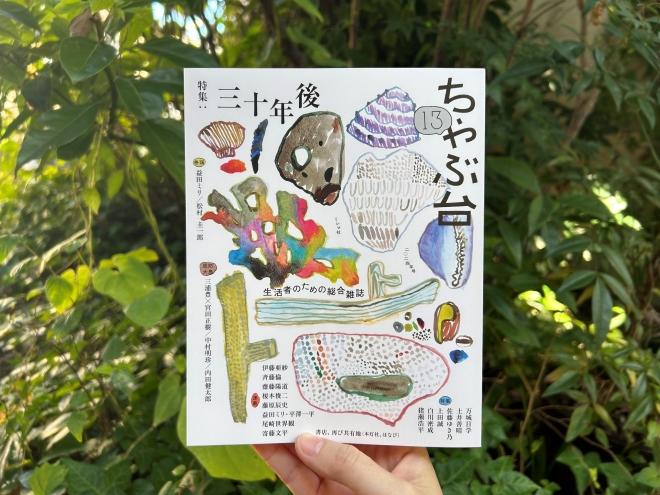
2024年10月刊の雑誌『ちゃぶ台13 特集:三十年後』に、上田誠さんがエッセイ「劇団と劇の残しかた ~時をかけるか、劇団」を寄稿されています。ぜひ、本連載とあわせてお楽しみください。
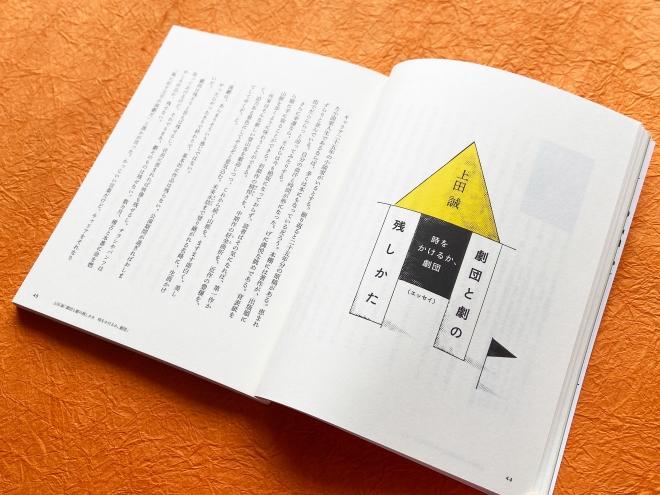
上田誠さん、ミシマ社通信に寄稿!
万城目学さん著『新版 ザ・万字固め』(2025年1月17日発刊)にはさみこまれている「ミシマ社通信」に、上田誠さんが熱い原稿を寄せてくださいました。タイトルは「万城目文学の恐ろしさ――脚本化を許さぬ文章の完成度について」。こちらから一部お読みいただけます!
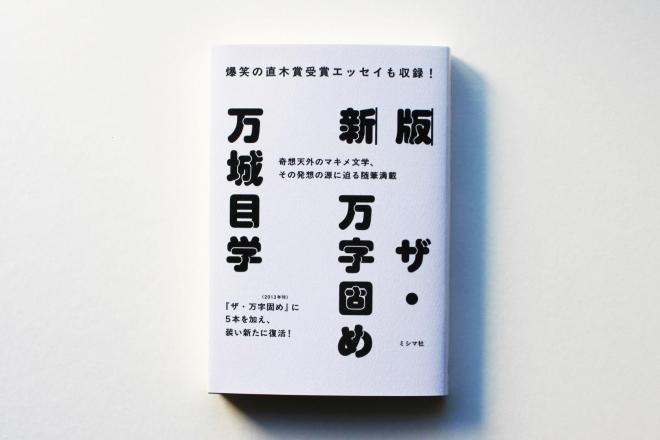


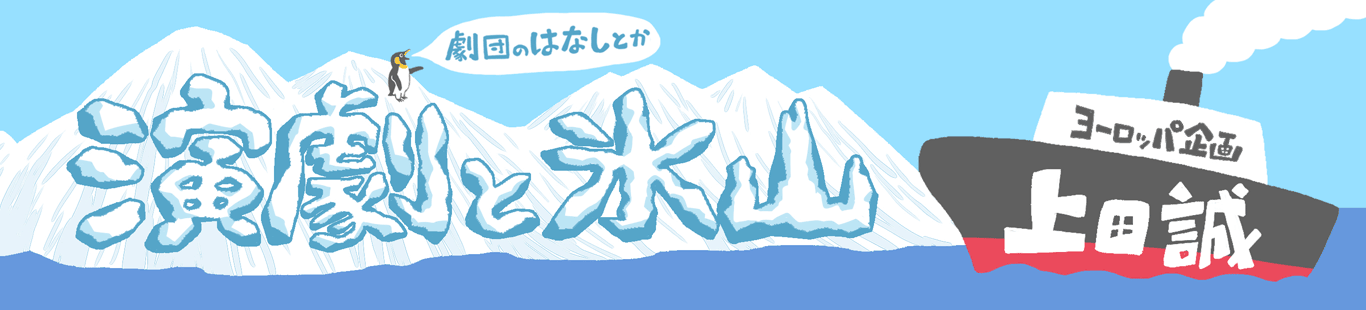
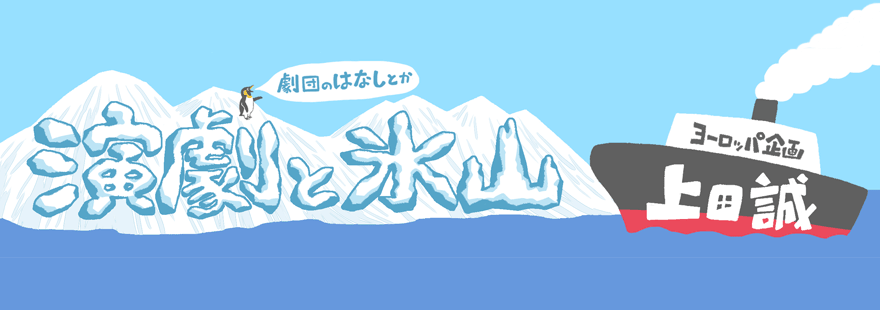

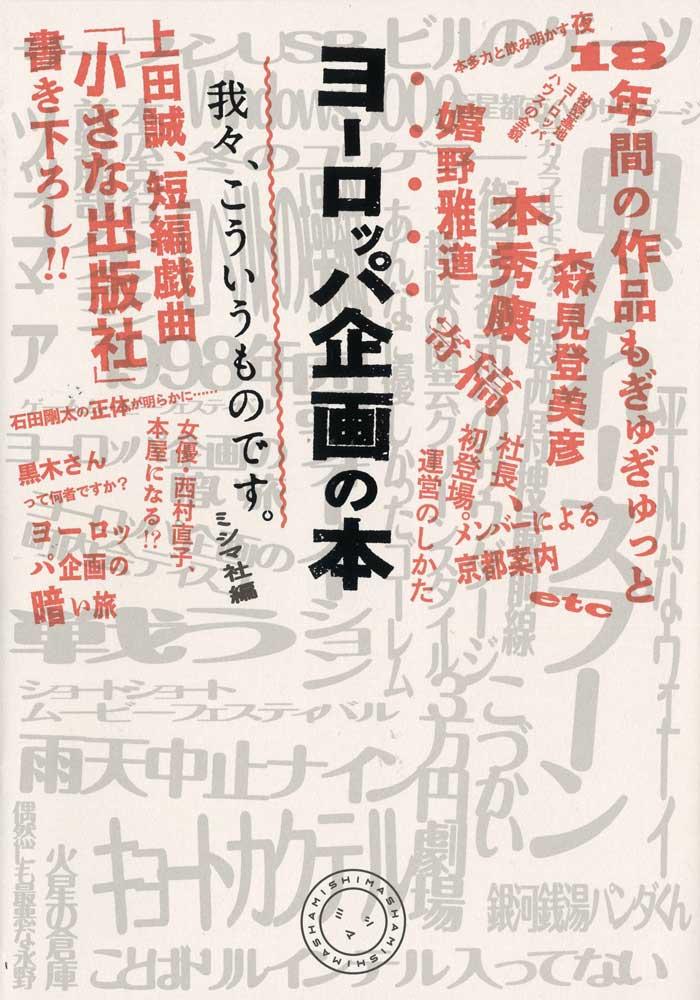


-thumb-800xauto-15803.jpg)


