第18回
松居さんとリライト。
2025.08.28更新
見返すとその夜、僕は唐突にラインを送っている。Amazonのリンクを貼り、「これをいつか僕脚本で松居さんに撮ってもらいたいですよ」と。
リンク先は、ハヤカワ文庫の小説「リライト」。法条遥先生による、破格のギミックを持つ青春タイムリープSF。僕が読んだのはラインを送るより何年も前だけど。
そして送った相手の「松居さん」は、松居大悟監督。さん付けで呼んでいるけど後輩で、このあと書くが、松居さんが僕のことを「師匠」と呼んでくれることもあり、そのときは「先生」と呼び返す。仕事をするバランス上、そのほうがいいからだ。
分かりにくい始まりだが、今となっては僕もよく分からない。それまでのラインのやり取りの助走があったわけでもなく、いきなりふと思いついたように映画企画というか妄想を伝えている。もしかしたら酔っていたのか、なにか自分だけの昂ぶりがあったのだろう。そういうことを助走なしでラインできる相手でもある。
そして松居さんはそれに応えてくれ、「今アマゾンで頼みました。早急に読みます! 万博までにやりましょう!!」と、読んでもないのに似た温度で返事をくれている。
このやりとりをしたのは2020年の10月9日。そして5年後の2025年初夏、万博に先を越されはしたけど、映画「リライト」は、全国260館ほどで公開された。
松居さんと出会ったのは2007年だから18年前。見ず知らずの若者から劇団のアドレス宛にメールが届いた。
「大学で演劇をやっている松居大悟と申します。ヨーロッパ企画の『サマータイムマシン・ブルース』を見て演劇を始めました。今度、東京の演劇祭で劇をやるのですが、上田さんも同じ演劇祭にトークゲストで来られるそうですね。よかったらお話ししたいです」というような内容。嬉しいけど、日が違いそうだし、ちょっと面倒くさい人かもしれないしなんて返そうかな、とかって放っておいたら、「あのメール、どうなりましたかね」的な催促のメールがもう一通届いた。
こういうのって催促されるっけ。ほんとに面倒くさい人かもしれない、って思いながら、渋々返したのち、演劇祭で会ったらすごい意気投合して、作品も観てないのに飲んで喋って、そのうちに終電もなくなり、「家行っていい?」って松居さんの部屋に泊めてもらった。面倒くさい人は僕だった。けど後にも先にも、初対面の人どころか誰の家にも急に泊めてもらったことなんてないから、よほどもう少し一緒に居たかったんだと思う。松居さんは面食らってた。
松居さんの部屋には壁一面に張り紙がしてあって、「目が覚めたら走り出せ」「もっと面白く」「泣きながら笑え」などと、二郎系の店名かなと思うような押し出しの強い文言が、肉筆でびっしり壁を埋めていた。
下の方の壁には「下を見るな、上を見ろ」と貼られていたりもして、ギミックが利いているが落ち着かない部屋だな、と思った。こんな部屋で寝起きしているのかと思うと面白そうさしかなかった。劇を観たらまともに面白かった。
それから松居さんを劇団公演の仕込みに誘い、誘ったことを忘れていて僕が行かない、という狼藉をへてメンバーとも打ち解けたのち、今度は僕の本公演にくっついて、文芸助手をやってくれませんか、と誘った。
これも松居さんは快諾してくれ、2008年の「あんなに優しかったゴーレム」という公演の制作過程にみっちり付き合うべく、京都まで来てくれた。そこで僕があまりにも劇を書けなくて、泣いたり悶えたりといった背中を見せてしまい、松居さんは静かに「コメディは大変だな...」と思ったそう。僕は泣きながら笑えてなく、泣いてるだけだった。
ほどなくして松居さんは劇団「ゴジゲン」を立ち上げ、平行するように映画監督としてめきめき腕と名をあげ、いつからか松居さんは僕を師匠と、僕は松居さんを先生と呼ぶようになった。演劇と映画でそれぞれ先達しあってる感じだからちょうどいい。
にも関わらず、ふたりで同じ作品に関わったことはほとんどなく、いつか松居さんと僕のタッグで映画でも作りたいねえ、なんてよく話していた。
そんなことがあっての冒頭のラインはやはり唐突で、でも振り返ってみれば、出会ったときのメールも、宿泊も唐突だった。唐突でもなんとなく大丈夫なふたりだ。
ラインしてから1か月後、松居さんから「とんでもないですねこれ。面白すぎます。時間もので、青春でもあり、ホラーでもある! 実写でやるととんでもなく背徳的な作品になりそうです。機会探ります!」とのリアクションが届いた。
引用でラクしてごめんなさいですけど、「リライト」はまさにそういう作品。初めて世に出たのは2012年だそうで、僕が読んだのはその少しあと。書店でふと「SF史上最悪のパラドックス」と書かれた帯を見つけ、時間心がどくりと脈打った。
読んでる間じゅうずっとザワザワどきどきしたし、展開がある閾値を超えた瞬間の衝撃はおそろしかった。意図して、かの名作「時をかける少女」を本歌取りしつつ、その考えうるもっとも胸糞でトリッキーな解釈を、黒い情熱で書ききったような、しかし文章の中には優しい夏の風が吹き抜けてもいるような。まさに破格のリライトだった。
SFというものの底抜けの企みと悪意を見た気がしたし、SFってこういうジャンルなんだよ、とぎゅうっとなった。作者は法条遥という新人だそう。神をも恐れぬ人がいるなあ、と思い、そのときは映画のことなんて想像もせず、「リライト」は圧倒的作品として僕の胸にしまわれた。
胸にしまわれたが本棚にもしまわれ、そして割と目に付くところにしまわれていたため、ときおり背表紙を目にして意識に上るつど、「映画化できたら面白かろうなあ」という妄想が転がされていたんだと思う。
それがあの夜花開いたんだきっと。松居さんのエモーショナルなところと僕のロジカルなところが、「リライト」ならどっちも爆発させられるかもしれない、って。とにかくロジカルな仕掛けがみっしり詰まった、グロいほど整合性で満たされた脚本を僕は書く。松居さんならそこにエモーショナルな風を吹かせ、骨組みなんてまるで感じさせない、情動に溢れた映画にしてくれるだろう。
法条先生となんの接点もなく、映画化のお許しがいただけるかさえ分からないのに勝手に盛り上がった。もちろんプロデューサーもいない。だけど松居さんも夜の熱に当てられてくれた。
脚本家と監督がこうして盛り上がったところで、企画には手足が生えず、そのうちしなびてしまうのが関の山なんだけど、松居さんはほんとに方々に打診してくれ、一年後にはプロデューサーを見つけ出し、その見つけられてしまった岡田プロデューサーは、法条先生と出版社に開発の許可をとりつけ、社内にも企画を通してくださった。
言い出しっぺで先輩のくせに、このプロセスにおいて何一つ動かなかった僕は、「目が覚めたら走り出せ」を何も体現できていない不肖の師匠であるが、こんなふうにフリを回収することならできる。ロジカル担当の僕とエモーショナル担当の松居さんによる映画が、主に松居さんの頑張りによって動き出した。
2022年、脚本開発が始まった。松居さんと岡田さんと僕の3人で、まずは時間構造のルールを定めた。
原作小説は「リライト」の名の通り、時間線が上書きされるような仕組みになっていて、それがえも言われぬ不気味さを生んでいる。だけど映画化においては、さらに整合性を強調したい。これはひとえに僕の都合によるもの。得意技に持ち込みたかったし、過去いち複雑なパズルに挑みたかった。原作の卓抜なアイデアや怖さを残したままで、それはできそうに思えた。
松居さんと岡田さんの合意をとりつけ、法条先生のご海容もえて、難解な詰め将棋を解くような作業へ。ここからが地獄で、書いてて楽しいエピソードはないけど、パズルが仕上がるまでに丸一年かかった。
松居さんと岡田さんは泣けるほど根気よく付き合ってくれたけど、「そろそろ脚本いけますかね」という柔らかな催促を何度も聞いた。初めてメールをもらったとき以来の催促だ。しかしそんな悠長な状況ではなく、岡田さんはストレスで少し丸く禿げていた。ずいぶん申し訳ないことをした。
松居さんとは打ち合わせの帰りに、よく天下一品でラーメンを食べた。なんでかそれがルーティーンになり、そこで映画のこと、劇団のことをよく話した。
劇団はお互い過渡期のようなタイミングで、代表同士だから悩みも似ている。さすがに僕のほうが長くやっているから、先輩っぽく話せることも少しだけ多かった。
反対に映画は松居さんに多くのことを教わった。レンズのことから業界のことまで。
そういえば僕がかつて、大きな映画に関わっては書いた脚本が塩漬けになるのを悩んでいたら、自分の力が及ぶサイズで映画を作ることを教えてくれたのも松居さんだった。
そこから劇団で映画を作り始めた。「ドロステのはてで僕ら」「リバー、流れないでよ」。小さな映画がちゃんと形になったし、自分たちで映画を作れている実感が持てた。まったく映画においては松居さんは先生なのだった。
そんな松居さんと、今は「リライト」という大きな映画を作ろうとしている。
はじめ僕なんかは、尖った映画をコンパクトに作るようなイメージだったけど、岡田さんは「大きな映画にしましょう。ちゃんと予算かけてやった方がいいですよこれ」って言ってくれ、予算繰りに奔走してくれた。
それを受けて松居さんは、「だったら尾道で撮影したいです」と言った。僕はなんてこと言うんだチンさん、と思った。チンさんとは松居さんの昔のあだ名で、ちょっと恥ずかしい由来を持つ。ついそう心で呼んでしまうほど、それは身の程知らずの提案に思えた。
尾道といえば大林宣彦監督の魂の地であり、映画「時をかける少女」の舞台。そこで「リライト」を撮るということは何を意味するのか、分かってるのかチンさん。下手なもの撮ったら、尾道どころか映画界を歩けなくなるぞ。
本当にそのくらい思ったけれど、チンさんの気持ちはまっすぐだったし、岡田プロデューサーも「やりましょう」と禿げながら即断だった。やがて僕もほだされた。たしかにそこを塗り替える覚悟じゃないと「リライト」じゃないよな、って。
だったら、と方針をがらりと変えた。邪道上等の尖った映画ではなく、王道の青春映画にする。原作の驚きや切れ味は残しながらも、観終わった後には青春の残り香が爽やかに香り、明日への希望も残るような、エバーグリーンな名作にする。
プロットがあらかたできたころ、シナハン(シナリオハンティング。脚本のネタを拾いに現地へ行くこと)に一泊二日で出かけた。松居さんと岡田さんと、ラインプロデューサーの石井さんと4人で、尾道や瀬戸内海の島々を見て回った。
行けばその気になるし、特に尾道は、本当に映画のために出来ているような街で、ロープウェイからの眺めは、もうこの街で撮る以外に考えられない、と思わせた。
夜、スナックへ出かけてみようとなった。映画のクライマックスにはスナックが登場するので、もしかしたらいいロケ地が拾えるかもしれない。「リンダリンダ」というスナックに目星をつけて入ったら、内装から広さまですべてが理想的で、もうこの店で撮る以外に考えられない、と思わせた。よくそう思わせてくる街だ。
もはやロケ交渉もしてしまおう、となり、ママであるリンダさんに気に入られようと、リンダさんのカラオケに合わせて盛り上げ、僕は叩けないドラムを叩いた。松居さんを見るとソファーですやすや寝ていた。チンさんめと思ったけど、最初にプロデューサーを見つけに動いてくれた借りを返せたような気もした。脚本が遅い借りは返せていない。
翌朝、僕はホテルで寝坊しかけたけど、松居さんは早朝から仕事をしていたそう。目が覚めたら走り出していた。こういうところで差がつくのだな、と思った。
シナハンで走る車の中で、主人公の美雪役は池田エライザさんにお願いしたいね、という話になった。キャスティング会議のつもりもなく、ふとした話から盛り上がって、そのままそれが実現した。シナハンにはこんな思わぬ成果もある。
ちなみに池田さんは松居さんと同郷で、僕もドラマでご一緒している。その時の池田さんは未来人役だった。今回は未来人に恋する役。
そして恋される未来人・保彦役には、仲良しであるイノッチに相談し、当時高校生の阿達慶さんを紹介してもらった。松居さんがオーディションして、居場所がここではないような初々しさが未来人にぴったりだった。
ほかのクラスメイトたちも、かつて松居組や僕の舞台で、ヒロインや主役を務めた人ばかり。映画の内容にも符合していたし、映画って縁でできていくのだな、ってしみじみ思った。ゴジゲンのメンバーや、うちからは藤谷理子さんも出てくれて、僕と松居さんのこれまでの歩みの、集大成というか大同窓会、ってかんじになった。
2022年の年の瀬、脚本の初稿がようやくできた。ずいぶん壮大になったなあ、と思い、尺を出してもらうと3時間半あった。なんちゅうもん書いたんですか、と松居さんは思っただろうけど、まずは労ってくれた。
とにかく整合性にだけは自信があるような、タイムトラベルの論文みたいな脚本になったけど、そこから松居さんとの共同作業の中で、説明しすぎているところを削り、感情の起伏を際立たせていった。
初稿でいったん力尽きてしまった僕は、脚本を松居さんにまるっと預けて、松居さんの思うように改稿してもらった。それを受けて、今度は僕がまた書き直す、という繰り返し。口には出さなかったけどリライト合戦だった。
途中からは、松居さんが直し、僕がそこを差し戻し、のループになった。ここまでくればどちらも正解だし、脚本はそろそろ監督のものになっていたので、最終的には松居さんが「現場で悩みます」という監督にしか使えない技を使って、9稿をもって撮影稿となった。季節はそろそろ夏の盛りで、撮影がすぐそこに迫っていた。
すこし戻った2023年6月、脚本を携えて、法条先生のもとへご挨拶に伺った。それまでお会いしたことがなく、出版社の担当の方も直接会うのは初めてだという。
どんな方なのか想像もつかなかったけれど、せっかくなので想像にお任せしておく。こんな方があの小説を書いたのだな、と嬉しくなった。
小説でもっともやりたかった箇所は、と尋ねると、「これですね」と先生から舌がぺろりと出た。相対性理論級の時間論の打ち立てかあ、と唸ったらそうではなく、重要登場人物である「友恵」のあるシーンで、あかんべえした舌に錠剤が乗っているところ。
いやそこなんですかって思ったけど確かに印象的なシーンだし、うっかり脚本には入れていなかった。松居さんに伝えると「たしかに面白そうですね。やってみましょう」となった。
橋本愛さん演じる友恵のあのシーンはそうして無事、映画に刻まれました。緊迫を破るチャーミングなシーンになったけど、撮影は大変だったそう。そりゃそうですよね、やってみてください。
クランクイン前、松居さんから「これはとんでもない船に乗ってしまいました」というラインが届いた。「やばい?」と尋ねると「激やばなんですよ」という。
映画中でも、クラスメイト全員の行動を矛盾なく制御する大頭脳労働、みたいなシーンがあるのだけど、まさに今スタッフがそうなっているそう。
たしかに地獄だろうなあ、空間のパズルね、と思ってそう送ったら「空間のパズルね、じゃないよ」と返ってきた。怒っているのかもしれない。この作業の凄絶さは、映画を観た方なら想像つくかもしれない。夏の盛りに、キャストスタッフ全員であれを理解して、実際にやるわけです。なんなら日に焼かれた校舎裏や、影ひとつない炎天下の屋上で。
松居さんからは、「あの夜飲んでよかったなぁと思ってもらうために頑張る」と、エモーションでしとどに濡れたメッセージが届いた。出会ってからの伏線が今まさに回収され、きれいなループを描こうとしている。
これは尾道の現場へ駆けつけて、松居さんの勇姿を見届けなきゃあ、と思っていたら、風邪をひいて現場に行けなかった。まじでめちゃくちゃ謝った。仕込みに誘っておいて行かない、あっちのほうを回収してしまった。
2024年2月、試写で「リライト」を観た。松居さんと岡田さんはもう嫌になるほど観ていて、僕はこの日が初めて。
尺は2時間ちょっとだそう。よくぞここまで短く、という松居さんへの感慨と、まだ長いですよねすいません、という岡田さんへのすまなさに挟まれながら、緊張しつつ鑑賞した。
素直にありえないほど面白かった。王道の青春タイムリープラブロマンスから始まって、一転ミステリになり、そこから非線形の展開をなんどか見せる、観たことないエンタメになっていた。映画というよりライドみたい。原作小説の鮮烈さをたたえ、尾道の風を纏いながら、僕の論理ジャングルジムの中を、松居さんのエモーションが迸り、恋をし、遊びまわっていた。
この知らないアミューズメント伝わるかな、とも思ったけど、隣で観ていたマネージャーに恐る恐る尋ねたら、嘘じゃなさそうな熱を帯びた感想が返ってきた。この人がそういうなら間違いない。それから1年半後、映画は公開された。
試写のあと、松居さんとどんなラインのやり取りをしたっけ、と思って今見返してみたら、観る前には「明日、お待ちしてますよ! 緊張します!」「映画史が変わる音を聴きにいきます」「時間史も変わりますね。もし都合よかったら飲みましょう」「いきましょう」という師匠と先生らしいラリーをしたのち、そこからあとは残ってない。
飲みに行ったのかも覚えてない。たぶん行ったんだと思う。初めての飲みは覚えているのにね。それでいい。ループはまだ閉じない。
編集部からのお知らせ
上田誠さん脚本×松居大悟さん監督の『リライト』
映画『リライト』は、6月13日より上映中です!
<イントロダクション>
監督:松居大悟、脚本:上田 誠のタッグが贈る!
史上最悪のパラドックス <タイムリープ×青春ミステリ>
この青春は、分解される―
数々の青春映画で若い世代から圧倒的な支持を集める松居大悟と、“時間もの”で高い評価を獲得している上田 誠(ヨーロッパ企画)。
“師弟関係”にある両者が初めてタッグを組んだ。原作は、「これを映画にしたい。やるなら松居大悟監督と!」と上田が熱望した、法条 遥の「リライト」(ハヤカワ文庫)だ。“SF史上最悪のパラドックス”として評判を呼んだ衝撃作を、上田脚本史上“最高に緻密な時間のパズル”で再構築し、松居監督が青春のもがき、輝き、そして感傷と希望で色鮮やかに綴ってみせた。
(映画『リライト』公式ページより)


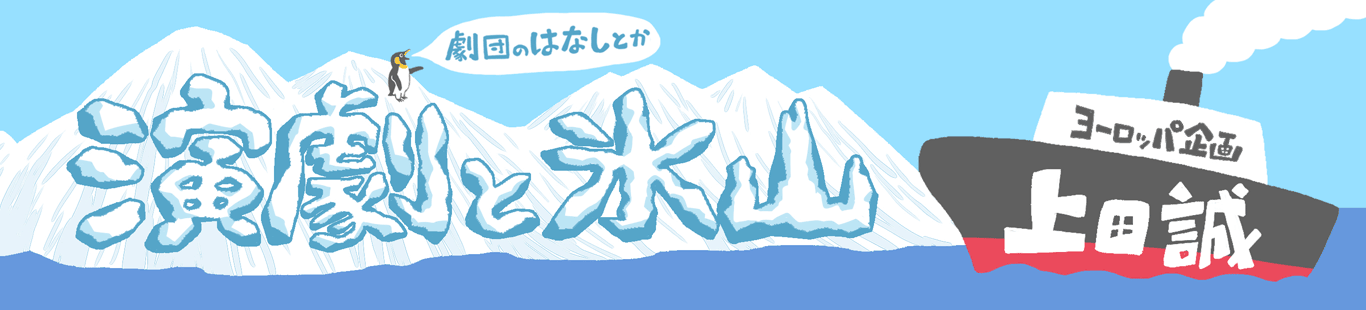
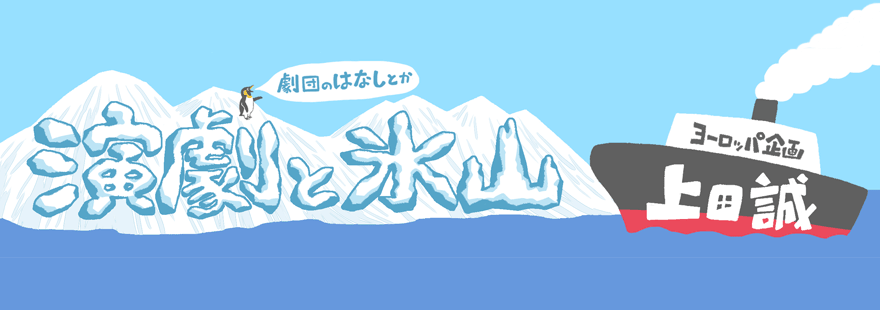

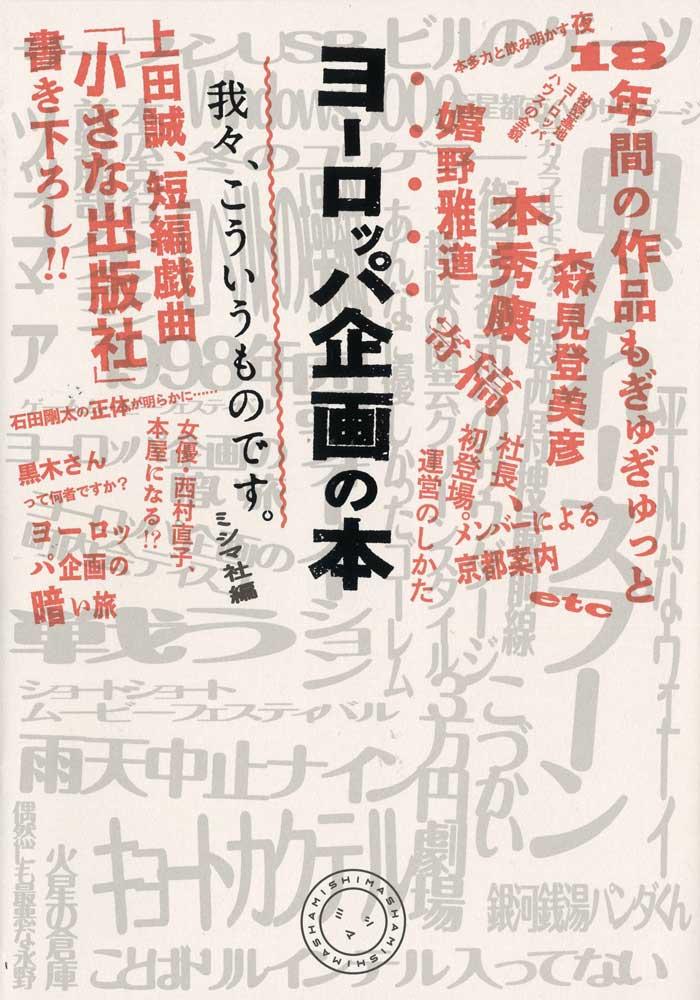


-thumb-800xauto-15803.jpg)


