第4回
オオカミの進化(伊藤亜紗)
2020.10.19更新
お返事ありがとうございます。今回もとても感動しました。お手紙を読むと、いつも初めての場所に連れ出される感じがします。
村瀨さんは介助者としてお年寄りの抗いをケアしているけれど、お年寄りもまた村瀨さんに関わられることで振り回されており、村瀨さんの抗いをケアしているのだ、と。考えてもみなかったことですが、きっとそうなのでしょうね。「抗い」の観点から見ることによって初めて、ケアすることがケアされることでもある、という側面に気づかされました。
ただしその場合のケアは、「相手のためを思って」みたいな目論見によってなされるものではないわけですよね。むしろそれは、目論見レベルではすれ違っているのに、演奏としてはシンクロしている不思議な即興音楽みたいなものですね。
盲導犬である村瀨さんを想像したら、最近読んだオオカミの話を思い出しました。
アリス・ロバーツというイギリスの人類学者が書いた『飼いならす』(斉藤隆央訳、明石書店)という本です。この本は、イヌ、コムギ、ウシ、トウモロコシなど、人間によって飼育栽培されるようになった十種類の動植物が、どのようにしてそのような関係を人間と取り結ぶにいたったのかを描き出しています。考古学や遺伝子解析など最新の科学の知見を駆使して描かれた壮大な本です。
面白かったのは、飼いならす過程というのは、一般に想像されるような「もともと野生だった動植物を、人間が自分の目的にかなうようにうまく手懐けて、品種改良していった」というようなものではない、ということです。言われてみれば当たり前なのですが、どんな生き物だって、自分と違う種をそんなに都合よくコントロールできるわけがないですよね。もしそんなことができていたら、人間は地球上のあらゆる動植物を、自分の思い通りにあやつっていたはずです。
飼いならす過程は、もっと非意図的で、偶然に満ちていたはずだ、とロバーツは言います。そして「飼いならす」とはむしろ、ある種の動植物がもっていた「飼いならされる力」を、そうとは知らず、人間が解放しただけにすぎないのではないか、と。
一章はイヌについての話で、そこでイヌの先祖であるオオカミのことが出てきます。さまざまな研究結果が示しているのは、オオカミが人間と協力するようになったのは氷河期ではないか、ということです。当時、人間はまだ狩猟採集民でした。集団でトナカイなどを狩って食していましたが、原始宗教的な意味があったのか、頭部は食べずに森に返す習慣があったと考えられています。
その食べかすを狙ってやってきたのがオオカミです。自分で狩るよりも、おこぼれをもらった方が、はるかに楽だからです。それで、次第にオオカミがテントのまわりをうろつくようになる。オオカミは好奇心が強く、それでいて慎重な動物です。人間も、近づきすぎたオオカミには攻撃をしたでしょうが、強面の彼らが近くにいることで、他の動物から身を守れるという利点にも気づいたはずです。
どっちがどっちを選んだのかはよく分からない、とロバーツは言います。いずれにせよ、人間が「飼いならし」だと思っていた過程は、実は「それぞれに利害関係を持った種のゆるやかな共生」のようなものであった可能性が高いのです。
そして、そんな共生が長く続くうちに、次第にオオカミは進化をしていきます。尻尾をあげ、より警戒心の低い現在の「イヌ」になっていったのです。もちろん盲導犬も、そのようにしてイヌに進化していった元オオカミの一員です。
ポイントは、こうした共生の過程で、人間もまた進化していった、ということです。オオカミをはじめとするさまざまな動植物と共生するなかで、人間は、男性の攻撃性を減少させ、他の個体と協力する社交性を身につけるに至ったのです。一種の「共進化」ですね。いっしょにいるだけで変わってしまう、種の枠組みが流動化してしまう、ということに驚かされます。
というわけで、「飼いならす」は実は「飼いならされ」でもあった、というのが本書のオチです。イヌやウシやウマを飼い慣らしたと思っていた人間は、実はいちばんうまく家畜化された種だった、ということですね(だから、本書の最終章は「ヒト」に当てられています)。
子どもの頃、近所の集会所でバザーがあって、そこで売っていたモルモットを十円で買ってきました。今考えると、そもそもなぜバザーにモルモットが出品されていたのかが謎なのですが、十円だったということは、たくさん生まれて困った人がいたのかもしれません。
家に連れて帰って、モルモットをケージに入れました。伊藤家で初めて飼うペットだったので、人間も緊張していたし、モルモットも緊張していました。しばらく放っておくと、やがておしっこをしたので、ここが今日から自分の家だと諦念したのだなと思いました。
飼い始めてどのくらい経った頃か忘れてしまいましたが、朝起きてみると、ケージにモルモットがいませんでした。夜行性なので、夜のうちに脱走していたのです。ケージは牢屋みたいで可愛そうだと思った母が、蓋(天井の部分)を閉めずにおいたのです。
どこに行ったのかと家じゅうを探すと、果たして、横倒しに置いてあったデパートの紙袋の中に鎮座していました。足で呑気に頭を掻いています。おしっこもウンチもし放題でした。カーペットは、茶色い毛でべちゃべちゃ、床近くまで垂れ下がっていたロールカーテンには見事な歯形がついていました。
それを見た母が、ものすごく喜んだのです。「よくやった、あっぱれ!」と。母もきっと「抗い」を探していたのだと思います。家族が寝静まったあとにモルモットが発揮した野生は、小学生だった私にも、「自分は飼われているつもりはない」と主張しているように見えました。これでやっといっしょにいることができる。喜ぶ母を見て、私も妙に安心したことを覚えています。
その日から、ケージの前についているドアを洗濯バサミで止めて、出入り口を常時解放しておくようになりました。モルモットは「自分がいつでも外に出られるようにしてくれたんだなあ」なんていうふうには思わなかったはずです。数日後には「あれ、ここに道があるぞ」「あれ、でちゃった」というような風情で「外出」するようになりました。そしてソファの下や紙袋の中に、たくさんの「別荘」をつくるようになりました。
大胆になったモルモットは、やがて人間の家の玄関からも出ていくようになりました。庭の木の下で日向ぼっこをしたいのです。でも庭にはときどき野良猫が来ます。そんなときは、白目をむいて全速力で家に逃げ帰ってくるのでした。
その頃はドラゴンクエストというゲームが流行っていました。ある日、そのゲームのサントラが入ったCDを買ってもらいました。さっそくプレイヤーに入れて聴き始めると、十曲くらい入っていたうち一曲に、モルモットが強い反応を示しました。いつものようにキュウリを食べていたのですが、その動作をパタリと止め、遠くの仲間の声に耳を澄ますように、鼻を高くあげて静止したのです。それ以降、私はその曲ばかりかけるようになりました。
思い返すと、あのモルモットとの生活も、どちらがどちらを飼っているのかよく分からない状態を、お互いが目指していたように思います。もちろん「進化」というほどのことは起こらないのですが、人間もモルモットも、お互いの抗いをケアしながら、少しずつ生活様式を変化させていっていました。
人間とモルモットをつなげていたかすがいは、物理的な環境でした。言うまでもなく、人間とモルモットは言葉が通じないのですが、物理的な環境は共有していました。扉を開けたり、紙袋に隠れたり、物理的な環境を少しずつ改変することが、抗いでもあり、ケアでもありました。人間にとっては紙袋でも、モルモットにとっては住処です。物だからこそ、思いはズレていくし、目論見は外れることができていました。
いっしょにいる、というのはとても不思議なことですね。いっしょにいる、というのは常に「思える」の次元でしか起こり得ない出来事であって、常にズレをはらんでいるものです。コバンザメとジンベイザメも、ヤドリギとそれが乗っかっている木も、たぶんそんな感じなのでしょう。細胞同士の関係も、そうなのかもしれません。自然界では、村瀨さんの言う「ズレまくりながら調和している」が当たり前なのかもしれません。
いっしょにいるためにお互いをケアしているのですが、そうしているうちに、思ってもいない方向へ進化の一歩を踏み出しているわけです。村瀨さんも、お年寄りと関わることで、既成概念がずいぶんと解体されたと書かれていました。「今日」「犬」「私」。確かに概念は、私たちに共通の認識を作り出す道具です。しかしながら、時間と空間の見当が覚束なくなり、言葉も記憶も曖昧になりはじめたお年寄りは、概念によらずに世界を、人を、捉えています。誤解を恐れずにいえば、別の種ほどにも根本が異なる存在に、介助する人が巻き込まれていく。巻き込まれる、というのは一種の進化ですね(be involved=evolution?)。
お年寄りたちは、村瀨さんだけでなく、周囲の物も進化させているように見えます。進化、というと変ですが、物のいろいろな可能性を引き出していますね。
送迎の車には乗ってくれなくても、引き揚げのための船だと言うと乗ってくれるお爺さん。共進化の原則から行くと、お爺さんには船が必要で、そのことによって車から船でもある可能性が引き出されています。湯飲みを持ちながら「モシモシ、モシモシ」と言うお婆さんも、湯飲みから電話の可能性を引き出しているように見えます(村瀨さんが教えてくれるエピソードのなかで、お年寄りがしばしば「何かを待つ」という状況に陥っているのが面白いなと思います。この待ちが、いろいろなものを進化させる力であるようにも思います)。
というわけで、とりとめもない話ばかりでしたが、今回は動物の回になりました。いっしょにいることの不思議を、ひきつづき考えていきたいです。


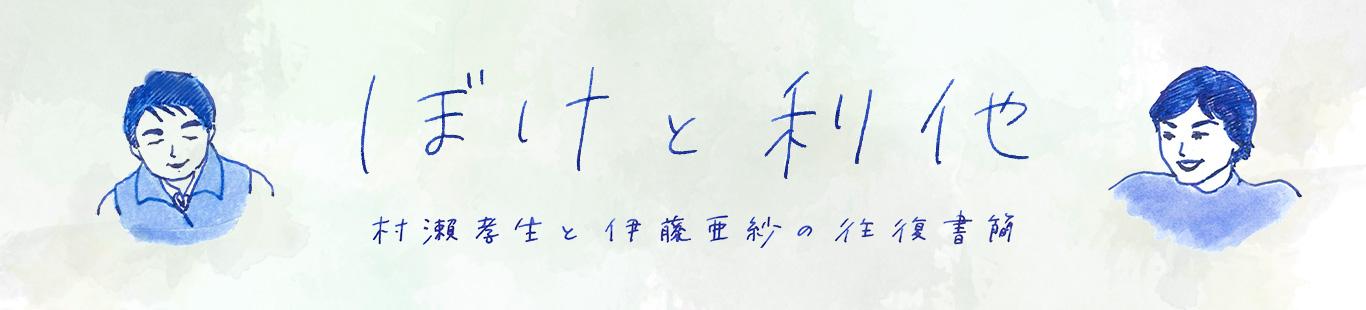



-thumb-800xauto-15803.jpg)


