第10回
ファッションについて
2018.04.25更新
ファッションについて何か書いてほしいという話を受けることがある。だいたいにおいて、「ファッションについて我々は知らないので」という接頭句がつくことが多い。しかし、私の感覚では物心ついた人間のほぼ全員がファッションについては体感的、身体知としてよく知っていると思う。ファッションは社会の仕組みや我々の振る舞いに密接に関係している。人の装いや有様(ありさま)の様相であるから、私は「様装」をファッションの日本語訳としたほうがいいのではないかと思っている。そういったファッションについて書きたいと思う。
文芸誌や文化誌の文脈では、知識として知っておきたいファッションという内容が期待されるだろうが、実際そういった文脈で提案されたものは本当に面白いだろうか。指摘してきておきたいのは、この文脈では知識でさえもファッションの一つであるということである。ポストモダン思想が知識階級において、かつて最新のファッションであったことを記憶している人も多いのではないだろうか。
また、別のファッションの文脈として、TPOに応じてこういったものを身に着けよう、といったHow-Toとしてのファッションも情報として価値があるかもしれない。しかし、筆者の積極的な関心はそこにはあまり無い。話の流れで書くことができれば良いと思っているが、ファッションの最も興味深い醍醐味は、TPOのような社会のルール、暗黙知としてのルールをフォローして上手く生きることではなく、逆にハックし、裏切ることによって、考えもしなかった新しいシーンを体感することだと思っている。
また、ファッションはファッションショーに登場するだけの「変わったもの」ではない。パリ、ミラノ、あるいはロンドンのランウェイプレゼンテーションで提案されるイメージはファッションの一側面に過ぎない。実際、一般人が普段着ることできないような前衛的なスタイルが提案されているというイメージから、そこにあるファッションというものが実社会と乖離しているものと見られがちだが、前衛的な現代思想がじわじわと実社会の言説に影響を与えるのと同様に、そこには隠れた社会のダイナミクスが存在しているのだ。
最近の話題を1つ取り上げてみたいと思う。2ヶ月ほど前、銀座にある中央区立泰明小学校の制服がアルマーニ監修のものとなったことが大きく報じられた。調べてみると、人々の反応の大半が批判的なもので、高価な制服を小学生に着せることに生理的嫌悪があるようだった。どうも校長の独断だったのも大衆の反応を助長したらしい。校長もなかなかパンクな選択をしたものである。
批判に対する反論として校長の決定に賛同する意見も多少あるようだった(マイノリティだったが)。それは、実際の価格を他の制服と比べると、それほど騒ぐほど高価なわけではなく、騒ぐほどではないのではないか? というものである。自分は好奇心をもってしばらくニュースを眺めていた。特に小学校の制服という1つの小さな現象が、数週間の間メディアに大きく取り上げられたということが驚きだった。
しかし、この問題でまず指摘しておきたいのは、現代ファッションがこれまで創造してきた「象徴や記号」の強大さのことである。そして、ジョルジオ・アルマーニという人物が作った「ARMANI」という記号の持つ意味だ。彼の作ったイメージは「富や権力、成功の象徴」と確かに密接に結びついている(特にこの国では壮年期から中年の特に男性が身につけるブランドというイメージがある)。アルマーニの制服。この一連の騒動は「富や権力、成功の象徴」を、それらとは縁の薄そうな小学生が毎日身につけるというイメージと事実が、社会通念上、常識的ではないと思われたことだろう。
マスコミは少なくとも有名と無名の間をさまよう著名人のゴシップ、込み入った経済政策や国際社会のニュースに比べると、このアルマーニ制服事件は世間にとって関心のある話題だと認識したらしい。「富や権力、成功」に対して大衆の持つ潜在的無意識を煽動し、怒りや不安を煽り、騒ぎに繋がったようだ。しかしこうして実際、大きな騒ぎが起きたという事実がファッションの持つ力の存在証明でもあると思う。
「富や権力」といった社会的記号を、実際に身につけられるものとして創造できるのがファッションデザインの力の一面であり、人々の感情を揺さぶるのもその力だ。これは我々が否応無しにファッションに関わってしまう一面でもある。
意外かもしれないがファッションに関わる人にとって、「制服」が嫌いな人は案外少ないと思う。デザインにルールがあることが制約ではないかという人もいるかもしれないが、この制約や規則といったものが堅くて融通の効かないものであればあるほど、そこには創造の余地があるからだ。皆が規則をフォローするが故に、そのトレンドに逆らうという立場に希少性が生まれる。そして希少性には価値が生まれるからだ。
ファッションは流行と翻訳されることが多いが、実際のファッションの創造的部分は、トレンドを外し、かつその存在を確個たるものにするかにかかっているといっていい。ありとあらゆる流行の多くは「オルタナティブ」、あるいは常識からやや脱線した考えや立場が主流に近づいたときに生まれるのだ。創造は世間の受容と拒否の狭間に存在するとき、最もその存在感を発揮する。
アルマーニの話に戻ろう。今ではラグジュアリーなファッションの一角を担う、アルマーニだが、彼の慧眼を示すものとして特筆すべきところは、彼が70年代後半から80年代に、当時の業界が常に注目していたパリではなく、ニューヨークに目を向けたことだった。1980年、リチャード・ギアが主演した『アメリカン・ジゴロ』への衣装提供で有名になったアルマーニだが、実社会で彼を有名にしたのは女性のビジネススーツだった。
当時、巷では女性の社会進出が謳われる中、ショップには男性と並んで働く女性の仕事着(ユニフォーム)がなかった。彼の作る女性のためのビジネススーツは文字通り、「パワースーツ(権力の服)」だったと思う。権力や成功を男性と同じように女性が自らの手で手に入れるという、新しい社会、そして女性の生き方のヒントを提案したのだ。
アルマーニのスーツがこれほどまでに世界中で有名なのは、ファッションのトレンドではなく、人間社会の様相を読み、向き合うことで別の有様を創造したことにある。「今を歩く新しい人間」が生まれたとき、その人たちのための「制服」が常に必要になる。ファッションは「富や権力」だけではなく、「知性」、「若さ」、「成熟」、「反抗」、あるいは「オルタナティブ」といった記号も創造してきた。そして、そのメッセージとともに生まれるイメージは各々の時代の現状(Status quo)に対し、反抗や変革しようとするメッセージを担っている。
こうやって「人の"様装"」と「社会の"様相"」の相関関係を見ながら考えると、ファッションも他人事ではないように思えるのではいだろうか。アルマーニの制服事件の話に戻れば、成功を手にする可能性を秘めた子供たち、というメッセージで考えればアルマーニの制服もあながち悪くないかもしれない。大人が決めたスタイルを自ら拒否し反抗する小学生はもちろんだが、もしかすると世間の批判に埋もれて誰も着なくなった制服をあえて、卒業まで着続ける小学生というのもパンクであるし、そういう生き方を志向する小学生が仮にもしいるとすれば興味が湧いてこないだろうか。
この連載では、これまでと同様、筆者が今を歩きながら、気になったワンシーン、そして今を歩く人々について書こうと思う。徒然なるままに。
※ アルマーニ関しては過去に彼の紹介記事をFREEMAGAZINEに寄稿しているので参考記事として紹介します。FREEMAGAZINE ISSUE#2 http://freemagazine.jp/giorgio-armani/


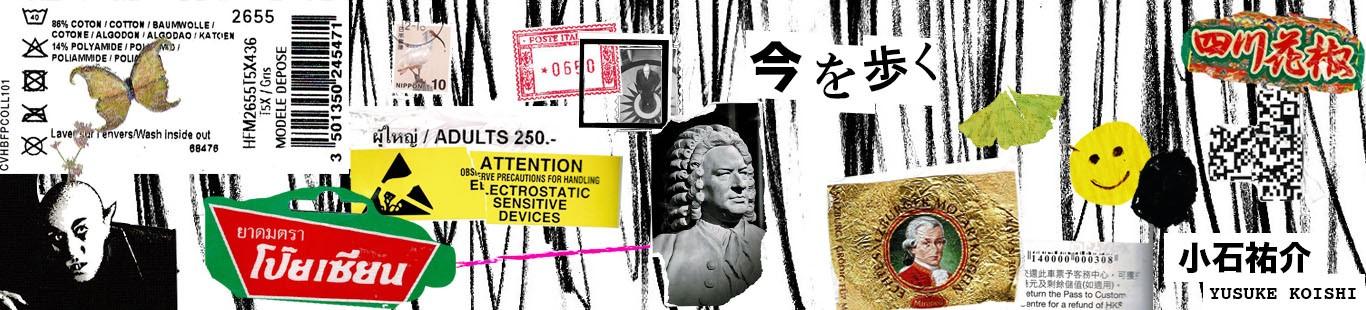
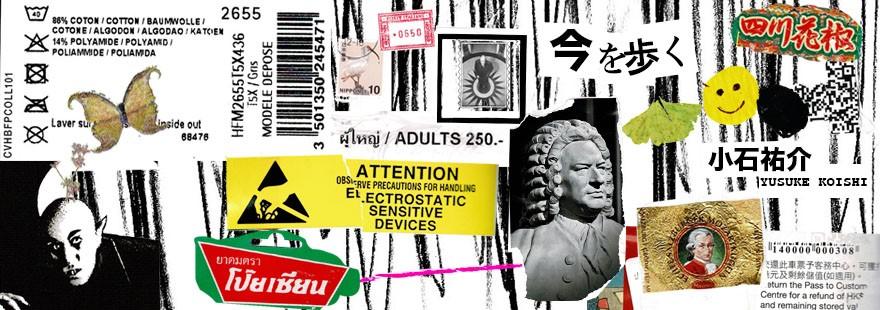



-thumb-800xauto-15803.jpg)


