第11回
ファッションアイテムとしての"MAKE AMERICA GREAT AGAIN HAT"
2018.06.20更新
"MAKE AMERICA GREAT AGAIN"というメッセージが刺繍されたベースボールキャップがある。ドナルド・トランプ大統領の選挙キャンペーンで使われた、通称「MAGA HAT」と言われるベースボールキャップだが、つい最近このMAGA HATがまた話題になった。
ミュージシャンであり、現在は自身のファッションブランドYEEZYも手がけるマルチタレントのカニエ・ウェスト(Kanye West)が、4月26日にトランプ大統領支持のメッセージと共に、ドナルド・トランプのサイン入りのMAGA HATをInstagramとTwitterに投稿したのだ。当然ながら、ニュースやソーシャルメディア上で上がったコメントの9割が彼に対する批判だった。カニエ・ウェストをフォローしていたファンはおろか、彼の友人でさえもInstagramやTwitterで彼のアカウントをアンフォローすることを宣言し、強く糾弾したのである。おそらく、カニエ・ウェストほどのコマーシャルな影響力がなければその批判に埋没していただろう(実はこの投稿の後、とあるインタビューで、「奴隷制度が選択肢だった」、という問題発言で別の炎上を起こしていたことも火に油を注いだ。ただしこの炎上については、カニエ・ウェスト自身の際どい発言の他に、その発言の前後のコンテクストを無視して切り取られ、拡散されてしまったことが炎上の主な原因であったようだ)。

歴史を振り返ってみても、もしかして今以上にたったワンセンテンスの言葉が力を持った時代はないのかもしれない。"MAKE AMERICA GREAT AGAIN"(アメリカを再び偉大に)という単なる一文は、ドナルド・トランプという象徴的な政治アイコンが取り上げたことで、「アメリカを再び偉大に」という言葉以上の意味を持つようになった。本来の意味だけでなく、大統領選挙によって分断されたコミュニティを象徴するメッセージとなってしまった。それはトランプ大統領がそうしたのではなく、それを受け取る「人」と「環境」の関係性から生まれたのである。言葉はそれ自体で意味を持たない。
最近、知人のスタイリストがこの状況を皮肉にとらえて、ピンク色のMAGA HATを被って歩いていた。いま、MAGA HATは過激なメッセージを発するファッションアイテムになっている。さて、これは何のメッセージを象徴しているのだろう。「私は愛国者です」というイメージに取る人はもはや希少種ではないだろうか。私は「ドナルド・トランプ(あるいは彼の政策)の支持者である」という意味はもちろんあるだろう。しかし、カニエ・ウェストのコンテクストはどうやら、「私は批判に臆することなく、他の人間にどう思われようと、構わない」というメッセージだったような気がする。おそらく一般人がニューヨークやボストンでこの帽子を被ることは、今は相当に「パンク」な行為になっているに違いない。ブルックリンのカフェで、この帽子を被っていたらおそらく、そっけない態度を取られるのではないかと思う。しかし、そんなニューヨーカー達が全て、"MAKE AMERICA GREAT AGAIN"という言葉自体に批判的かどうかを問えばどういう回答があるだろうか。比較はできないが、表立って身につけることができないという意味ではMAGA HATはいまや数百年前のこの国で、隠れキリシタンが持っていた十字架のようなものかもしれない。
言葉が招いた炎上といえば、日本でも以前似たようなケースがあったことを覚えている人もいるかもしれない。ニューヨークで活動する、写真家・現代美術家の杉本博司氏が2017年度の文化功労者に選出された際、「文化功労者として、これからも"国威発揚"を文化を通じて行っていく」とのコメントを発表したことに端を発した物議のことだ。「国威発揚」という言葉に対して、半ば生理反応的に国内の文化人から一斉に批判が沸き起こっていたが、改めて考えると「国威発揚」という言葉も難しい。それは歴史的背景、特にその言葉が使われてきた過去に起因する。漢字の意味どおり「国家の威信を(対外的)に高めていくということ」という形で機械的に読むならば、さして強い意味はない。当然ながら、識者や新聞が嫌悪したのは戦前と戦中の国粋主義とのつながりなのだが、この炎上は、言葉はそれを使ってきた人々とコミュニティの振る舞いによって、言語的な意味を超えてくることを改めて顧みたシーンだった。この炎上で奇妙だったのは、杉本博司という作家性や、アメリカという国で長く活動してきた杉本博司という人間がなぜあの発言をしたか、といったものは議論の俎上に殆ど上がらず、杉本本人が不在だったことである。そこにあったのは「国威発揚」に結びつく記号と、記号化した「国際的に活躍する日本人アーティスト」のみである。
カニエ・ウェストという存在も、この騒動によって「象徴的な記号」になってしまったようだ。先に述べた、奴隷制度に対する発言に起因する炎上も、彼がもともとトランプ支持者だったことで、トランプ支持者に批判的な人々が前後のコンテクストを無視して発言を切り取り、それを半ば意図的にソーシャルメディアに拡散したことが原因だった。これを見て、いまは「社会に対する態度、そしてその記録もファッションの一部になった」ということを感じた。おそらくしばらく前からそうだったのかもしれない。古代から現代に至るまで、人は外見で階級や所属を判断されてきた。しかし、今では「"我々"が関心を持つ対象」と「"我々"と"対象"の関係」そのものが、ソーシャルメディア上に公開されている。そしてそれは人間の外面と同じレベルで重要なファクターとなっている。ソーシャルメディア上の発言の積み重ねとそのデータの蓄積を我々は身に纏っているのだ。
炎上したインタビューの中、黒人コミュニティを代表してきたと自負するカニエ・ウェストは、「黒人だけでなく人間を代表していきたい」と述べる。一連の騒動をみて私は、「強く、そして中立的な存在という可能性」が、人類史を通してそもそもあったのだろうかという問いを突きつけられた気がした。我々は否応なしに判別されてしまう。
何か一つの態度をとることも、本当は大変な時代だと思う。それは衣服のように我々の身に纏わりつき、我々の文脈を支配する。MAGA HATという帽子被ったカニエ・ウェストもMAGA HATと同じ記号になるのだろうか? MAGA HAT、そしてカニエ・ウェスト自身も、その存在を認める者、嫌悪するもの両者が去り、誰も気にかけなくなるまでの間は、強いメッセージを放つ「ファッションアイテム」として存在するのだろう。
"Slavery Is A Choice" Kanye West FULL Interview on TMZ Live
炎上したカニエ・ウェストのインタビュー。
「奴隷制度は選択だった」とカニエが発言したTMZインタビューのほぼ全文翻訳。
ほぼ全文が日本語訳されていたので紹介したいと思う。


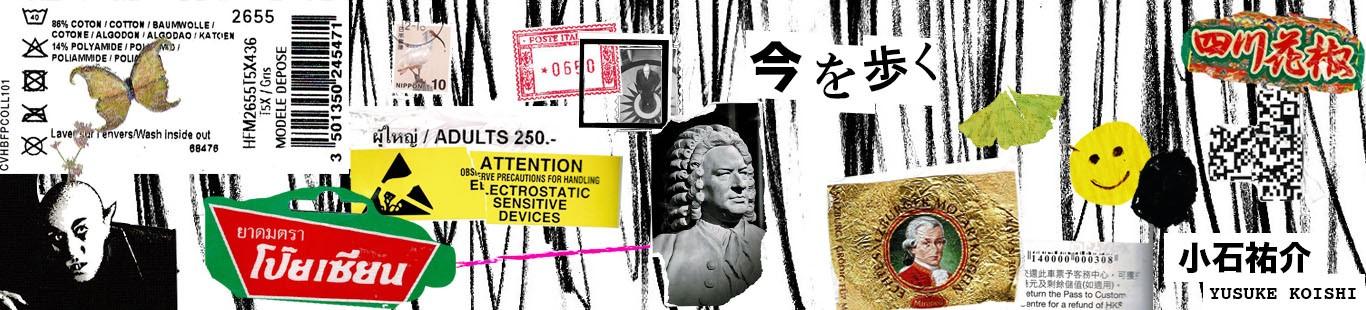
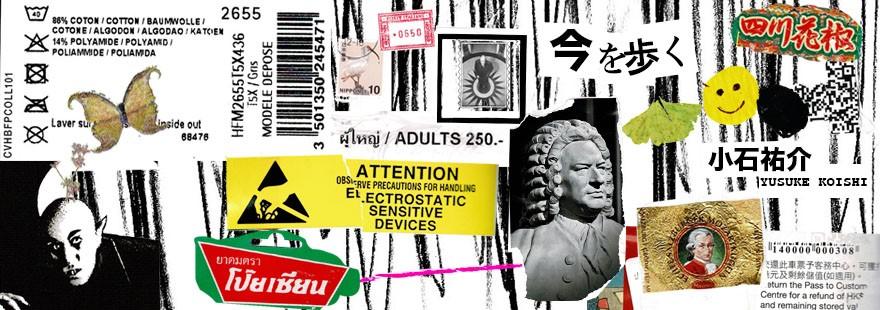



-thumb-800xauto-15803.jpg)


