第3回
ミツバチが生まれるとき
2025.11.07更新
個ではなくコロニーのために
働きバチという名前の通り、メスバチはオスバチとうってかわって本当に健気な働き者です。成長とともに、さまざまな仕事をこなしコロニーに貢献していきます。
まずその仕事の中身を詳しく解説するまえに、彼女たちメスバチが背負っている宿命について話しておかなければなりません。
彼女たちは永遠の処女です。
交尾することがないのです。「永遠の処女」。ちょっと口から出してみるとすごい言葉ですね。あまり人生において発した事のない言葉です。
働きバチはメスとして生まれながらも、生涯子供を産むということを放棄した存在です。
ミツバチの家族を構成する3種類の蜂たち、女王バチ、メスバチ、オスバチ。メスバチはこの中で不妊の階級なんです。
この不妊の階級が存在しているということに、かの有名な進化論の提唱者ダーウィンは大きく頭を悩ませたと言われています。進化論においては自然淘汰という原理が重要です。マイナスの側面を持つものは自然淘汰されていく。生き物として大きなマイナスとも思える、この不妊のミツバチ。
かつては社会性昆虫と呼ばれてきましたが、私たち人間の社会からは大きく異なることから、現在では「真社会性昆虫」と分類されるようになりました。他にもアリやシロアリがそうです。私たちの社会は「個」で構成されています。今は特に個人主義の進んだ時代ですよね。でも彼らは全く違います。「個」を重んじることはなく、あくまでもそのコロニーに重きを置きます。コロニーの存続のために、全てを投げ打って助け合いながら共存している。それは次の段階へと進化を遂げた生命の姿かもしれません。個を超えた存在である彼らは「超個体」、「Super organism」とも呼ばれています。
ミツバチの成長過程――羽化するまでまったく動けない
さあみなさんここからがいよいよ本番です。
ミツバチの成長の過程を一緒に辿っていきましょう。
まずは女王蜂が巣房の中に卵を産みつけるところからです。ここが全ての始まりです。
みなさん知っての通り、卵の次は幼虫ですね。そして幼虫が
これに対して不完全変態と呼ばれる昆虫もいます。蛹の時期がなく、卵から幼虫になって、そのまま成虫へと変化していくものたち。カマキリがわかりやすいですね。卵から生まれた時点ですでに小さな成虫の形をしています。
完全変態にしろ不完全変態にしろ、ほとんどの昆虫の幼虫は動くことができます。チョウを考えてみてください。アゲハチョウでもモンシロチョウでもイメージしやすいもので構いません。
エサとなる葉っぱに卵として産みつけられ、卵から孵化した小さなアオムシは自分自身の力で葉っぱを食べてぐんぐん成長していき、自ら蛹へ、そして成虫へと変化していきます。親はこの子供の成長に一切関わることはありません。
ですが、ミツバチの場合はまるで話が違います。
ミツバチは羽化するまでは自分の意思では全く動くことができないんです。
アオムシは自分の力で葉っぱを食べて、自分の力で蛹へとなっていきますよね。ミツバチはそうじゃないんです。幼虫の段階でできるのは口を開けることだけ。本当にそれだけなんです。
ただ口を開けてご飯を食べることしかしない。それだけで十分にこと足りてしまうのは、全て姉たちのおかげです。
自分で食事を取るのではなくて、巣房というゆりかごの中で、姉たちから食事を与えてもらうんです。この時の、いわば乳母とも言える働きバチの姿はとても甲斐甲斐しいものです。産むことを放棄した存在であるにもかかわらず、この姉たちからはどこか大きな母性のようなものすら感じます。1匹のミツバチが成虫へと羽化するまでに、姉たちが巣房を訪問する回数は2000回とも3000回とも言われています。1匹の姉バチが育てることができるのは2〜3匹の幼虫だと考えられています。
外の世界へと出ていくとき
そうしてご飯を与えられ続けた幼虫たちは蛹へと変化する準備ができると、ゆりかごである巣房は、まるで温かい布団を赤ちゃんにそっとかけてあげるかのように、ミツロウで蓋をされます。この蓋をかける作業をするのも姉たちです。
働きバチは卵から数えて3週間という時間をかけて羽の生えた美しい成虫へと変身していきます。
そしてついに変身が完了すると巣房にかけられた蓋を口で食い破って出てきます。この時ようやく初めて、働きバチは自分の意思を持って動き出すわけです。
暗い蛹の中から外の世界へと出ていく。これは養蜂家なら誰もがしょっちゅう見る光景ですが、とても感動的なんですよね。人間は卵から産まれるわけじゃないというのもあると思いますが、この羽化のシーンこそ、誕生の瞬間に感じるんです。
最初は巣の表面に棘のようなものが見え始めます。ミツバチの口ですね。一生懸命齧るんですが、本当にちょっとずつしか進まないんです。そうして、顔の前面、目や触覚が徐々に見えてくる。今まで一度も巣房から外へ出たことがないわけですから、体の一つ一つを動かすのにとても時間がかかるんです。まさにお腹の中から出てこようとしている赤ちゃんのようです。
そうして巣房からやっとの思いで出てきたミツバチが、みなさんが頭の中にイメージできるあの縞模様の可愛いミツバチです。その背中には今まで存在しなかった美しい羽がきちんとついています。本当に物凄い変身です。
ただこの時点では、まだ弱々しく、色も少し白っぽいんですね。あの黄色いミツバチとは少し違う。出てきたばっかりですから、白い産毛が目立っています。成虫になったばかりのミツバチは、そこで初めて外界に出てきたわけですから、まだ何も知らない。何ひとつ見たことがない状態ですね。
ある日突然に、何万ものミツバチが働くけたたましい都市の中に産まれるわけです。ここでまず凄いなあと思わず感心してしまうのは、自分のするべきことを知っているということですね。
最初のうちミツバチはまだ歩くこともおぼつきません。非常にゆっくりですね。当たり前です。まだ動かした事のない体ですから。
さあ、彼女たちが一番最初におぼえる仕事はなんでしょうか? ここからはミツバチの仕事について具体的にみていきましょう。




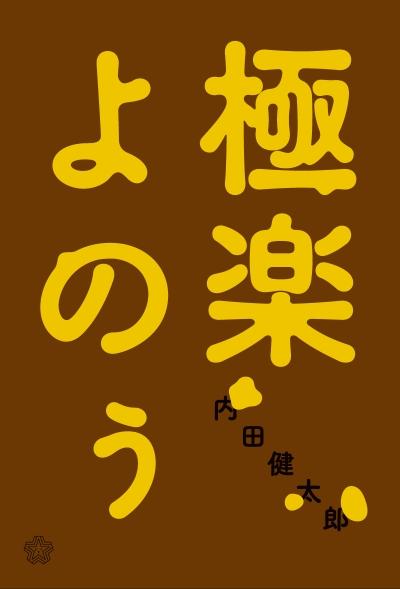




-thumb-800xauto-15803.jpg)
