第9回
困っていると受け入れ初めてわかること
2021.01.05更新
※本連載は都合により今回が最後となります。
この連載が今のところ訴えているのは、とにかく僕は困っていたし、困っていた時期が長かったということだ。こう書くと「そうですか。それで具体的に何に困っていたのですか?」と思う人もいるだろう。だけど、そう聞かれても困る。かいつまんで話すことができないからこうして書いているからだ。「身体も心もバラバラになりかけで、他の人ができることができなくて、日常生活を送るのが実はものすごく大変だった」と言えば嘘ではないけれど、そういうふうにはっきりと言えないからこその困りごとなのだ。
そもそも僕は自分が困っているとは思っていなかった。あからさまにわかりやすい困りごとではないから「こういう事情で困っているのです」と人に訴えることもできなかった。自覚のないままに数十年生きてきたわけだ。
何に困っているのかわからない
「無自覚のままでいられたのおかしくないですか?」と問われたら、「おかしいかもしれないけれど、人が本当に困っているときは、何に困っているか案外わからないものですよ」とかつての当事者としては言いたい。
だから「ああ、困ったなぁ」と声に出してみることを思いつきもしない。「しんどいな」はある。けれども「いや、これは難儀なことだぞ」という判断ができない。「困ったことになったかもしれない」くらいは思っても、本当に自分の置かれた状況をそうやって断じるだけの自覚が訪れない。
地球で生きていると絶えず重力がかかっているわけだけれど、常日頃から足を踏ん張って身体を支え、「ああ、大変なことだ」と嘆かないだろう。それと同じで、困っているはずの自分であっても、いつも通りの普通の自分だと思えば、「困っている」がことさら意識されない。
会社へ行くという困りごと
今の世の中で困りごとであるにもかかわらず、そのようにカウントされないで、しかも特殊なものではなく、多くの人が共感できるものとして何があるだろうか。そう考えると意外と「毎日会社へ行くこと」だったりしないだろうか。僕の長らく抱えてきた困りごととはちょっと違うけれど、それでもほんの1年半ほどの会社員の経験があるので、そこから類推して困っていることへの無自覚さについて述べたい。
たとえば朝起きても寝不足の慢性化でが寝た気がしない。その上、歯を磨いていたら毎度のように吐き気を催して、洗面台でえずく。身体がだるくて「あー、会社に行きたくない」といつものように思う。そんなふうにいくら感じても、思っても「いつものように」と習慣化された判断を自分に対して与えてしまうと、吐き気やだるいという身体が訴えかけている状態を無視できてしまう。
確かにトイレで吐いてしまうかもしれないし、満員電車で冷や汗をかいて、ようやく着いた駅の階段でうずくまってしまうかもしれない。もちろん本人は無視しているつもりはないのは、「体調が悪い」というのはちゃんとわかっているからだ。でも、その「わかっている」は本当は何を理解していることなのか? と問うた途端にわからなくなる。困りごとが困りごととして認められていないからだ。
なぜそうなるかというと、自分をみまっている困難という現実は直視するものではなく、克服されるべき課題にいつの間にかスライドしてしまっているからだ。「仕事だから仕方ない」といった、なまじ社会性のある事柄だとそういう厄介さが生じてしまう。「会社へ行く」のは「いつものこと」だし「当たり前」。この自動化された行為によって克服は可能になる。起きたら歯を磨き、服を着替えてと出勤に向けて、嫌々であっても滑らかに身支度を整えていく。社会と接続するための円滑な動きは、本当はものすごい負担を心身に強いた上で達成されたことのはずだ。
けれども「会社へ行く」という、「みんなが当たり前にしていること」という設定を前にしては、吐き気や身体を重く感じたとしても、それらのぎこちない身体の反応は、暮らしを成り立たせる上でまるで「無目的」に思えてしまって仕方なくなる。
身体の不調が自分の中で発言権を持たなくなるのは、それとぴったりと背中合わせでくっついて、物凄いプレッシャーを与える「働かないと生きていけないぞ」という内心の声の存在も大きい。加えて、ほんの少し遅れて「他にやりたいことがあるわけでもないだろう?」という声が追い討ちをかける。それを耳にするとなぜか薄らとした罪悪感を覚えてしまう。一度聞いてしまっては「やりたいことがなくても別にいいじゃないか」と切り返せなくなる。心身の不調をつぶさに感じることが無目的にしか至らないとの思いがいっそう際立ってくる。そうなると困っているにもかかわらず、「困っていること」は傍に追いやられてしまう。
内心の声の持つ権力
どうやら「内心の声」に僕らは独特の重さと権力を与えてしまっている。身体が感じてしまう吐き気やだるさに気を留めたとしても最終的には無視するのに、この声への引っかかり具合、関心の向け方ときたら尋常ではない。耳を塞ぐことなく真面目に聞いてしまうのは、内心の声はいつも正しいことを言っているように聞こえるからだ。
いや、正確に言うと「正しいこと」を知らせているのではなく、その声は僕を、あなたを絶えず罰している。声は正しさの名のもとに脅迫し、罰を下す。手酷い打撃を食らっているのに、なぜか素直にいつもそれを受け入れてしまう。どちらかというと、僕らの方が罰されたがっていて、その機会をいつも狙っている。
一見すると自堕落な生活をしているように見える人でも、生真面目にも声と罰を受け入れている。仮にその人が「どうせ自分は-」と言うとしたら、そこに開き直りをみるだろうか。僕はその人に内心の声が咎め、数え上げた罰への弾劾に従順な姿を見てとる。また周囲の期待に応えた、自堕落さを行っているようにも感じる。と言うのも、本人がやりたいことを心からやっているのであれば、「どうせ」といった言葉を口にしないからだ。自分を否定する声を僕らは好んで聞いている。自分を罰そうとする仕打ちをなぜ受け入れるのか。人それぞれ抱えているはずの「困っていること」を体感としてちゃんと把握できていない。そこが要因として大きいのではないか。
優しくない声をなぜ信頼してしまうのか
過労から来る嘔吐や睡眠不足による倦怠感は克服すべき問題ではない。単なる事実であり、現在の心身の状態だ。それを体感する上で気を付けなくてはいけないのは、僕らは声に対して誤解を大いにしていることだ。あなたは「内心の声」を自分の声と思っているかもしれないが、本当はそうではない。「幻聴ということですか?」と問う前に冷静になって考えて欲しいので、こう提案してみる。「声」と捉えると、発している意味に引きずられて、すぐさま自分を自動的に罰してしまうので、声ではなく「音」と言い換えてみる。すると、よく聞くとあくまで自分の声質に似ているけれど、ところどころ野太かったり甲高かったり、なだめすかしたり急き立てる調子の音もあるとわかってくる。単一の音ではなくポリフォニーだ。
それに「内心」と言っているけれど、本当に僕らの内側で種が芽を出すようにして自然と形成されたのだろうか。それとも「そうでなければいけない」といった外部で言われていた正しさを僕らが受け入れ、その受容した数がポリフォニーを作り出しているのだろうか。僕は後者だと思っている。自分が従うに至った考え方を象徴する人たちの声音が内心の声を作り上げたのではないか。そうなると、内心の声に従うほど自分を否定し、嫌悪していって当然だろう。「そうでなければいけない」は「いまの自分はダメだ」と表裏一体になっているからだ。
以前の連載で書いたように、僕はサインペンで舌に色を塗らないと気持ちが不穏になるとか、字を書こうとする筆圧が強すぎてペンの芯をしょっちゅう折るだとか、しゃべろうとして言葉を口にした途端、押し黙ってしまうとか、自分のしでかしたことに自分がつっかえ、転けてしまうことの連続で生きてきた。内心の声は「おまえはおかしい」といった調子ではあっても、「ああ、困っているんだね。それは大変だったろう」と手を差し伸べることはついぞなかった。自分に優しくなれない声を信頼するなんておかしくないだろうか。
克服という罠
自分の言葉に、振る舞いに自信がない。自信が持てないのは、自分の言っていることが周囲に正当に扱われないからで、それも仕方ないなと思ってしまうのは言葉がくぐもっているし、どもるし、つっかえるからだ。言葉が喉元で詰まる。息が詰まる。おまけに首が詰まる感覚が甚しくて、つい首をコキコキ鳴らしてしまう。押し黙った人間が目をパチクリしながら首を振ったりするわけだから、周囲は扱いに困ったことだろう。僕は困っているし、周囲にとっては困った人でもあった。そこで「困っているんです」という事態を説明する言葉と僕はどうしてつながれなかったのか。
その理由は「自分の言葉に振る舞いに自信がない。自信が持てないのは、自分の言っていることが正当に扱われないからで、それも仕方ないなと思ってしまうのは言葉がくぐもっているし、どもるし、つっかえるからだ」という時系列で説明したことが全てを物語っている。
本当は「言葉がくぐもり、どもり、つっかえた」という事実があっただけだ。その状態がどこからやって来たのかはわからない。わからない状態に自分があるという事実に耐えられなくて、時間を逆転させて「自信がない」から自分の説明をはじめ、最後は言葉がうまく話せないことに原因を求めた。「言葉がくぐもり、どもり、つっかえた」に一切の根拠を押し付けた。
これが困っている事実を自覚することを回避させたのだ。僕は言葉がうまく話せず、身体が捻れたり、引きつったりすることに困っていたのであって、自信がないとか「奇矯なことをしてまともではない」とか罰する内心の声に権力を与えてしまう必要はなかった。自罰に励む暇があったのなら、自分の困りごとを自分ごととして体感すべきだった。内心の声に権力を与えるのは、それに従えば自分の弱さが克服されると思うからだ。これは大変な誤解だ。
歪んでいて何が問題?
服従がもたらすのは克服ではないし、解決でもない。どもったり捻れたり、吐き気を感じ、目眩を感じる自分の心身がある。克服や解決は「今まさにそうある」ことをひたと見据える勇気を持たず、「そうあるべき姿」に向けて逃げる。
これを現実を不正確に認識させる「認知の歪み」というのかもしれないが、僕は「認知の歪み」という言い方とそれを用いた説明が生理的に好きではない。「生理的」ということが大事なのだと思う。「生きる
「認知が歪んでいる」から内心の声に従属したという説明が合理的で、それを受け入れて、自分の過去を「認知の歪み」という視点で捉えたとしたら、またしても僕らは自身としてではない、他者の声に従っているだけになってしまう。内心の声に耳を貸さなくなったとしても、今度は外部の声の正しさに身を委ねるだけではないか。
「本当ならば、そうであったはずの自分」を探し、「そうはなれない自分」の認知を歪みとして扱ってしまう。そのことに僕はためらう。確かに歪んでいるかもしれない。けれども僕は誰かに歪まされたのではなく、歪むことを真っ当に真っ直ぐに行って来た。そういう自負がある。真っ当に歪んだことを感じるからこそ、初めて正しく歪みをそれとして正しく理解することができる。それが困っている自分と向き合うスタートラインに立つことになる。
※本連載は都合により今回が最後となりました。ご愛読ありがとうございました。


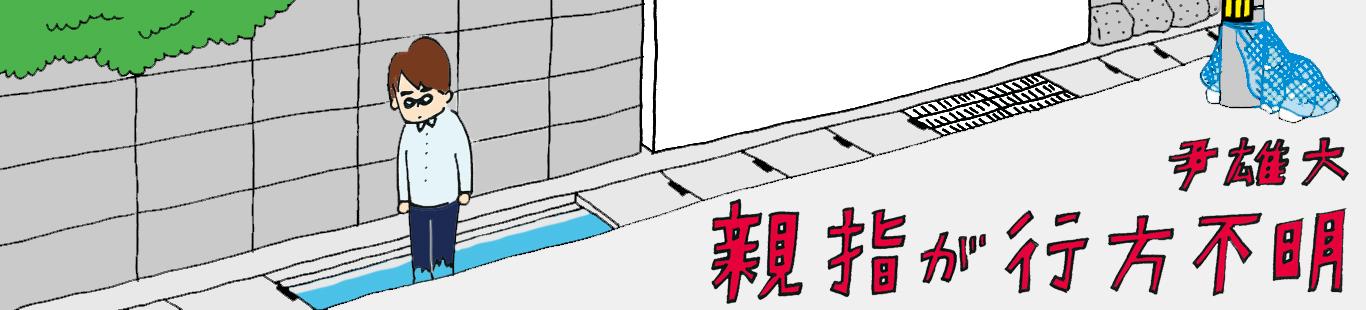




-thumb-800xauto-15803.jpg)


