第2回
なんのためのオリンピック?
2021.05.19更新
【お知らせ】
本連載が、書籍『スポーツ3.0』になりました!
加筆を経てさらに充実した、これからのスポーツ論を
お楽しみいただけますとうれしいです。
「『する』『観る』『教える』をアップデート!
根性と科学の融合が新時代をひらく。
元アスリートとして、声を上げつづけてきた著者の到達点がここに。」
東京オリンピック・パラリンピック(以下東京五輪)が開催に向け、その歩みを止めることなくひた走っている。変異株の流行で国内の感染者が増え続けるなかでも、主催者側は強行開催の姿勢を一向に崩さない。開催を見直す素振りすらみせないその態度に、世間の目はますます厳しくなりつつある。
テレビやネットから東京五輪関連のニュースが慌ただしく流れてくるなか、私が愚の骨頂だと感じたのは「看護師500人の派遣要請」である。
3度目の緊急事態宣言が出される直前の4月下旬、大会組織委員会(組織委)は、大会期間中の医療スタッフとして看護師500人の確保を日本看護協会に原則ボランティアで要請した[1]。
このニュースを最初に目にしたとき、周囲の音がかき消され、時が止まるとともに目の前がクラクラした。「怒髪天を衝く」という表現は、まさにこういうときに用いるのだろうと思う。
組織委の武藤敏郎事務総長は会見で『医療体制が逼迫しているのは重々承知している。地域医療に悪影響を与えないようにするのが大前提』だと述べた[2]。
言葉の意味だけをたどれば医療体制や社会への配慮を思わせる文面ではある。だがこれは、医療現場の実情を把握していない人にしか口にできない言葉だ。もし「重々承知」しているのなら、あらたに看護師を派遣してもらうことが引き起こす医療現場へのさらなる負担に思いが及ぶはずで、そこにはうしろめたさがつきまとい、発言の際にそれが言葉の端々ににじみ出ると思うからである。
ことの重大さを理解していれば、人は言葉を慎重に選び、情理を尽くして語るものだ。だが、その口ぶりからは慎重さがもたらす「ためらい」がまったく感じられない。さも当然であるかのように、前々から決まっていたことだから仕方ないと、まるで開き直っているように見える。
案の定、そのあとただちに医療関係者からの反発を招いた。
愛知県医労連などがTwitterデモを行い、ハッシュタグ「#看護師の五輪派遣は困ります」がトレンド入りした[3]。また東京都立川市の立川相互病院では、「医療は限界 五輪やめて!」「もうカンベン オリンピックむり!」と書かれた紙が窓に貼り出された[4]。さらには本番に向けた陸上のテスト大会が開かれた国立競技場周辺では市民団体によるデモが行われ、「医者もナースも限界だ」などと訴えかけた[5]。
医療関係者がこのコロナ禍でどれほど身を削りながら仕事に従事しているかは、連日、報道されている。
医療従事者の仕事は感染者の治療だけではなく、PCR検査後に陰性が判明するまでの患者への対応や、本来は清掃業者が担うはずの「レッドゾーン」内のトイレや床の掃除も行っていること[6]。また、国からの通達で月4回に制限されている夜勤も月6〜7回やらないと回らず、妊娠しても夜勤を免除できないほど現場は人手不足であること[7]。自らが感染する恐れを抱えながらも日夜こうした仕事に取り組んでいることを思えば、頭を垂れるしかない。
ウイルス感染で亡くなった人はすぐに納体袋に入れられるという。遺族はその遺体をチャックを閉める直前にドア越しに見るだけとなり、最期のお別れができない。やり場のない悲しみを抱える遺族に立ち会う心境がどれほどのものかは、想像するにあまりある。
家族から心配され、感染を恐れる周囲からの偏見に晒されながらも最前線に身を置く医療従事者がいる。だから、いまの社会はかろうじて成り立っている。それに思いが至らない人たちが組織の要職についていることが歯がゆい。
この点だけでも東京五輪は中止するしかないと思うのだが、これ以外にも東京五輪が社会におよぼす負の影響はある。ひとつ挙げるとすれば、いま国会で審議されている出入国管理及び難民認定法(入管法)の改正にも東京五輪は根深く関わっている。
2016年に「東京五輪の年までに、不法滞在者ら社会に不安を与える外国人を大幅に縮減することが喫緊の課題」という内部通達が入管の局長名でなされている。以降、不当に拘留される外国人が増えているという。
不法滞在者のなかには命からがら母国から逃げ出した人もいる。生まれ育った国での生活を捨ててまで逃げ出すには相当な覚悟がいる。ともに暮らした人たちと別れてまで逃げ出さざるを得なかったのだから、そこにはよほどの事情があったのだろう。それを一様に「社会に不安を与える外国人」として、長期にわたり施設に勾留するのは血も涙もない人間の所業だ。助けを求めた彼らの手をはたき落とすようなこの通達が、東京五輪の開催に向けて出されていたことは、決して忘れてはならない。
それにしても主催者側がここまで非人道的にふるまい、たくさんの犠牲を払うことを厭わず開催に固執する理由はなんなのか。
米有力紙が東京五輪の中止を促す記事を相次いで掲載した[8]。そのうちのひとつ「ワシントン・ポスト」によれば、執筆者であるスポーツジャーナリストのサリー・ジェンキンス氏は、『いまのこの段階で夏季五輪の決行を考える人がいるとしたら、その主要な動機は「お金」である』と述べ、命よりもお金を優先する国際オリンピック委員会(IOC)の会長のトーマス・バッハ氏を「ぼったくり男爵」と揶揄した[9]。
これだけ明確に、しかもユーモアを交えながら東京中止を訴えかける記事は残念ながら国内ではお目にかかれない。なぜなら東京五輪のスポンサーに大手新聞社が名を連ねているからである。世論の変化によってやや風向きが変わりつつあるにしても、これまでずっと東京五輪に批判的な意見を意図的に見落とし、掲載したとしても両論併記などオブラートに包んだ報道に終始した。オフィシャルパートナー&サポーターである各紙が、五輪礼賛ムードの醸成に一役も二役も買ってきたのである。
主催者およびそのスポンサーがひた隠しにしてきたものとはなにか。それはジェンキンス氏が指摘する「お金」、つまりそもそもオリンピックとは「お金儲け」を目的とした商業イベントに過ぎないという事実である。なりふり構わず開催に固執するのは「お金」が得られるからである。しかもそれは一部の人たちだけが与る恩恵にすぎない。
オリンピックを開催する目的はアスリートのためでもなく国民のためでもない。つまり「お金」なのだ。
私たちがどれだけの犠牲を払おうともIOCは莫大な放映権料をぼったくろうとしている。そのことに気づいた私たちが下すべき選択肢はひとつしかない。中止である。
「すべての人たち」が健やかに過ごせる社会は理想に過ぎないかもしれない。だが、それは目指さない限り達成できないし、目指さなければ見る見るうちに社会は野蛮と化すだろう。理想的な社会を追い求めるプロセスを通じて、いわばその運動性をエネルギーにして、あるひとときにかろうじて実現するものが「理想の社会」である。
このプロセスの運動性を担保するものに、反オリンピックがある。商業主義に毒されたオリンピックに反対の意思を示し続けることが、理想の社会に一歩でも近づく道筋になると私は思う。少なくともコロナ禍における医療従事者にさえ負荷をかける、いまのようなかたちでのオリンピックは不要どころか有害であり、社会に対して「災害的な負担[10]」をかけなければ開催できないオリンピックとは、この機にきっぱりと決別しなければならない。
[1] 「毎日新聞」2021年4月26日
[2] 「スポーツ報知」2021年4月27日
[3] 「デイリースポーツ」2021年4月28日
[4] 「朝日新聞」2021年5月7日
[5] 「共同通信」2021年5月9日
[6] 「京都新聞」2021年1月15日
[7] 「週刊文春」2021年5月20日号
[8] 「東京新聞」2021年5月12日
[9] 「クーリエ・ジャポン」2021年5月7日
[10] ジュールズ・ボイコフ『オリンピック 反対する側の論理』(作品社)2021年





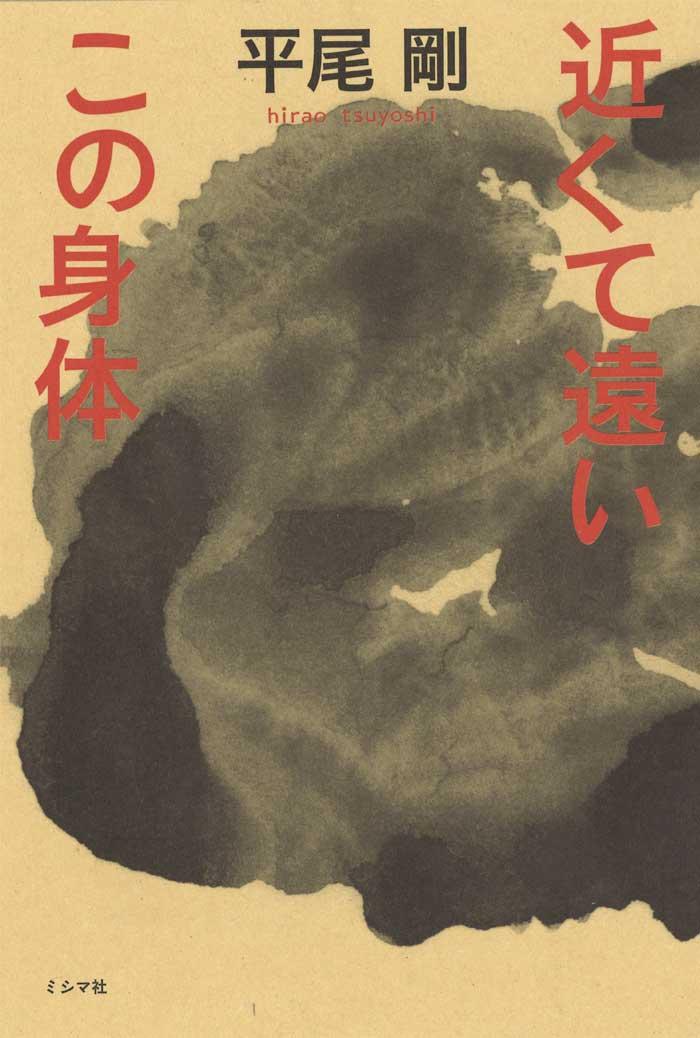



-thumb-800xauto-15803.jpg)


