第1回
土井善晴先生×中島岳志先生「一汁一菜と利他」(1)
2020.07.27更新
2020年6月20日、MSLive!にて、土井善晴先生と中島岳志先生のオンライン対談が行われました。料理研究家と政治学者、そんなお二人のあいだでどんなお話が繰り広げられるのか、一見、想像がつきづらいかと思います。ですが、自分たちの足元からの地続きの未来を考えるとき、中島先生が最近研究のテーマに据えられている『利他』と料理・食事のあいだには、大切なつながりがあることが、対話を通して明らかになっていったのでした。
今回の特集では前半と後半の2回にわけて、そんなお二人のお話の一部をお届けします。
自然−作る人−食べる人という関係
中島 私たちはいま、コロナの経験によって、環境や自然の問題に本格的に直面しています。私は、私たちの日常と自然の関係を考えるときに、台所という場所の重要性がこれから大きな問題になるのではないかと思っています。土井先生のご著書『一汁一菜でよいという提案』は、私が取り組んでいる「利他」というテーマにとって非常に重要な本なのですが、そのなかで土井さんは、こんなことをおっしゃっています。
「地球環境というような世界の大問題をいくら心配してみたところで、それを解決する能力は一人の人間にはありません。一人では何もできないと諦めて、目先の楽しみに気を紛らわすことで、誤魔化してしまいます。一人の人間とはそういう生き物なのでしょう。しかし、大きな問題に対して、私たちができることは何かというと「良き食事をする」ことです。」
「どんな食材を使おうかと考えることは、すでに台所の外に飛び出して、社会や大自然を思っていることにつながります。」
土井 私は料理研究家という職業柄でしょうか、コロナの問題が起こる以前から、自然というものをとても意識していました。環境汚染などの問題を知らせるニュースを見ると、不安でいてもたってもいられなくなります。
料理をすることは、自然に触れることです。さっきまで畑にあったものに手で触れて、食べる人のことを思って料理をする。この「自然−作る人−食べる人」という関係のあいだに、利他がはたらきます。食事は本来「作る」と「食べる」がセットになった行為なのですが、いまの世の中では、この関係性がゆがんで、「食べる」側面ばかりが気にされていると思います。
中島 土井さんは料理を作る人に焦点を当て、そして、作り手の心の状態が多様であることも考えて、料理を提案しておられます。たとえば『素材のレシピ』という本では、作り手のモードによって料理は変わっていいとおっしゃる。「余裕ないモード」のときは、一汁一菜で十分いいと。
土井 「作る」は、「自然=地球」と「食べる」のあいだにあるもので、常に自分の時間とも関わります。時間のないときに一汁三菜なんてできっこない。それを基本とか理想だと思うと、現代社会では、大変なプレッシャーになります。一汁一菜とは、料理は誰でもできるんだということです。女性も、男性も、子どもたちも、ほんとに誰でもできる。そして地球とのつながりにおいては、食品ロスもなくなるのです。
民藝と家庭料理にあらわれる、作為のない美
中島 土井さんが語られる家庭料理と民藝の関係性も、とても面白いです。土井さんは、海外での修行から帰国して懐石料理のプロの料理人を目指していたとき、お父様から家庭料理の料理学校の跡を継ぎなさいと言われ、それが最初は嫌だった。そのときに京都の河井寛次郎記念館を訪れて、大きな感銘を受けたと。
土井 河井寛次郎や濱田庄司といった民藝の作り手たちは、淡々と仕事をし、生活するなかで、そこに美しいものがあとからついてくるように生まれることを、発見したのが、柳宗悦の民藝(論)の始まりです。河井寛次郎記念館で、家庭料理もそれと同じだなと思ったのです。毎日食材という自然と向き合い、直に触れながら、家族を思って料理する。そういった日々の暮らしを真面目に営み、結果として美しいもの(暮らし)がおのずから生まれてくる。プロの料理人を目指していた私がそのとき下にみていた家庭料理のなかに、本当に美しい世界があるということに、気づいたのです。それは「家庭料理は民芸」だという発見でした。
中島 河井、濱田、そして柳宗悦といった民藝の人びとにとって重要だったのが、浄土教の「他力」という考え方です。美しいものをつくろうという芸術家のはからいや作者性ではなく、無名の庶民が淡々と仕事をしてつくりだすもののなかに、阿弥陀の本願という「他力」がやってきて美しさがあらわれる、という観念を彼らは持っていました。
土井 家庭料理も、盛り付けた料理に作った人の顔が残っていてはいけないんです。お料理した人は、消えなくてはならないのが和食です。はからいを作為と考えると、作為という作り手の自我が残っていたら、気持ち悪くて食べられないと思いませんか? その人(の作為)を食べることになってしまう。民藝には、基本的に作者の銘が入っていません。つまり「作品」ではないのです。料理の器(道具)とは、それを使う人が、調理道具のバットやボールのように使うこともできるし、でき上がった料理を盛ることもできる、しかも量を限定しない。(民藝の)道具は、どのようにでも使える万能性があります。家庭の暮らしで用いる道具(器)や料理に、美が生まれるということが、重要な問題です。「道具は要望に無心で応えようとしている」と考えるのは、我々は道具を擬人化して見てきたからです。
中島 土井さんが、「私の名前で料理を作ろう」という世界から、家庭料理という、無名性のなかに溶け込むような世界に行かれたのは、料理人として大きな転換だったのではないでしょうか。
土井 そうですね。プロの料理人の世界にはオリジナリティーの重要性があります。それは本来、欧州の発想なんですが、そういうものが情報として日本人に刷り込まれ、普通の人も時に、料理はクリエイションだと思うのはそのせいです。家庭料理にはそうした作為のあるクリエーションは必要ないし、発想もなかったのです。私は民藝論と出会うことでこのことを深く考えはじめたのですが、料理は、プロの料理とか家庭料理という区別をする以前にまず、自然に触れて手を使って料理をすることですよね。たとえばこの民藝の自然器も(石皿を見せながら)、日本人は生き物のように捉えてきたところがあると思います。縄文人にとっては土器も八百万の神様だと信じていました。まさに人間と自然のあいだに、なにか情緒性が生まれてくるものを感じているんですね。
 (左)土井善晴先生(右)中島岳志先生
(左)土井善晴先生(右)中島岳志先生
ハレではなく、自然をそのまま受けとる日常の食事
中島 土井さんは、日本の家庭で料理をしている人たちがなぜこんなに苦しいかというと、「ハレ」の料理を作ろうとしすぎているからだと。それに対して、一汁一菜を提案される。私たちは「ハレ」を消費しすぎているのでしょうか。
土井 実はハレ(非日常)とケ(日常)は対立するもののように言われています。私もそのように考えてきましたが、誤解の無いようにケハレの意味を少し説明しておきます。日本人の世界観であるケハレとは、ハレの日(まつりごと)・ケハレの日(日常)・ケの日(弔い事)の三つに分けられます。ですから、ケハレの日常生活にも、ハレ的な小さな楽しみがあるものです。そもそもハレの料理(おせち料理や寿司、赤飯など)は、神様のために人間が拵えたものを、神様と一緒に食べる(神人共食)という慣習です。それは、澄んだお吸い物やお肉のヒレやロースのいいところだけ、魚の白身のおいしいところだけを用いる料理です。となると、使わない部位は、ハレの日には相応しくないものとして廃棄しないまでも除かれます。それを「澄ませる」というわけです。これに対して、日常では一物全体(いちぶつぜんたい)と言われるように、無駄をせずすべて食べるという考え方ですが、捨てるところがなにもない、ということです。ハレを現代では祭り事ではなく、ご馳走を食べる日(贅沢をする日)として、おいしいもの(握り寿司やステーキのようなわかりやすいおいしさ)や、きれいに整えられたものになると、カロリー過多になってメタボの原因を作り、また、食品ロスの問題につながります。それは、地球にとっても不健康です。
中島 ハレを日常の食卓に持ち込すぎているのではないか、もういちど日常のなか、民藝的な価値のなかで料理のあり方をみなおそうという考え方には、「はからい」の問題が関わると思います。浄土教には、人間の賢しらなはからいが「自力」で、そうではなく自分自身の無力というところに立ったときに、大きな「他力」がやってくるという観念があります。土井先生はあるインタビューのなかでこうおっしゃっています。
「まずは人が手を加える以前の料理をたくさん経験するべきですね。それが一汁一菜です。ご飯と味噌汁と漬物が基本です。そこにあるおいしさは、人間業ではないのです。人の力でおいしくすることのできない世界です。味噌などの発酵食品は微生物がおいしさを作っています。[...]人間はまずくすることさえできません。そういった毎日の要となる食生活が、感性を豊かにしてくれると私は思っています。」(朝日新聞)
料理は人間業ではない、という言葉はとても重要だと思います。
土井 和食では基本的に、「おいしいものを作ろう」とは考えません。もともとおいしいものを、おいしく食べなさい、それでないともったいないという考え方ですね。そのために、きれいに洗うとか、アクを抜くとか、きちんとした下ごしらえをとても重要視します。だから、安心して食べられる。一つひとつのけじめをつけることは、「美味しくしよう」という作為ではなくて、まさに一木から仏さんを彫り出すように、きれいなものを彫り出すことです。きれいにしたら、あとはそのまま食べればいい。相手は自然ですから、おいしくないときもあります。それは自分の責任ではなく、ああそういうものだと、そのまま受け取ったらいい。実はそれが、一汁一菜の心であり、誰が作ってもおいしいという世界がそこにあるんです。
(後半に続きます)
***


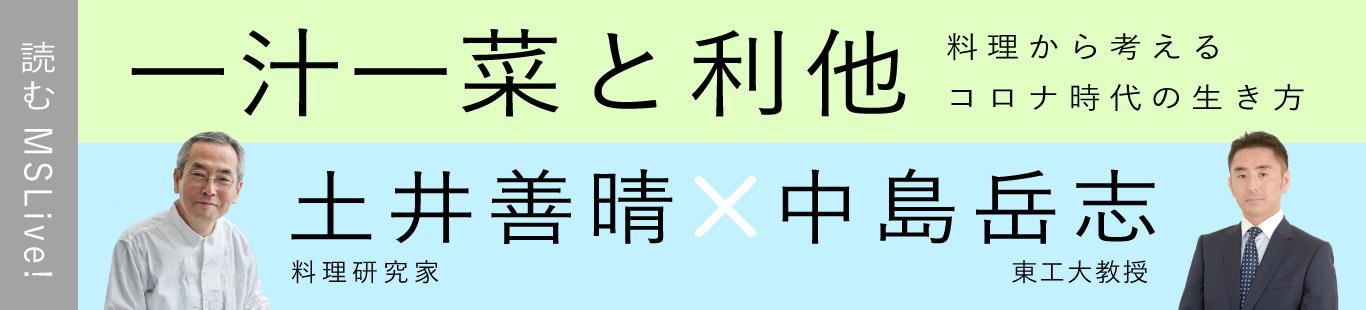

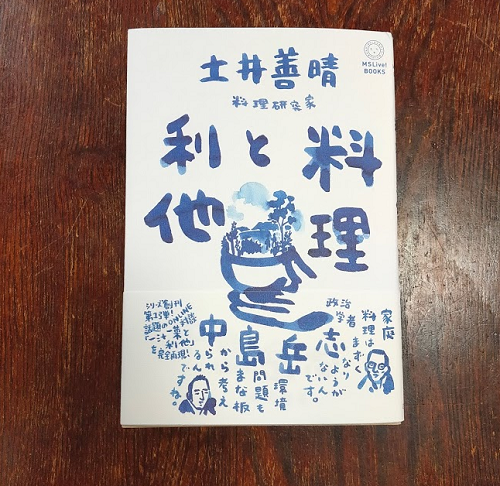


-thumb-800xauto-15803.jpg)


