第1回
2019.11.03更新
息子がシャボン玉で遊びたいというので、昼食後に庭に出ると、足元で落ち葉がパリパリと鳴って、あぁ、秋だ、と思った。
つい先月まで青々としていた木々の葉が、柔らかさと瑞々しさを失い、生物としての崩壊へと向かう途中でいま、僕の足に踏みつけられたのだ。
パリ。クシャリ。
昨日の雨の名残りで湿った落ち葉と、太陽に照らされて乾いた落ち葉と、一歩ごとに音色が違う。
パリ、くさ、クシャリ。
葉の生命力が重力に屈し、土に着地したのはいつだろうか。僕の知らないどこかの枝から、僕の耳に届かない微かな音を立て、この葉たちはみな、地球の質量の中心に向かって、ひらひらと落下したのだった。
葉が、葉でなくなっていく途中に、靴に踏まれて生じた音は、僕の見なかった葉の過去を表現している。葉の形、葉が浴びた雨、葉に降り注いだ光の記憶が、音の波となって僕の鼓膜に届いたのである。
季節 のなかで 、出来事が起こるのではない。落ち葉の音、木漏れ日の表情、シャボン玉を追いかける息子の後ろ姿 として 季節は到来してくる。
あるのはただ出来事の連鎖だ。
葉は壊れながら僕に季節をもたらし、虫たちには寝床を与える。バクテリアには豊かな栄養となり、雨にとっては土に浸み込むまえの最後の障壁となる。
葉は、ただ因果の連鎖にしたがって壊れていくだけである。だが、それがどこに、どんな意味をもたらしてしまうかはわからないのである。
僕の鼓膜に届いた音波は、「パリ、くさ、クシャリ」というオノマトペに訳され、僕の記憶や思考と相互作用しながら、指先の筋肉を動かす。キーボードが叩かれ、電気の回路がめまぐるしく開閉をくり返していく。
あるのはただ出来事の連鎖だ。
こうして生まれた文に、仮に「作者」がいるとするなら、踏まれたすべての庭の葉たちも「作者」の重要な一部ではないか。
自己同一性 というのは曖昧なものである。どこまでが僕で、どこからがそうでないかを確定させることは不可能である。僕は、僕でないものたちが織りなす 網 のなかにいる。庭の葉も木漏れ日も、シャボン玉も、空気の震えも、すべては僕でないものたちが織りなすこの網の大切な一部だ。この網に、閉ざされた境界はない。
錯綜するメッシュのなかにあっては、自分だけ「清潔」で「正しく」あることはできないのである。どこにいても、自分は自分でないものに侵されている。だから何をしても、思いもしない仕方で間違っている可能性がある。すべてを無傷なまま見晴らせるような、守られた安全圏はない。
僕たちはいま、このことを日々ますます深く自覚しつつある。自覚せざるを得ない状況に追い込まれている。これまで安定した「世界」と思われていたものが、あちこちで破れ始めているからだ。
地球は著しい速度で温暖化している。ハリケーンや台風は年々強大化し、氷床は海に溶け出していく。海洋循環のリズムは崩れ、海水面の上昇によって、いくつもの都市が居住不可能になる。
僕たちはもう、人間中心主義的であり続けることができないのである。スムーズで首尾一貫した、一つの尺度のもとに閉じた「世界」という概念は、もはや機能しなくなっているのだ。アメリカで独自の環境哲学を展開しているライス大学のティモシー・モートンは、これを「世界の終わり」と呼ぶ。
世界の終わりは、難解な理論や哲学の帰結ではない。うだるような夏の暑さとして、強大化していく台風として、黄砂とともに飛来してくる見えない化学物質として、僕たちは日々、自分が、いかに自分でないものに深く侵されているかを、学び続けていくことになる。モートンはこれを、「エコロジカルな自覚(ecological awareness)」と呼ぶ。
エコロジカルな自覚とは、おびただしく多様な時間と空間の尺度があることに目覚めることである。そして、人間はこの広大で、必然的に不首尾な可能性の空間のごく狭い領域の一つにすぎないのだと、また、人間の尺度がいちばん偉いわけではないのだと、気づいていくことである。(Timothy Morton, Humankind, 2017)
僕の細胞の一つ一つには、何百ものミトコンドリアが棲みついている。「酸素危機」の時代に僕の細胞の祖先と内部共生を始めた彼らは、いまもせっせと細胞にエネルギーを供給している。銀河の中心には太陽の何百万倍もの質量を持つブラックホールがある。太陽から降り注ぐニュートリノは毎秒約百兆個のペースで僕の全身を通過している。素粒子が生成消滅し、星雲がめぐる。このすべてを一つの尺度に、閉じ込めることなどできないのである。
一つの尺度で閉じる純粋な「世界」というのは、それ自体が人間中心主義(anthropocentrism)の偏狭な視野が生んだ錯覚でしかない。とすれば、 世界の終わりのあと にいる僕たちはいま、何を頼りに生きていけばいいのだろうか。虚無的になるのでも、 冷笑的 になるのでもなく、錯綜する網を、網のまま生きていくには、どうすればいいのだろうか。
モートンは、いまこそラディカルに思考を 減速 させるときなのだと語る。減速とは、思考の停止や鈍化ではない。一見するとスムーズに作動している言葉や概念を疑い、それを自分の言葉として、迷い、逡巡しながら、再び 使い直していく のだ。あまりに深く人間中心主義に冒された人間の語彙や所作を、エコロジカルな自覚のもとで、再び編み直していくのだ。
世界が終わり、僕たちは傷ついている。だが傷こそ、自分でないものたちの 訪問 の痕跡である。二度と傷つかないように自分を守るのではなく、不可解の訪問を深く 聴 すことのできる者に僕はなりたい。
一つの尺度で 他 を 裁 き、すべてをただ効率的に 捌 いていく時代ではもうない。僕らはみな等しく弱い。穴だらけで、開かれた網の一部として、 原理的に 脆弱な存在である。だからこそ、互いに聴し合うことができる。不可解なものたちと、不可解なまま、付き合い続けることができる。
ここは、そのための言葉と思考のリハビリの場である。
ご縁のあったすべての読者の 訪問 を心から歓迎したい。
編集部からのお知らせ
森田真生さんのトークイベントが開催されます。
■11/17周防大島 数学の演奏会in周防大島 2019 Talk&Walk Live
日程:11月17日(日)14:00〜(13:30開場)
場所:周防大島・円満山 正覚寺
■11/23京都 数学ブックトークin京都 2019秋
日程:11月23日(土)14:00〜(13:30開場)
場所:恵文社一乗寺店 コテージ
ちゃぶ台Vol.5にご寄稿いただきました。
10月20日に発刊した、ミシマ社の雑誌『ちゃぶ台Vol.5』に森田真生さんの随筆「聴し合う神々」が掲載されています。本連載と合わせて、ぜひ読んでいただきたい作品です。


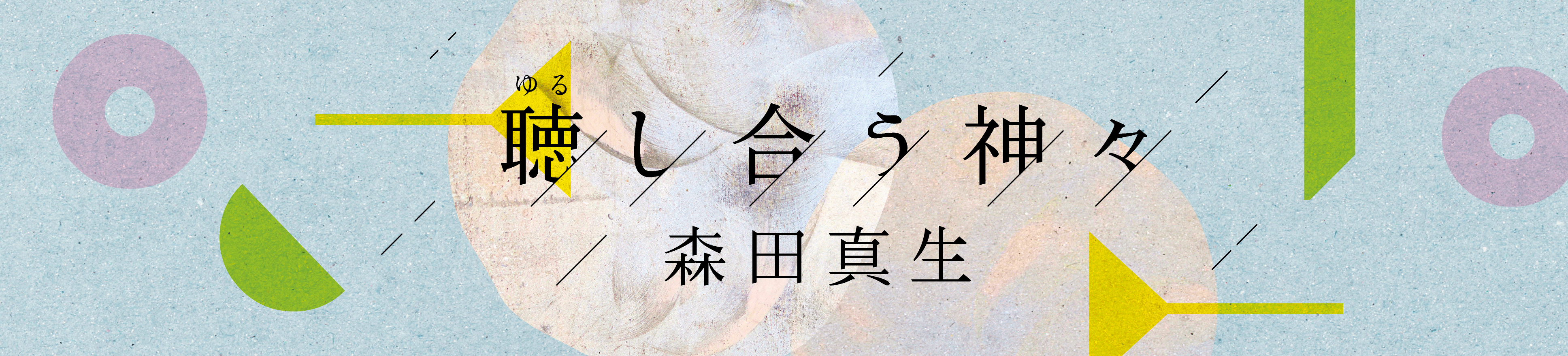






-thumb-800xauto-15803.jpg)
