第2回
2019.12.15更新
先月、リチャード・パワーズの『オーバーストーリー』を読んだ。手に取ろうと思ったきっかけは、作家のアミタヴ・ゴーシュ(Amitav Ghosh)が「気候」を主題とする重要な作品の一つとして、あるインタビューのなかでこれを紹介していたことである。記事を読んですぐに原書を注文したが、届く前に邦訳が出ているのを書店で見つけ、思わずその場で購入してしまったのである。東京から京都に向かう新幹線のなか、さっそく夢中になって読み始めた。
地球温暖化に伴う気候変動は、物理的に人間の生活を脅かしているだけでなく、私たちの考え方そのものを根底から揺さぶっている。自分と自分でないものを、人間と自然、精神と環境などと、内と外、あるいは図と地の構図で切り分けようとする発想自体が行き詰まっている。うだるような夏の暑さ、強大化する台風、夥しい生物種の絶滅に翻弄されながら、哲学的な思弁の帰結としてではなく、静かに進行する日常の不気味な変容として、常識とされてきたものの見方の機能不全が露呈していく。
「自然」や「環境」とこれまで呼んできたものたちが、もはや安定した背景ではなくなったいま、私たちは何を考え、どう生きていけばいいのだろうか。科学に耳を傾け、事実を謙虚に受け止めることはもちろんとしても、すでに
未だ到来していないものを感じながら、自分でないものたちと共存(coexist)していく。そのためには、あまりに深く人間中心主義が染み込んでしまった人間の言葉を、少しずつ人間でないものたちと調子を合わせながら、解きほぐしていく必要がある。
たとえば人間の心を単に物に投影するのではなく、物たち自身の声を言葉として引き出していくためには、どのような言葉と文法を用いたらいいのだろうか。
こうした課題を正面から引き受けていくためには、科学を踏まえた上でさらに、柔軟で大胆な文学的想像力が必要になる。気候の危機と共存していくための新しい言葉と
物語の主役は木々だ。正確には、樹木たちの声を通奏低音としながら、誰が主役ともつかないような仕方で、図と地が曖昧なまま「オーバーストーリー」は進行していく。せわしなく動き続ける人間スケールの時間が、人間から見ればただ「じっとしている(holding still)」ように見える木々たちの時間と混じり合っていくのを感じながら読み進めていくことになる。
物語の前提として、地球温暖化による人類と森林の危機がある。危機において人は行動を求める。だが「行動(act)!」と人が叫ぶとき、その「行動」のイメージはしばしば深く人間中心主義におかされている。
木々だって立派に活動している。もちろんその動きは、人間の速度から見ればあまりに遅い。そのため、動物の動きを見分けるために進化してきた人間の認知能力によっては、動きとして検知されることがない。だからこそ、人間活動の安定した「背景」あるいは「環境」として、森林や木々は暴力的な操作、あるいは搾取の対象とされてきたのである。
だが、大地や森林はもちろん、透明な空気でさえ、人間活動の安定した「背景」ではないのだ。このことを、私たちは温暖化していく地球上でいま、身を以て学習している。人間の活動によって排出された二酸化炭素が大気中に蓄積し、著しい速度で地球が温暖化している。大規模に変動していく気候は、翻って私たちの生存を脅かしている。大気も気候も、人間活動の安定した背景ではなく、生命の網を構成する変動可能な一部だったのである。
内と外を清潔に切り分けることの不可能性に目覚めていく私たちは、
ものはただじっとしているだけで、あらゆる場所へ旅することができる。
A thing can travel everywhere, just by holding still.
木が発する、こんなメッセージから『オーバーストーリー』は始まる。
STILL
じっとそのまま。それでも。まだなお。
木はただその場でじっとしている。何のために枝を伸ばしていくのかわからないまま、それでも、まだなお、生長を続ける。そうしていまや、地上のあらゆる場所に広がり、大気と、生命活動に必要なエネルギーを生成している。
物語には八組の人間が登場する。彼らにもまた、それぞれ「hold still」してしまう瞬間がある。病気によって、事故によって、文脈はそれぞれ違うが、みなそれぞれに、それまで順調に作動していた人生が、機能不全を起こす瞬間がある。だが彼らのそれぞれの道は、むしろそこから開かれていくのだ。
自力で人生を切り開こうとすることによってではなく、むしろ自力の作動が意に反する形で行き詰まってしまったとき、そこに思わぬ他者が訪問してくる。そこから彼らは、自分でないものたちと調子を合わせるように、新しい道を歩み始めていくのだ。
私はこの物語を読みながら、ティモシー・モートンの「rest」という言葉を思い出していた。「rest」とは、単に
restは、他者を「そのままにしておく(leave alone)」ことである。そうすることで自分でないものたちを「聴す」ことである。それは、他者との共存の道を開く
『オーバーストーリー』のなかで、樹木を危機から救おうと立ち上がった一人に、夢のなかで木々が語りかける場面がある。
私たちを救うだって? いかにも人間が考えそうなことだ。
Save us? What a human thing to do.
木々は笑う。
ゆっくり、何年もかけて笑う。
危機の時代、人はますます「行動」を求めるようになる。
行動によって、行動に立ち向かう。これとは別の道はないのか。
人間でないものたちの存在が、私たちに別の可能性を示唆する。その言葉を聞き取るためには、じっとその場で、耳を傾けてみる必要がある。
(*1)"Rest in this 'positive' sense suggests a deep acceptance of coexistence." (Timothy Morton, Hyperobjects, p.198)
編集部からのお知らせ
森田真生さんのトークイベントが開催されます。
■2020年1月9日(木)京都
「独立研究者越境対談 森田真生×朴東燮」
日程:1月9日(木)19:00〜(18:30開場)
場所:恵文社一乗寺店 コテージ
■2020年2月2日(日)東京
「数学ブックトークin東京 2020 立春」
日程:2月2日(日)13:30〜(13:00開場)
場所:青山ブックセンター本店内・大教室
ちゃぶ台Vol.5にご寄稿いただきました。
10月20日に発刊した、ミシマ社の雑誌『ちゃぶ台Vol.5』に森田真生さんの随筆「聴し合う神々」が掲載されています。本連載と合わせて、ぜひ読んでいただきたい作品です。


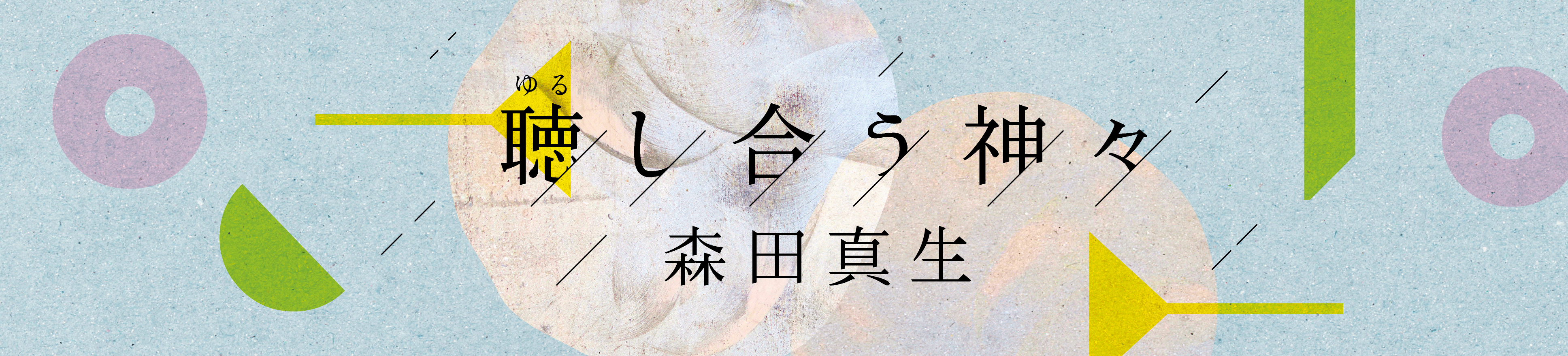






-thumb-800xauto-15803.jpg)
