第3回
2020.02.10更新
「たんぽぽさんおはよー!」「カモさん待って待ってー!」と、我が家の三歳児は、人間と同じように、人間でないものたちにも話しかけていく。子どもにとって、言葉を交わし合うことのできる相手は、人間だけではないのだ。
大人になるにつれ、人は人間以外のものに語りかけなくなる。人の見ているところでたんぽぽに、「おはよう!」とあいさつするのは、大人にとっては少なからず勇気のいることである。
人間でないものたちが、人間と同じように言葉を発する物語は「童話」と呼ばれる。非人間との会話を堂々として許されるのは、なぜか「
そもそも大人が使う言葉は、人間同士のやりとりのために作られている。だから、植物や鉱物に語りかけようとすると、どこかつたなく、まるで子どもの言葉のようにたどたどしくなる。
『オーバーストーリー』[1]にレイ・ブリンクマンという知的財産権を専門とする弁護士が出てくる。彼はある日、脳出血を起こし、自宅で寝たきりになる。以来、窓から庭の木々を眺めて過ごす日々が始まる。
そんな彼の口が開いて、ふと不可解な声を出すときがある。それはまるで赤ん坊のような、意味をまだ持たない言葉である。妻の耳にはそれが、「何(what)」と「誰(who)」の中間の音に聞こえる。
脳出血の後遺症で彼は自由に顔の筋肉を動かすことができないのである。だから彼は、自分の言葉を正しく分節することができない。「正常に」発話できる人間の側からすれば、彼の言語能力は明らかに退行している。
だが、そもそも相手が人間かそうでないかに応じて、疑問詞を使い分ける規則そのものが、英語話者を拘束してきた一つの習癖にすぎない。それは、人間と人間以外の区別を自明とする「人間中心主義(anthropocentrism)」を暗に前提とした言葉の思い込みである。
「人間の権利」のためにたたかってきた弁護士のレイは、日々、ひたすら窓から木々を眺めているうち次第に、木々の存在と同調(attune)していく。彼の思考と感性はやがて、人間中心主義の暗示から解かれて、人間と非人間を区別しない不可解な疑問詞を生み出すにいたる。人間の常識から見れば言語の退行であるが、人間でないものたちを含めた立場から見ると、むしろ言語の解放である。
日本語には「もの」という言葉がある。これが文脈に応じて「者(person)」にも「物(thing)」にもなり得る。木々と同調していくレイ・ブリンクマンのように、日本人もまた、かつてはpersonとthingの区別が曖昧な世界を生きていたのだろうか。
「者(person)」が「物(thing)」と同じ地平に立つこと。それは、「物」を「者」に擬える擬人化ではない。
人であることを特別視し、そこから自己中心的に物を見晴らすのではなく、人であることが物であることと地続きになる場所に降り立っていくのだ。芭蕉はこれを「物に入る」と言い[2]、西田は「物となる」と言った[3]。
物が物に触れるとき、そこに
物に触れて「あな、うつくし」と情が感く。この感動を宣長は「あはれ」と言った。彼の言うように、「いきとしいける物はみな情あり」とするなら、物にも物の「あはれ」があっていいはずである。
宮沢賢治は動物や植物だけでなく、鉱物のあはれにすら接近を試みた稀有な詩人だ。『気のいい火山弾』の「
近世ドイツ語にrockenという言葉がある。その場で腰を振る動きを意味する言葉だという。ティモシー・モートンはこれを踏まえて、「その場にいながら動き続けること」こそが、rockという言葉の本義だと論じる[5]。
岩はその場でrockしている。どこにもいかないまま、大気や、太陽の光に応じて、その場で繊細な活動をしている。温度や湿度によって岩の状態は変わる。雨粒が岩に当たれば、表面にいた微生物たちが動く。火成岩は何万年もかけて人間活動が生み出した二酸化炭素を吸収していく。そして、人間には気づくことができない緩慢な速度で風化していく。
地質学的な時間のスケールで見れば、あるいは、極めて小さなスケールで見れば、岩もまた環境に応じて、常に動き続けている。賢治の童話は、その岩たちの「情動」に接近していく。岩はたえずrockしている。物に触れて感いているのは、人間の心だけではないのだ。
万物にそれぞれのあはれがあることに思いをいたすとき、人間でないものへと語りかけていくのは、もはや子どもたちだけではなくなる。大人もまた、植物や鉱物と同じ地平に降り立ち、つたなく、しどけなく、物と共にあり続けるための言葉を探し始める。
「童話」という言葉がなくなる。
[1] リチャード・パワーズの『オーバーストーリー』については連載二回目を参照ください。
[2] 「松の事は松に習へ、竹の事は竹に習へと、師の詞有しも、私意をはなれよといふ事也。習へと云は、物に入てその微の顕て情感ずるや、句となる所也。たとへ物あらはに云出ても、そのものより自然に出る情にあらざれば、物と我二つになりて其情誠にいたらず。私意のなす作為也」(『三冊子』)
[3] 『日本文化の問題』
[4] 『石上私淑言 上巻』
[5] The early modern German "rocken," a rare term for wiggling the butt. To sway gently. The Swedish "rucka," to move to and fro. Rocking gathers a whole set of resonances to do with moving in place, oscillation, moving while standing still. (Timothy Morton, Humankind, p.179)
編集部からのお知らせ
森田真生さんのトークイベントが開催されます。
■2020年3月1日(日)京都
「数学ブックトークin京都 2020啓蟄」
日程:3月1日(日)14:00〜(13:30開場)
場所:恵文社一乗寺店 コテージ
ちゃぶ台Vol.5にご寄稿いただきました。
10月20日に発刊した、ミシマ社の雑誌『ちゃぶ台Vol.5』に森田真生さんの随筆「聴し合う神々」が掲載されています。本連載と合わせて、ぜひ読んでいただきたい作品です。


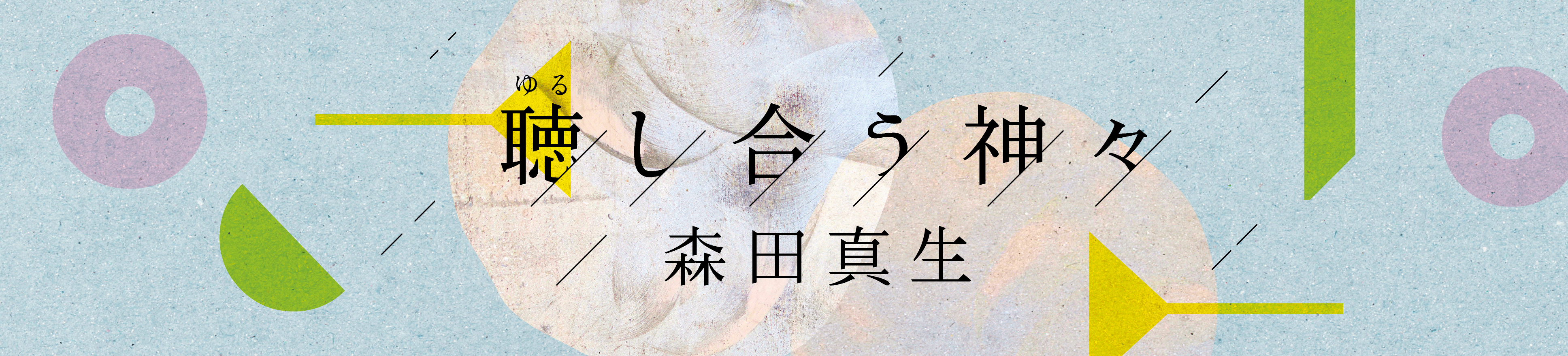






-thumb-800xauto-15803.jpg)
