第4回
石の上にも三年
2022.08.24更新
本連載が『仲野教授の この座右の銘が効きまっせ!』というタイトルで、一冊の本になりました。2024年3月15日(金)より、書店先行発売です。書籍では、たっぷり30本の「座右の銘」を収録。ぜひお楽しみください。
こんな座右の銘いらんやろ、というお題で書いていますけど、必ずしもその言葉を全否定というわけではありません。そらそうですわな、ある言葉を座右の銘にする人がいるということは、なんらかの真実(らしきもの)を含んでいるはずです。
ただ、座右の銘というのは、多くの場合、短いセンテンスです。刈り込まれすぎているがために、意味がわかりにくくなることがありそうです。断定的になりすぎているというきらいもあります。それに、多くは昔から語り継がれている言葉ですから、時代にそぐわなくなっている場合も。で、今回はその三拍子がそろっているのではないかという格言、石の上にも三年、であります。これはもう、ほとんど全否定したい。
自慢じゃないが飽きっぽい性格である。そういうと聞こえが悪いが、自己肯定感が強いので、あっさりしている、あるいは、判断が速い、という言い方もできるのではないかと密かに思っている。密かにといいながら、書いてしもてるけど・・・。なので、石の上にも三年とか聞くと、イヤミを言われているのかという気がすることすらある。だから、そもそも気に入らん。
石の上にも三年、というのは、てっきり達磨大師の故事に由来するものだと思い込んでいた。「
そうではなくて、もっと昔、二千年ほど前に、インドのバリシバ尊者が80歳で出家し、三年もの間、石の上で座禅し続けて悟りを開いたという故事によるという説もあるらしい。その間、横になって眠ることもなかったというのだから、意志も強いけど、きっと体も強い人やったんでしょうな。細かいことはさておき、どちらにも共通しているのは、長い年月をかけて悟りの境地に至った、ということである。まぁ、そういうこともありえるのだろうとは思う。
なにを隠そう、私は悟りを開いた経験がある。もう40年ほども前、加賀の白山でのことだ。山で修行を積んだ、という訳ではない。友人の運転する車で登山に行ったのだが、その帰りに山道でスリップして、2メートルくらいの崖を転落したのだ。いかなる力学が働いたのかわからないが、天井を下にしての着地であった。
その時、景色がスローモーションのように見えた。うわっ死ぬかも、と思ったけれど、過去の思い出が走馬灯のように巡るようなことはなかった。だからきっと死なないんやわ、とつまらんことを考えていた。ほんの短い間に、である。こういった時は、脳が異常なまでに機能するんでしょうな。頑強な四駆だったこともあって、幸いなことに怪我はなかった。
当時は若かったし、やたらと厳しい大学教員だった。しょっちゅう怒りながら指導していた。いまなら間違いなくアカハラでアウトである。ところが、この事故の後、大学院生がどのような失敗をしても、まったく腹が立たなくなった。悟りだ。周りに、どうやら悟ったようで、心が平穏で澄み切っていて、なにも腹が立たなくなったと話していた。
すると、生意気な若者が、そんな数秒で開いた悟りは、きっとすぐに解けるはずだという。それ以前の私なら、そんなことあるかアホボケカス! と叱り飛ばしていたところだが、なにしろ悟っていたので、怒りの気持ちもわいてこない。ふぉっふぉっふぉっ、だから悟りを開いたことのない者は困るのぉ、とか鷹揚に構えていた。が、正しいのはその若者だった。一週間もたたぬうちに元にもどってしもうた。
何が言いたいかというと、人間は悟りを開くことができるが、その境地に至るには、どれくらい時間がかかるかというのは、前もってわからないのではないか、ということである。さらにいうと、何年経ってもあかん場合だってあるはずだ。実際、バリシバ尊者は三年で、達磨大師は九年かかったのだ。もしバリシバ尊者がいなかったら、石の上にも三年ではなくて、壁の前でも九年とかいう信じられない格言ができていたかもしれない。ここはバリシバ尊者に感謝の意を表したい。とはいえ、三年でも長すぎるのではないか。
三年というのは、あくまでもある程度以上の長い期間を示すものであって、具体的な年月をさすのではないという解釈もあるだろう。しかし、こういう言葉というのは、結構な拘束力を持ってしまう。まぁちょっと君、三年はがんばってくれたまえ、とか簡単に言いたくなるおっさんがあちこちにいてそうやないですか。
バリシバ尊者や達磨大師の頃とは時代が違う。ものごとの進むスピードが速くなっている。どんな我慢かにもよるが、いまならせいぜい1年、いや3ヶ月くらいではないか。それ以前に、どの職場でもストレスチェックが義務づけられている時代、いつになったら成功するかわからないのに、やたらと我慢すること自体がおかしいんとちゃうんか。そんなことするくらいなら、我慢などせずに済む方法を見つけるべきだ。
江戸時代に博多で活躍した禅僧、
これだけなら何のことかわからないが、そこに「座禅して人が仏になるならば」という賛が添えてある。秀逸ではないか。禅画なのでいろいろな解釈が可能だろうけれど、しょうもない無駄な努力など無意味だと教えているようにしか思えない。
石の上にも三年、どう考えてもあきませんやろ。石の上より畳の上、とか、石の上より布団の上、とかいう精神があらまほしいんとちゃいますかね。きっと仙厓和尚だって同じ意見やったに違いありませんで。よう知らんけど。
(編集部より)
読者のみなさまからの「座右の銘」を募集しています。
このたび、仲野先生が読者の方からの「こんな座右の銘なんですけど、どないですやろ?」相談を受けてくださることになりました。仲野先生に「好かん!」認定された座右の銘は、いつかこの連載の中で、取り上げるかもしれません。ぜひお気軽にお寄せください。連載へのご感想も、お待ちしています。
お送りいただく方法
メールにて、件名を「こんな座右の銘」として、下記アドレスにお送りください。「座右の銘」とともに、座右の銘としている理由やきっかけなどもぜひお寄せください。
hatena★mishimasha.com (★をアットマークに変えてお送りください)




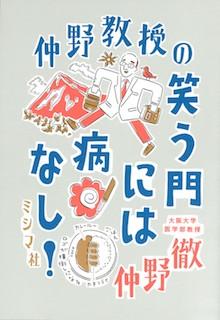
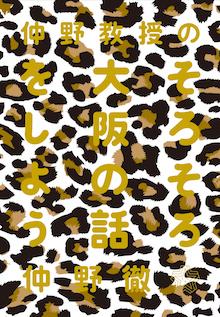




-thumb-800xauto-15803.jpg)
