第2回
めひこ再訪後編 「女性」の集会
2018.06.03更新
前回は、わたしが一年ぶりにメキシコシティに降り立ち、チアパス州まで南下して、タイムスケジュールがおそろしく狂った末に、「第一回世界の闘う女性たちの集会」の会場にたどり着いたところまでを書きました。
「第一回世界の闘う女性たちの集会」は、サパティスタ民族解放軍(EZLN)の自治区に世界中の「女性」が集まって、「女性」をめぐる問題について考える、というイベントです。考える、といっても、朝から晩まで座って討議を行うわけではありません。世界各国からやってきた合計約7000人の女性たちが、広い会場を20数ブースに分けて、バスケやサッカーの試合をやったり、音楽や演劇やダンスを披露したり、アートのワークショップに参加したり、色々なアクティビティをとおして交流するのです。
 会場内の様子。こんなにひとがいました。奥の右側が中央ステージ。左端には会場に泊まり込むためのテントが映っています。
会場内の様子。こんなにひとがいました。奥の右側が中央ステージ。左端には会場に泊まり込むためのテントが映っています。
前回の記事で図らずも詳述してしまった「壊れかけの車騒動」をともに乗り越えた友人たちは、会場でわたしにこんな提案をしてくれました。
「わたしたちも最終日に、太鼓を叩いて、ナワトル語の歌を歌うステージをやるんだけど、一緒に出ない?」
彼女たちは、音楽部門に出場する予定だったのです。そして本番2日前にして、舞台に立つメンバーにわたしを入れようとしている。
スポーツなりダンスなり遊びなり、なにかをみんなでやるときはほぼいつもそうなのですが、メヒコの多くの人は、個人のレベルの違いを全然気にせず、飛び入りを許しちゃうところがあります。メンバーを拡大することに、あまり抵抗がない。練習不足とか、素人とか、関係ないのです。いっしょにやろうよ、と。
そういうわけで、ステージ上で太鼓を叩いて歌うことになりました。せっかく寛容に誘ってもらったにもかかわらず、勝手に「義務感」に駆られてしまったわたしは、「残り2日・・・!」と思いながらひとり猛練習。一言も話せないナワトル語(先住民言語のひとつ)の歌詞のメモを取り、メロディを歌ってもらってレコーダーに録音し、何度も聴いてひたすら覚えました。おかげで本番は無事終了し、わたしは思いがけず「出演者」側になれたのでした。
さて、「女性だけで集まって、女性のことを考える」この集会が開かれた背景には、いまのメキシコのどのような事情が関わっているといえるでしょうか。
当然のことですが、女性をめぐる問題は、ここ最近になってからメキシコ社会で急速に取り扱われはじめたわけではありません。メキシコはマチスタ(男性至上主義)の国、また、セクシャルマイノリティに不寛容な国である、という指摘は一般的によくなされます。メキシコだけが特にそう、と言うつもりは全くありません。しかし、そうした傾向が、メキシコ社会の多くの人にとって生きにくさの原因になっていることは事実であり、性のテーマはこの国のなかで、様々なかたちをとって、いくつもの時期を跨いで問われてきました。
今回の集会についても、その意義や目的や動機をひとつのものに集約することはできません。ですがここでは、いま「闘う女性」の集会が開かれたメキシコの文脈として、わたしにとって重大だと思われるテーマをひとつ示してみることにします。
それは、近年のメキシコ、ひいてはラテンアメリカ全体の女性をとりまく、「フェミニサイド(スペイン語ではFeminicidio。直訳は、「女性の殺害」)」という問題です。
フェミニサイドは、「性・ジェンダーを理由に、女性が(おもには男性から)殺されること」を意味します。性的侮辱や女性蔑視が殺害に結びついたものであるため、事件は多くの場合、暴行やレイプを伴います。
メキシコでは1990年代初頭からフェミニサイドが問題化し、いまに至るまでの20数年間で、この状況は拡大・激化してきました。事件の加害者は、犠牲者の女性の近親者であることもあれば、知らない人という場合もあります。後者の場合だと、麻薬犯罪組織と関連して性産業が拡大し、そこに巻き込まれた女性が殺害される、というのが典型的なケースのひとつです。いずれにせよ、フェミニサイドは、性を理由にした社会的不公正や差別感情が、社会経済的な状況と絡み合いながら、殺人という最悪のかたちをとってあらわれたものといえます。
ある統計では、フェミニサイドの発生数が多い世界25か国のうち、14か国がラテンアメリカの国となっています。数字を並べることが事態を理解するための最良の手段であるとは言い切れませんが、参考までに、次のような統計もあります。ラテンアメリカでは1日に約12人の女性がフェミニサイドの犠牲となっており、このうち約7人はメキシコ人女性。またメキシコ国内では、過去数年間においては年間2500人以上の女性がフェミニサイドの犠牲者となっているうえ、3分ごとに4人の女性が性暴力を受けているとも言われています。
こうしたことを背景に、ラテンアメリカでは2016年ごろから、女性を主題とした社会運動が強まっているのです。"Ni una menos"(これ以上ひとりのマイナス(犠牲)も出さない)や、"#Miprimeracoso"(#わたしの最初の性的いやがらせ)といった言葉をつながりのきっかけにして、女性が中心的担い手となった示威行動が起こっています。
わたし自身、メキシコ滞在中に出入りする大学のキャンパス(メキシコ国立自治大学)では、「フェミニストのストライキParo feminista」によく出あいます。今回の旅のあいだにも、一緒に昼食を食べる約束をしていた友達から「いまストライキをやってる」という連絡が入った日がありました。封鎖されたキャンパスの前で彼女に会うと、ストの理由についてこう教えてくれました。「ある女子学生に性暴力を振るった大学教授にたいして、大学が研究費を与えようとしてる。そのことに抗議して、哲学・文学部の女性のグループがストを企画したの」。
「世界の闘う女性たちの集会」でも、フェミニサイドが起きているわたしたちの世界について考えること、そして、それに対して抗議の声を上げることの必要性が、強く訴えられていました。
イベントを主催したサパティスタ民族解放軍(EZLN)は、「言語や文化や身体的特徴や考え方において様々な違いをもっているけれども、『女性である』ということ、そして、『女性であるがゆえに蔑視や差別や暴力といった深刻な問題に曝されている』ということにおいては同じ立場にあるわたしたちが、こうして出会えるように、この集会を開いた」と述べています。
会場には幼い少女からおばあさんまで、いろんな考え、いろんな身体、そしていろんな性自認をもつ「女性」がいました。だから、あるべき「女性」の枠組にこだわる必要はまったくなく、そのような同化的な空気をわたしは少しも感じませんでした。
しかしやはり、「女だからおなじ」なにかがあることも事実で、女性の身体をもっている、あるいは社会から女性として認識されるがゆえに、わたしたちは、命の危機にすら結びつくようなリスクを現に分け持ってもいるのです。女ばかりで集まったこのイベントは、「女性であること」について、いろいろな角度からの見方を与えてくれました。
イベントが終了した自治区を後にするため、友人らと再び車に乗り込みます。
行きの時点で半壊していたワーゲンは帰りも絶好調。相変わらず火を噴きながら、山道に次々と部品を落として走行。それをジープがうしろからすべて確認し、ひとつずつ拾って追いかけます。
車内では、やっぱりあのステージ飛び入りは迷惑ではなかったか、といつまでも気にするわたしに、彼女たちは、「なーに言ってんの! なにごとも一緒にすることが大事なんだよ」と。厳しい現実と向き合い、痛みを叫ぶようにメッセージを交換しながらも、みんなで楽しく集まることを忘れないこと。縮むこころを、何度も広げてくれるような旅になりました。


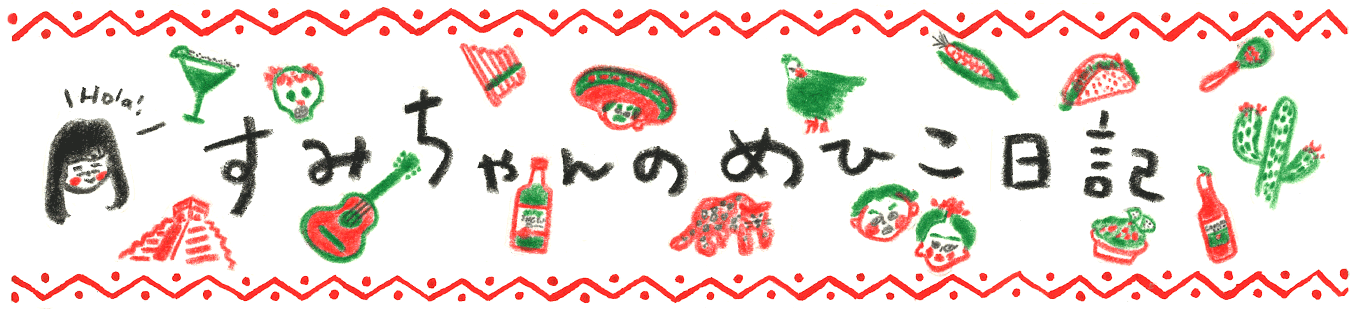
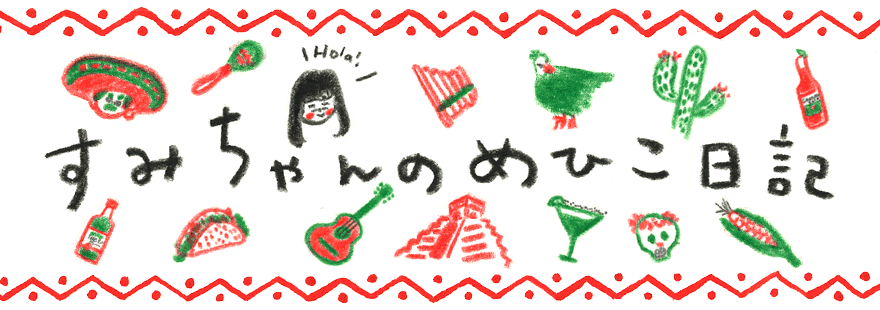





-thumb-800xauto-15803.jpg)
