第4回
枝豆の収穫に失敗し、再起をかけて植えた人参が
2025.08.11更新
好きなことを自分の生業にするのはなかなか大変で、大概の場合は好きなことが丸っと好きな要素だけでこの世に独立していることはなく、好ましくない成分で薄らとコーティングされていたり、生理的に触ることが難しい箱やわけの分からんフォルダへの仕分けを強要されたり、場合によっては好悪の本質が見えないような状況に追い込まれたりするのは、多くの人がそれぞれの分野で体験していることだと思う。
音楽も例外ではなく、というか、そうした苦悩のど真ん中のような存在で悩ましい。
もう俺は好きなことしかやらぬ。と決めて意地の中心のような場所で座禅を組み、自分らしい作品に邁進していくと、音楽産業のような場所では孤立せざるを得ない。というか「私の好み」というのは、様々なものからの影響はあるにしても、それを自我と決めてつけてこの世に配置するためには、徹底的に孤立する以外に方法がないというのが正直なところだと俺は思う。
しかし、人間が社会に関わらずに暮らすのは、食べ物ひとつ取っても難しい。自生する野草の種を独自に採取して農業を始めたり、刃物などの文明の利器を使わずに素手で猪を仕留めて生のまま食べたり、野生動物に近いナチュラルな暮らしをしたいと思っても、生まれて直ぐに野山に放置されて山犬に育てられたという人は皆無に近いわけで、原初の猿人に戻ろうにも、それは文明や社会への叛逆みたいな順路でしか成り立たない。そうした遡行的な反逆は、どこまで行っても社会的な行為なのではないかと思う。
音楽はそもそも、社会からの独立や孤立という向きとは逆の、共生とか調和とか、集団としての人間が上手くやっていくための精神の発展の流れに大きく言えば沿っていて、社会はおろか群れから離れ裸で単独狩猟採集生活というところまで戻るのはとても難しい。
仕方がないので、時折「私の好み」に衝突してくる、私が好まざる誰かの好みとも付き合い、なんとか折り合いをつけていこうというのがダイバーシティー(多様性)というか、それこそ社会そのものだと思うが、多くの人が知っている通り、それは口で言うほど簡単ではない。
と、ここまで書いたところで、妙にいろいろな仕事が立て込んで忙しくなり、どうしてこのような文章を書き始めたのか忘れてしまった。
こういう場合には、ここまでの原稿を一度破棄して、頭から書き直すのが随筆とかエッセイの正しい書き方のような気もする。が、放って置いた原稿を、当初のプランを思い出せないまま書き進めるのも、「正しさ」みたいな考え方がぶつかり合って乱反射し、様々な角度から押し寄せ、それらに小突き回される世の中に対する反抗なのかもしれないと思った。
正しさとは一体何なのだろうか。
この春先に、パッケージに印刷された適正な種蒔きの時期に従って、枝豆の種、すなわち大豆をプランターに植えた。正しい時期の正しい豆蒔きということで、直ぐに大豆は発芽して、すくすくと育った。俺は気が早いので、早めにビールを買って冷やしておいたほうがいいのかしらと、ソワソワしながら暮らした。正しさに対するリサーチも抜かりなく行い、収穫量を増やすために、途中で成長点と思しき若い葉を詰む行程も忘れなかった。
その正しさの果てで、俺は自宅で真夏のビール祭りや、ベランダビアガーデンなどを開催しただろうか。否。今年収穫し食べることができた枝豆はたったの一粒だった。
どういうわけか大豆の葉は妙な感じで萎れていって、どんどんと勢いがなくなり、ほとんどの株が枯れてしまったのだった。辛うじて収穫できた枝豆は、居酒屋の枝豆の小鉢の底に残っているような、赤ちゃんみたいな豆粒が一つ入った房で、特段味が濃いでも薄いでもなく、記憶に残らない一粒の豆として、嚥下されていったのだった。
とても悲しかった。
あまりに悲しかったので、正しい時期ではないけれど何かの種を新しく蒔かずにはいられなかった。
葉が生い茂るタイプの野菜を再び正しく育てようとして、同じように枯れてしまったら悲しい。立ち直れる気がしない。いくらか考えたうえで、根菜の種を蒔いてみることにした。人参を選んだ。
人参は瞬く間に芽を出し、スクスクと育った。なんかイメージと違う感じの芽というか葉の形だったけれど、ここから人参らしくなるのだろうと思って、正しく朝晩、水をやり続けた。人参はどんどんと葉を伸ばした。こんなに葉が伸びるのだろうかと不安になった。地上に生い茂る葉のサイズ感から考えると、プランターを突き抜けるくらいの巨大な人参でないと植物としてのバランスが悪いと感じた。うんとこしょ、どっこいしょ。引っこ抜くにはお爺さんやお婆さん、近所の犬などの助けもいるかもしれない。大豆が急に枯れたことも含めて、何らかの呪いや祟りかもしれないと思って家族に相談してみたところ、どう見てもトマトではないかということだった。
恐ろしいことだと思った。
俺が育てていたのは人参ではなく、トマトであった。
種を取り違えるなんて阿呆すぎる。それは家庭菜園とか農業とか以前の問題で、うっかりのレベルが違う。絶望するくらいレベチの阿呆なので野山に戻ろう、ドングリを拾って団子を作り、それを主食にして暮らそう。とは考えなかった。むしろ、ラッキーだなと思った。もしかしたら冷やしトマトでビールが飲めるじゃん、と浮き足だった。
正しい枝豆の収穫に失敗し、再起をかけて植えた人参がトマトだった、みたいなことが音楽で起こった場合、俺はそれなりに魂を削られて、しばらく寝込んでしまうような気がする。誰かから依頼された仕事だった場合は自信を失うだけでなく、仕事がなくなってしまうかもしれない。
しかし、誰に頼まれたわけでもない菜園の場合、植物相手のままならなさもある程度受け入れているので、精神を磨耗するようなダメージにはならない。大豆がほとんど枯れてしまったことは悲しいけれど、その後は特別な期待もない。植物たちには申し訳ないが、今では元気に育ってくれれば何でもいいと思っているし、なんなら最終的にトマトの実が成らなくても、それはそれでいいかなと考えている。こちらが適当なのだから、特別な見返りは求めていないのだ。
食えるか食えないかみたいな、生活に直結する農業であった場合、こんなふうには考えられなかっただろう。経済的な意味での「食える」も切実だけれど、生命を維持するための食物という意味での「食える」はもっと重い。そういう状況に追い込まれないということの幸せを、噛み締める。失敗してもいいということは、とても幸せなことなのだと思う。
俺たちは何にせよ、とにかく金銭の支払いに追い回されて、なるべく短い時間と少ない予算のなかで結果を出すことが最良だとされる社会を生きている。そういう環境のなかでは、失敗の中から新しい何かが見つかるという機会も減っていく。そもそも失敗が許される場所が少なくなっていると感じる。それは、作っている本人にとっても、何らかの成果を待ち望む我々にとっても損失だろう。
トマトのプランターの隣では、大豆と同じ時期に埋めておいたドングリが芽を出していた。ドングリは種類にもよるけれど、簡単に団子にして食べられるような木の実ではない。食べられるものをどうにか見つけて、工夫しながら、私たちの祖先はやってきたのだろう。大体がトマトは本来、日本の野菜ではない。トライ&エラーの川下で、俺たちは失敗即アウトとはならない豊かな時代を生きている。
素敵なことだと思う。
失敗は成功のマザー。長嶋茂雄の言葉だ。おおらかに失敗できるような、音楽スタジオを作りたいと思ったのは、いつのことだったかしら。


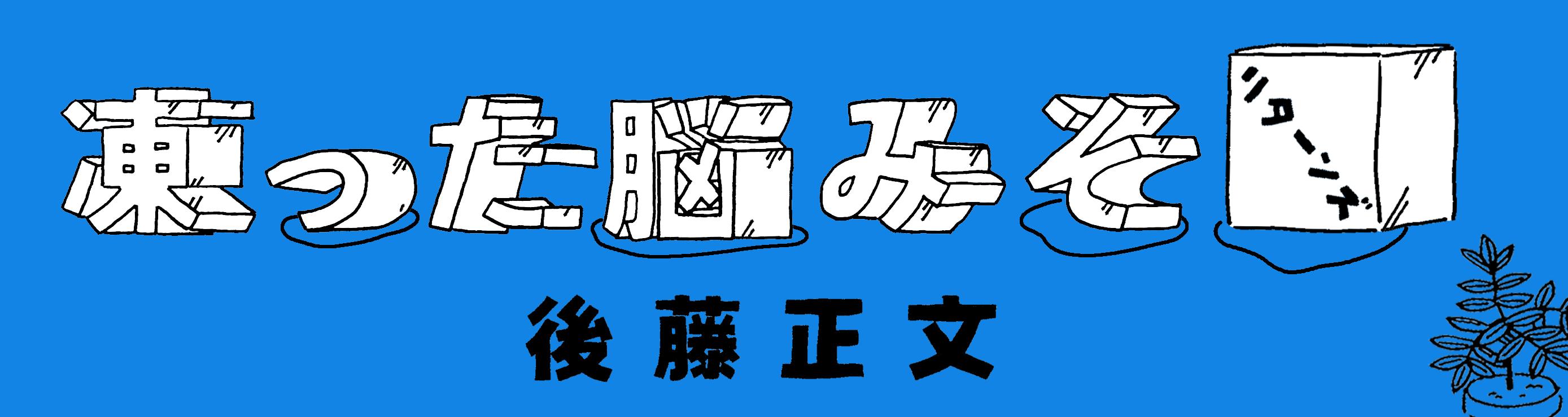

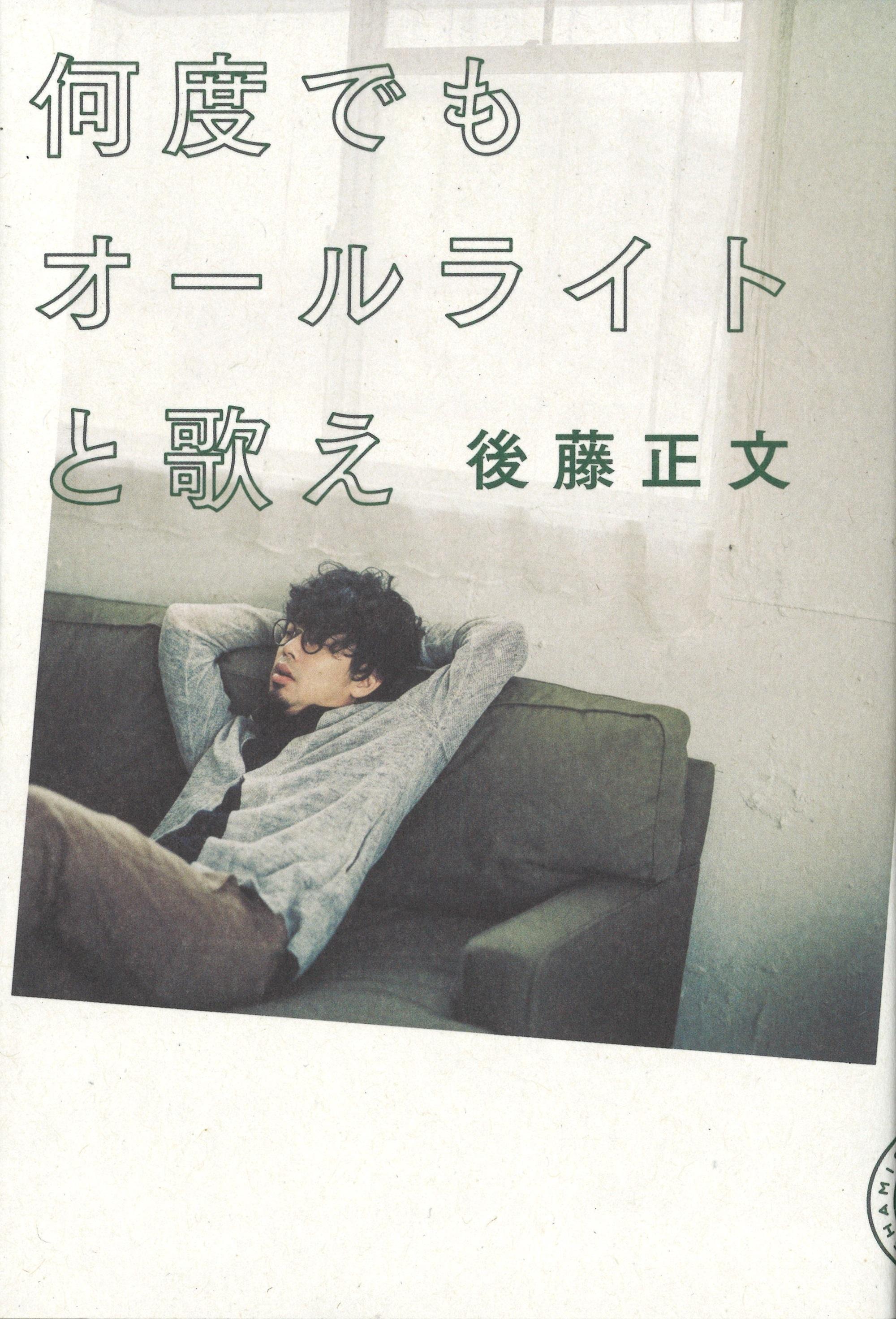
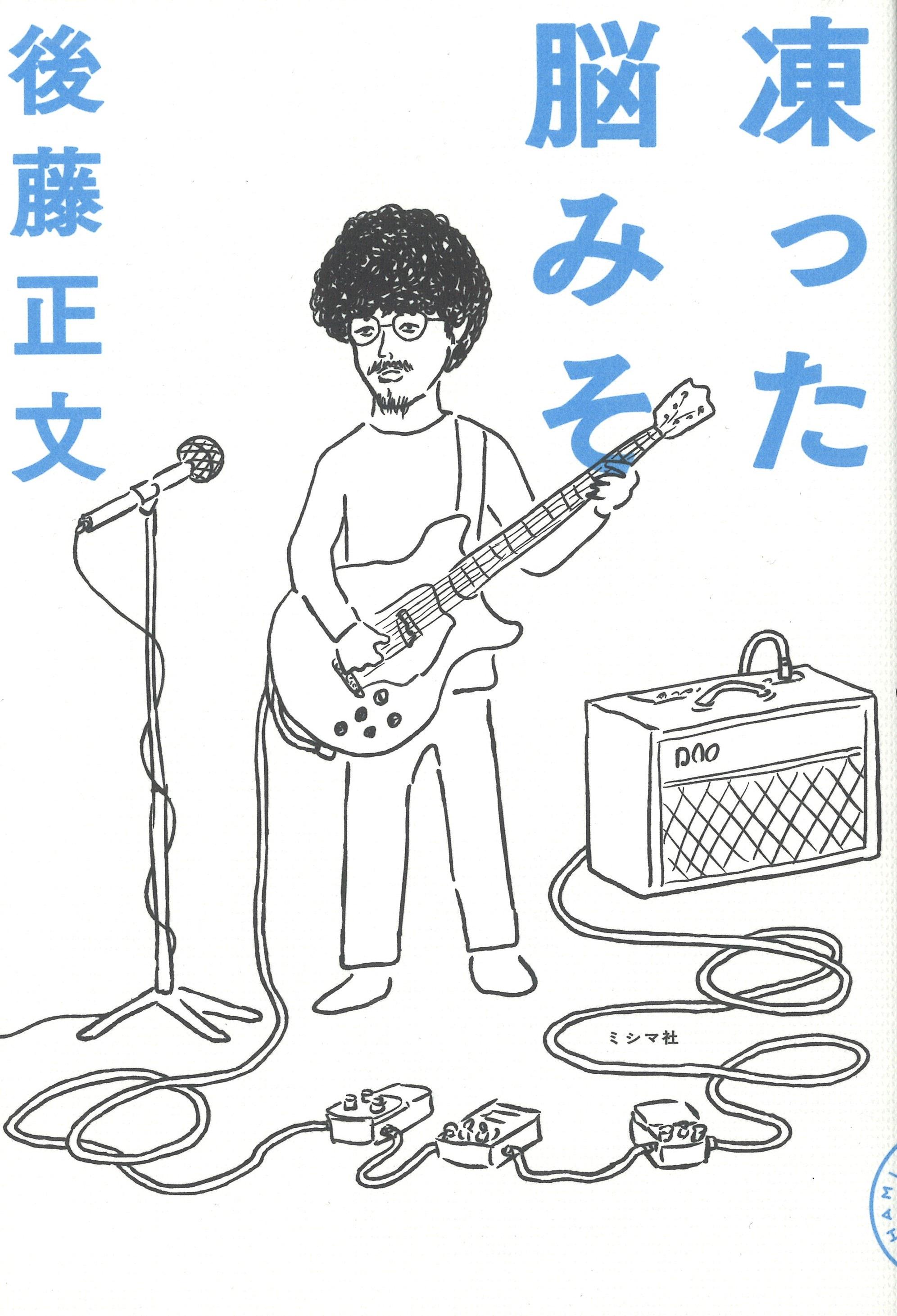


-thumb-800xauto-15803.jpg)


