第3回
洋ロック 邦ロック
2025.12.03更新
お年玉でエレキギターを買ったのは、高校に入って間もなくロックバンドを結成したときだ。ボディのトップがアニメ「魔法使いサリー」に出てくるサリーちゃんのパパの頭みたい、といって若い人にわかってもらえるかどうかわからないが、クワガタムシの角のようになったあずき色のギターだ。世界的に有名なアメリカのギターメーカー、ギブソンのSGという人気モデルをコピーしたものらしく、1万円もしなかったと記憶している。デザインの著作権なんていい加減な時代だったから、ギターにもコピー商品が結構出回っていた。要するにニセモノなのだが、音はよかった。
バンドのメンバーは5人。女子校なのでみんな女の子だ。キーボードが何人か入れ替わったが、ドラムとベース、リードギターとサイドギターは固定メンバーだった。キーボード以外はみんな初心者で、少しだけギター経験があった私がリードを担当することになったものの、アコギの弾き語りとはかなり勝手が違うし、テクニックを教えてくれる人もいないので、いつまでたってもうまくはならなかった。
そもそも歌謡曲やフォークの弾き語りで満足していた私がなぜロックバンドを始めたかというと、前回書いたようにビートルズの「オール・マイ・ラヴィング」をきっかけに洋楽に魅了されていったからだが、もう一つ大きな理由があった。学校問題だ。
中高一貫の私立女子校に通っていたのだが、わが家の財政状況には不相応でまったく校風になじめずにいた。学費をめぐって親がしょっちゅう喧嘩していたこともあって、もう高校は公立に行くしかないと脱出を試みたものの受験にあっさり失敗してしまい、出戻りの暗い気分で高校生活をスタートさせていた。入学した頃の写真を見ると、笑顔の同級生たちの中で私一人だけ世も末のような表情をしている。あの絶望は確実にロックをやる素地になったといっていいだろう。
学校にはバンドをやっている生徒はいたが、当時流行し始めたニューミュージックを演奏することが多く、ロックバンドはなかった。そもそも軽音楽部というものがない。コーラス部は全国大会に出場するほど実力があって学校をあげてバックアップしていたのに、同じ音楽でもずいぶん扱いが違うなと思ったものだ。風紀が厳しかったこともあるが、ロックをやる生徒は不良というイメージがあって、推奨されない感じだった。
ベースのMはパーマをかけて職員室に呼び出されたし、サイドギターのNは男子校の生徒と駅のホームで話している姿を卒業生に目撃されて学校に告げ口された。キーボードのKはピアノの練習に支障があるからという理由で、親に辞めさせられた。鍵盤の重さが違うからだそうだ。
私は私で、父親と家庭内紛争状態だった。当時ベイ・シティ・ローラーズというスコットランドのアイドル系バンドのギタリスト、パット・マッグリンのファンで壁にポスターやブロマイドを貼りまくっていたら、ある日、バリバリバリーッと全部破られてしまったのだ。
日本人とは結婚しない! エジンバラに行ってパットと結婚するんだーっ!
などと思い込んでいたほどだから、尋常ではない熱病にかかっていたことは間違いない。
家でおとなしくアコギを弾き語りするだけならよかったのに、突然、エレキを担いでスタジオに通い始めたものだから、このままでは不純異性交遊に走るんじゃないかと思われたのかもしれない。せいぜい文化祭に出ることが目標だったが、演奏するのがビートルズでもベイ・シティ・ローラーズでもなく、白塗りの顏で火を吹くハードロックのKISSとなれば、まあ、親は力尽くで止めにかかるわなあと今ならわかる。口だけは達者だったから、親や先生のいうことをことごとく素直に聞けない娘ではあった。
でもこれはもう半世紀近く前の昔ばなし。最近の高校生バンドってどうなってるんだろうと気になって、マンガ賞に次々ランクインして話題の『ふつうの軽音部』(原作/クワハリ、漫画/出内テツオ)を1巻から最新刊まで全部読んでみた。ロックをやりたくて、ギターを弾けないのにいきなりエレキを買って軽音部に入部した新入生の鳩野ちひろ。彼女が個性豊かな部員たちに囲まれて悩み苦しみ成長していく日々を描いた青春ドラマなのだが、読み始めてまもなく気づいたことがある。
男女がくっついたり離れたりして人間関係が気まずくなるというのは昔とあまり変わりはないが、みんな基本的に素直で不良じゃないし、家庭にそれぞれ事情はあれど、親とはまあまあ仲良しだ。私の高校時代とまったく違うなあと思ったのは、みんなもっぱら「邦ロック」、すなわち日本のロックを演奏していることだ。
銀杏BOYZの「エンジェルベイビー」やandymoriの「everything is my guitar」にしても、ELLEGARDENの「ジターバグ」やHump Backの「拝啓、少年よ」にしても、ちひろや彼女の仲間が演奏するのはみんな日本の曲だ。歌詞が日本語だから、ちひろたち自身の言葉になってストレートに刺さる。まずメロディが飛び込んでくる外国語の曲と違って、サバシスターの「覚悟を決めろ」じゃないけど、やっぱり音楽が好きーっ、という熱い想いが伝わってくる。すごくおおざっぱな言い方をしてしまうと、ブルーハーツの子どもたち、といった印象だ。
もちろん私も日本語のロックを演奏したことはある。フォーク・ロックと呼ばれるアリスのヒット曲「今はもうだれも」、サザンオールスターズの隠れた名曲「奥歯を食いしばれ」はブルース・ロックだ。でもそのくらいかな。他校の文化祭や高校生バンドが集まるライブ会場に行くと、男子はほとんど洋楽を演奏していた。レッド・ツェッペリンやディープ・パープル、ピンク・フロイドにローリング・ストーンズ。ファッションまで彼らのマネをして、長髪でほっそいパンツを履いている。繰り返し出てくるギターのリフや激しいドラムがかっこよくて、どのバンドが一番うまいか競い合っているようにも見えた。
ただ、今になって疑問に思うのだが、彼らはどこまで歌詞を理解して演奏していたんだろう。リフがあまりにも有名なディープ・パープルの「Smoke On The Water」の「湖上の煙」ってなんのことだと思っていたんだろう。歌詞をざっくり意訳すると、「モントルーにレコード作りに行ったら、フランク・ザッパがライブやってて、ラリったどっかのバカが銃をぶっぱなしやがってあたりは火の海、湖上に煙がたちこめて、空は真っ赤」って、なんやそれ?
ご存じ、クイーンの「Bohemian Rhapsody」は、いきなり、「おかあさん~、ボクやっちゃったよ~」ってマザコン全開だし、レッド・ツェッペリンの「天国への階段」って、だれかを追悼する歌だと思ってなかった? かくいう私だって、歌詞そっちのけでKISSの「Got To Choose」を演奏していた気がする。何度もこのタイトルをみんなで叫ぶんだけど、えーっと、何を選べっていってんだっけ?
だからこそのちに、赤い王冠に赤マントがトレードマークの「王様」というミュージシャンが、ディープ・パープルの曲を直訳の日本語で歌う「深紫伝説」でデビューしたとき、おいおい、そんなこと歌ってたんかーいってみんな腰を抜かしたのだ。ギターテクニックが完璧だからなおさら自虐的に聴こえるというか、「ひーふーみー、はい!」の掛け声で始まる直訳日本語の歌詞と超絶かっこいいメロディの落差が大きすぎて、テクニック偏重気味の元ロッカーおじさんたちに大受けしたんじゃないかな。
王様がイーグルスの名曲「ホテル・カリフォルニア」ならぬ「旅館カリフォルニア」を演奏したユーチューブ動画に、「アルバムの歌詞カードの和訳は理解不能でしたが、王様の訳はわかりやすい! この歌がベトナム戦争を非難した歌だということが理解できました」(内山朋紀さん)というコメントがあって、思わず膝を打った。やっぱりそうなんだ。
「直訳ロッカー 王様」というご本人のインスタをのぞいたら、今年CDデビュー30周年で全国をライブツアー中だった。こりゃ行かないわけにはいかないっしょ! さっそくチケットを予約した。
「ぼくらの時代は日本のロックってほとんどなかったんだよね」
都内のライブハウスで会った60歳のドラマー、Keiさんがいった。これから舞台に呼ばれてKISSを叩くらしい。
「だからずっと洋楽ばかりやってたんだけど、歌詞はそっちのけだったなあ。『ロックンロール・オールナイト』のナイトって、nightだと思ってたやつけっこういるよ。niteなのにね」
niteはnightのスラングで、ロックやポップスの歌詞にはよく出てくる。正しい英語なんかどうでもいい、感じろ! というロッカー精神が込められているようだが、そこんとこ、みんなあまりわかってなかったってことだ。
それにしても、なぜ私たちは意味もわからずに、あんなに「洋ロック」にのめりこんでいたんだろう。思春期のありあまるエネルギーの持っていき場だったことは間違いないが、やっぱり英語はかっこいい、洋楽は先をいってると思っていたんだろう。貧乏だけど、恋人と銭湯に行くささやかな幸せや切なさをうたう「四畳半フォーク」から一刻も早く抜け出したかったのかもしれない。
邦ロックの世界はヒット曲ぐらいしか知らないので私に語る資格はないが、今どきの高校生バンドは歌詞の意味を理解して演奏していることはわかる。みんなポジティブでほんわかして、大声で叫んでいてもやさしい。やっぱり、邦ロックの源流の一つはブルーハーツなんだろうなあ。「人にやさしく」がロックになるって気づかせてくれたんだから。あれ、なんだか、現代の邦ロックってフォークのメンタリティーに近いような気がしてきた。
さて、各地に散らばるわがSNSバンドの合同練習日がやってきた。楽器がないとか、近所迷惑になるといった理由で家では演奏できないドラムやバイオリンの奏者がスタジオにいて、それ以外はズームというオンラインミーティングのアプリでつながるようにした。みんな本名も職業も知らないままだが、オフ会で面識はあるからさほど緊張はしない。リハビリ中の私はまだギターを担げないので、ズームで参加した。
スタジオの様子は画面を通じてわかる。この日はドラムの@森ひろきさんが小学生の子どもたちを連れて参加している。中高時代は吹奏楽部、その後はプロのメタルバンドで本格的にドラムを叩いていた人だから、彼がいるだけで土台は安定する。子どもたちはお父さんがドラムを叩く姿を見るのが初めてだから、言葉にはしないけど、パパってすごいと思ったんじゃないかな。
スタジオのミキサーとオンラインのメンバーとの連携は、元電車の運転士、@どんこめさんが担当している。メカニックにすこぶるくわしく、自分で作曲や編集もしてしまうマルチプレイヤーだ。
画面ではよく見えないのだが、バイオリンの@まーにくんと、クラリネットの@りらちゃんの音も聴こえてくる。みんなの特技を知ってメンバーをつないでくれた@みぃさんはオカリナを吹く。このあと踊りのお稽古があるらしく着物姿だ。
さあ始めようとなって、いきなり問題が発生した。スタジオにいる人たちの演奏はオンラインのメンバーにちゃんと聴こえるのだが、オンラインのメンバー同士の演奏がほとんど聴こえず、聴こえてもかなり遅延するのだ。ズームはもともと会議のために設計されたアプリだから、音声を聞きやすくするためノイズが抑制されている。このため楽器の音はノイズとして認識されてしまうようなのだ。通信の遅延も会話なら気にならないレベルだが、合奏となるとまったく話にならない。
コロナの自粛期間中、世界中のアーティストが合奏する映像をユーチューブでよく見かけたが、あれは個別に収録した演奏を再編集したもので、リアルタイムの合奏ではない。ネットワーク越しのリアルタイム演奏というのは、音楽家たちにとってかなりの難題であることをこの日初めて知った。
うーん、困ったねえとつぶやいていると、中部地方に住むベーシストの@Naoさんから、ヤマハのシンクルームというソフトを使ってみたらどうかと提案があった。聞けば、楽器演奏に特化したシステムで、国内のミュージシャン同士なら遅延ゼロではないものの、光回線を使えば隣りの部屋でセッションしているぐらいの感覚まで近づけるようだ。
へえ、そりゃあすごい。さすがヤマハだ。そんな便利な近未来技術を開発していたのか。さっそくオンラインのメンバーは、@Naoさんが開設してくれたシンクルームに接続して演奏することになった。
会話と映像はズームで、演奏はシンクルームで確認する。技術の進歩がなければ成立しなかったと思うと、私たちのバンドってかなり現代的だなあと思えてきた。
それでもいざ演奏を始めると、どうもうまくいかない。自分の楽器の音ばかり聴こえてきてしまい、互いの音を聴き合うことがむずかしい。生で合わせるときのような高揚感もない。リズムや音が多少ずれても、一体感が生まれるスタジオ演奏とはほど遠い。もっと困ったことに、スタジオのメンバーにはシンクルームのメンバーの音が聴こえていないことが判明した。
どうする? どうする? 画面の向こうでみんな困り顔だ。やっぱり実際に集まって合わせたいよね、となるのは時間の問題だった。





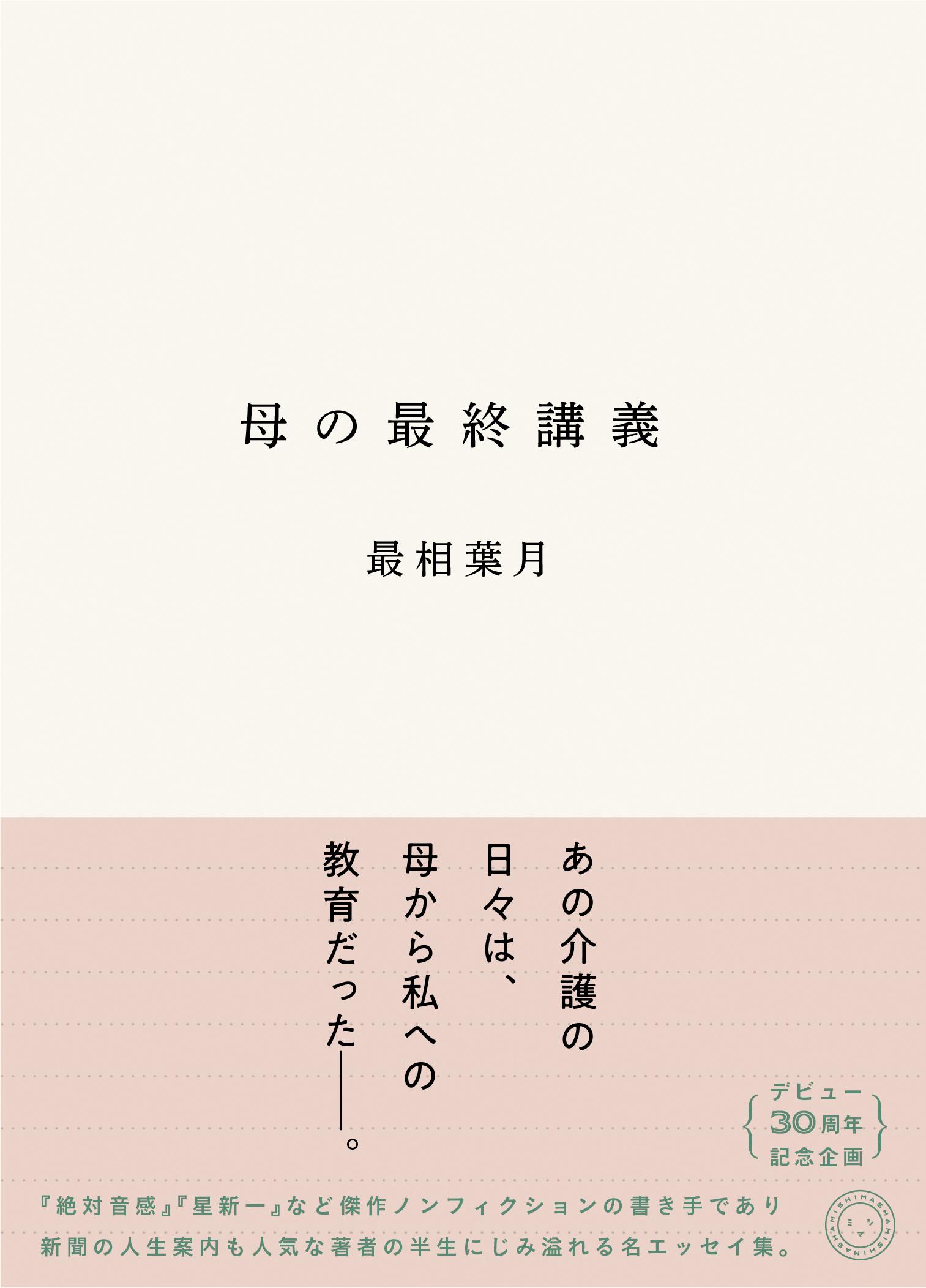



-thumb-800xauto-15803.jpg)


