第5回
恋愛:男女七歳にして席を同じくせずって国なんだけども。
2025.07.11更新
うちの息子はアニメでもなんでも恋愛ものが嫌いです。「なんでわざわざここに恋愛要素入れるわけ!?」と、画面に向かってよくキレてます。まあねえ、人類は大昔から恋愛至上主義だからねえ、現代だって変わらんわけよ。スマホをつらつら眺めていると、モテ・愛され・沼らせ・・・だのなんだのいろんなキャッチコピーが広告にも出てきて、物語でも物販でもなんでも、ここが商業として成り立つ重要な部門なんだよなあと思うことしきりです。まあ、生物の大目的が「遺伝子の複製を作って残す」ことなのだから、生殖のトリガーとなる恋愛が重要視されるのは生き物として当然なんだろうし、一大市場になるんだろうなあ。
健康関連だと雑誌特集で話題になる「恋愛でホルモンがでる」「SEXで綺麗になる」「筋トレでモテ」あたりが定番ではないでしょうか。今まで読んできた医学古典の中に、恋愛や筋トレでモテたり綺麗になったりする話は一切無かったと記憶しています。馬王堆帛書にある「導引図」にある動きは気功法の先祖と言われる健康体操ですが、あれも別に重いものを持ったりやスクワットして筋力を強化するようなものではないしね。
ですが・・・「SEXで若がえる」、「SEXで不老長寿」になるための道教の技法は実際に存在します。房中術と言います。
房中術についての書籍で日本で一番有名なのは、医心方『房内』でしょう。『医心方(いしんほう)』は平安時代中期、宮廷医であった丹波康頼によって編纂された日本最古の医学書で、全30巻から成ります。中国の隋・唐代の医書の重要箇所の引用により構成され、養生・内科・外科・婦人・小児・鍼灸など広範な内容を網羅しています。すでに失われてしまった医書の内容が多数、原書そのままの内容で含まれているので大変重要な古典とされているのです。
で、そんな大切な医学書に、「SEXで若がえる」、「SEXで不老長寿」の方法が含まれているわけなのです。本気で信じていたのでしょうね。内容は男性が女性の精気を性交渉によって吸い取る方法です。基本的に、房中術は身分の高い男性が対象とされるもので、ごく稀に女性でこの方法に精通したものがいるとされています。元々は道教の一派から発生している技術です。
医心方・房内
<原文>
至理第一
玉房秘訣
黃帝問素女曰∶吾氣衰而不和,心內不樂,身常恐危,將如之何?素女曰∶凡人之所以衰微者,皆傷於陰陽交接之道爾。夫女之勝男,猶水之滅火,知行之如釜鼎,能和五味以成羹,能知陰陽之道者成五樂,不知之者,身命將夭,何得歡樂,可不慎哉。素女云∶有采女者,妙得道術。王使采女問彭祖延年益壽之法。彭祖曰∶愛精養神,服食眾藥,可得長生。然不知交接之道,雖服藥無益也。男女相成,猶天地相生也。天地得交會之道,故無終竟之限。人失交接之道,故有夭折之漸。能避漸傷之事,而得陰陽之術,則不死之道也。采女再拜曰∶願聞要教。彭祖曰∶道甚易知,人不能信而行之耳。今君王御萬機,治天下,必不能備為眾道也。幸多後宮,宜知交接之法。法之要者,在於多御少女而莫數瀉精,使人身輕,百病消除也。
<現代語訳>
至理第一黄帝が素女に問うた
「私の気は衰え、和らいでおらず、心の中も楽しくなく、常に身が不安で恐ろしい。
これをどうしたらよいだろうか?」
素女は答えた
「すべての人が衰え弱くなる原因は、陰陽の交わりの道に反しているからです。
女性が男性に勝るのは、水が火を打ち消すようなもの。
釜や鼎のように調和して働けば、五つの味を合わせてうまい羹(あつもの)ができるように、陰陽の道をよく知る者は、五つの楽しみ(五楽)を完成させることができます。
しかし、それを知らない者は、命を短くし、どうして楽しみが得られましょう?
ですから、慎まなければならないのです。」
素女はさらに言った
「あるとき、采女の中で、道術をよく会得した者がいました。
王はその采女を使わせ、彭祖に長寿の法を尋ねさせました。」
彭祖は答えた
「精を大切にし、神を養い、多くの薬を服すれば長生きはできよう。
しかし、交接の道を知らなければ、薬を飲んでも効き目はない。
男女が相成ることは、天地が互いに生み出し合うのと同じこと。
天地が交わる道を得ているから、終わりというものがないのだ。
人がその道を失えば、早死にするようになる。
この"だんだんに傷つくこと"を避け、陰陽の術を得れば、それが"不死の道"となる。」
采女は再拝して言った
「ぜひ、その要点をお聞かせください。」
彭祖は言った
「道はきわめて分かりやすいのだが、人々はそれを信じて行おうとしないのだ。
今、君王は万機を司り、天下を治めておられる。そのためすべての"道"を尽くすことは難しいでしょう。
けれども後宮の女性が多いことは幸いであり、交接の法を知るべきです。
その法の要は、少女と多く交わっても、頻繁に精を漏らしてはならないということにあります。それにより、身体は軽くなり、百病が取り除かれます。」
・・・これが医心方・房内の第一に書かれていることなのです。『若い女の子とたくさんセックスして、射精をしないことが要』だと。うわあ、でしょう。こんな話が医学書に含まれているわけですが、古代中国では「七年男女不同席,不共食。」男女7歳にして席を同じくせず、ともに食せず・・・とされていたのです。この言葉は皆さんも知っているでしょう? 『礼記・内則』に書かれています。これは礼記のなかの古代中国の家庭内の礼儀や男女・親子・夫婦の関係を詳細に定めた章で、儒教の生活規範を具現化した文献です。出産・育児・養老・教育・婚姻・食事作法など、日常生活のあらゆる場面における礼を説き、身分や年齢、性別に応じたふるまいを体系的に記述しています。儒教で大切とされている、家族と社会秩序の維持を目的としたものです。
礼記・内則
<原文>
六年教之數與方名。七年男女不同席,不共食。八年出入門戶及即席飲食,必後長者,始教之讓。九年教之數日。十年出就外傅,居宿於外,學書計,衣不帛襦褲,禮帥初,朝夕學幼儀,請肄簡諒。十有三年學樂,誦《詩》,舞《勺》,成童舞《象》,學射御。二十而冠,始學禮,可以衣裘帛,舞《大夏》,惇行孝弟,博學不教,內而不出。三十而有室,始理男事,博學無方,孫友視志。四十始仕,方物出謀發慮,道合則服從,不可則去。五十命為大夫,服官政。七十致事。凡男拜尚左手。女子十年不出,姆教婉娩聽從,執麻枲,治絲繭,織纴組紃,學女事以共衣服,觀於祭祀,納酒漿、籩豆、菹醢,禮相助奠。十有五年而笄,二十而嫁;有故,二十三年而嫁。聘則為妻,奔則為妾。凡女拜尚右手。
<現代語訳>
六歳になったら、数や方角、名前を教え、七歳になると男女別々に席に座り、同じ食卓につかない。
八歳になると出入りや食事で年長者に道を譲るよう教え、九歳では日付の読み方を教える。
十歳で家庭教師のもとに通い、外で寝泊まりし、読み書きや算術を学び、服装は布製の簡素なものを着る。礼儀作法の初歩を朝夕学び、素直さや誠実さを身につける。
十三歳で音楽を学び、『詩経』を暗誦し、「勺の舞」を習い、成人前には「象の舞」を舞い、射や馬車の御し方を学ぶ。
二十歳で冠礼(成人儀式)を行い、礼法を本格的に学び、絹の衣服を身につけ、『大夏』の舞を習い、孝や悌(兄弟愛)を実践する。知識を深め、外には出ない。
三十歳で結婚し、家事や男としての務めを始め、四十歳で仕官する。物事に通じ、計画を立て、道理に合えば従い、合わなければ退く。
五十歳で大夫に任じられ、政務を担当し、七十歳で引退する。男子の拝礼は左手を上にする。
女子は十歳まで外出せず、乳母から穏やかで従順なふるまいを教わる。麻や繭を扱い、糸を紡ぎ、布を織り、女性の家事を学んで衣服を供する。
祭祀の様子を見学し、酒や食事、漬物や調味料を納めることを手伝い、儀礼の中で供物を供える所作を学ぶ。
十五歳で笄を差し、二十歳で嫁ぐ。事情がある場合は二十三歳までに嫁ぐ。
正式な婚姻(聘)であれば妻となり、逃避婚(奔)であれば妾となる。女子の拝礼は右手を上にする。
ここに出てくる、「聘」と「奔」が現代でいう「お見合い・結納などの手続きを経る結婚」と「恋愛結婚」に当たるものです。聘でなかったら正式な妻にはならないということですが、この時代、自由恋愛がなかったわけではありません。「詩經」には男女の恋愛についての歌が含まれています。『詩経』は中国最古の詩歌集で、周代(前11世紀~前6世紀)に成立したとされ、305篇の詩を収録しています。「風」「雅」「頌」の三部から成り、民間歌謡から王朝の祭祀歌まで多様な内容を含みます。恋愛・労働・政治・宗教など生活全般が題材で、儒教では経典として重視され、孔子は道徳教育に用いました。
『詩経』の「関雎(かんしょ)」(『国風・周南』第一篇)
<原文>
関関雎鳩、在河之洲。
窈窕淑女、君子好逑。
参差荇菜、左右流之。
窈窕淑女、寤寐求之。
求之不得、寤寐思服。
悠哉悠哉、輾転反側。
参差荇菜、左右采之。
窈窕淑女、琴瑟友之。
参差荇菜、左右芼之。
窈窕淑女、鐘鼓楽之。
<現代語訳>
ミサゴが「かんかん」と鳴き、川の中州にいる。
しとやかで美しい女性は、立派な男性の良き伴侶だ。
高ささまざまに生えて水面に揺れる荇菜(水草)を、右に左に求めるように、
しとやかで美しい淑女を、昼も夜も求めてやまない。
求めても得られぬと、寝ても覚めても思い焦がれる。
長い長い夜、寝返りを打ち続けて眠れない。
揺れる荇菜を、右に左に選ぶように、
しとやかな淑女と、琴と瑟の様に調和して仲良くすごしたい。
揺れる荇菜を、右に左に摘み取るように、しとやかな淑女を、鐘や太鼓の音楽の様に楽しみながら暮らしたい。
特定の女性に恋焦がれている様子が歌われていますね。ただし、この場合は男性視点しか描かれていません。なので、彼女がこちらをどう思っているかは全くわかりません。また、琴瑟は夫婦が仲睦まじい姿の象徴、鐘太鼓は正式な婚姻時の音楽の暗示であるとされています。ですので、この場合、恋焦がれている男性が正式な婚姻を申し込む前の歌ということになるのでしょうね。恋愛が描かれているものの、現代だったらいきなり婚姻を申し込みにくるヤバイ人・・・になってしまうかもしれません。
じゃあ、普通の恋愛ってその時代にはないのか。あります。『詩経』の「静女(せいじょ)」(『国風・邶風』)が現代の恋愛とほぼ同じです。
静女其姝、俟我於城隅。
愛而不見、搔首踟躕。
静女其孌、貽我彤管。
彤管有煒、説懌女美。
自牧帰荑、洵美且異。
匪女之爲美、美人之貽。
<現代語訳>
しとやかなあの娘はなんと美しいことか。城の片隅で私を待っていてくれる。
しかしかくれて姿が見えず、私は頭をかきながら立ち尽くす。
しとやかな娘はなんと可愛らしいことか。私に赤い笛を贈ってくれた。
その赤い笛はきらめくばかりに美しい、娘の美しさもすばらしい。
野原で美しい荑を摘んでくれた。それは本当に美しく、しかも珍しいものだった。
その草自体が美しいのではなく、美しい人が贈ってくれたからこそ、価値があるのだ。
こちらは女性が赤い笛を男性に贈っていますので、相思相愛であることがわかります。自由恋愛ですよね。でもこの歌は「奔放な歌である」とされて儒教的には大変よろしくなかった様です。結婚前にかなり仲睦まじくなってますからね。こっちの場合は結婚するならおそらく「奔」になるのかなと思われますねえ。いわゆる駆け落ちですよ、駆け落ち。現代日本では駆け落ちなんて、言葉自体がもう死語ではなかろうかと。
ちなみに、現代医学的に「恋愛でホルモンがでる」「SEXで綺麗になる」というエビデンスは、ほぼないに等しいです。「筋トレでモテ」に関しては、男性ホルモンが増加するというエビデンスは存在しているので、少しは関係するかなと思いますが......私の身の回りの女性は、あまりに筋肉隆々としている男性の腹筋を見て「ひっくり返したカブトムシみたいでちょっと・・・」とおっしゃる人が多いかな・・・うん・・・。




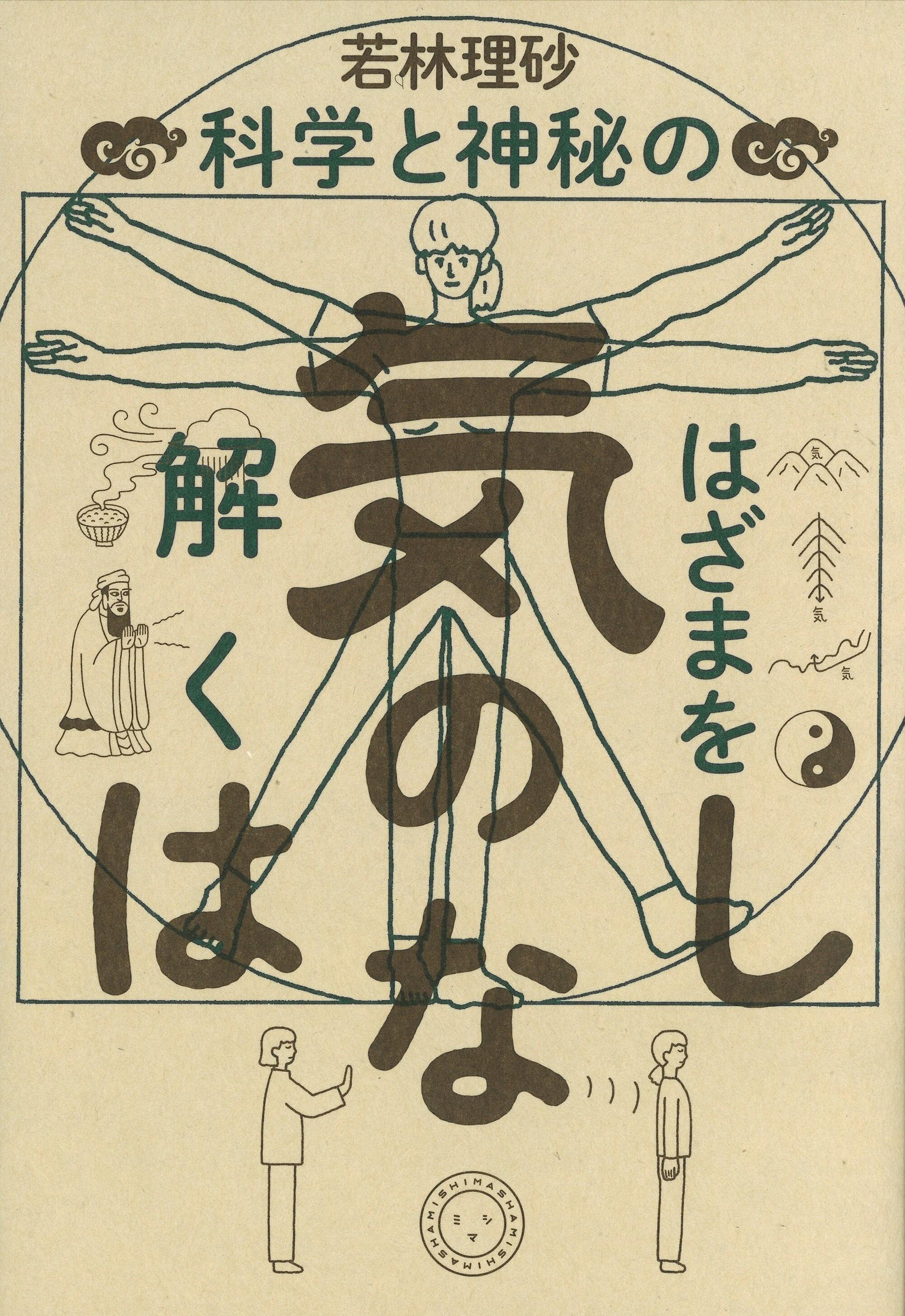
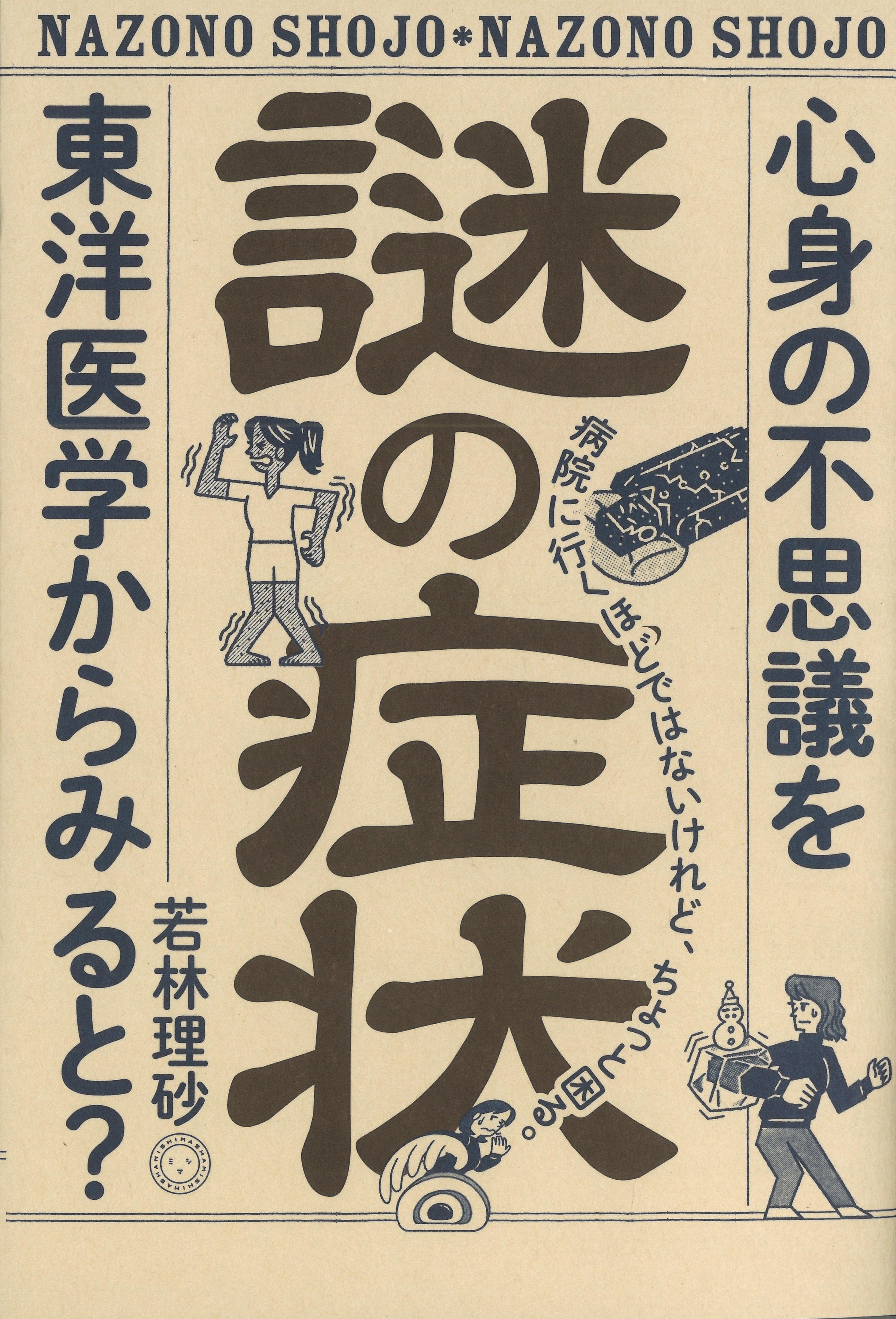


-thumb-800xauto-15803.jpg)


