第3回
清潔であることと健康
2025.05.08更新
掃除をすると健康になれる、幸せになれる、さらに運気が向上するという考え方が浸透しているのですが、じゃあこれは一体どこからきているのだろう?と。とりあえず、現状私が読んできた医学古典に、掃除の記載はなかったんですよ。病人の居室を綺麗にしろとか、医者は衣服を正して手を洗えとか、どこにもなかったのです。
まあそれもそのはず。医師が清潔にしなければならないとされるようになったのはだいぶ後世のことです。ゼンメルワイスって名前をご存知ですか? ハンガリー生まれの19世紀の産科医で、医師が手指洗浄をしなかったことが産褥熱を伝播させ、産婦をを危険に晒していたことを解明した医師です。ですが、彼の発見は学会によって徹底的に否定され、彼自身はメンタルを病んで失意のうちに亡くなるのです。
中国医学の歴史の中では、世界で初めて開腹手術をしたとされている華佗ですが、これも特に消毒らしいことは書かれていません。まずは、後漢書から。
『後漢書(ごかんじょ)』は、中国後漢時代(25〜220年)の歴史を記した二十四史の一つで、南朝宋の范曄(はんよう)が中心となって編纂したものです。全120巻からなり、帝紀・列伝・志の構成をとる。前漢の『漢書』を継ぎ、後漢の政治、人物、制度、文化などを記録していいます。
後漢書 巻八十二 方技列伝 華佗
【原文】
方藥に精しく、劑を處するに數種を過ぎず、心に分銖を識り、稱量を假(か)らず。針灸も數處を過ぎず。若し疾ち發して內に結すれば、針藥も及ぶ能(あた)はず。乃ち、先づ酒を以て麻沸散を服せしめ、醉ひて覺ゆる所無きに因りて、腹背を刳破し、積聚を抽割す。若し腸胃に在れば、則ち斷截し湔洗し、疾穢を除き去る。既にして縫ひ合せ、神膏を傅(つ)く。四五日にして創癒え、一月の間に皆平復す。
【現代語訳】
薬に詳しく、方剤を処方するにしても生薬の数は数種類だけで、正確な配合量を体に叩き込んであり、秤を使わずに仕上げることができました。鍼灸も経穴数個だけにとどめました。病気が体の内部で激しく進行し、鍼や薬で届かないような場合には、まず酒で「麻沸散(まふつさん)」という麻酔薬を飲ませ、意識がなくなったところで腹や背中を切り開き、体内にたまった腫瘍や膿を取り除きました。腫れが腸や胃にあるときは、それらを切断して洗い、病の原因を取り除いたあとで縫合し、神膏という薬を塗ることで、4〜5日で傷が癒え、1か月もすれば元通りに回復しました。
手術を行う際に麻酔薬である麻沸散を使用していますが、体表の消毒は行なっていませんし、手を洗浄したり、衣服を変えたりなどは書かれていません。この時代、抗生物質もなかったので、この処置だとおそらく手術部位に感染を起こし、死に至るんじゃないかなと思います......体表近くの膿瘍を切った時ではなく、内臓を切断した場合は特に危ないだろうなあ、と。ちなみに、鍼灸の場合、「気を補う」として昭和の頃には口に鍼を含んで温め、そのまま刺すことも行われていて、その際にもちろん鍼の消毒はありません。この技法は古典内に書かれているので、大昔はもっと行われていたと思われます。古代の医療における衛生というのはこんなものだったのです。
病気の予防のために部屋を綺麗にしろと主張したことで有名なのはナイチンゲールです。その著書「看護覚え書」のなかで、換気や居室の清潔さがいかに重要かを指摘しています。
『看護覚え書(Notes on Nursing)』は、フローレンス・ナイチンゲールが1859年に著した看護の基本書です。病人を癒す環境づくりの重要性を説き、換気・清潔・食事・静寂・観察など、家庭でも実践できる看護の原則を示しました。
【原文】
There are other ways of having filth inside a house besides having dirt in heaps. Old papered walls of years' standing, dirty carpets, uncleansed furniture, are just as ready sources of impurity to the air as if there were a dung-heap in the basement. People are so unaccustomed from education and habits to consider how to make a home healthy, that they either never think of it at all, and take every disease as a matter of course, to be "resigned to" when it comes "as from the hand of Providence;" or if they ever entertain the idea of preserving the health of their households as a duty, they are very apt to commit all kinds of "negligences and ignorances" in performing it.
【日本語訳】
家の中を不潔にする方法は、汚物の山以外にもある。 何年も経った古い壁紙、汚れた絨毯、掃除されていない家具などは、地下にゴミの山があるのと同じように、空気を不浄にする原因である。 人々は教育や習慣から、家庭を健康にする方法を考えることに慣れていないため、そのようなことをまったく考えず、あらゆる病気を当然のこととして受け止め、「摂理の御手から」やってきたら「諦める」ようにするか、あるいは、家庭の健康を守ることを義務として考えたとしても、それを実行する際にあらゆる種類の「怠慢と無知」を犯しがちである。
『看護覚え書」からわかることは、家を綺麗にしなければならないということのレベルが全然違っていたということなのですよ。この段落の前後を読むと、ロンドンでは流し台は石造りでいつも濡れていて異臭を放ち、家の近くに肥溜めと厩舎があり、下水は家の地下に澱んでいたのです。
じゃあ、「掃除をすると健康になれる、幸せになれる、運気が向上する」とされる話のおおもとは一体どこなのか。これはどうやら、中国の文化から来ているようです。紀元前八世紀ごろの記述に基づいて書かれている尚秉和 著『歴史社会風俗事物考』には、
(十九)古の箒
古くは、喪禮に臨む際、又は惡魔祓ひに桃茢なるものを用ひたが、茢は箒であり桃の木を棒にした箒が桃茢である。或は黍穰、薍穗をもつて作つたともいふ。薍は荻ともいひ、秋に實がのれば萑といつて、その穂で作る。黍穰は黍の穗、秋に實の落ちて後、縛つて箒にするが、今日でも北支の人家では多くこれを使つてゐる。昔は、子弟が掃除する際の禮法では、必ず箒を塵取の上にのせ、塵取の口を胸にあてゝ、中に箒を入れてゐるから、恐らく二尺以上ではなかつたであらう。まさに今と同じである。桃の棒の箒は、今日庭掃除や高所を拂ふ時に使ふ、木の柄をつけた長箒を想はせる。
とあります。悪魔祓いに桃の木を使用した箒が使われており、さらに掃除には礼法まであったようです。
『唐律疏議(とうりつそぎ)』は、唐代の律令制を代表する法典で、653年に完成し増田。律(刑法)と、それに対する公式の注釈「疏」と「議」から構成され、刑罰・行政・家族制度などを体系的に規定しています。明確な法理と罰則、儒教的倫理観の融合が特徴で、後代の宋・元・明・清の法制にも大きな影響を与ました。
その、唐の時代の法律書『唐律疏議 卷第二十六」には、
【原文】
侵巷街阡陌
其穿垣出穢污者,杖六十;出水者,勿論。主司不禁,與同罪。
疏 議曰:其有穿穴垣牆,以出穢污之物於街巷,杖六十。直出水者,無罪。「主司不禁,與同罪」,謂「侵巷街」以下,主司並合禁約,不禁者,與犯罪人同坐。【現代語訳】
街路や小道を侵害する場合
もし壁に穴を開けて汚物を街路に流す者がいれば、杖刑六十回を科す。ただし、水を流すだけの場合は罪に問わない。監督官がこれを禁じなかった場合、その罪は犯罪者と同等とする。
疏 議曰く、壁に穴を開けて汚物を街路に排出する行為は杖刑六十回に処される。一方で、水のみを排出する場合には罪に問われない。「監督官が禁じなかった場合、その罪は犯罪者と同等とする」とは、「街路や小道の侵害」に関して、監督官もまた規制すべき責任があるため、それを怠った場合には犯罪者と同様の処罰を受けることを意味する。
とあり、そこらへんに汚いものを流すと厳しい罰を受けることが見受けられます。公共の場の清潔さを保つことが法律によって定められていたのですね。昔のパリやロンドンのように朝っぱら窓から汚物を投げ捨てるなどもってのほかだったわけです。
『史記(しき)』は、前漢の司馬遷が著した中国最初の本格的な通史で、天地創造から前漢の武帝時代までを記録しています。全130巻で、本紀・列伝・表・書・世家の五体構成を採用し、帝王から庶民まで多様な人物を描いています。特に人物列伝の筆致が高く評価され、中国歴史記述の模範とされています。
その『史記』「魏公子列傳」には、下記のように書かれています。
【原文】
魏王怒公子之盜其兵符,矯殺晉鄙,公子亦自知也。已卻秦存趙,使將將其軍歸魏,而公子獨與客留趙。趙孝成王德公子之矯奪晉鄙兵而存趙,乃與平原君計,以五城封公子。公子聞之,意驕矜而有自功之色。客有說公子曰:「物有不可忘,或有不可不忘。夫人有德於公子,公子不可忘也;公子有德於人,願公子忘之也。且矯魏王令,奪晉鄙兵以救趙,於趙則有功矣,於魏則未為忠臣也。公子乃自驕而功之,竊為公子不取也。」於是公子立自責,似若無所容者。趙王埽除自迎,執主人之禮,引公子就西階。公子側行辭讓,從東階上。自言罪過,以負於魏,無功於趙。趙王侍酒至暮,口不忍獻五城,以公子退讓也。公子竟留趙。趙王以鄗為公子湯沐邑,魏亦復以信陵奉公子。公子留趙。
上記の中の、この一文ですね。
趙王埽除自迎,執主人之禮,引公子就西階。
【現代語訳】
趙王は宮殿を掃き清めて自ら出迎え、主人の礼を尽くし、公子を西の階段へと案内した。
と、王自ら掃除をして、公子を招き入れる描写があります。王様が宮殿の掃除をすること自体が想像がつかないですよね。どうやら、元々中国には掃除を尊ぶ文化があった様子なのです。もちろん道教にも斎戒潔斎があり、道灌を掃き清めてお香をたいて清浄にすることが大切にされていました。
そして仏教です。ブッダには、周梨槃特という弟子がいて、すべての弟子の中で一番愚かだったとされるのですが、全くお経を覚えることができずにいた彼にブッダが一枚の布を与え、「塵を除く、垢を除く」とだけ唱えて、他の弟子の履物を磨きまくる修行をさせます。これによって悟りを得たという伝承があるんですな。この辺りの伝承が中国に伝わり、元々あった中国の掃除文化と混じり合いさらに強化され、現在の禅宗の偏執的とも言えるくらいの掃除修行につながるわけです。
あとは・・・風水ですね。明代に成立したとされる『陽宅三要(ようたくさんよう)』は、中国風水における家相術の重要な古典で、「門(玄関)・主(主人の居所)・灶(かまど=台所)」の三つを最も重視すべき要素としています。明代以降、実用的な家相指南として広く読まれ、現在の住宅風水にも強い影響を与えており、家造りの基準とされる書です。
『陽宅三要』には、このような記述がありました。
【原文】
一、门:是指宅的大门,若是大型的宅院、工厂、公务机关、有围墙围起来的,则是指围墙出入的总门。门乃进出之路,气口也,以小太极论之。房门、厨房门、厕所门等,所有的门皆有动气,故影响人生之祸福。因为风水重点论述吉与凶重于动、吉者动则吉上加吉、凶者动则凶祸更烈!
【現代語訳】
一、門(もん)
これは住宅の大門(玄関)を指す。もし大型の邸宅、工場、公的機関などで塀に囲まれている場合は、その塀に設けられた出入口の「総門(正門)」を指す。
門は出入りする通路であり、「気の入口(気口)」でもある。これを小太極(陰陽の小単位の気の流れ)として論ずる。部屋の扉、台所の扉、トイレの扉など、すべての扉は「動気(気を動かす)」を持ち、それゆえに人の禍福に影響を与える。
風水では吉凶を重視し、特に「動」に重点が置かれる。
吉のものが動けば、吉にさらに吉が加わり、凶のものが動けば、より一層の災いを招くのである。
この「気口」がキーワードになりますね。気の出入り口。気とは、動くことと流れることが正常で、滞り澱むと穢れて異常なものになると考えられているものです。この辺りは拙著『気のはなし』をお読みいただければ幸い。このため、気口や気の流れる通路になる「風や人が通る道」をなにかで塞いだりすることは厳禁と考えられるのです。だから余計なものを通り道に置いたり、物理的な汚れであるゴミや埃を放置したりしてはならないのです。
おそらく風水の古典で掃除がはっきり書かれていない理由は、掃除して、気が流れる清らかさを保つことが日常的にも当たり前のことだったため、記述するに至らなかったのではないでしょうか。「気なんだから、わかるよね?」という話です。とはいえ、現在のような衛生観念が発達した時代ではありません。一般的な掃除はどんなだったのかを垣間見ると、
尚秉和 著『歴史社会風俗事物考』には、弟子が先生に対して掃除をする際のやり方が書かれていました。管子 弟子編からです。『管子(かんし)』は、中国戦国時代に成立したとされる書物で、政治・経済・軍事・哲学など多岐にわたる内容を収めています。春秋時代の斉の宰相・管仲の名を借りており、全76篇から構成されています。古代中国の経世済民思想を知るうえで貴重な資料となっています。漢代以降の政治思想にも大きな影響を与えました。
【原文】
凡拚之道實水于盤攘臂袂及肘堂上則播灑室中握手執箕膺揲厥中有帚入戸而立其儀不忒執帚下箕倚于戸側凡拚之紀必由奧始俯仰磬折拚毋有徹拚前而退聚於戸内坐板排之以葉適己實帚于箕先生若作乃興而辭坐執而立遂出弃之既拚反立是協是稽
【現代語訳】
凡そ掃き清めるという道は、まず水を手に取り、袖をまくり、肘まで腕を露わにして、部屋の中に撒き散らすことから始まる。
それから手に箒を持ち、ちり取りを胸の前に抱え、その中に帚を入れて戸口に立つ。
その所作は正しく乱れず、箒を持ってちり取りを下に置き、戸のわきに立てかける。
すべての掃除の規範は、まず奥から始めるべきである。
掃くときは身をかがめ、礼をするように深く折れ、拝するように静かに掃き、決して乱暴に掃いてはならない。
掃いたものは前に寄せ、後ろに下がりながら、戸の内側にまとめていく。
腰を下ろして板に座り、それを葉として整え、自分の前へと適切に寄せ、ちり取りにしっかりと掃き入れる。
先に座していた者がもし何か作業をしていたならば、起き上がり、その場を辞して立ち上がり、箒を持って外に出て、それを捨てる。
掃除が終わった後は再びその場に立ち戻り、調和を保ち、礼儀をもって全体を整えるべし。
ここに、箒の使い方が礼法として書かれています。ちりとりを胸に抱えてその中に箒を入れるということは、箒自体が結構小さかったのでしょうね。水を撒き散らしたらどうやって拭いていたのかが書かれていないのが気になります。この記述では拭いていないですよね。埃を抑えるために細かく撒き散らした......ということなのかもしれないですね。
ということで、掃除で健康になる......というはなしも、あんまり東洋医学とは関係がないだろうと思われます! でも、掃除はしたほうがいいよ、現代人。健康に寄与することは、西洋医学的にはっきりしてるからね! ホコリが舞い上がればアレルギーの原因になるし、黒カビが生えていると喘息になるし、モノが多すぎればダニも出るし、ダニは病気を媒介するし、なんなら床に物を置いていて足を引っ掛けて骨折もしますし。私も昨日、久しぶりに大掃除したよ!!




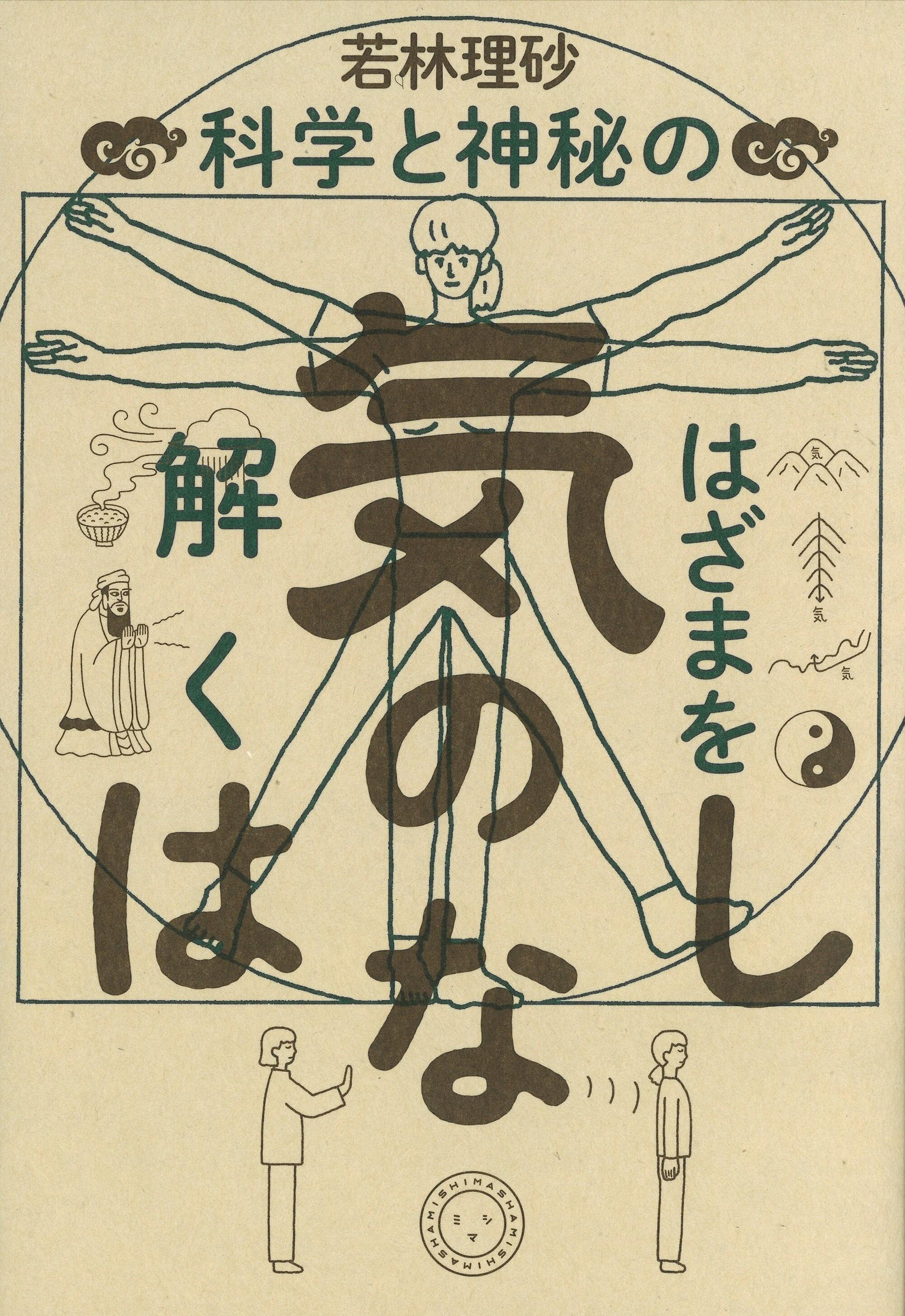
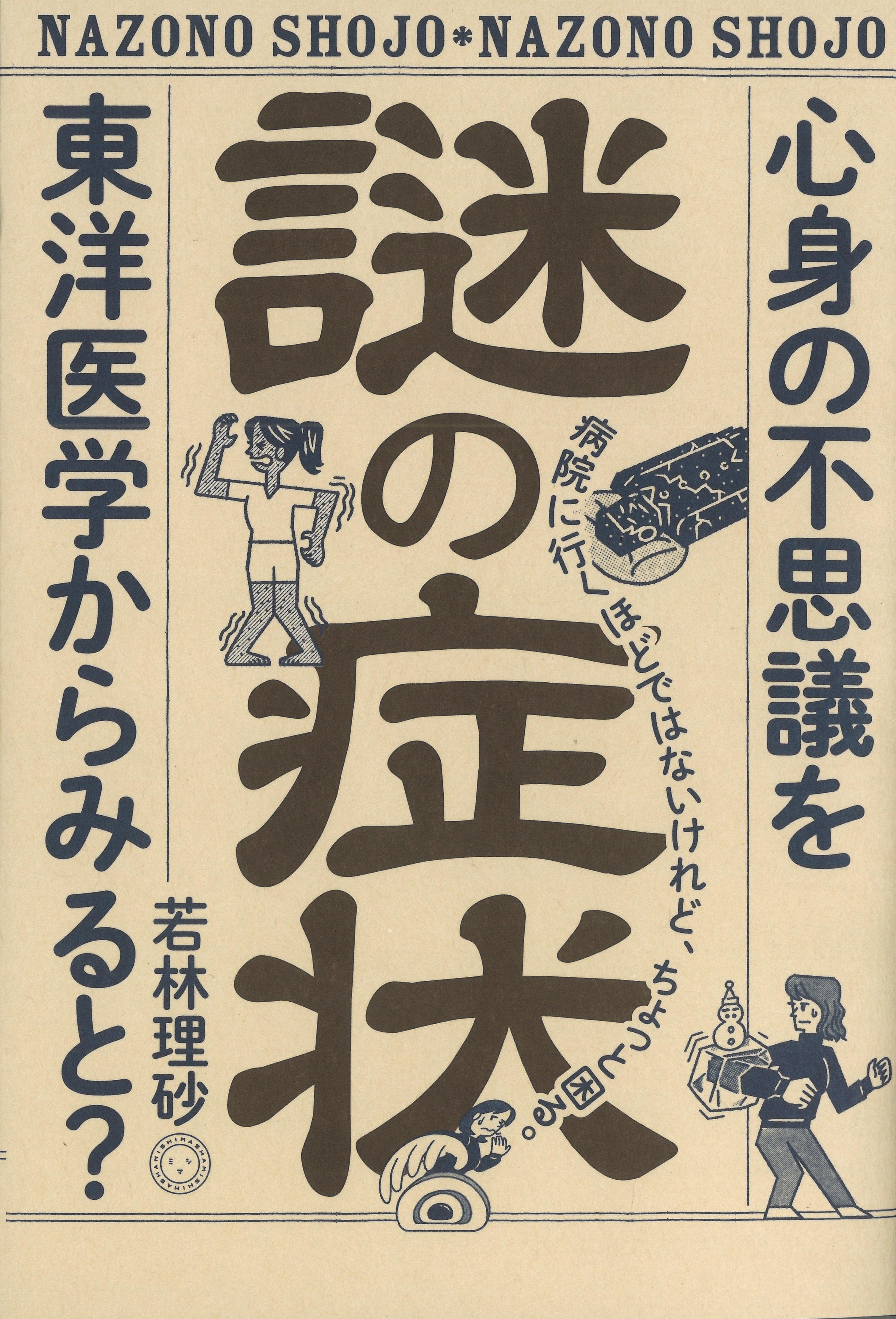


-thumb-800xauto-15803.jpg)


