第9回
斉民要術に見られる調理と食事
2025.11.04更新
みなさん、お家でどんなフライパンとお鍋使ってますか。うちは、取手が取れるティファールシリーズを時々買い換えながら使っています。テフロン加工ってものすごく便利なんですが、使っているうちに段々剥がれてきちゃって、こびりつくようになってきちゃうんですよね。
テフロン加工でつるっつるのほうがスルッと焼けて楽しいから、オムレツやパンケーキを焼くために新しいティファールのフライパンを卸して、しばらく使ってから炒め物などのフライパンに卸していく方式にしています。で、炒め物がこびりつくようになったフライパンが廃棄処分になっていきます。深いお鍋の方はこびりつく料理自体をそこまでやらないので、滅多に買い替えないですね。
子供の頃、テフロン加工がなかった時代のフライパンでした。鉄のフライパンですね。「ちゃんと育てるとこびりつかないよ」と言われるのですが、祖母と母がめっちゃ育てたフライパンでも普通にこびりついていました。綺麗に焼くには油をかなり入れないとダメなんですよ。たった40年ほど前の話ですが、テフロン加工が一般的な現在からは考えられないですね。
そんな、鉄の鍋釜すらなかった頃。中国の青銅器で貴重なものとして「鼎(かなえ)」が挙げられますが、これはものすごい貴重品でした。そのため、基本「土器の調理道具」が使用されていました。テフロン加工のフライパンみたいな感じに、手軽に土器の上でスルッと焼き物や揚げ物はできないでしょう?
それだけでなく、現代と比べるとかまどの火力も低かったのです。現代のガスコンロやIHコンロのように微細な火力の調整ができるわけでもありません。薪をくべるかまどには、パッと温度を上げ下げできる機能はありません。木の実や菜種を圧搾して採る食用油も貴重品ですし、気軽に揚げ物なんてできません。ですので、「羹・臛(あつもの)」と呼ばれる煮込み料理と濃厚なスープがご馳走の中心をなしていました。
中国最古の料理レシピが書かれている『斉民要術』は530〜550年に書かれたものとされています。中国北魏時代の賈思勰(かしきょう)によって著された、現存最古の総合的農業技術書です。農耕・園芸・畜産・養蚕・食品加工・醸造・保存法など、農民の生活全般を体系的に記録しています。後世の中国・日本の農業や民生技術に多大な影響を与えた重要な古典です(参考:「『斉民要術』の料理構造」南 廣子)。
煮込み料理の一例をみてみましょう。鴨の臛を作る方法です。
巻八 羹臛法第七十六
<原文>
作鴨臛法:用小鴨六頭、羊肉二斤、大鴨五頭。蔥三升、芋二十株、橘皮三葉、木蘭五寸、生薑十兩。豉汁五合、米一升、口調其味。得臛一斗。先以八升酒煮鴨也。
<現代語訳>
鴨の臛を作る法。
小鴨六羽、羊肉二斤、大鴨五羽を用いる。
葱三升、芋二十株、橘の皮三葉、木蘭(モクレン)五寸、生姜十両、豉汁五合、米一升を加える。味は口により調える。臛一斗を得る。まず八升の酒をもって鴨を煮るのである。
羊と鴨を煮込んでますね。他のレシピではすっぽんや豚足、羊の足、うさぎ、魚などを煮込んでいます。目を引くのは橘の皮・木蘭でしょう。橘皮は熟したみかんの皮を乾燥させたものです。木蘭は厚朴のことでしょうか。どちらも生薬として使われています。生姜は言わずもがな、様々な漢方に配合されています。土鍋でこれを煮込むと・・・美味しいんじゃないでしょうか。
おそらく、このような煮込み文化が東洋医学の湯液(漢方薬)の文化を発達させたのだろうなと思います。金属器ではなく、土鍋で長時間煮込んで作る薬液。もしこれが鉄や青銅製の鍋であったなら、金属が溶け出してしまって薬効が違うものになっていたでしょうし、使う生薬によっては体に悪影響を及ぼすものになっていたかもしれません。今でもエキス剤ではなく乾燥した生薬を煮出して飲む場合は、土瓶やガラス製の器具など、生薬の成分を損なわないものを使うことが推奨されています。
酸っぱい・苦い・甘い・辛い・しょっぱいの五味をバランスよく揃えて食べる・・・と、現代の薬膳では教えられたりしますが、『斉民要術』の時代の調味料を先ほどの南廣子氏の報告に見てみると、甘みは「蜜」「飴」を使用していて、調理に使う頻度は低い様子。それ以外の調味料の使用頻度を見ると、酸味と塩味が主なもので、そこに「豉」(味噌と乾燥納豆の中間のような発酵食品。味としては・・・適切な表現と言えるかどうかですが、ダシ入り八丁味噌みたいな感じです)が入ってくるような感じですね。なので、甘み少なめのしょっぱい・酸っぱい、肉・魚のダシ味中心の食事だったと考えるのが妥当でしょう。サトウキビの栽培のしかたは『斉民要術』にあるけど、砂糖は一般的じゃなかったしね。「甘」は伝統的に甘みとして直接的には食事に沢山は入ってないのですよ。なので、穀物類を噛み砕いた時の甘みがこれに当たると考えられています。
『傷寒論』が成立したのは後漢末期の200年ごろなので、『斉民要術』よりもだいぶ先んじています。ご存知の通り、傷寒論の漢方には甘草・大棗という甘みを加える生薬が多用されているので、甘さを足す資材は蜜や飴の他にも知られていたわけです。それでも料理には、塩味・酸味+豉が好まれていたということなのでしょうね。そう考えると、「五味を揃えてバランスよく」というのは特別な考え方だったのかもしれないです。まあ、五味って、どれかを極端に摂り過ぎるのを戒める方が本体で、毎食毎食バランスよく摂取するのを推奨する考え方でもないしね。みんな意外とここを取り違えるんだけどもさ・・・今日の食卓は酸味が足らないわ、足さないと! 苦味も! とかってやりがちでしょう。そうじゃなくて、本質は極端な偏食を戒めるものです。甘いものばっかりとか、しょっぱいものばっかりとか、そういう食べ方ね。
ちなみに、甘草・大棗は脾胃の気を益すことと諸薬をまとめる働きを期待して配合されているのですが、いわゆる甘味料として飲みにくい生薬の味を和らげるので入ってるのではないの? と疑っています。現代でもそうやって薬の味を整えていたりするでしょう?・・・という話をしたら、「いや先生それは・・・」と苦笑いをされたことがあります。その時代、高価で貴重な生薬を矯味剤として使うことはないでしょう!? って話です。確かにそうなんだけども。湯液、貴族階級のためのものだったのですから、私は今でも微妙に疑っています。甘い方が飲みやすいじゃん、ねえ?
麹を作成する技術が『斉民要術』には含まれており、これを使用した漬物が掲載されています。日本でも東北に伝わっている麹を使用した漬物は甘さが際立つものです。また、麹を使うと甘酒を作ることが可能で、斉民要術にはこれを使用した漬物も掲載されています。日本でも昔は各家庭で水飴や甘酒を作って利用していたことが知られています。麹にお粥を足して保温すると簡単に甘酒になるのです。水飴は本来、麦もやし(発芽した麦芽)を使用するのですが、台所で作るなら大根を利用する方法が知られています。
逆に、甘酒を使用した漢方薬というのは、私は聞いたことがありません。水飴は大建中湯などに配合があります。麹そのものは「神麹」として半夏白朮天麻湯や加味平胃散に配合されています。これは甘みをつけるというより、消化を助ける意味合いで配合されているとのこと。甘酒の方が手に入れやすい甘味料だけれど、これを利用している漢方がないということは、甘草や大棗の方が薬効があると考えたのか。そうすると矯味剤ではないのかなあ。益気補脾の働きと矯味剤を兼ねてるとかじゃないのかなあ。『傷寒論』が記されたときはパンデミックの最中だったから、乾燥していて簡単に持ち運べる甘草や大棗が使いやすかったのか。甘酒、現代では機械を使用して一気に乾燥させて粉末にしたものもありますが、自然乾燥させるとなると簡単にカビそうですもんね。
そうだ、現代では廃れてしまった技術の「薬酒」が斉民要術で紹介されています。
浸藥酒法
<原文>
以此酒浸五加木皮,及一切藥,皆有益神效。用春酒麴及笨麴,不用神麴。糖、瀋埋藏之,勿使六畜食。治麴法:須斫去四緣、四角、上下兩面,皆三分去一,孔中亦剜去。然後細剉,燥曝,末之。大率麴末一斗,用水一斗半。多作依此加之。釀用黍,必須細????(臼+手という字),淘欲極淨,水清乃止。用米亦無定方,準量麴勢強弱。然其米要須均分為七分,一日一酘,莫令空闕,闕即折麴勢力。七酘畢,便止。熟即押出之。春秋冬夏皆得作。茹甕厚薄之宜,一與春酒同,但黍飯攤使極冷,冬即須物覆甕。其斫去之麴,猶有力,不廢餘用耳。
<現代語訳>
この酒を使って五加木(ゴカヒ。ウコギ。)の樹皮を浸す。また、あらゆる薬をこの酒に漬けると、いずれも霊験あらたかで、効き目がよくなる。
酒を造る際には「春酒用の麹」または「笨麹」を用い、「神麹」は使わない。
糖と「瀋(しん、もろみ)」でこれを封じ込めて貯蔵し、牛馬などの六畜が食べないように注意する。
麴を整える法。まず、麹の四つの縁・四隅、上下の二つの面を斧などで削り取る。それぞれ三分の一を削る。さらに内部の穴(麹菌が繁殖して空いた部分)もくり抜く。その後、細かく刻み、乾かして天日にさらし、粉にする。
おおよそ、麹粉一斗に対して水一斗半を加える。たくさん仕込む場合は、この割合に従って水を増やす。
酒を造る際に黍(きび)を用いるなら、必ず細かく砕き、何度も洗い清めて、水が完全に澄むまで洗うこと。米を使う場合には決まった分量はない。麹の力の強さ・弱さを見て、加減すればよい。
ただし、米は必ず七等分しておくこと。一日に一度ずつ「酘(たく)」を行い、途切れさせてはならない。間が空くと、麹の発酵力が弱まってしまう。七回の仕込みを終えたら、もうそれでやめる。発酵が熟したら、酒を絞り出す。
春・秋・冬・夏、どの季節でもこの方法で仕込むことができる。ただし、使用する甕(かめ)の厚さや質は、春酒の造り方に準じる。また、黍飯(きびの蒸し飯)は広げて十分に冷ますことが大切。冬には甕の上に覆いをかけて保温すること。なお、削り取った麹の部分にもまだ発酵の力が残っているので、捨てずに他の用途に再利用してよい。
「糖と瀋(しん、もろみ)でこれを封じ込めて貯蔵」とあるので、漬け込んだ上から発酵中のもろみに糖を混ぜたものを注いで液面に浮かせ、表面にカビなど生えないようにしながら一緒に発酵させる方法です。このもろみは、麹とお粥で作るタイプのものではなく、酒粕に糖分を足したタイプの甘酒に似ています。発酵途中なら微発砲の薬酒ができそうな感じですね。我々の知っている蒸留酒に漬け込むタイプの薬酒とはだいぶ違います。
どんなものでもその時代の技術的な発展に依存しているので、そこを抜きに考えることはできないんですよねえ。油をきっちり使わないと新品だろうがなんだろうが必ずこびりつくフライパンなんて、今じゃ考えられないでしょう? その時代の金属加工や熱源などをある程度理解した上で医療技術を考える視点が必要だよなあと、ブワッと上がる炎と中華鍋を振るう映像なんかを見て思うのでした。大昔のチャーハンって、今と比べるとべちゃっとしてたんだろうなあ・・・。




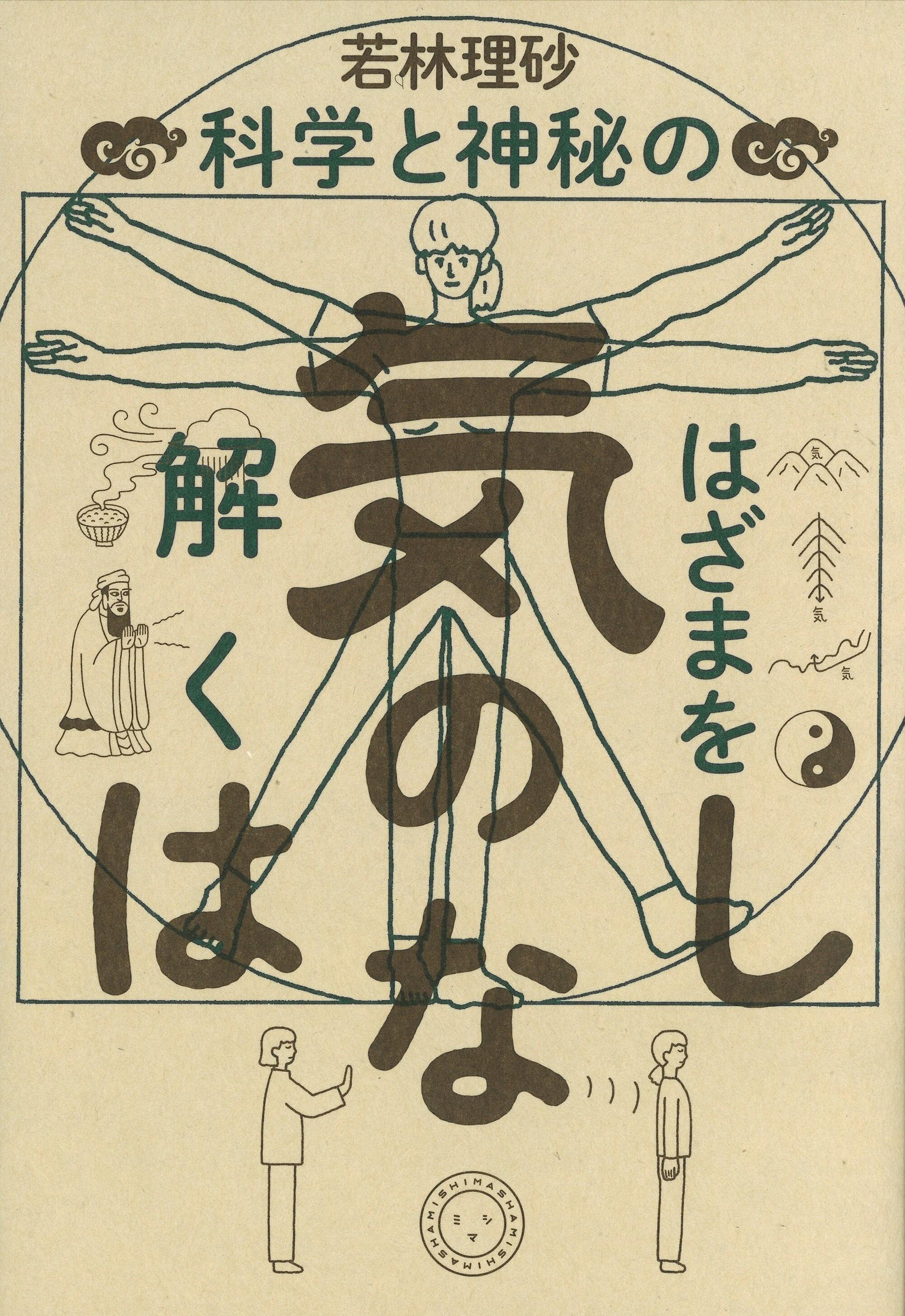
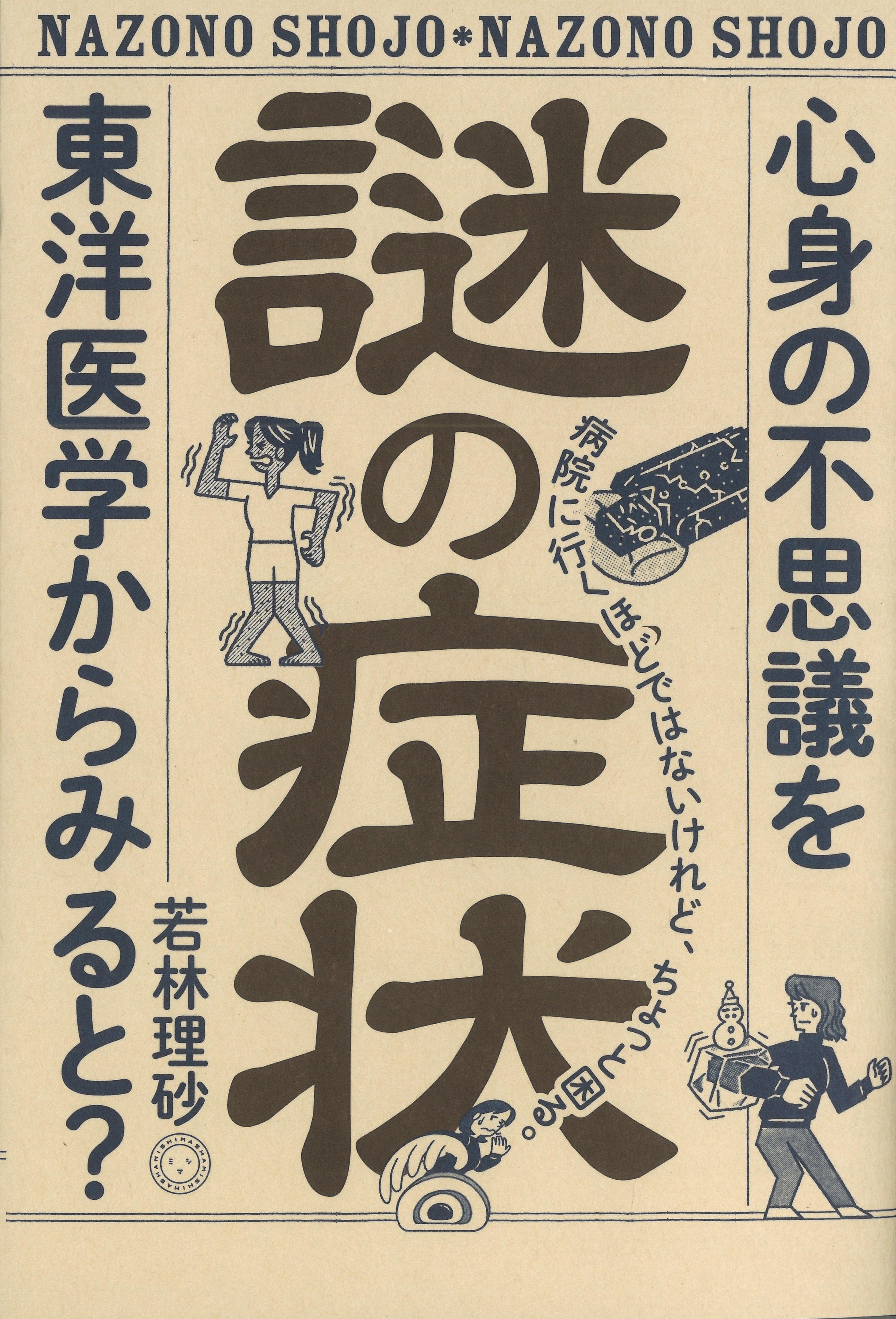


-thumb-800xauto-15803.jpg)


