第8回
酒を果汁のように。酒の度数の変遷。
2025.10.01更新
酒池肉林。肉の林と酒の池を作って・・・などと聞いて、「うわ〜すごいな、そんなにお酒飲むのか。相当強かったんだな」と思ったことがある人は少なくないのではないでしょうか。ちなみに私は結構強い方で、若い頃は一緒に飲みに行った男性を潰して帰ってくることもしばしばありました。今でも飲めば相当飲めるのですが、ほとんど飲まない人になりました。
坂本龍一さんの治療担当をしていた際、毎週末往診をするので自分が体調を崩さないようにするためにあまり飲まなくなっていたのですが、彼の大きい手術が全部終わるまでの間、うまくいきますように・・・と、願掛けとして酒断ちしていたんですよ。それがきっかけでほぼ日常では飲まない人になりました。今では、お祝いや旅行先などイベントで飲むくらいですね。普通の外食程度ではノンアルコールです。これは、教授からのプレゼントだと思っています。
我々が飲んでる酒類・・・アルコールを作るには、酵母が必要なわけです。パンにはイースト、日本酒にはコウジカビ、ワインにはワイン酵母。さて。どんなものでも発展の歴史というものがあるわけで。最初は果物などが自然に発酵してたまたま酒になったものを飲んで酔っ払ってたんだろうと推測されています。そのうち酒を作り出すようになるのですが、最古の農業・牧畜・衣食住技術書の『斉民要術』には世界で初めての製麴について書かれています。そこにはまじないの文句が書かれているのです。
<原文>造神麴并酒第六十四
祝麴文
東方青帝土公・青帝威神、南方赤帝土公・赤帝威神、西方白帝土公・白帝威神、北方黑帝土公・黑帝威神、中央黃帝土公・黃帝威神、某年某月某日辰、朝日、敬みて五方五土の神に啓す:
主人某甲、謹みて七月上辰を以て、麥麴數千百餅を造作す。阡陌縱橫にして疆界を辨へ、須らく五王を建立し、各々封境に布く。酒・脯の薦を以て相祈請す。願はくは神力を垂れ、勤めて所領を鑒し、蟲類をして蹤を絕ち、穴蟲をして影を潛ましめよ。衣色は錦布のごとく、或は蔚たり或は炳たり。熱を殺す火燌は、以て烈しく以て猛く、芳は薰椒を越え、味は鼎を和するを超ゆ。飲むに利ある君子は、既に醉ひ既に逞し、惠む彼の小人も、亦恭しく亦靜かなり。敬み告ぐること再三、格言斯に整ふ。神之を聽きたまへ、福應自ら冥す。人の願ひ違ふこと無く、畢く永きを從はんことを希ふ。急急如律令。
祝ふこと三遍、各再拜す。
<現代語>
東の方の青帝の土の神とその威神、
南の方の赤帝の土の神とその威神、
西の方の白帝の土の神とその威神、
北の方の黒帝の土の神とその威神、
中央の黄帝の土の神とその威神に、
某年某月某日の辰の刻、朝日を拝しつつ、
五方五土の神々に敬って申し上げます。
主人である某甲は、七月の良辰を選び、
麦麴を数千数百枚の餅に造り上げました。
区画を縦横に分けて境界を定め、
五人の「王」を立て、それぞれの境を守らせます。
酒と脯(干し肉)を供え、これを祈り願います。
どうか神々の御力を垂れて、勤めてお守りください。
虫の類はいっさい跡を絶ち、
穴居の虫も影を潜めるように。
その姿は錦の衣のように華やかに、
あるいは青く、あるいは輝き映えるように。
熱を鎮める火は烈しく猛く燃え、
香りは薫る椒(はじかみ)を越え、
味は鼎の調和を超えるように。
これを飲む君子には、十分に酔い楽しませ、
これを受ける小人にも、また恭しく静かにさせます。
敬って再三申し上げます。
この言葉は整えられております。
神々よ、どうかお聞きくだされ。
福の応えはおのずから幽玄に至ります。
人の願いに違うことなく、末永く従わせてください。
律令のごとく、ただちに成就あれ。
この祝詞は三度唱え、
そのたびに二度ずつ拝礼します。
この時代の製麴方法は空気中の酵母が自然につくのを待つものです。斉民要術に見える製麴方法は、蒸しあげた麦をそのまま使うのではなく、粉にしてこねて餅状にしたものを並べて酵母がつくのを待ちます。
<原文>凡作三斛麥麴法:蒸、炒、生,各一斛。炒麥:黃,莫令焦。生麥:擇治甚令精好。種各別磨。磨欲細。磨乾,合和之。 七月取甲寅日,使童子著青衣,日未出時,面向殺地,汲水二十斛。勿令人潑水,水長亦可瀉卻,莫令人用。其和麴之時,面向殺地和之,令使絕強。團麴之人,皆是童子小兒,亦面向殺地,有汙穢者不使。不得令人室近。團麴,當日使訖,不得隔宿。屋用草屋,勿使瓦屋。地須淨掃,不得穢惡;勿令濕。畫地為阡陌,周成四巷。作「麴人」,各置巷中,假置「麴王」,王者五人。麴餅隨阡陌比肩相布。訖,使主人家一人為主,莫令奴客為主。與「王」酒脯之法:濕「麴王」手中為椀,椀中盛酒、脯、湯餅。主人三遍讀文,各再拜。 其房欲得板戶,密泥塗之,勿令風入。至七日開,當處翻之,遷令泥戶。至二七日,聚麴,還令塗戶,莫使風入。至三七日,出之,盛著甕中,塗頭。至四七日,穿孔,繩貫,日中曝,慾得使乾,然後內之。其麴餅,手團二寸半,厚九分。
<現代語>
凡そ三斛(さんこく)の麦麹を作る法:
蒸した麦、炒った麦、生の麦をそれぞれ一斛ずつ用いる。
炒麦は黄色になる程度で、決して焦がしてはならない。
生麦はよく選び、極めて精良なものを用いる。
それぞれの種類を別々に挽き、粉にする。粉は細かく挽くこと。
粉が乾いたら混ぜ合わせる。
七月の甲寅(こういん)の日を選び、童子に青衣を着せて、日の出前に「殺地(さつち、禁忌の方角)」に向かわせ、水二十斛を汲ませる。
この水は誰もこぼしてはならない。長く汲み上げたものは捨ててもよいが、人に使わせてはならない。
麹を和えるときもまた殺地に面して和え、極めて強くしっかりと練る。
麹を団ねる人は皆童子や小児であり、また殺地に面して行う。
汚れのある者は使ってはならない。人が室近くにいてはならない。
麹を団ねる作業は、その日のうちに必ず終わらせ、宿に持ち越してはならない。
麹を造る屋は草屋を用い、瓦屋ではならない。
地面は必ず清掃し、不浄であってはならず、湿ってもならない。
地に区画を画いて畦道を作り、四方に通路を成す。
「麹人(きくじん)」を作って各巷に置き、「麹王」を仮に設け、王は五人とする。
麹餅は畦道に沿って肩を並べるように並べる。
お正月のお餅を常温の空気中に放置したことがある人はわかると思いますが・・・書かれている通りにやったら麦の餅にカビが大量につくのが想像できるでしょう。うまくいってもその時々で全然違うコウジカビが生えたでしょうし、場合によってはただのカビが大発生して失敗したこともたくさんあったのではないでしょうか。ですので、呪術を施して良い麹がつくように祈ったのです。
現代で飲まれている主な醸造酒のアルコール度数は、
* ビール::約5〜7度
* ワイン::約12〜15度
* 日本酒::約15〜16度
ですが、この製麴法で醸造されたお酒はドブロク的なもので、アルコール度数が低めの5〜8%程度、うまく発酵させても10〜12% 程度になるかと思われます。ビールと同じかそれよりは強く、ワインより低い程度。それなら大量に飲めるかあ......と、思ったんですよね。これなら、酒池肉林、できるかもしれないなあ、と。それと多分、池の周りも酒臭くないですよね、きっと。販売されているドブロクを飲んだことがありますが、ふわっと爽やかな酸味のある香りがするのですよ。醗酵が続いていて微炭酸のものは、ピチピチと跳ねる泡が上がって、白くとろっとして酸味と甘みがあり、微炭酸の乳酸飲料の風情があります。これが池に満たされていたら・・・いいですねえ。美味しそうです。
黄帝内経・素問に酒の飲み過ぎを戒める一文があります。
<原文>
上古天眞論篇第一.
上古之人.其知道者.法於陰陽.和於術數.食飮有節.起居有常.不妄作勞.故能形與神倶.而盡終其天年.度百歳乃去.
今時之人不然也.以酒爲漿.以妄爲常.醉以入房.以欲竭其精.以耗散其眞.不知持滿.不時御神.務快其心.逆於生樂.起居無節.故半百而衰也.<現代語>
上古の人、その道を知る者は、陰陽に法り、術数に和し、飲食に節あり、起居に常あり、妄りに労を作さず。故に能く形と神と倶にし、もってその天年を尽くし、百歳を度りて乃ち去る。
今時の人は然らず。酒をもって漿(果汁。ジュース。)とし、妄をもって常となし、酔いて房に入り、欲をもってその精を竭くし、もってその真を耗散す。満ちるを持するを知らず、時に神を御せず、その心を快くするを務め、生の楽しみに逆い、起居に節なし。故に半百にして衰う。
この「以酒爲漿」というのが、飲み過ぎを戒める言葉です。ノンアル飲料を飲むようにゴクゴク飲むということですね。わざわざ書いてあるということは・・・そのように飲む人が多かったということでしょう。アルコールは強烈に湿気と熱を体に作り出すので、慢性的に多く飲み続けると健康を害することになります。
『黄帝内経・素問』は戦国〜前漢期(紀元前4世紀〜前1世紀ごろ)に成立したと考えられています。一方、『斉民要術』は北魏末〜北斉期の農業技術書で、6世紀半ば(約550年ごろ) に賈思勰によって編纂されています。ですので、素問が成立した時代のお酒は、斉民要術に書かれたものと同等程度のアルコール濃度か、それより低かった可能性が高いわけですよ。それでも「以酒爲漿」と書いて戒めていたのです。
さて。じゃあ、現代人の私たちがアルコールとどう付き合ったらいいかは・・・もうお分かりですよね。ビールくらいのアルコール度数でも、たまに飲む程度で十分だってことです。だって、ジュースだって毎日飲んだらダメでしょう? そんなふうに考えてアルコールと付き合っていきましょ。




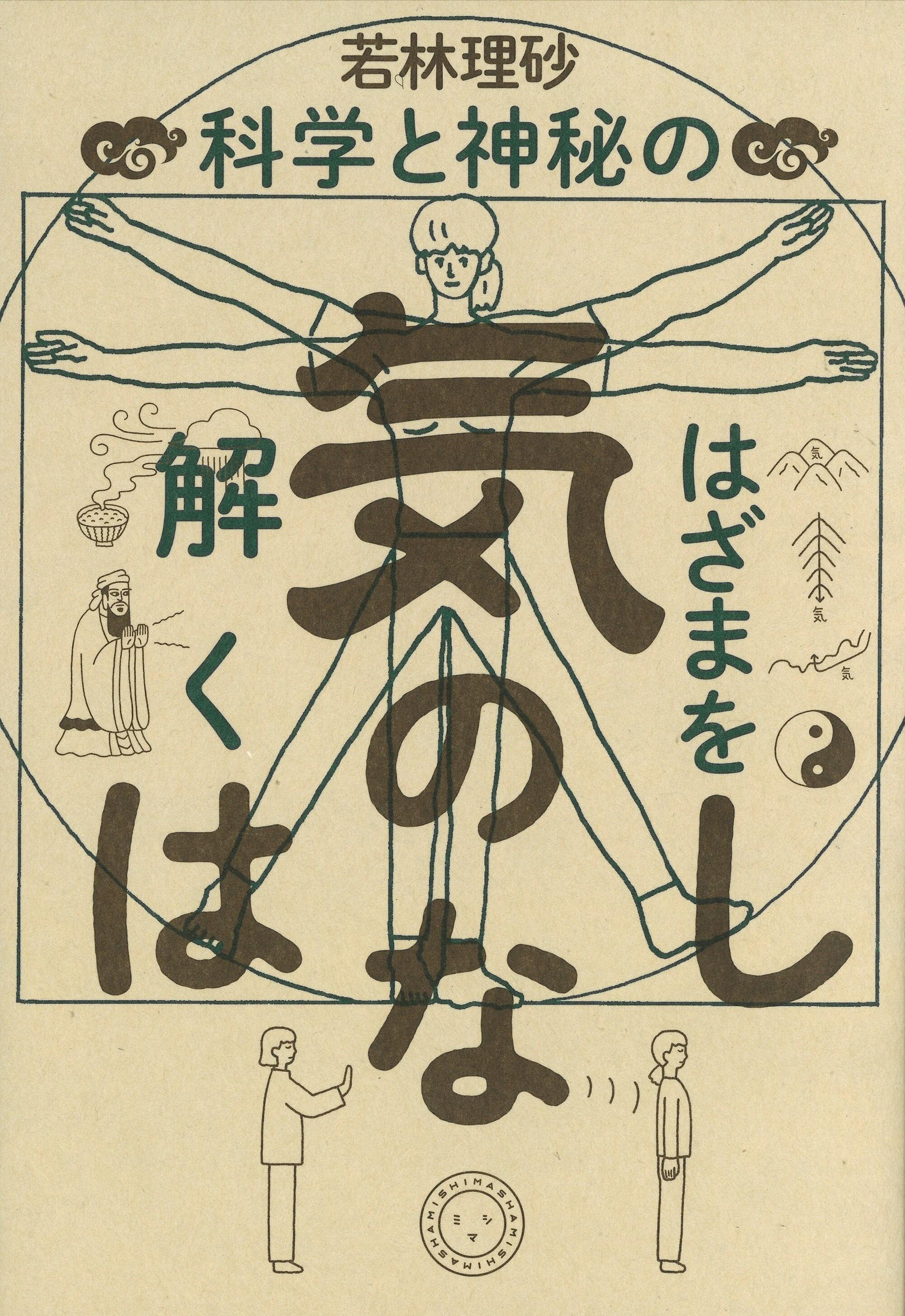
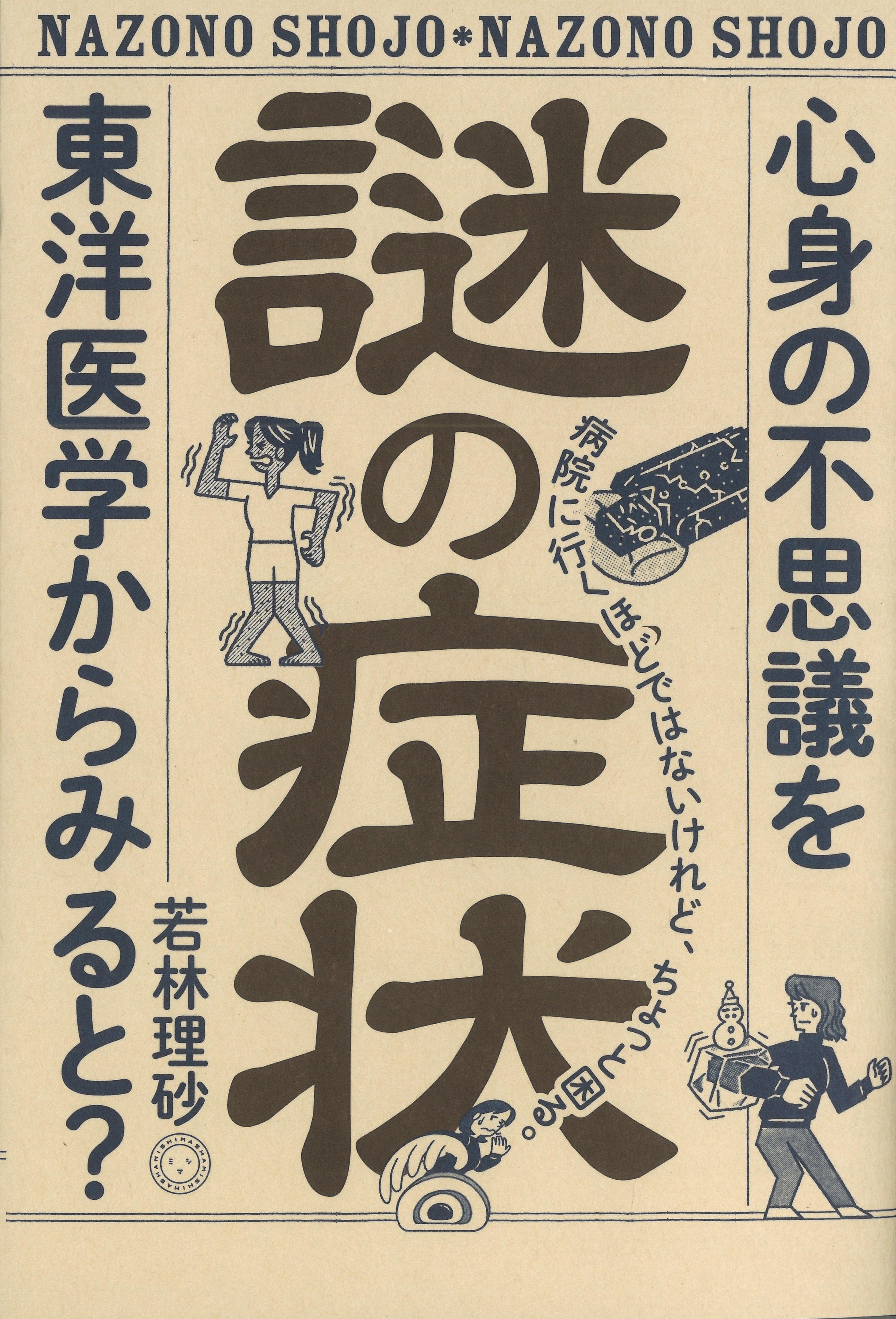


-thumb-800xauto-15803.jpg)


