第6回
西太后の美容法
2025.08.08更新
とうとう白髪染めをやめることにしました。といっても、白髪そのままの色にする訳ではなく、普通のカラーにするために一回ブリーチで黒染めを落とし、グレージュで染めたのですよ。最近はこういうのを「白髪ぼかし」っていっていたりするそうで、メッシュを入れたりする場合もあります。最近の木村拓哉さんがそんな感じです。彼のinstagramを見ると、最近の髪色がわかりますよ。
年齢とともにどのような美しさを目指すか。美魔女とかアンチエイジングよりもウェルエイジングとか色々言われるようになりました。美容整形のハードルも下がりましたしね。前回、房中術で永遠の若さを・・・という話をしました。『素女経』で黄帝に房中術の話をしていたのは素女という房中術に長けた女性という設定でしたが、その方法は女性が若さや長寿を得るものではなく、男性向けの技法でしたよね。女性向け房中術というのははっきりとした形で残されたものはありません。
孫思邈の「千金翼方」は、中国の古典医学書で、唐代に書かれた医学書ですが、この中の「婦人面藥第五」に見られる処方には、
・髪を黒く豊かにする
・吹き出物を治す
・シミそばかすを消す
・シワを消す
・肌を白く美しくする
などで、現在の女性と変わらない欲求を持っていたことが伺えます。
中国の美容法で有名な人物として、楊貴妃と西太后を挙げておきましょうね。楊貴妃は傾国の美女として有名ですが、楊貴妃が行っていた美容法の記録は、残念ながら唐代の文献に残っていません。ですので、現在楊貴妃が行っていたと紹介される美容法は後代の推測に基づくものです。
西太后は、映画「ラストエンペラー」の冒頭に出てきたおばあちゃんのイメージが強いと思われますが、 晩年の写真を見てもシワがかなり少なく、その時代の70歳代とは思えないほどです。こちらは写真が残るほど近代の人物なので、『御香縹緲錄』に実際に彼女が行っていた美容法がしっかり残されています。

The_Ci-Xi_Imperial_Dowager_Empress
パブリック・ドメイン, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1480659
『御香縹緲錄』(ぎょこうひょうびょうろく)は、清末民初の宮廷生活を描いた回想録で、作者・德齡(デリン)が西太后に仕えた経験を基に、西太后の人物像や清朝宮廷の風俗、女性の暮らしを詳細に記録した貴重な文化資料です。少し長くなりますが、原文と、日本語訳を付します。
其中這一就是每隔十天服食珠子所研成的粉末一次,究竟伊老人家每服一次珠粉需要幾許珠子,我倒不曾給伊仔細算過,只知道研珠粉用的珠子都是揀的小珠,但一般也是晶圓瑩潤,價值極巨的真珠。每次研成的粉末,約有一小茶匙模樣。那茶匙是銀製的,式樣和普通的不同,大概總是專為太后服食珠粉而定制的。這服食珠粉的一件事,施行已有幾十年之久。從不曾間斷過,差不多已成為一種固定的章制了;每隔十天,幾乎是在同一個時辰上,那專門負責研磨珠粉的太監便用一幅黃絹托著那柄銀匙,將研就的珠粉獻到太后面前來。太后也無須再問什麼話,一瞧這人踅進來,便知是該服珠粉的時候到了。那太監便顫巍巍的將那一茶匙的珠粉授給太后,太后一接過來,便伸出舌頭把那粉倒了上去;其時我們站在旁邊承值的人已早就給伊端整下一盅溫茶,只待伊把珠粉傾入口內,便忙著送茶過去,伊也不接茶杯,就在我們手內喝了幾口,急急的把珠粉吞下去了。「珠粉這一樣東西的分量是很重的!」有一次,伊曾經告訴過我關於服食珠粉的功用。「如其稍稍服食幾許,那是很能幫助我們留駐我們的青春的,它的功效純粹在皮膚上透露,可以使人的皮膚永遠十分柔滑有光,年老的人可以和年輕的人一般無二;只是服食的分量千萬要少一些,而且每兩次之間,一定要隔著相當的日子,或其服食的分量太多了,或是沒有規定的時間,隨便隔幾天就服食一次,那末非但對於人體無益,簡直還有大大的有害咧!」
現代語訳
その中のひとつが、十日に一度、真珠を砕いた粉末を服用することでした。
太后が一回にどれくらいの真珠を使うか、私は正確には把握していませんでしたが、使われるのは小粒ながらも透明感のある、きわめて高価な本物の真珠ばかりでした。粉末にした後の量は、およそティースプーン一杯分ほどで、そのスプーンは銀製で、形も通常のものとは異なり、恐らく太后のために特別に誂えられたものだったのでしょう。
この「真珠粉の服用」はすでに数十年も続けられており、ほとんど儀式のように習慣化していました。毎回、ほぼ決まった時刻になると、専任の太監が黄絹(こうけん/高級な絹布)の上に銀のスプーンをのせて、挽きたての真珠粉を太后の前へ恭しく差し出すのです。
太后は何も尋ねることなく、その太監が入ってくるのを見れば、「真珠粉を服用する時が来た」とすぐに察し、太監の手から銀のスプーンを受け取ると、舌を出して粉をその上に注ぎました。そのとき、私たち側仕えの者はすでに一杯の温かいお茶を用意しており、太后が真珠粉を口に含んだと同時に、すぐそのお茶を差し出しました。太后は茶碗を手に取ることはなく、私たちの手から直接数口飲んで、素早く真珠粉を飲み下されました。
「真珠粉というのは、それ自体の分量がとても重要なのよ」
ある日、太后は真珠粉の効用について私にこう語ってくださいました。
「ほんのわずかずつ定期的に服用するなら、私たちの若さをとどめる助けになるの。効き目は肌に直接表れて、肌がいつまでも柔らかく、光沢を帯びたままでいられるわ。年を取っても、若者と同じような肌でいられるのよ。ただし、服用の量には気をつけなければならないの。少しでも多すぎたり、毎回間隔をきちんと空けずに、あるいは服用量が多すぎたり、定められた時間を守らず数日おきに適当に服用するようなことがあれば、人間の体にはまったく利益がないばかりか、かえって大きな害となるのです」
真珠の粉の入った化粧品に関しては、80年代バブルの頃、円がとても強かったために巻き起こった海外旅行ブームの際、香港からのお土産品として大流行したことがあります。美容目的の真珠仕様については、本草綱目に項目があります。
『本草綱目』は明代の李時珍が編纂した中国最大の薬物学書で、約1900種の薬物とその性質・効能・処方などを分類・記述されています。日本を含む東アジアの伝統医学に大変大きな影響を与えています。
珍珠(《開寶》)、蚌珠(《南方志》)
集解
李曰︰真珠出南海,石決明產也。蜀中西路女瓜出者是蚌蛤產,光白甚好,不及舶上者采耀。欲穿須得金剛鑽也。
(中略)
修治
李曰︰凡用,以新完未經鑽綴者研如粉,方堪服食。不細則傷人臟腑。
曰︰凡用以新淨者絹袋盛之。置牡蠣約重四五斤以來於平底鐺中,以物四向支穩,然後著珠於上。乃下地榆、五花皮、五方草各(剉)四兩,籠住,以漿水不住火煮三日夜。取出,用甘草湯淘淨,於臼中搗細重篩,更研二萬下,方可服食。
慎微曰︰《抱朴子》云︰真珠徑寸以上,服食令人長生。以酪漿漬之,皆化如水銀,以浮石、蜂巢、蛇黃等物合之,可引長生。
時珍曰︰凡入藥,不用首飾及見屍氣者。以人乳浸三日,煮過如上搗研。一法,以絹袋盛,入豆腐腹中,煮一炷香,云不傷珠也。
氣味
鹹、甘,寒,無毒。
主治
鎮心。點目,去膚翳障膜。塗面,令人潤澤好顏色。塗手足,去裹塞耳,主聾(《開寶》)。磨翳墜痰(甄權)。除根,治小兒難產,下死胎胞衣。
現代語訳
珠(《開寶》)、蚌珠(《南方志
李時珍曰く:
真珠は南海で産出され、石決明(アワビの殻)と同じような産地である。蜀(現在の四川)中の西路、女瓜(じょか)という地域で採れるものは、蚌(ハマグリ)や蛤(アサリ)から産するもので、光沢があり白くてとても良質だが、海外からの輸入品ほどの輝きはない。穴をあけるには金剛石(ダイヤモンド)が必要である。
(中略)
【加工法(修治)】
李時珍は言う──薬用にするには、新しく完全なもので、まだ穴を開けて装飾品にしていない真珠を粉末にすれば、服用に適する。もし細かく粉砕されていないと、人体の内臓を傷つけてしまう。
また言う──使用には清潔な真珠を絹の袋に入れ、重さ4〜5斤の牡蠣を平らな鍋に置き、四方を支えて安定させたうえで、その上に真珠をのせる。さらに地榆(じゆ)、五花皮(ごかひ)、五方草(ごほうそう)をそれぞれ4両(刻んだもの)加えて包み、水で満たして絶えず火を通し、三昼夜煮る。取り出した後、甘草湯で洗い、臼で細かく搗いてふるいにかけ、さらに2万回以上研磨してから服用する。
慎微は言う──『抱朴子』に「一寸以上ある真珠を服用すれば長生きできる。乳漿(ヨーグルト状の液体)に浸すと水銀のように溶ける。これに軽石・蜂の巣・雌黄などを加えると長命を保てる」とある。
李時珍は言う──薬に用いるには、装飾品にしたものや死体の気に触れたものは使ってはならない。人乳に三日間漬けて、上記の方法で煮て搗き、さらに研磨するべきである。もう一つの方法としては、絹の袋に入れ、豆腐の中に入れて香一柱の間(およそ15〜30分)煮るというものもある。これは真珠を傷めないとされる。
【性質(氣味)】
味は塩辛く甘く、性質は冷たく、毒はない。
【効能(主治)】
心を静め、目に点じれば角膜の濁りや膜を取り除き、顔に塗れば潤いと良い肌色をもたらす。手足に塗れば、耳の詰まりを除き、難聴を治す(『開宝』)。濁りを磨いて痰を鎮める(甄権)。また、胞衣が下りない場合や、死胎の排出を助ける。
私の母もお土産品の真珠粉入りの美容クリームをもらっていました。本草綱目では美容目的なら外用薬として使用されていますが、西太后は飲む方が効くとどこで知ったのでしょうね。そういえば、クレオパトラが真珠をお酢で溶かして飲んだという伝説もありましたね。プリニウスの『博物誌』にある逸話だそうですが、これは美容目的ではなくて自分の豪奢を誇るためでした。
クレオパトラは、ローマの将軍アントニウスに「自分は一度の食事で1000万セステルティウス相当の金額を費やすことができる」と言いました。しかし、アントニウスが信じないため、クレオパトラはその宴会を実現できるかできないかの賭けを持ちかけたのです。後日宴会が開催され、いつもと変わらない料理が運ばれてくる様子を見たアントニウスが、「やはり無理ではないか」と言ったところ、クレオパトラは身につけていた大変高価な真珠のイヤリングの片方を奴隷に持って来させた杯の酢に入れて溶かし、それを飲み干した・・・と。
真珠は日本の御木本幸吉が1893年に半円真珠、1905年に真円真珠の養殖に成功するまでは天然物しかなく、命懸けの素潜りで採取する強烈に高価な品物だったのです。西太后は1835年11月29日生まれの1908年11月15日72歳没ですので、彼女が飲んでいた真珠は天然物でしょう。かかった費用はいったいいくらになったのか、見当もつきません。
さて、真珠ですけども、その成分はほぼ炭酸カルシウムでできており、残りがコンキオリンというタンパク質+多糖類、少し水も含んでいるそうです。炭酸カルシウムって、貝殻と同じ成分です。コンキオリンは真珠の3〜5%くらいしか含まれておらず、あの大きさの真珠の粒に5%のタンパク質では・・・まあ、ほぼ意味はないでしょうね。真珠の母貝の真珠層と貝殻本体を粉にして使ったら同じ成分がたくさん取れるし便利かなあ、というところです。真珠の艶肌は、真珠を飲んだり塗ったりするよりも、養生したほうが手に入ると思いますよ。おそらく費用は真珠を飲む方法の数千分の1で済むのではないかしらん。
他にも、西太后は毎食数十皿を作らせてその中から自分の体調と気分に合った数皿だけを食べていたとも伝わっています・・・多分残りは廃棄処分です。超もったいない。これだって我らには「お惣菜コーナー」「テイクアウト」「カットフルーツ&カット野菜」という強力なツールがあるわけですよ。多分スーパーマーケット1店舗で西太后のわがままバイキングよりずっと品数豊富だと思います。品物を適切に選びさえすれば彼女の美しさにも勝てると思いますよ! 知らんけど!




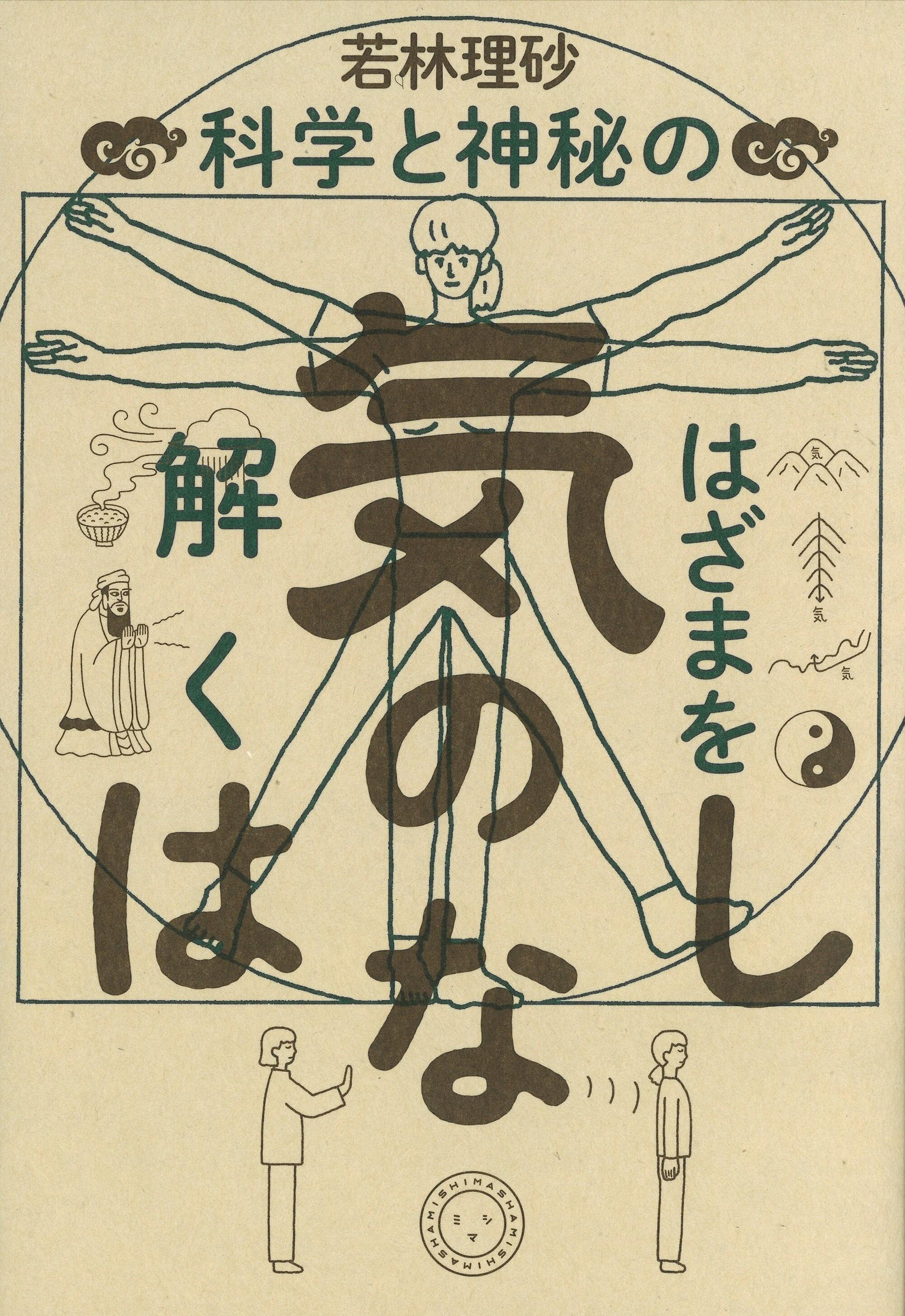
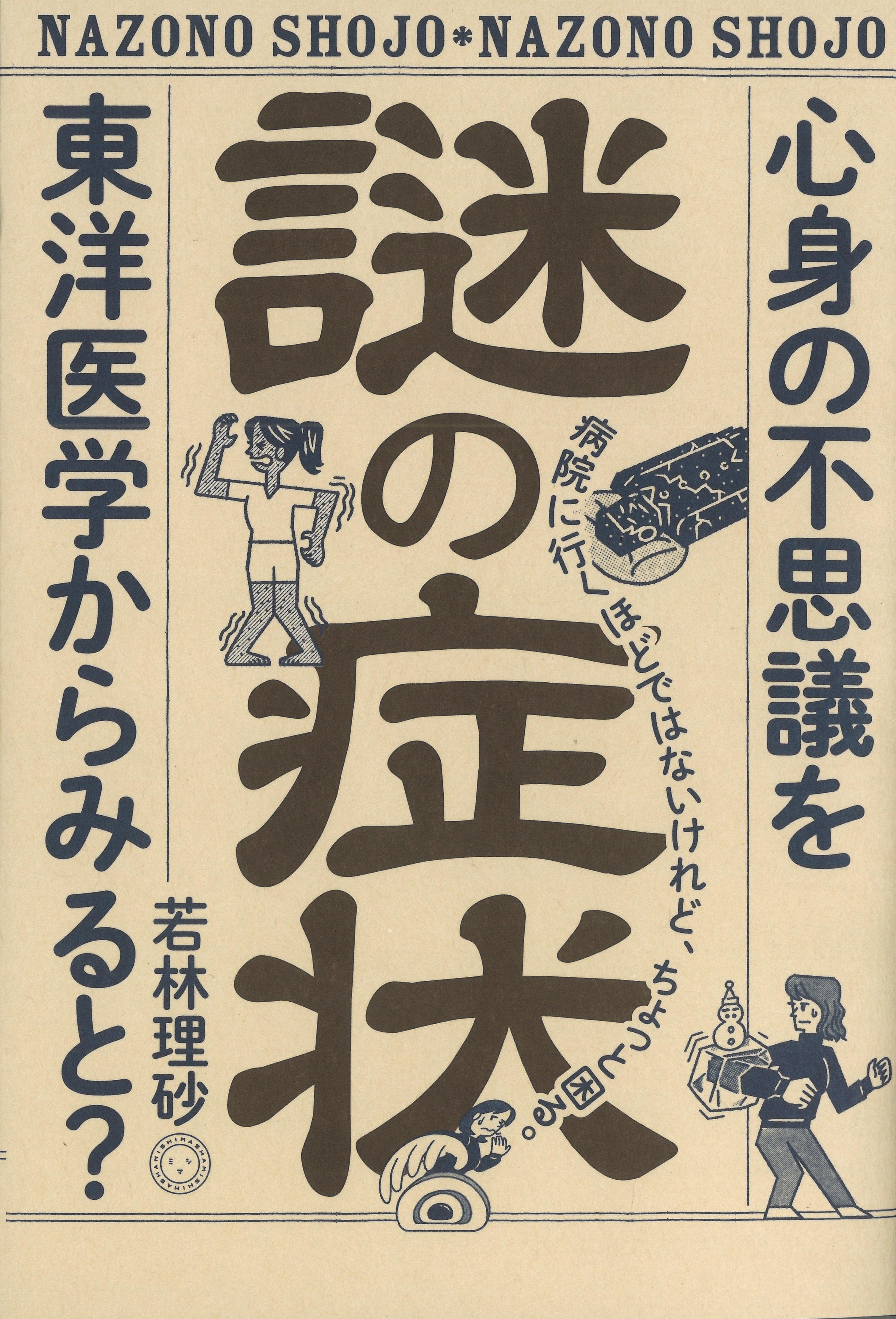


-thumb-800xauto-15803.jpg)


