第9回
イソギンチャク使いの技術、ほか
2022.01.03更新
イソギンチャク使いの技術
角、ツメ、キバ、針、毒。動物の武器は数あれど、キンチャクガニの持つ武器は独特です。多くの動物の武器は、例えばサイの角やゾウの牙、ヘビの毒のように、体にもともと備わっているものです。一方キンチャクガニは、他の生き物を文字通り「持つ」ことで武器とします。使われるのは、触手から毒を打ちこむイソギンチャク。カニは天敵に出くわすと、ハサミで持ったイソギンチャクを振り回して戦います。
人間も他の生き物を武器にしています。例えばゾウ。あの巨体で敵を蹴散らす効果は抜群でしょう。しかし、いかんせん生き物はこちらの思い通りにならないもの。戦象は、いったん制御を失うと味方だろうが見境なく突進していくので、実は扱いにくい武器だったそうです。じゃあ、キンチャクガニはどうかというと、これが見事な技術でイソギンチャクを飼い慣らしています。
キンチャクガニはいつでも両のハサミにイソギンチャクを1匹ずつ持っています。イスラエルのバル=イラン大学のイスラエル・シュナイツァーさんたちは、そんなカニからイソギンチャクを2匹ともとりあげました。するとカニは、近くにいる別のキンチャクガニに襲いかかり、そのうち4割ほどがイソギンチャクを1匹奪い取ることに成功しました。そしてカニは、あろうことか、手に入れたイソギンチャクを2つに裂き、両手に1つずつ持ったのです。せっかく手に入れたのに死ぬのでは?
ところがなんと、イソギンチャクはしばらくすると失った部分を再生し、カニはそれぞれ両手に完全な武器を持つ形に戻りました。これで元通り。再生能力を持つ動物は、例えばプラナリアのようにイソギンチャクの他にもちょくちょくいるものですが、キンチャクガニはこの能力を自分のために使うのです。こんなことする生き物は他にいません。
それにしてもイソギンチャクにしてみれば、いつも道具として持ち運ばれ、運が悪いと引きちぎられてしまうのですから、なかなかハードな生活です。それどころか、成長をカニに邪魔されてさえいます。カニは、エサを捕らえた後、イソギンチャクを遠ざけて食べられないようにしたり、それでもイソギンチャクがエサを口にした場合は、脚を使って取り除いたりするのです。持ち運びに便利なようイソギンチャクを小さくとどめているのでしょう。実際イソギンチャクは、カニの手から離れて暮らすと、6週間で2倍以上大きくなるそうです。
イソギンチャクの中には、キンチャクガニのいないところでは決して見つからない種類もいます。つまり2つに引き裂かれようが成長を邪魔されようが、カニに頼らないと生きていけないのです。イソギンチャクさんそんな飼い慣らされた生き方で大丈夫? と思うのですが、それはきっと人間側の勝手な思い込みなのでしょう。
典拠論文
Schnytzer, Y., Giman, Y., Karplus, I., & Achituv, Y. (2017). Boxer crabs induce asexual reproduction of their associated sea anemones by splitting and intraspecific theft. PeerJ, 5, e2954.
Schnytzer, Y., Giman, Y., Karplus, I., & Achituv, Y. (2013). Bonsai anemones: Growth suppression of sea anemones by their associated kleptoparasitic boxer crab. Journal of experimental marine biology and ecology, 448, 265-270.
ホネクイハナムシの甲斐性
生き物は死んだらそれでお終いというわけではなく、その後も他の生き物のエサになることでしばらくは役割を果たします。中でも体の大きなクジラは食いでがあるのか、海の底に沈んだ死体の周りには沢山の種類の生き物が暮らし、何十年も続く生態系ができあがります。その中には、クジラの死体の上でしか見つからないものさえいます。
そんな動物の一つがホネクイハナムシ。ゴカイの仲間で、細長い体の周りに管を分泌し、中で暮らしています。1匹1匹はあまり大きくなく、10cmにもならないほどですが、クジラの骨の表面にたくさん集まり、草が生えているかのようです。彼女たちは細菌を住まわせた根のようなものをクジラの骨の中に伸ばし、脂分を取り込んだ細菌から栄養をもらっています。そのため、口も胃も腸もありません。
なぜ「彼女」と呼ぶかというと、私たちの目に映るホネクイハナムシのほとんどがメスだからです。オスはというと、メスが住む管の中に何匹もいてメスから栄養をもらって生きています。サイズは1mmより小さく、動く能力も失っていますが、メスに食わせてもらっているので構わないのです。じゃあオスは何をしているかというと、大家さんであるメスのためにもっぱら精子を作っています。
米国カリフォルニア大のグレッグ・ラウズさんたちは、そんなホネクイハナムシの中に、オスが肉眼でも見えるほど大きくて、寄生生活をせず、自分で栄養をとり独立して生きている種類がいることを見つけました。交尾も行い、他のオスとは違って、2匹以上のメスと子を作ることができます。といっても、骨に根っこを食い込ませているので歩き回ることはできず、体を伸ばして届く範囲にいるメスしか相手になりませんが。ちなみに、縮むと2mmくらいの大きさのオスですが、メスを探すときは15mmほどまで体を伸ばすようです。けなげです。
独立した生き方は私たちから見れば「普通」なので、このようなオスから特殊な寄生生活が進化してきたのだろう、と、うっかり思ってしまいます。ところが、この種類は、寄生生活をしていた種類が、もう一度独り立ちし「普通」の生き方に戻ったと考えられています。生活のすべてを他人におんぶに抱っこできるという、一部の人には夢のような生活を捨てるなんて、何を考えてるのでしょう(いや、何か考えて生き方を変えたわけではないのでしょうが)! 実際、このようなオスの逆戻りは、ホネクイハナムシで初めて見つかった現象で、滅多に起こることではないようです。じゃあどうしてこんなことが起こったのか。残念ながら、まだそこはよくわかっていないので、働かない誰かさんをなんとかしたいという期待には応えられません。あしからず。
典拠論文
Rouse, G. W., Wilson, N. G., Worsaae, K., & Vrijenhoek, R. C. (2015). A dwarf male reversal in bone-eating worms. Current Biology, 25(2), 236-241.
編集部からのお知らせ
書籍化をお楽しみにお待ちくださいませ!
本連載は、今回でいったん終了となります。この連載を含む書籍が今年中に発刊となる予定ですので、どうぞお楽しみに!


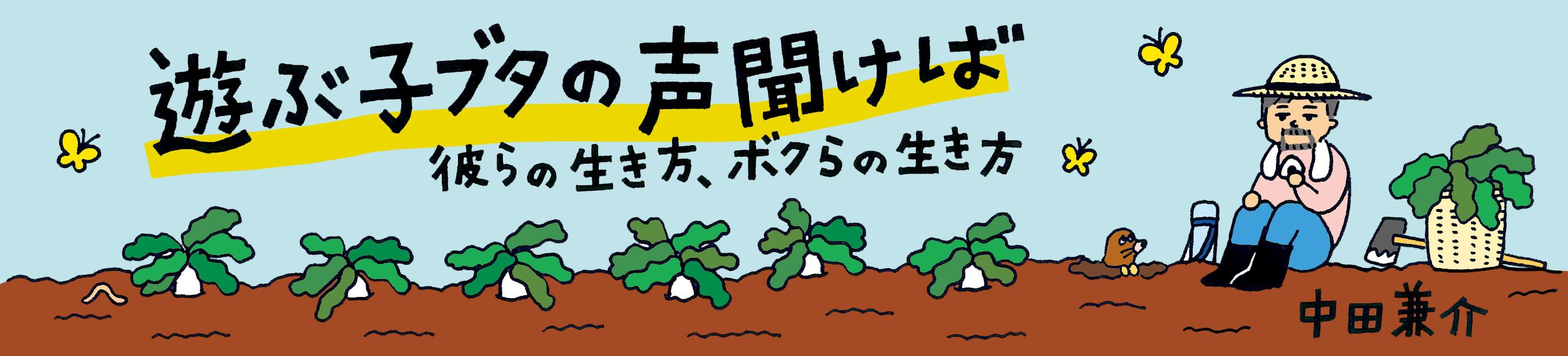

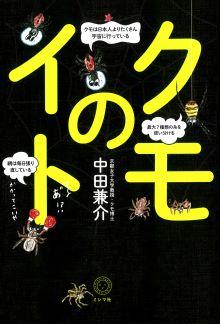


-thumb-800xauto-15803.jpg)


