第7回
寿司3貫の孤島から生き延びて
2025.11.10更新
無人島に寿司を3貫だけ持っていけるとしたら何を選びますか。
これは一緒にポッドキャストの番組を作っている友人が放送用に考えたトークテーマだ。
これを素朴な質問と捉えて、サーモン、サーモン炙り、サーモンハラス炙り、と無邪気に大好きなサーモン縛りの注文を考える人がいるかもしれない。あるいは想像のなかだったら金銭的な枷がないのをいいことに、本鮪大トロ3貫などと欲張る人もいるだろう。
ポッドキャストの番組的としては、こうした話題で無邪気に盛り上がったほうがリスナーも楽しいだろう。落語における枕のような役割を期待して、友人は敢えて軽めの質問を用意してくれたのだと思う。
一方で、本当に軽い質問なのだろうか、というのが俺の考えであり、ミュージシャンの書いた雑文を読むほど好奇心が旺盛な読者の皆にも、一緒に考えてほしい。
まずは、無人島に何の用事ででかけるのかということが、この設問にとって肝要なのではないかと思う。
例えば、レジャー。これは単なる旅行である、ということであった場合、軽い気持ちでサーモン縛りを選ぶのも悪くない。日々の労働、家事、育児、介護、そういうものから解放される場なのだから、サーモンくらい好きなだけ食べさせてほしい、みたいな考えも納得できる。
しかし、レジャーだとしたら、3貫縛りはおかしい。そして行き先は島なのだから、大量の酢飯または米と寿司酢を用意して向かい、魚介類は現地調達が理想的だと考えるのが一般的ではないかと思う。寿司という料理に拘泥せず、白身の魚はカルパッチョにして楽しみたい、そう考えたとしても不思議ではない。漁業権の設定されていない貝類を集めて、酒で蒸したり、バターで焼いたりしたものも食べるのもいい。だってレジャーだもの。
そうはさせてもらえない理由について考えた。
おそらく、向かう先の島は前述したようなレジャーが許されない、もしくは物理的に娯楽一般が不可能なタイプの無人島なのだろう。断崖絶壁の孤島で、上陸するのも命懸けの岸壁に無理やりタラップを掛けるのかもしれない。
毒蛇、毒虫、毒猿、毒熊などが跋扈するような、人間にとってはこの世の地獄と呼ぶべき島を想像する人もあるかもしれないが、寿司3貫を食べる余裕はあるのだろうから、そうした考えは退けたい。直ぐに死んでしまうような場所ではないだろう。
ただ、3貫に限定されているところが気になる。他に食べるものが与えられない、あるいは所持できないというニュアンスが、「無人島に寿司3貫」という状況には含まれているのではないかと思う。それぞれに3貫の寿司が配られる、あるいは持参が認められたとして、これを食べたら帰りましょう、というシチュエーションへの着地は想像し難い。食べ放題ではなく、3貫に限定している時点で、船員たちは参加者を置いて帰るに決まっている。最後の晩餐としての3貫と考えるのが筋だろう。
恐ろしいことだと思った。
もはやこれまで。48年の長いようで短い人生だった。最後の寿司なのだから、きっぱりとした態度で好きな寿司ネタを選ぼう。やっぱり鮪かな、鰹もいいな、巻き寿司を頼んだら酢飯の量が増えて少しでも長生きできるかもしれないなと、好物に振り切るべきか、腹持ちの良し悪し的なコストパフォーマンスについて考えるべきか、余命の限られた人生の最後の選択の時間を少しでも楽しもうと考え込んでいると、腹の底のほうから、むくむくと生き延びたいという気持ちが迫り上がってきた。
俺にはまだやり残したことがある。
今から10年ほど前のこと。40歳を前にして、俺は50歳でサウンド・エンジニアの末席にきっちり座ろうと決意した。10年をかけて勉強して、制作現場も体験し、アーティストの副業や趣味とは絶対に呼ばせない気概で、仕事の依頼が来るような人間になりたいと考えた。
そうした決意を頼りに「さて現場だ、経験だ」と言っても、バンドの知名度があるとはいえエンジニアとしては無名の俺に仕事があるわけではなかった。仕方がないので、仕事を作った。自分の作品のなかで、録音エンジニアとして関わることができる場所を増やしていった。また経済的に恵まれないインディー・ロックバンドなどの相談に乗って、自分のできる仕事を無償で、あるいは破格の低賃金で提供しつつ、現場に参加する機会こそを報酬と考えて、勉強させてもらうようにした。
そうして仕事を増やしていくうちに、バンドからの収入には敵わないが、いくらかの報酬を受け取れるようになった。ここが末席、めでたし、めでたし。とはならなかったのは、自分のバンドが置かれている制作環境とインディーズの制作環境にかなりの差があったからだった。
最初のうちは「そういうもんだよね」というドライな気持ちがあった。メジャーとインディーに予算の差があることは、資本主義経済の社会のなかでは、ある意味では仕方がない。その差に対するある種の怨念がインディーズの燃料であり、アイデアと情熱で下剋上じゃボケ、くらいの気概は誰もが持っていた。しかし、状況がみるみると変わった。音楽ソフトが売れなくなった。戦争で資材が不足し世界的に機材の価格が上がった。それに加えて政府の金利政策によって円安が進んだ。ほとんどが輸入品の音響機材が高騰するのは必定。それならばライブだと息巻いたが、新型コロナウイルスのパンデミックという厄災もあった。八方塞がりであった。
こうなってくると格差が広がる。富めるものは富み、貧しきものは貧しいまま、ある種のループに陥ってしまう。社会の在り方だけでなく、配信などのプラットフォームの仕組みも、格差拡大に加担していると言えなくもない。こうした状況に目を向けず、まあ自分が死なない程度にはバンドが転がってるので善しとしよう、とは考えられなかった。
一緒に作業しているミュージシャン、バンドマンの多くは仕事を持ちながら、素晴らしい音楽を作りつづけていた。俺は半分支援、半分勉強というかたちで参加した彼らとの音楽制作の現場で、その音楽や姿勢に感動しつつ、少しずつ憤りを深めていった。ここまで差があるのはどういうことなのだろうと考えた。
何かをせねばならぬ。
そう思って様々な方向に走っては壁にあたり、跳ね返っては壁に当たり、紆余曲折の末に辿り着いたのが音楽家支援のためのレコーディング・スタジオとコミュニティーづくりだった。多くの人の支援を受けて、スタジオはもう少しで完成というところまで漕ぎ着けた。
なんとしても、この寿司3貫の孤島から生き延びて、もう一度本州に、駿河湾のあたりから上陸せねばならない。そういう決意に満ちている。
そう考えると、なるべくカロリーが高いほうがいい。ここは助六一択だと思った。太巻きを一本とお稲荷さんをふたつ。油揚げに染み込んだ甘い汁こそが俺のエネルギー。燃えよ贅肉。この日のために中年男性らしく肥えてきた。
メラメラと燃えていた。
太巻きを口いっぱいに咥えて、なんとなく縁起の良さそうな方角に向かって「エホー!!」と叫んだ。


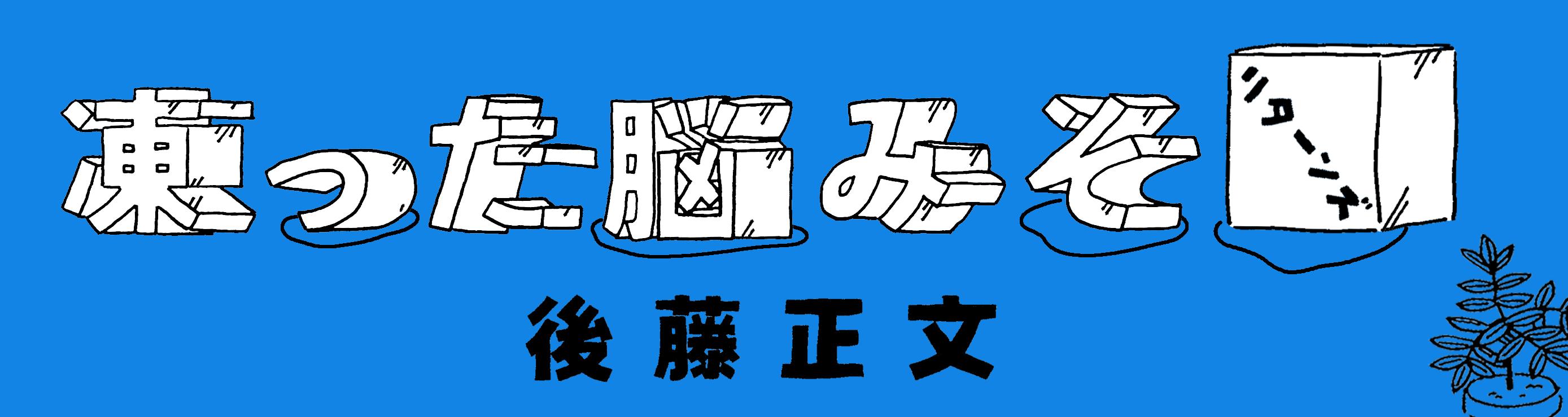

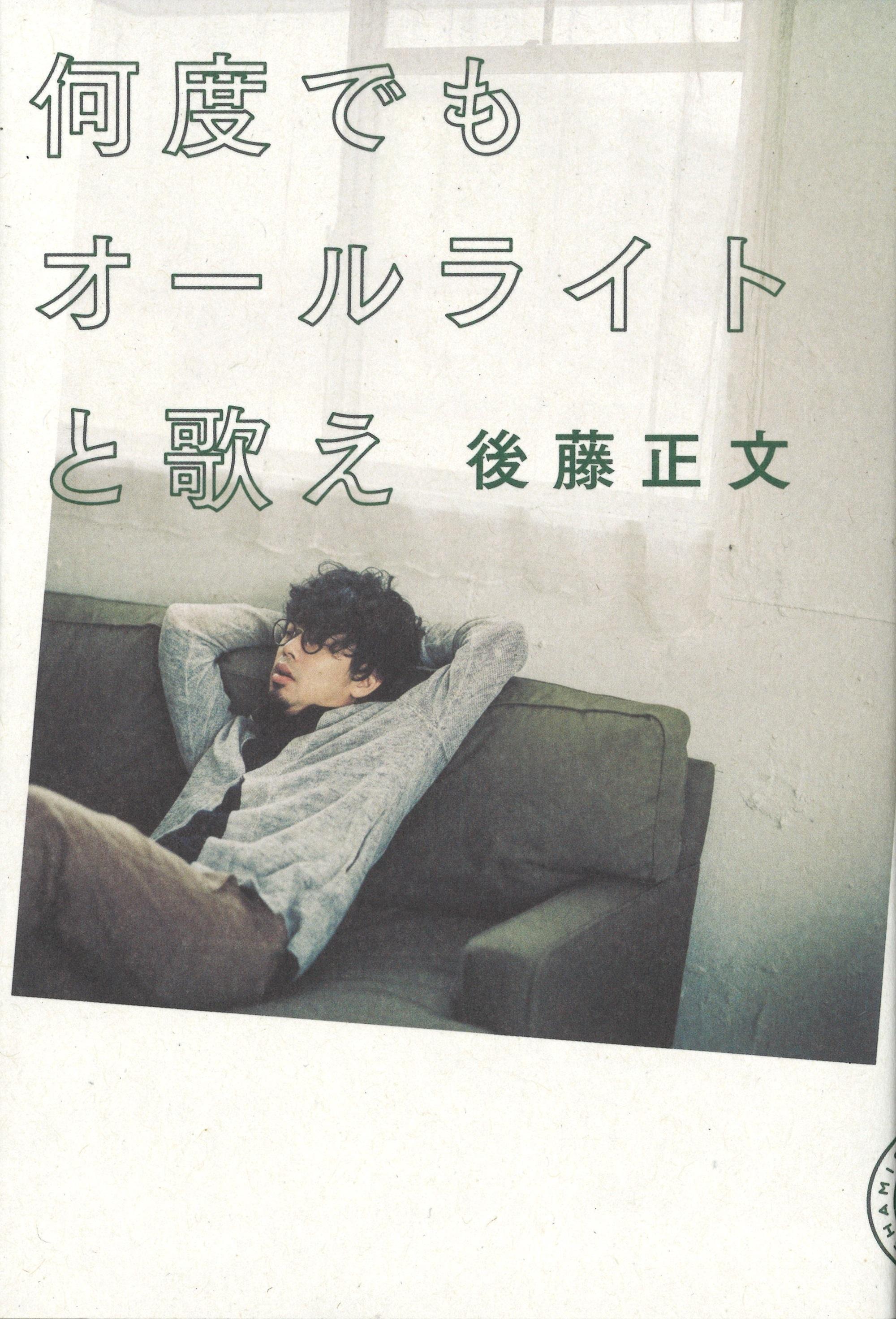
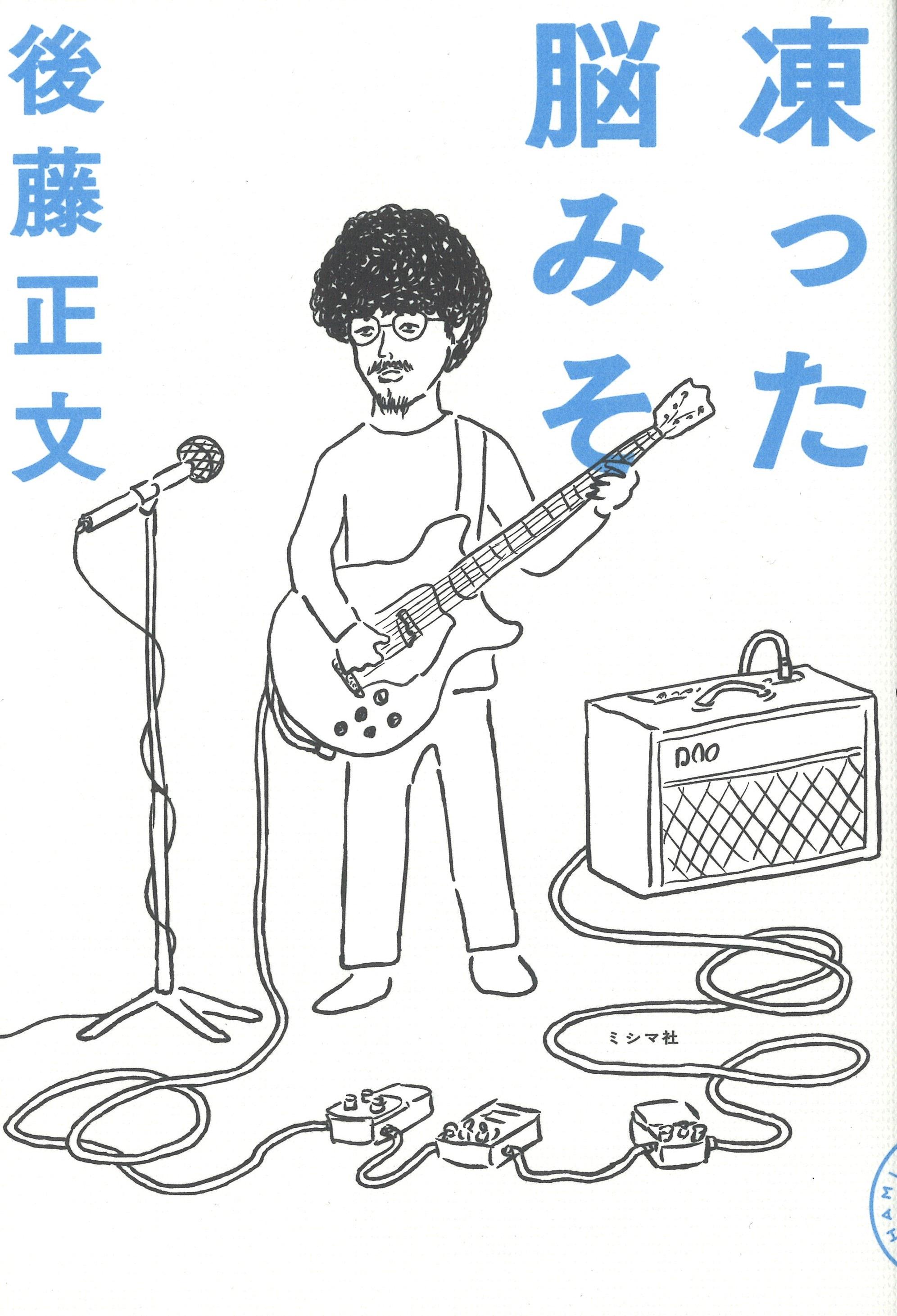


-thumb-800xauto-15803.jpg)


