第4回
日大アメフット部危険タックル問題が浮き彫りにしたこと
2018.07.06更新
先月からの続きを楽しみにしていただいていた読者には申し訳ないが、今月は特別寄稿として、日大アメフット部危険タックル問題について書く。
5月6日に行われた関西学院大学との定期戦で、日大の選手が、ホイッスルが鳴らされたあとにもかかわらず相手の死角となる背後からタックルを行った。ルールを逸脱し、ともすれば大けがにつながりかねないこのタックルが問題視されてから、約2ヵ月が経過した。SNSによる拡散を機にマスメディアは挙ってこの問題を報道し、巷間に流布するに至った。
問題発覚当初からしばらくは、加熱し続けるその報道ぶりにやや辟易としながらも事の成り行きを追いかけていたのだが、登場人物のあまりにお粗末な対応にほとほと呆れ、小さくない憤りも伴って、次々と湧いてくる他罰的な感情を抑えられずにいた。
事の詳細はこれまでに報じた各媒体に譲るが、僕がどこに憤りを感じたのかを具体的に挙げれば、ひとつは内田正人元監督および井上奨元コーチのスポーツ指導で、もうひとつは日大およびそのアメフット部の運営体制と謝罪を含めたその後の対応である。記者会見や謝罪会見の様子、新聞各紙や各週刊誌の記事などから、事の顛末が徐々に明らかになってゆくなかで、途方もない怒りがその程度を増しながら僕の心を覆い尽くした。これほどまでに悪辣な問題がかつてあっただろうかと、スポーツにまつわる問題をすべて網羅しているわけではない自らの無知を棚に上げてまで、そう強く感じたのである。
唯一の救いは、危険タックルをした加害者がとった行動で、そうせざるを得ない情況にまで追い込まれたという点で「被害者」でもある当該選手の記者会見である。彼だけが真実を口にしていたように見受けられたからだ。決して拭い去れない自らの非を認めた上で、他者の落ち度をあげつらうことなく自分の言葉で記者からの質問に訥々と応える姿には、感動すら覚えた。300人を超える記者に囲まれながらも、それに臆することのない堂々とした立ち居振る舞いは、見事としかいいようがなかった。
いつしかニュースの見出しが、史上初の米朝会談やモリカケ問題をはじめとする国会での騒動、サッカーW杯での日本代表の躍進に取って変わり、以前の加熱した報道が沈静化した今になって、僕はようやく冷静さを取り戻しつつある。「取り戻しつつある」という表現にとどまるのは、数々の政治的な案件が未だ解決していないにもかかわらず、それを優先的に報道しないメディアのあり方への不満が断続的に続いているからだが、ここでは深入りしない。日大の第三者委員会による中間報告で、あの危険タックルが内田氏と井上氏の指示で行われたことが明らかになり、事件の全貌がおおよそ概観できた今、このたびの日大アメフット部危険タックル問題が浮き彫りにしたことについて思うところを書いてみたい。
結論からいえば、この事件が浮き彫りにしたのは、日本スポーツ界で長らく続いている「軍隊式指導法」である。上官の命令に逆らわない従順な兵士を育てるという指導法が、そのままスポーツ界において肯定的に遂行されてきたことを、改めて白日の下に晒した。
科学の進歩にしたがって、徐々に否定されつつあるものの未だ根強く残る「根性主義」もまた、その元をたどれば「軍隊式指導法」にたどり着く。上官つまり監督やコーチの指示は、たとえその内容が理不尽であったとしても逆らうことは許されない。理不尽さをはじめとする過酷な情況を乗り越えるのに根性は不可欠である、そう考えるのが「根性主義」である。
「現場」には様々な矛盾が生じるものだし、「現実は厳しい」と考えるときの念頭にあるそれを乗り越える必要性を否定はしない。この社会を生きる上で立ちはだかる様々な問題は、その解決法も含め往々にして理路整然としていない。だから時と場合によって根性的な働きかけは不可欠ではある。ただ、だからといって根性を礼賛し、それだけが超克をもたらすと考えるのは浅薄である。
根性も、ときに必要だというだけの話である。2年前に惜しまれつつなくなった元ラグビー日本代表選手および監督の平尾誠二氏は、生前、「科学的根性」の研究が急務であると指摘していたが、もし真の根性論があるのだとして、それを構築するとすれば、この視点が重要になると僕には思われる。
常軌を逸した厳しさを、根性を発揮して乗り越えれば然るべき成長を遂げるという稚拙でシンプルな物語への信奉は、私たちの心の深部にしぶとくこびりついているように思う。
まさに日大アメフット部危険タックル問題が報道される最中、僕はかつてのチームメイトやスポーツ関係者、部活動関係者に、食事をする機会や教育実習校への訪問時などを利用して、この問題についての見解をそれとなく訊ねた。社会問題にまで発展したこの件を、スポーツに関わる人たちはどのように受け止めているのか、それが知りたかったからだ。
総じて反応は鈍かった。「そうはいってもスポーツに厳しさは必要だからね」という趣旨を言外に匂わすように、語尾を濁して話題が逸れていくのである。このたびの問題が悪質だと認めながらもきっぱりと否定はしない。公になったことをさも運が悪かったように言う人も中にはいて、思わず頭を抱え込んでしまった。
日大アメフット部は前年度に大学日本一に輝いている。それを引き合いにして、「軍隊式指導法」が競技力向上に資すると考える気持ちはわからないでもない。心身ともに追い込まれ、二進も三進もいかない情況に置かれると人は爆発的に潜在能力を開花させるからだ。地震などの震災で、瓦礫の下敷きになった我が子を助けるべく母親が折れた柱や家財を持ち上げたというケースは枚挙に遑がない。いわゆる「火事場の馬鹿力」である。平時では発揮できない力が緊急時には発揮される、生物学的反応ともいうべきこうした能力を利用した指導法は、それなりには有効だ。
ただこの方法には、決して見過ごせない落とし穴がある。命に関わる緊急時の対応としての「火事場の馬鹿力」を、頻繁に引き出すことで失われるものがあるからだ。
かの試合において、危険なタックルをした選手は心身ともに追い込まれていた。
ある時期に練習を休んだことを理由に、日本代表候補に選ばれる逸材でありながら日常的に練習への参加が許されず、5月6日の試合のスターティングメンバーからも外されていた。スポーツ界ではこうした情況を指して慣習的に「干す」と表現するが、彼はまさしく「干されていた」。
試合に出場するには練習を積み重ねるしかない。自らの競技力向上に加えて、首脳陣に自らの存在をアピールする機会、それが練習だ。その練習に参加させてもらえないのは、首脳陣の眼中に彼がいないことを意味する。最も卑劣なイジメとされる「無視」に相当するこの干され方は、当の選手に途方もない孤立感をもたらす。努力する場そのものを失い、先行きが極めて不透明な選手の精神状態はズタズタになる。
こうした情況に追い込むと同時に、そこから脱する手段を指導者は用意する。それがあのタックルだった。
ルールを逸脱してでも相手に怪我をさせることを目的としたタックルをすれば、またかつてのような日常に戻れるぞ。そう指導者たちは囁いた。いや、忖度させるような仕方で本人にそっと伝えた。チームを束ねる監督である当の本人は手を汚さず、子飼いのコーチを使って、それとなく。
つまりあのタックルは首脳陣が巧妙に仕掛けた「踏み絵」だった。
この「踏み絵」は、適切に理性が働く人間に踏むことはできない。公平性や道徳を重んじる人間にとって、この葛藤を乗り越えることは至難の業だ。人としての尊厳をかなぐり捨てなければ決して実行できない。理性を捨て、感情を暴発させて、いわば「鬼」にならなければ、その一歩を踏み出すことはできないのだ。
当該選手にとって苦渋の決断であったことは論を俟たない。彼の胸の内を想像すれば、こうして書きながらに心が苦しくなる。
日大アメフット部が、「踏み絵」を踏ませることによって選手を「鬼」にする「軍隊式指導法」を採用していたことが明らかになった。ひとりの若者に、人としての尊厳を棚上げさせるような指導をしていた首脳陣は然るべき処分が下されて当然だろう。「鬼」は一兵卒としては有能かもしれないが、将としては無能である。感情を暴発させて事に当たる指揮官のもとでは、結果的にたくさんの兵を死に至らしめる。戦略を練り、戦術を立案するためには、直面する情況を的確に把握する冷静さが不可欠だからである。
教育機関である学校での部活動が育てるべきは、軍隊でいうならば一兵卒ではなく将となる資質であり、それよりもなによりもひとりの人間として自律する能力だろう。理性を働かせ、感情を抑制しなければ自らを律することなど到底できない。理性と感情、冷静と情熱のあいだで揺れ動く情動を自制して適切な行動をとることこそが自律だ。
合気道家・現代思想家の内田樹氏は、ここでいうところの自律を「胆力」と捉えている。
胆力があるというのは、極めて危機的な状況に陥ったときに、浮き足立たず、恐怖心を持たず、焦りもしないこと。どんなに破局的な事態においても、限定的には自分のロジックが通る場所が必ずあると信じて、そこをてがかりにして、怒りもせず、絶望もせず、じわじわと手をつけてゆく。とんでもなく不条理な状況の中でもむりやりに条理を通していく。胆力とはそういう心構えではないかと僕は思っているんです。 −−『教える力、育てる力 一流スポーツ指導者の秘伝公開』(セオリーmook)
と述べ、頭に血が上って「鬼」になることと方向がまったく違うと指摘している。
確かに「鬼」が集まればそれ相応の競技力を発揮する。たとえば血走る目で、涎を垂らしかねないほどに感情を高ぶらせながらプレーする選手(あるいはその集団)は、対面する相手に「なにをしでかすかわからない恐怖」を植えつける。理性が働かず、感情が暴発する人間を前にすればほとんどの人は戦慄するものだ。勝利という結果だけを追い求めるのであれば、これでよいのかもしれない。それなりの戦績も収めるだろう。
だが、これをもって競技力の向上と考えるのは早計である。もしこうした選手(あるいはチーム)が優勝するのであれば、それはそのスポーツ界全体が成熟していないと考えなければならない。選手を心身ともに追い込む「軍隊式指導法」では、じっくり時間をかけなければ育むことが難しい自律心、あるいは『胆力』が置き去りにされる。スポーツ指導者は「鬼」ではなく、それらを兼ね備えた人間をこそ育てなければならない。
僕は「鬼」にはならない。
一度「踏み絵」を踏んだことで、このままだと自らが「鬼」になってしまうことに恐怖を抱いたかの選手は、じっくり自省した上で記者会見に臨み、勇気を振り絞ってそう決意表明したのだと思う。この決意表明を僕は真摯に受け止める。
大人の怒声に怯え、心理的に圧迫されながらのプレーが強いられた子供に自律心が芽生えるはずがない。常にその顔色をうかがいながらの活動で身につくのは「従順さ」だ。あるいは従順なフリをしてその場を凌ぐ「ずる賢さ」である。長らくのスポーツ活動を通じて身につくのが「従順さ」や「ずる賢さ」であり、それを撥ね退けるために「鬼」にならなければならないのであれば、スポーツに未来はない。
スポーツ界は、古くて新しいこの問題に真正面から向き合わなければならない。「鬼」を量産する旧態以前の「軍隊式指導法」にきっぱりと決別する必要がある。そしてこの問題はスポーツ界だけにとどまらないだろう。社会のあちこちで問題視されているパワーハラスメントも根っこは同じだ。「スポーツは社会の縮図」だといわれて久しいが、そうならばスポーツ界の変革はやがて社会のありようを逆照射するはずである。
スポーツは変わらなければならない。
スポーツ界から、変わらなければならない。
やや遅すぎた感もあるが、今がまさにその時だと思う。
このテクストが悩めるスポーツ指導者と選手や子どもたち、そしてその親たちを励ますことを願い、また自戒も込めて、ここに記す次第である。





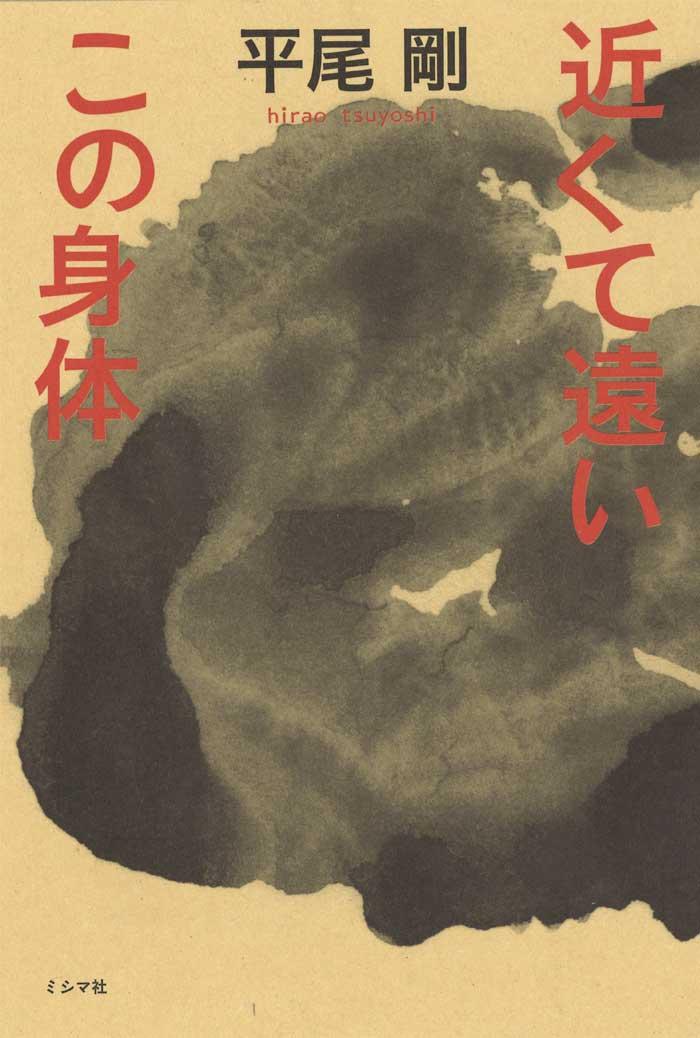




-thumb-800xauto-15803.jpg)
