第2回
筋力アップのメカニズム
2018.05.09更新
そもそもなぜ筋トレをすれば筋肉がつくのだろう。
すでに精力的にからだを鍛えている人にとって、この問いは愚問に違いない。そんな当たり前なことをいまさら問いかける必要があるのかと思うかもしれない。しかし「当たり前なこと」というのは、すでに知っている側からすればそうでも、その道に詳しくない人からすれば「新たな発見」となる蓋然性が高い。集団内での共通理解である「当たり前なこと」は、その集団の外側にいる人にとっては当然のことながら当たり前ではないからだ。
ラグビー経験者にとってニュージーランド代表が長らく世界ランク1位を保持する強豪国であることは、周知の事実である。だが、ラグビーのラの字も知らない人にとっては「へぇー」となる。「当たり前なこと」を語る際にはちょっとした照れくささがつきまとうが、その照れくささにめげることなく丁寧に説明することは、共同体の枠を超えて共通理解を広げるためにとても大切なことだ。
というわけで、今回は筋肥大のメカニズムについて書いてみたい。ちなみに勘のいい方はすでにお気づきであろうが、こうして長々と前置きしたのは筋トレ経験者である僕自身が照れくささにめげないためである。あしからずご了承いただきたい。
では始めよう。
人間のからだは「周辺環境」に適応するようにできている。たとえば、ピアノを始めれば指先の動きがどんどん精密になってゆくし、サッカーを始めれば練習を重ねるうちに脚でボールを器用に扱えるようになる。長距離走を繰り返せば持久力がつくし、短距離走だとそれに応じて瞬発力が増す。周囲の環境がそれ相応の動きをからだに強いることで、徐々に僕たちのからだはつくられてゆく。つまり「周辺の環境」という鋳型通りに僕たちのからだは変化をするわけだ。
筋トレもまた「周辺環境」のひとつである。日常生活の一部に、局所的に筋肉を動かすという動作が組み込まれ、その環境に応じてからだは変化してゆく。
たとえば、アームカールという筋トレのメニューがある。これは上腕二頭筋(いわゆる「力こぶ」)を鍛えることを目的としたメニューで、脇を閉めてバーベルやダンベルを持ち、腕を伸ばした状態から肘を曲げ伸ばしするというものだ。こうすることで上腕二頭筋に集中的に負荷がかかり、徐々にその太さを増してゆく。
1回、2回、3回・・・。休憩を挟んでまた1回、2回・・・と上げ下げしていくと当然のことながら限界が訪れる。疲労困憊となった時点でその日はおしまい。2日ほど経ってまた1回、2回・・・と上げ下げを続ける。このサイクルを繰り返すと、バーベルやダンベルを持ち上げるという動作にかたどられて、からだがだんだん適応してくる。つまりその重量を楽に持ち上げるための筋肉がついてくるわけだ。ランニングを始めてしばらく経つと脚の筋肉がつくのと同じである。
このとき筋肉では、それを構成する筋繊維が破壊されている。からだの限界を超える運動を繰り返したことにより、筋繊維の一つ一つが壊されているのである。筋トレしたあとに襲う激しい筋肉痛は、「もうこれ以上は力を発揮できません、壊された筋繊維を修復するまでちょっと待って欲しい」というからだからのシグナルである。だから激しい筋肉痛になれば、それ以上負荷をかけてはいけない。休ませなければならない。
壊れた筋繊維を回復させるために必要となるのがタンパク質である。タンパク質は筋肉を構成する栄養素だから、これを大量に摂取すればそれだけ回復が早まることになる。通常の食事から摂取してもいいし、それで足りなければプロテインサプリメントで補ってもいい。近年、各社からさまざまな種類のプロテインサプリメントが発売されているのはそのためだ。筋トレ後の筋肉を回復させるためにタンパク質の摂取は不可欠である。
さらにもう一つ必要なのが成長ホルモンである。これにはタンパク質の合成を促進する作用があり、睡眠中に大量に分泌されることがわかっている。だから効率的な筋肥大を望むならば睡眠を疎かにしてはいけない。激しく動いて、たくさん食べて、よく寝る。運動、栄養、休養という健康の三要素と同じだと考えれば理解しやすいだろう。
この一連のプロセスをわかりやすく理解するために、筋肉を建築物にたとえてみよう。
筋肉を構成するタンパク質はいわば「建築資材」であり、成長ホルモンは「現場監督」である。まずはダンベルやバーベルなどの「建機」を使ってひたすら壊す。半壊状態のそれを修復するための建築資材を食事やプロテイン含有食品で体内に送り込み、現場監督が指令を出すことによって、スムースに再建される。
そしてここがポイントだ。
人間のからだは実に不思議で、壊れた筋繊維は元の状態よりも太く大きくなるようにできている。折れた骨が以前よりも太くなり、擦り傷のあとにかさぶたができて以前よりも皮膚が厚くなるのと同じで、筋肉も以前の状態を超えて大きくなる。柱が強化され、より高層化された建築物として生まれ変わる。こうして筋肉は肥大してゆくのである。
これを「超回復理論」という。筋トレに関する研究が始まった1960年代頃からずっとこの理論が正しいとされてきた。
ただ最近では新たな研究結果が出ていて、この理論は覆されつつある。筋トレ前の状態よりも強化される、つまり「超回復」するのは筋肉ではなく、「筋中のグリコーゲン貯蔵量」であることが最近の研究で明らかになった。
筋中のグリコーゲンとは筋肉が収縮するためのエネルギー源である。この貯蔵量が増えるということは、以前よりも増して筋肉を収縮させることができることを意味する。すなわち、ダンベルやバーベルを以前よりも回数多く上げ下げすることができるようになるということだ。筋肉そのものが強化するのではなく、その出力としての「筋力」がアップするというわけで、先に書いた建築物のたとえでいえば、耐震構造が施され、冷暖房やネット環境が整備されて、もともとの建物よりもその機能性が充実するということになる。ただ見た目には明らかに筋肉量が増えるので、建物である筋肉自体も高層化するのは間違いないとは思うのだが。
いずれにしても「筋力」がアップすることに変わりはなく、このメカニズムが覆されたとしても筋トレ実践者にとってさほど大きな影響を及ぼすものではない。
要は、局所的に筋肉を疲れさせ、プロテインサプリメントや食事によってタンパク質を大量に摂取し、成長ホルモンの分泌を促すために睡眠をとる。この一連のプロセスを経て、筋肉はその大きさも、機能も、以前の状態を超えて獲得するのである。
いうなれば筋トレは、身体の恒常性であるホメオスタシスを最大限に利用して、ひたすら筋肉を疲れさせる作業といえる。高度な動きを身につけるべく取り組む諸種の運動とは質そのものが違い、あるひとつの筋肉にターゲットを絞って部分的にひたすら筋肉に刺激を与えるのが、筋トレなのである。
編集部からのお知らせ
●平尾さんが、ラグビーフランスリーグTOP 14 プレーオフ準決勝を解説します!
日時:5月26日(土)深夜(キックオフ時間は23:15、放送開始はおそらく23:00〜)
放送:WOWOW
対戦カードは未定です。
詳しくは→http://www.wowow.co.jp/detail/109025
●公開講座「ラグビーを知ろう」に登壇
日時:6月8日(金)および6月15日(金)19:00〜20:30
場所:神戸神話女子大学三宮サテライトキャンパス
センタープラザ教室(阪急三宮駅から徒歩5分)
定員:40名
受講料:1500円
受講対象:高校生以上
詳しくは→https://www.kobe-shinwa.ac.jp/ckc/extention/


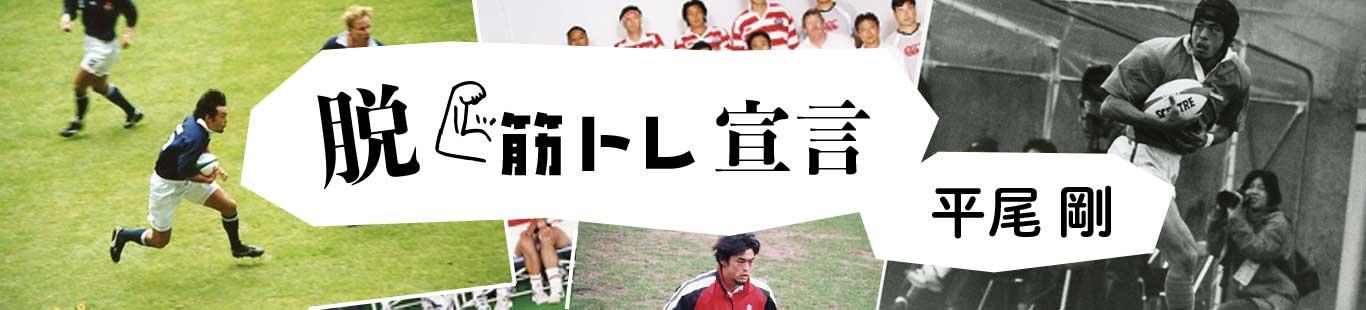
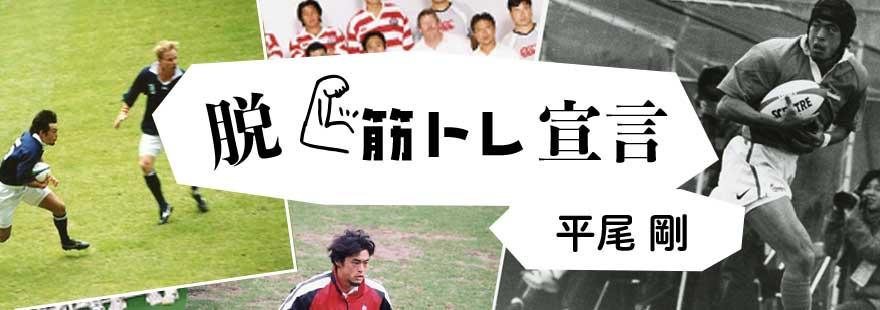

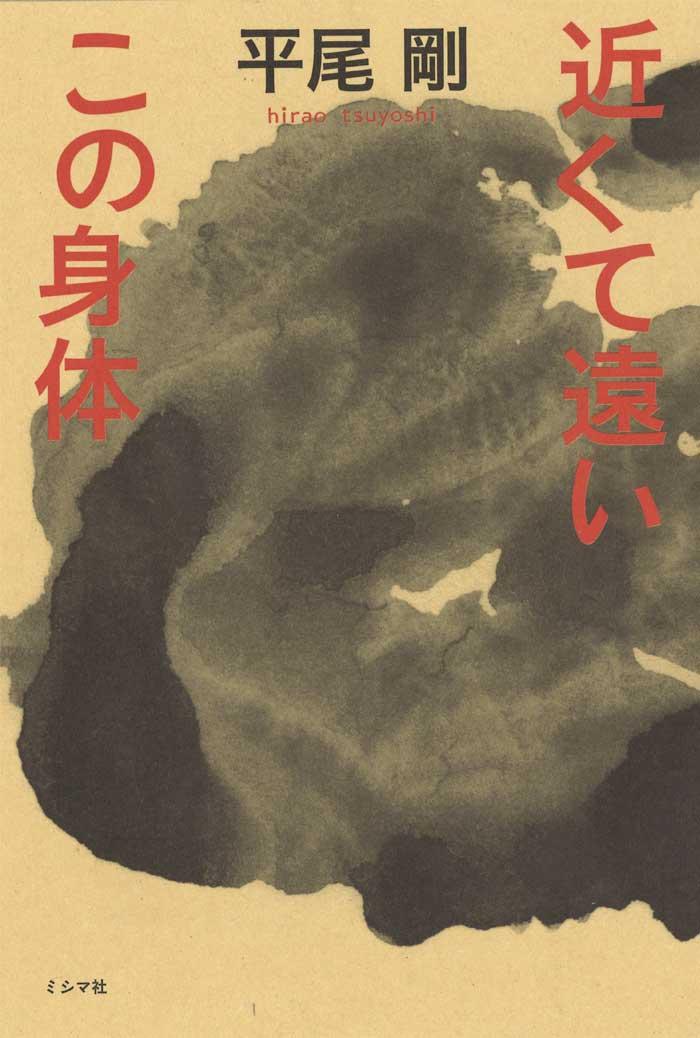




-thumb-800xauto-15803.jpg)
