第9回
身体知とは〜始原身体知〜
2018.12.05更新
ここまで筋トレの弊害についてつらつらと書いてきた。からだのハード面における強化を図るのが筋トレの目的で、特定の動きを習得するために必要なコツやカンなどの身体感覚をそのプロセスにおいて置き去りにする。ここに筋トレの落とし穴がある。
コツやカンを掴むためには感覚世界に身を置くことは避けられない。自らの感覚を探りながらその動きに必要なコツやカンを捉えることが、動きの習得なのだ。そしてこの感覚世界は運動主体からすればまるで暗闇を歩くような困難さを強いられる。上達している手応えもさほどなく、練習や稽古などの取り組みそのものが正しいのかさえもあやふやになることもある。だから「感覚世界に身を置く」というのは口で言うほど容易ではない。
ここからいよいよ話が佳境に入る。
今回から感覚世界に身を置くための方法、つまり暗闇を歩くためのガイドラインを書いていこうと思う。感覚世界の見取り図なるものを示してみたい。筋トレに頼らず運動を習得するための、つまりコツやカンを掴むためのよすがとなるテクストになることを目指して。
発生論的運動学という学問がある。フッサールからメルロ=ポンティに連なる現象学をもとに、クルト・マイネルが創始したこの学問は金子明友が日本に持ち込んだ。ほとんどの運動指導の現場では、からだを機械に見立ててその性能を高めるための筋トレやストレッチ、すなわち生理学的アプローチと、運動主体の意欲を高めるための叱咤激励、すなわち心理学的アプローチに終始している。運動を習得するにはこころとからだを鍛えることが近道で、それが最善の方法だとナイーブに考えられているが、この学問はここに疑問を投げかけている。
繰り返すが、それぞれのスポーツ種目に求められる特殊な動き、すなわち「わざ」の習得にはそれに求められる感覚を掴まなければならない。だからこそパフォーマンスの際に運動主体の内面に生ずるコツやカンなどの感覚を指導することこそが、スポーツをはじめとする運動指導をする者にとっての喫緊の課題だ。理論や概念を論理的に学ぶ座学とは違い、実技指導では「わざの感じ」を掴むことが目的で、だから運動指導者はそれをこそ教えるべきで、つまり運動指導者は、感覚指導ができて初めてその役割を担いうる。こう考える発生論的運動学は、運動主体の感覚習得や運動指導者の感覚指導について詳細に研究を重ねてきた。
動きを実践するときに、運動主体の内面に生じる感覚を「動感」という。たとえば跳び箱を前にしたときに、「なんとなくこんな感じでからだを使えば跳べるはずだ」と思える人は、跳び箱を跳ぶための動感が充実している。逆に、「どんな感じで跳べばいいのかさっぱり見当がつかない」と思う人は、その動感は空虚である。料理人が手際よく包丁で食材を切り分ける作業は、包丁さばきに必要な動感が充実しているからできるのであって、普段ほとんど料理をしない人が包丁を手にしてもその動感が空虚だからぎこちない動きになり、どことなく様にならない。誤って手を切るのではないかと傍目にも危なっかしく映る。
ボールを投げる、蹴る、バットであるいはラケットで打つといった動きにもそれぞれに必要とされる動感がある。運動習得という現象そのものを厳密に掘り下げれば、この動感を充実させることが最大の目的であり、ポジティブな心構えも、発達した筋肉やからだの柔軟性も、つまりのところはこの動感の充実に収斂される。
だから発生論的運動学は、生理学的および心理学的アプローチに頼る運動指導は、結局のところ運動主体の自学自習に丸投げしているに過ぎないと批判してきた。肉体的にハードな練習を課し、意欲を高めるために励ますだけでなく、動感を発生させるための感覚指導ができて初めて運動指導者と呼べるのであり、まずもって感覚世界を熟知することが運動指導者には求められるのである。
さて、この学問の問題意識を共有したところでいよいよ感覚世界の見取り図を描いていきたい。
発生論的運動学では「身体知」という概念を基底に据えている。マイケル・ポランニーが提唱した「暗黙知」をもとに作られたこの概念は、言語化・数量化できない身体の作動の総称を意味している。たとえばラグビーならば、迫り来る相手選手の間隙を縫って走るプレーは、相手との間合いを見切り、スピードと進行方向の角度を絶妙にコントロールすることで可能となる。「間合い」、「速度調節」、「進行方向の切り替え」など言語化・数量化に馴染まないこれらのパフォーマンスが身体知の範疇に属する。この能力は反復横跳びや50m走の結果と必ずしも比例しないところがおもしろい。徒競走が速い人が鬼ごっこもうまいとは限らないわけで、運動場面をよくよく観察してみれば、運動主体がそれぞれの仕方で身体知を駆使していることにすぐ気がつくはずだ。
私たちが運動場面において因襲的に「運動神経の良し悪し」だと解釈してきたさまざまなパフォーマンスは、この身体知という概念を当てはめればより深く考察できるようになる。運動神経のよさ、もっといえば先天的に獲得された運動能力とみなしてきたものも実のところ身体知なのであり、その充実度をみることで浮き彫りになるのである。
ではさっそくその中身をみていこう。
身体知は、始原身体知、形態化身体知、洗練化身体知の3つに分けられる。
まず始原身体知は、いわばすべての動きの基本となる動感能力で、おおよそ生まれ持った能力として私たちが解釈しているものとみなしてよい。その性質からさらに体感身体知と時間化身体知の2つに分けられる。
体感身体知とは、私たちに馴染んだ言葉に置き換えれば空間認知能力とほぼ同義である。これは「今、ここ」がありありと感じられる身体知で、具体的にいうと、対象との距離がわかる遠近感能力、視覚に頼らず周囲360度を捉えられる気配感能力、自分のからだのニュートラルポジションがわかる定位感能力がある。
遠近感と気配感は、その語感から想像できるだろう。視界の内外にいる人やある物体など「対象との隔たりを感知する動感」である。たとえばバスケットボールにおいて相手ディフェンスを撹乱する効果的なパスを繰り出すポイントガードはこれらに秀でていると考えられる。自分をマークする、あるいは背後に忍び寄る相手ディフェンダー、あるいはサポートしてくれる味方選手のポジションや彼らとの距離が感知できるからこそ、最適なプレーが選択できる。隔たりがわかるからこそ自身と対象とのあいだに生じたスペース(空間)を把握できるわけだ。
スポーツ場面だけでなく日常生活においても、私たちは知らず識らずのうちにこれらの動感を働かせているように思われる。
たくさんの人々が行き交う街中を接触することなく歩けるのがそうだ。すれ違うはるか手前でその人との距離を感じ取り、右あるいは左に微妙にコースを変えているからぶつからずに済む。あるいは見通しの悪い曲がり角では、向こうから人が歩いてこないかを探るべく気配感を働かせ、また夜道を歩くときは背後から近づく人の気配に敏感になっているだろう。外部に放射されたこの動感感覚は、わずかな空気の振動で対象を認識し、物音や声の大小で距離を測っている。
もうひとつの定位感は、自らのからだのかたむきがわかる動感である。体操選手は空中でひねりを加えながらからだを回転させても着地を見事に決める。これは回転しながらに上(天)と下(地)を感知しているからできることであり、重力がはたらく地球上での安定姿勢であるニュートラルポジションからどれだけかたむいているのかがわかるから、着地の直前に身を翻して脚を地面に着くことができる。内村航平選手は、目まぐるしく移り変わる視界に、ときおりわずかに飛び込んでくる屋根の色を視認することでからだのかたむきを把握しているというから驚きだ。練習の賜物とはいえ凄まじい定位感能力の持ち主である。
当然のことながらこの定位感もまた、私たちは日常生活で発揮している。
ほとんどの人は転びそうになったときに危険を察知して、転ばないように踏ん張ったり、あるいは転んだときのために身をすくませ、手をつく準備をするだろう。「このままでは転んでしまう」という瞬時の判断は、ニュートラルポジションからのかたむきが閾値を超えたことを感知できるから下すことができる。片足立ちができるのも、沼地や砂浜を歩けるのも、この定位感が働いているからである。
この動感を私たちになじみのある言葉に置き換えれば、バランス感覚となろう。たとえば福祉の現場で問題となっている高齢者の転倒を防止するためには、まずはこの動感を充実させることを目指すべきだろう。かたむいたからだをニュートラルポジションに戻すために筋力は不可欠なのだが、それに先んじて、かたむきを感知するこの動感の衰えを回復しなければ絵に描いた餅となる。この定位感が空虚なままだと筋肉は単なる重りと化すから、ますます転倒しやすくなるわけで、まったくの逆効果となる。
不安定きわまりない二足歩行を宿命づけられた人間にとって、この定位感はなにをするにおいても充実させなければならない動感であると私は考えている。
ここまで述べてきた始原身体知は、想像力を働かせば主に幼少期の遊びの中で培われるものだと推測できるだろう。たとえば遠近感は、「鬼ごっこ」で鬼から逃げ回るなかで知らず識らずのうちに養われるだろうし、気配感は「かくれんぼ」でその隠れ場所を探り当てようとするとき、あるいは「ハンカチ落とし」でハンカチを背後に置かれた瞬間を感じ取ろうとするときに如何なく発揮されているはずだ。定位感については「木登り」や「ジャングルジム」あるいは水中で、なんとかバランスを保とうとして充実させているのではないか。
さらに遡って、まだ歩くのもままならない幼児期は、床に置かれたおもちゃやリモコンを目指してハイハイするときに遠近感を、視界にいない母親を探すときに気配感を働かせているかもしれないし、大人に抱えられて「高い高い」されているさなかには定位感が育まれているのかもしれない。相手が乳幼児なだけにその真偽を確かめることはできないが、具に観察すればこんなふうに見立てることもできる。
人それぞれに固有の仕方で感知する身体感覚は曖昧で漠然としているが、この身体知という概念をあてはめてみればその豊饒性に気がつくはずだ。身体感覚なるものは私たちの想像をはるかに凌駕する奥行きを持っている。からだを使って何かをするときに、意識するしないを問わずほぼ自動的に働いているのが身体感覚であり、体重が減らず筋肉量が増えなくとも、試合に勝っても負けても、身体感覚はその使い方に応じて豊かになってゆくものなのだ。とくに心身が発達途上の子供にとってその効果は顕著で、だからとにかくからだを使って遊ぶことはなによりも大切なのである。
次回は、「形態化身体知」について書く。特別な動きとしての「わざ」を身につけるために発揮される身体知とはいかなるものなのだろう。





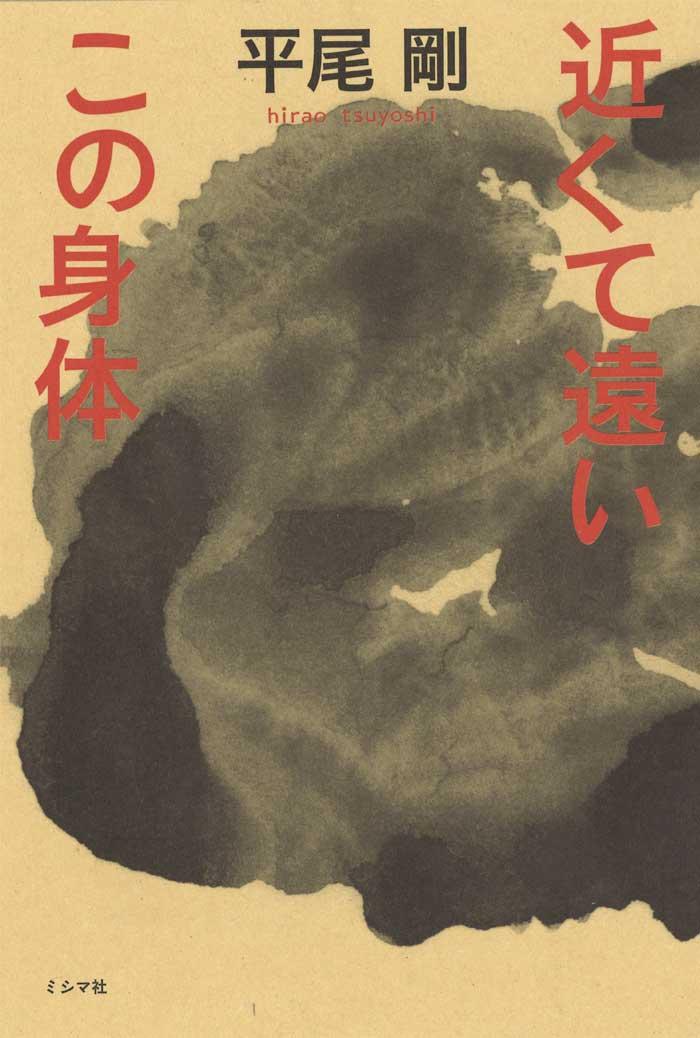




-thumb-800xauto-15803.jpg)
