第10回
身体知とは〜形態化身体知その1〜
2019.01.12更新
前回は、おおよそ幼少のころに遊びの中で培われる身体感覚を指す「始原身体知」について書いた。私たちは運動場やグラウンドで運動能力に長けた子供を目にしたとき、つい反射的に「あの子は先天的に運動神経がよい」と解釈してしまうものだが、よくよく観察するとその限りではない。定位感や遠近感、気配感といった身体知が実は働いているのであり、これらはこの世に生まれ落ちたあと、つまり後天的に充実させることができると発生論的運動学は考えている。海、川、山など自然の中で伸び伸びとからだを動かしたり、「かくれんぼ」やボール遊びなどの遊戯を通じて知らず知らずのうちに育まれる身体感覚をこの学問は的確に分析している。
こうした始原的な身体知の次に今回取り上げるのは「形態化身体知」である。これは特別な動きを身につけるための身体知であり、端的にいえばコツとカンのことだ。スポーツのみならず、料理人の包丁さばきや書道家の筆さばき、楽器の演奏など、それぞれのジャンルに求められる特別な動きとしての「わざ」を身につけるためには、コツをつかみ、カンを働かせなければならないのはいわずもがなである。「わざ」の習得に励んできたほとんどの人は、なにかを特別に意識することもなくただ感覚的に動作を反復することを通じて、コツやカンを身につけてきたに違いない。かくいう僕もその一人である。
発生論的運動学はこのコツとカンを構造分析している。
コツとカンはおおよそ同じものであると私たちは認識しているが、この両者はその性質において明確に異なる。発生論的運動学では、「骨」を語源とするコツを「自我中心化身体知」といい、論理的思考と対照を成すカンは「情況投射化身体知」という。
バスケットボールにたとえて説明すると、このスポーツの基本技術であるドリブルのコツをつかむためには反復練習が不可欠だ。鞠付きのように「叩く」のではなく、「押し込むように」して、まるで手に吸いつくようにボールを弾ませるという動きが、このスキルには求められる。そのためには肘や手の平、肩関節を柔らかく使わなければならない。腰を低く落とすことも必要だ。
このとき、当人の意識はからだの内側に向く。実際にボールに触れる腕を中心に、からだ全体をどのように使えばよいのかを感覚的に試行錯誤するわけだ。このプロセスを通じていつしかコツをつかめるときが訪れる。
そう、コツは内側からつかみとるものなのである。
ただし、ドリブルのコツをつかみ、上手くなったところでいざ試合で通用するかというと、それはまた別問題である。こちらの行く手を阻む相手選手がいて、サポートする味方選手がいる。コートのどのエリアに自分が位置しているのかを把握していなければならないし、ドリブルをするのかパスをするのかの判断を強いられる。つまりそのときどきの情況に応じたプレーが必要となる。このときの当人の意識は、そのほとんどが外側に向けられる。ドリブルを上手に行うための腕の動きに気をとられていたら、情況を把握することは叶わない。カンは、意識を外側に向けつつ働かせるものなのだ。
コツをつかむには「意識の宛先」をからだの内側に向ける必要がある(自我中心化)。これに対し、カンを働かせるには周囲へと投射しなければならない(情況投射化)。どちらか一方だけでは成り立たないのが「わざ」の習得で、コツをつかむことと、カンを働かせることを同時的に行えるようになることが運動習得のゴールである。この二律背反こそが、運動そのものを難しくもオモシロくもしている。
これらをふまえた上で、まずはコツからみていこう。
まず一つ目に、「動く感じを意図的にわかろうとする力」としての「触発化能力」が挙げられる。たとえば野球のバッターなら「ボールを打った瞬間の感じ」、バスケットボールなら「シュートを放った瞬間の感じ」、ラグビーなら「タックルした瞬間の感じ」など、そのプレーがもたらす感じを探ろうとしているかどうかがこの能力だ。
ヒットになった、シュートが入った、相手を倒せたという好ましい結果が得られたのだからそれでよしとするのではなく、あくまでもからだの実感としてどうだったのかをわかろうとすること。からだの内側に意識を向けて体感を探ろうとするこの力は、コツをつかむための土台ともなるべき身体知といえる。
こうして動く感じを意図的にわかろうとして反復するうちに、バットの芯を食ったかどうか、膝と肘が連動したかどうか、相手のからだの芯をとらえたどうかなど、うまくいったときとそうでないときの体感にコントラストが生じてくる。打球の勢いや、シュートの軌道、体勢の崩れ具合などを参考にしつつ、体感の濃淡を感じながら反復するうちに、やがて「しっくりくる感じ」がわかってくる。スムーズな動きには筋肉が隆起するような「力感」がなく、意外にも手応えがないことに気がつく。
つまり、一回一回の動きで得られる動感を評価できる。これを「価値覚能力」という。これが充実してくれば、ヒットになったけどバットの芯をわずかに外した、たまたまシュートは入ったけれど望む軌道ではなかった、相手は倒れたけれど力がうまく伝わらなかったなど、その後の帰結に引きずられることなく動きの質そのものを見極められる。ここまでくれば反復することそのものが楽しくなるだろうし、この「からだとの対話」のなかでその身体感覚はどんどん深まってゆく。
「触発化」、「価値覚」に加えて、コツを構成する能力はさらにあと2つあるのだが、それは次回に書くことにしよう。


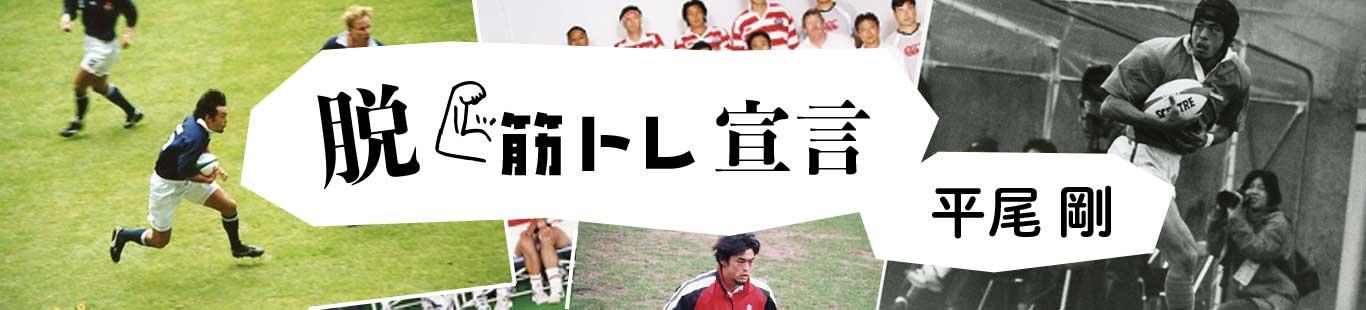
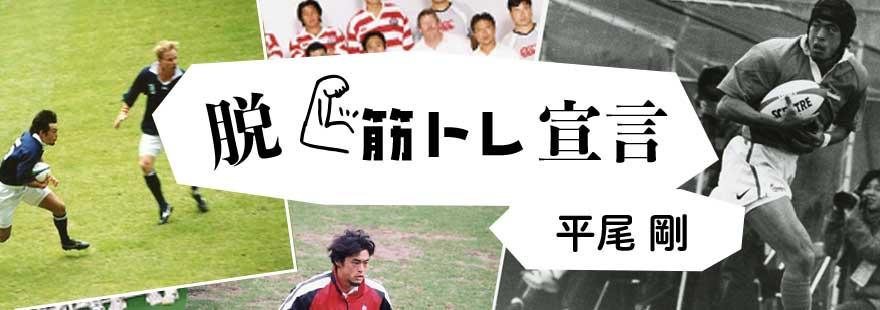

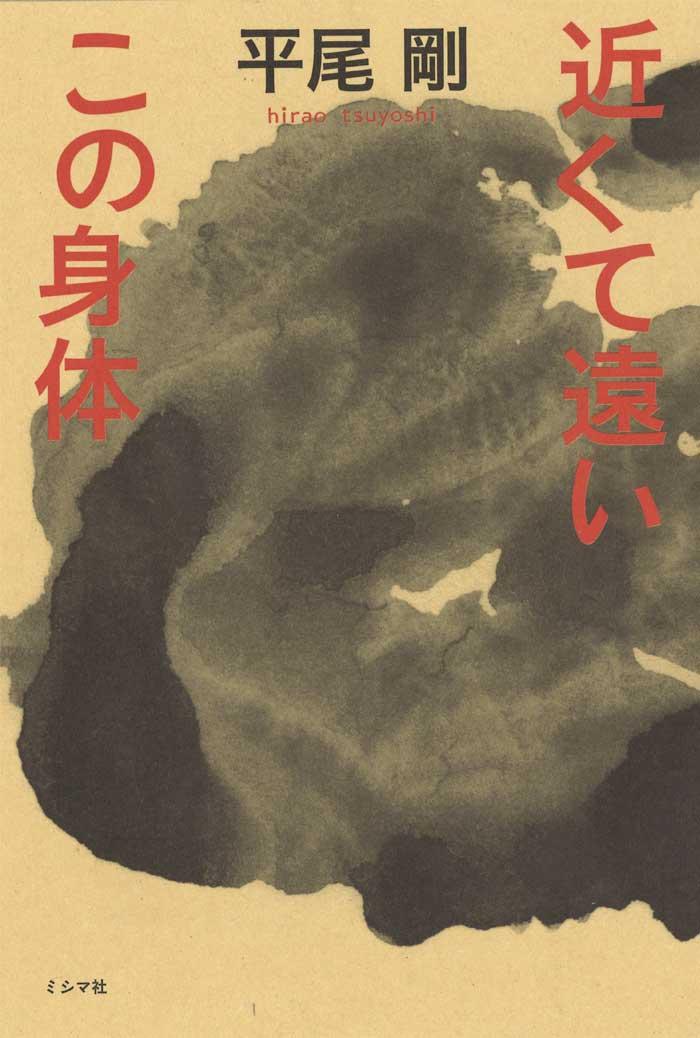


-thumb-800xauto-15803.jpg)


