第12回
身体知とは〜形態化身体知その3〜
2019.03.10更新
運動習得に必要なコツとカン。前回(形態化身体知その1、その2)までにコツを書き終えたので、今回からはカンについてその詳細を述べていきたい。引き続きこれからもいささか説明的な文章が続くことになるが、これは僕自身の筆力が未熟ゆえのことだからその点はどうかご海容いただき、最後までつき合っていただければありがたい。
繰り返しになるが、発生論的運動学ではカンのことを「情況投射化身体知」と呼ぶ。コツが自我中心的に、つまりからだの内側での現象であることに対して、カンはからだの外側、つまり自らが置かれた情況を含み込んで運動現象を捉えたときに発生する。端的にいえば、意識がからだの内側を向くときに発生するのがコツで、外側を向くときに発生するのがカンである。
これらの概念は論理的に解釈しようとすれば混乱を招くので、今回もまた具体的な場面を紹介しながら専門用語をみていくことにしよう。
カン(情況投射化身体知)は次の3つに分けられる。
① 伸長化能力
② 先読み能力
③ 情況把握能力
これらの能力はその性格からさらに2つに分けられる。
① 伸長化能力 = 徒手伸長化/付帯伸長化
② 先読み能力 = 予描先読み/偶発先読み
③ 情況把握能力 = 情況シンボル化/情況感能力
それでは詳しくみていこう。
伸長化能力とは、文字通りからだがその輪郭を飛び越えて伸びる感覚(能力)である。「徒手」というのはからだが伸びる、「付帯」というのは道具にまで伸びる、という感覚を指す。
まず徒手伸長化能力の方だが、たとえばサッカーのゴールキーパーは、背後を視認せずともゴールの横幅や高さがわかる。だからシュートを打たれてまもなくその強さや軌道をみて、ゴールの枠内から外れていればボールに触れない、枠内に収まっているからセーブする、という判断ができる。ゴールの枠外に放たれたボールにわざわざ触れるのは好ましくない。触れてゴールラインを割ればコーナーキックを相手に与えることになり、新たなピンチを招くからだ。このときのゴールキーパーの身体感覚は、からだの内外を分ける境界線としての皮膚をはるかに超えて、背後のゴール付近にまで広がっている。身体感覚が拡張しているのである。
あるいはバスケットボールのドリブルをするときもそうだ。細かく移動しながらドリブルし続けられるのは、手から離れたボール付近にまで身体感覚が伸びているからである。急加速や急停止、急激な方向転換をしてもなおドリブルできるのは、この感覚が充実していることを意味する。ディフェンスの接近によってプレッシャーを受けてもドリブルしながらキープし続けるためには、この能力を涵養することが不可欠なのだ。
ラグビー経験を通じてずっと不思議に感じていたことがある。
試合を観戦していると試合ごとにグラウンドの広さが変わって見えるのだ。カテゴリーが上になればなるほどグラウンドが狭く見える。高校生同士の試合も、オールブラックス(ニュージーランド代表チームの愛称)をはじめとする強豪国同士の試合でも、グラウンドの面積は同じであるはずなのに、主観的にはそれが伸び縮みする。
おそらくこれは、選手一人一人の徒手伸長化能力が広範囲に渡っているからだろう。どこにボールを運ばれてもそれをすぐさま察知できるという一人一人の身構えで、グラウンドに点在しているはずのスペースが塗りつぶされている。ディフェンスラインの背後には面積的に大きく広がるスペースがあるのだが、たとえそこにキックを蹴られてもすぐさま対応できるだろうという予測が、観る者に立つ。だから俯瞰的に見下ろす観客の目にはスペース(隙間、スキ)がないように映る。
野球でもそうで、たとえば外野という広大なエリアをたった3人で守っているにもかかわらず、まるで打球が飛んでくるのを予測していたかのごとくさらりと捕球できるのは、選手に備わる徒手伸長化能力が高いからだ。ここまでなら捕球できるという範囲が、カテゴリーが上位になるほど広い。自分を中心に描いた円が広ければ広いほど手つかずのスペースはなくなる。野球における守備範囲の広さはそのままこの能力に直結していると僕は思う。
この身体知は、心理学でいうところの「パーソナルスペース」とも類似している。混み合うエレベーターの中で、他人との距離が近すぎてどこか落ち着かないという経験をしたことがある人は多いはずだ。あまりに距離が近すぎると自分という存在が脅かされるかのような体感を呼び起こす。脅かされていると感じるのは、自分という存在が皮膚を境界線とする自らのからだから拡張して、周囲の環境へとせり出しているからである。「縄張り」や「間合い」と言い換えても差し支えないと思うが、私という存在は、周囲に気を張りめぐらすことで成り立っているともいえるのだ。
だからほとんどの人たちは、その落ち着かなさをやり過ごすべく上を見上げてエレベーターの進み具合をチェックする。いち早くこの場を去りたいという潜勢的な欲求を抱えながら。
さて、日常場面に目を向けてみよう。
たとえば駅のホームから落ちずに歩けるのがそうで、黄色い線の外側と内側とではその緊張感から身構えが変わるはずだ。内側だと安心できるが、外側だと人と接触するなどして落ちるかもしれない危険を察知して緊張感が増す。このとき、周囲の人との距離に敏感になり、スマホ歩きの人とぶつかるかもしれない蓋然性を想像して、私の身体感覚は半径数メートルにまで伸びている。
駅だけでなく、渋谷のスクランブル交差点や梅田の地下街など、多方向からたくさんの人が流れ込む人混みを誰ともぶつかることなく歩けるのも、この能力が発揮されていると考えられる。
昨今、スマホ歩きが社会問題となっているが、この問題についても徒手伸長化能力で説明がつく。
駅のホームに落ちる、あるいは誰かにぶつかるといった危険性については言わずもがなだが、それに加えてスマホ歩きはそうして歩く本人の身体感覚を劣化させる方向に働く。画面に意識が固着することでこの伸長化能力を発揮する機会をみすみす逸しているからだ。私たちのからだ、とくに身体感覚は、日常の何気ない場面でも使われている。刺激しなければ充実させることができないのが身体感覚であり、徒手伸長化能力が無意識のうちに情況に投射することによって育まれていることを思えば、とてももったいない。ここではないどこかに意識を向けるのではなく、「今ここ」に繋ぎとめておくこと。そうすることでからだそのものを練り上げることができる。
幼い子供は、ときに人混みの前で立ち尽くす。あるいは親と手を繋ぐことでやっと歩き出せる。心身、とくにこの徒手伸長化能力が未発達だからこれは当然なのだ。誰しもが昔は幼い子供だった。人混みを歩くといった、今となってはごく当たり前にできることも、その昔は十分にできなかった。これを思えば私たち大人のからだは実にかしこい。スポーツジムに通わずとも、科学的トレーニングに精を出さずとも、私たちのからだは身体感覚を駆使しながら日常場面を生きることによってひそかに育まれている。
と、ここまでが「徒手伸長化」能力である。
次は「付帯伸長化」だ。これは先にも述べたように道具にまで伸びる感覚である。
この感覚を極限にまで鍛え上げた選手がイチローである。彼のからだはバットと一体化しているといっても過言ではない。
大リーグに移籍後、ボテボテのゴロで内野安打を量産する彼をアメリカメディアは批判した。クリーンヒットのような爽快感を伴わない「ボテボテの内野ゴロ」を、観客をはじめとする各メディアは受け入れなかった。ホームランに無上の価値をおくアメリカならではの批判である。それに対してイチローは、わざとボテボテのゴロを打っている、バットの芯をわずかに外すことで打球の勢いを殺して内野安打にしているという主旨のコメントを口にした。これも技術のひとつであると断言した。そうして200本以上の安打を10年間打ち続けたことで彼の存在は徐々に認められ、小技を絡めてコツコツと得点を重ねる「スモールベースボール」の醍醐味をあらためてアメリカ社会に知らしめたのは有名な話である。
芯をわずかにずらす?!ボールをバットに当てることがやっとの素人には想像もできない技術である。球速に緩急をつけ、変化球を織り交ぜて投げ込まれるボールを、あの細長いバットに当てるのでも精一杯なのに、打点を精密にコントロールできるというのだからさすがプロフェッショナルだ。
この技術は、バットをまるで自分のからだの一部のようにフレキシブルに使える身体感覚があってこそ成立する。腕を動かすように、あるいは指先を使うような感覚で操作できるのは、バットが身体化していなければ不可能だ。イチローは、大きく曲がったあとにワンバウンドしたボールすらヒットにできる。それほどにバットがからだの一部と化しているのである。
テニスプレイヤーが打つ瞬間にボールをこすり上げて回転を掛ける技術もそう。ゴルファーがドローやフェードを打ち分けるのもそう。彼らの身体感覚はラケットおよびクラブにまで伸びている。指先でなにかをつまむような確実な身体実感をもってそれらの道具を使っているのである。
この能力もまた日常場面で生かされている。
書き慣れたペンを使うときとそうでないときの感覚差が実感できる人は、この能力を発揮しているといえる。常日頃から使用しているペンが書きやすいのは、太さやペン先の柔らかさなどにからだが馴染んでいるからである。握ったときのなんともいえない落ち着きは、指先とそのペンとの境界がなく、まるで自分のからだの一部になっていることの証左である。どの指にどれくらい力を入れればよいのかがわかっている。というよりも、そんなことをわざわざ意識せずとも自然に握ることができる。
履き慣れた靴、着こなした服、長年かけ続けた眼鏡、アクセサリーなど、これらを身につけたときとそうでないときの身体感覚を比べると明らかな違いがあることに気がつくだろう。自動車もそうだ。運転に慣れたマイカーはアクセルやブレーキの踏み具合、車幅感覚がわかる。だが、レンタカーなど乗り慣れない自動車を運転するときにはそれがわかりづらい。しばらく運転するうちに馴染んでくるだろうが、それは道具としての自動車に自らの感覚を伸ばすことができるようになったからだ。「私が自動車を運転する」という主従関係ではなく、「私と自動車が一体化する」という並行的で融合的な現象がここには生起している。
この感覚差に注意を向けるだけで付帯伸長化能力はより充実してゆく。僕がラグビー選手だったころに口酸っぱく言われた「道具にこだわりを持て」という助言は、ここにその真意があったのだと今になって思う。
イチロー選手は他人のグラブやバットに触らないそうだ。たとえわずかであっても他人の感覚が手に残るのが嫌なのだという。当然イチロー選手は発生論的運動学を知らない。プロフェッショナルと呼ばれる人たちが自らのからだを通して辿り着いた経験知には、私たちが学ぶべきことがたくさん詰まっている。
(つづく)





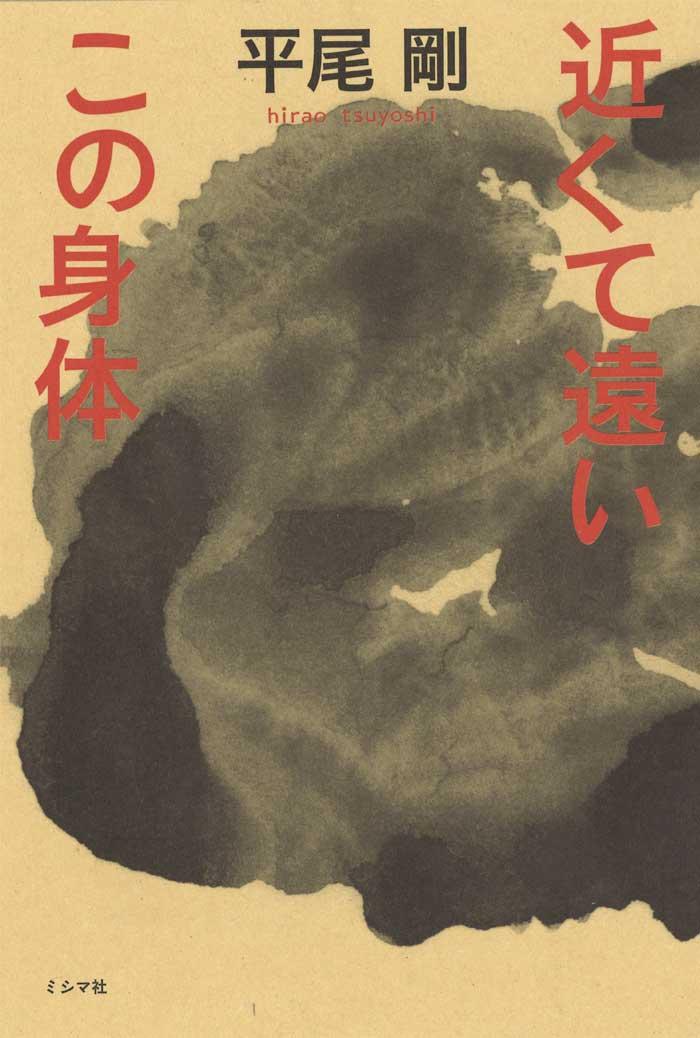




-thumb-800xauto-15803.jpg)
