第4回
崖の上の歌(1)
2025.05.20更新
山に入るとすぐに、風化した石灰岩の石垣が目に入る。木の根が絡みつき、苔むして青ずんだ様子は自然物のようにもみえるけれど、いまから六百年以上も前、ここに城があった頃に造られたものだ。そばには太い根を岩に張りめぐらせ、天に差し上げた枝から何本も気根を垂らした大きなガジュマルの樹がそびえている。この山の主のようだ。
下生えと朽葉に覆われた山道を登ると、からりと開けた場所に出る。その隅に一本だけ、すっくりと伸びたパパイヤの木。斜面に生い茂るクバの樹冠を透かして、下界に船越の集落が見える。
ここには十四世紀の半ば頃から十五世紀の初頭まで、この土地を治めていた
湧上さん 〔この近くの〕
糸数 グスクがですね、尚 巴 志 の配下に攻められて、それを加勢しにここ〔船越城の按司〕も出ていったわけですね。その時にやられたみたいですね。そして、やられたもんだから、その人の妹の祝女 さんは......向こう側に祝女井泉 といって、祝女がよく使ってた井戸があるんですが、自分の兄さんが亡くなったから、それを悲しんで、毎日この井戸に来て泣いていたという。それで、祝女井泉というのを、涙 泉 と〔名前を〕つけてあるんです。井戸はもう形もなくなっていますけんどね(2)。
十五世紀の初め頃、この辺りの山々は群雄の割拠する戦場だった。船越城は当時、その南東に位置する糸数城の支城としての役割を担っていたらしい。糸数城が尚巴志の配下の軍に攻め込まれたとき、救援に向かった船越按司の軍はこの山で敵軍と戦って敗れ、按司は討ち死にしたといわれる(3)。
そして時代は下り、二十世紀の半ばにこの場所はふたたび戦場になった――前とは比較にならない規模で。
湧上さん ......それで、この辺一帯には陣地はないけれど、
暁 部隊というのが留守兵として、〔首里方面の〕戦場に行かんで、ここにいたんです(4)。――この場所にいたんですか。
湧上さん はい。この辺の山一帯ですね。そんで、それ〔暁部隊の兵士〕が動きまわるもんだから、ここに特に〔米軍の〕弾が来て。
ここに船越の区民の壕があるんですが、ここで二、三名ぐらい、弾に当たって亡くなってるんですよ。
一九四四年三月、南西諸島方面の防衛強化を目的として、沖縄県に第三十二軍が創設される。それ以降、沖縄諸島における軍の配備はめまぐるしく変転したが、船越の位置する
一九四四年七月中旬、玉城村に第九師団(
この年の十二月から翌年の一月にかけて、フィリピン・レイテ決戦を重視した大本営の要請によって、沖縄の基幹兵力であった第九師団が台湾に転進する。かわって玉城村には第六十二師団(石部隊)歩兵第六十四旅団独立歩兵第十五大隊が移駐し、船越にはこの大隊の一個中隊と独立速射砲第三十二中隊が駐屯した(7)。
一九四五年三月二十三日、玉城村を含む沖縄諸島の各地は米軍による激しい空襲に見舞われ、翌二十四日には港川沖に米軍艦隊が現れて艦砲射撃を開始する。同月二十六日、
同年の五月以降、首里方面の戦闘に敗れた部隊の残存兵や他地域からの避難民が、米軍の進攻に押されてこの地域に続々とやってくるようになる。五月の下旬になると、県道を通って南部へ向かう兵士や避難民の動きにつられて、船越から前川へ、さらに雄樋川を渡って
湧上さん ここに隠れて、向こう〔首里〕からの避難民がずっと〔摩文仁の方へ〕行くのを見てるわけですね、区民は。それで、危なくなったなということで、〔避難民に〕ついていったという説があるんですね。
それ以外に、もうひとつの説は、ここに暁部隊兵がおったもんだから、上から米軍はそれを見て、機銃掃射した。それにびっくりして区民の皆さんも一緒に逃げていったという(10)。〔...〕その方が、大きな要因じゃなかったかなという気がしますね。
按司の屋敷があったという高台からは、船越の集落の向こうに遠く八重瀬岳を見晴らすことができる。それは、戦時中に避難民たちの向かった方角だ。この山に隠れていた船越の人びとは、眼下の県道に連なる避難民の群れを見て、あるいは山に潜む部隊を狙う敵の攻撃に巻き込まれることを恐れて、山を下りて南へと向かっていったのだろうか。その行先が、やがて最も危険な戦場になることも知らずに。
湧上さん そのときに、うちの祖父はまた道に出てね、道端の畑でイモを収穫なんかしていますからね。船越の住民が〔南へ向かって〕行くのに......。
――それを見てらしたわけですか。
湧上さん 〔祖父は〕「ここにいたほうがいいよ」と言いよるけんど、みんな行きよったと。
――でもそんな、こっちで機銃掃射なんかに遭ったら......。
湧上さん 向こうからね、〔米軍に〕攻めやられたもんで。
――おじいさんはよく落ち着いて、イモを収穫してられましたね。
湧上さん そうですねえ。
ふたたび山道を下りて、山裾を巻く道路をさらに北に向かって歩く。この道は、かつて上山にあった
山裾の窪みに、泉が暗く光っている。いまも使っている人がいるのだろうか、奥に小さな香炉が設えられている。
――水が豊かですね、いまも。
湧上さん そうですね。子どもの時は、ここは一人では歩けなかったです、怖くて。
――怖くて?
湧上さん はい。木が鬱蒼としてましたからね。
やがて私たちは道路から逸れて、センダングサの群生する薮を踏み分けて山の中に入った。どこかで鶯が鳴いている。
湧上さん こういう岩があります......向こうにもこれがあるんですね。壕の入り口は、ちゃんと見えないかもしれないが。
山裾の斜面に張り出した岩の陰に、よく見ると幅の狭い洞穴がいくつも口を開けている。その一部は土砂に埋もれ、一見しただけでは穴があることには気づかないだろう。
――これはその、掘ったんですか、住民が。
湧上さん そうですね。当時は掘って。〔...〕こういう岩陰に、あっちこっち〔避難壕を〕作ってるんです。
屈んで覗き込むと、穴は思ったよりも深く、その奥を見通すことはできない。
湧上さん じつはここは、うちの土地だったんです。〔...〕そういうことで、よくここを通ってました。そして、〔当時〕ここにおった人は、お父さんは
馬 車 持 ち 。――バサムチャー?
湧上さん 荷馬車でね、荷を運んでいるんです、あっちこっちに。それで、その家の息子は当時、〔国民学校の〕高等二年生。
その息子はお父さんと一緒に、美田連隊に弾薬を運ぶ仕事をやってたんです。そして、それ〔運搬している間〕は助かったんだけど......。
私たちの立っている道の、壕の前あたりの空間を指して、湧上さんは言葉を継ぐ。
湧上さん ここに弾が飛んで。
――ここに?
湧上さん はい。ここでこの人、亡くなってるんです。
その奥に洞穴を隠した岩肌を見、目を上げて周囲の木立を見る。この場所にかつて銃弾が飛び交い、ここで誰かが倒れた。その痕跡は、でも、どこにも見つけられない。
(つづく)
(1)按司とは、十二世紀から十五世紀にかけてのグスク時代に各地の村落共同体を支配していた有力者のこと。十三世紀になると城塞としてのグスクを築き、互いに勢力抗争を繰り広げた。十四世紀頃には「世の主」と呼ばれる強力な按司が現れ、沖縄本島の北部・中部・南部にそれぞれ城を築いて小国家を形成した。十五世紀には最も有力な按司であった尚巴志が三山を統一し、琉球に統一国家が誕生した。沖縄県立総合教育センター「琉球文化アーカイブ」参照(二〇二五年五月四日閲覧)。
(2)本章に登場する湧上洋さんの語りは、二〇二四年三月七日に南城市玉城船越で行ったフィールドワークの録音記録に基づいている。
(3)船越誌編集委員会(二〇〇二:三一)、遠藤編(二〇〇二:一七二−一七五)参照。
(4)一九四五年二月中旬以降、港川と近隣地域に展開していた海上挺進第二十八戦隊と海上挺進基地第二十八大隊のことかと思われる。海上挺進第二十八戦隊は四月末に豊見城村高安に移動したとされるが(『南城市の沖縄戦 資料編』専門委員会 二〇二〇:四四二)、湧上さんによれば、船越にはそれ以降も数隻の舟艇が残されており、少なくとも五、六名の兵士が上山に残存していた可能性がある。これらの部隊については知念村史編集委員会(一九九四:五九−六五)、船越誌編集委員会(二〇〇二:三八二)、玉城村史編集委員会(二〇〇四:一〇七)、『南城市の沖縄戦 資料編』専門委員会(二〇二〇:四三八−四四三)、「糸数アブチラガマ――沖縄戦の実相を現在に伝える」参照(二〇二五年五月四日閲覧)。
(5)船越誌編集委員会(二〇〇二:三八一)参照。
(6)『南城市の沖縄戦 資料編』専門委員会(二〇二〇:五五三)参照。
(7)独立歩兵第十五大隊は一九四四年十二月七日から翌年の二月一日まで玉城村に駐屯した。『南城市の沖縄戦 資料編』専門委員会(二〇二〇:二三六)参照。
(8)船越誌編集委員会(二〇〇二:三八一−三八二)、玉城村史編集委員会(二〇〇四:九八−九九、一三五)、『南城市の沖縄戦 資料編』専門委員会(二〇二〇:三八六−三八七)参照。
(9)玉城村史編集委員会(二〇〇四:一三五−一三九、一六三−一六四)、『南城市の沖縄戦 資料編』専門委員会(二〇二〇:五五七−五五八)参照。
(10)『玉城村 船越誌』にはつぎのような記述がある。「六月三日、米軍は、その日の午前中に糸数区まで進攻し、糸数
参照文献
遠藤庄治編 二〇〇二『たまぐすくの民話』玉城村教育委員会。
玉城村史編集委員会 二〇〇四『玉城村史 第六巻 戦時記録編』玉城村役場。
知念村史編集委員会 一九九四『知念村史 第三巻 戦争体験記』知念村役場。
『南城市の沖縄戦 資料編』専門委員会 二〇二〇『南城市の沖縄戦 資料編』南城市教育委員会。
船越誌編集委員会 二〇〇二『玉城村 船越誌』玉城村船越公民館。


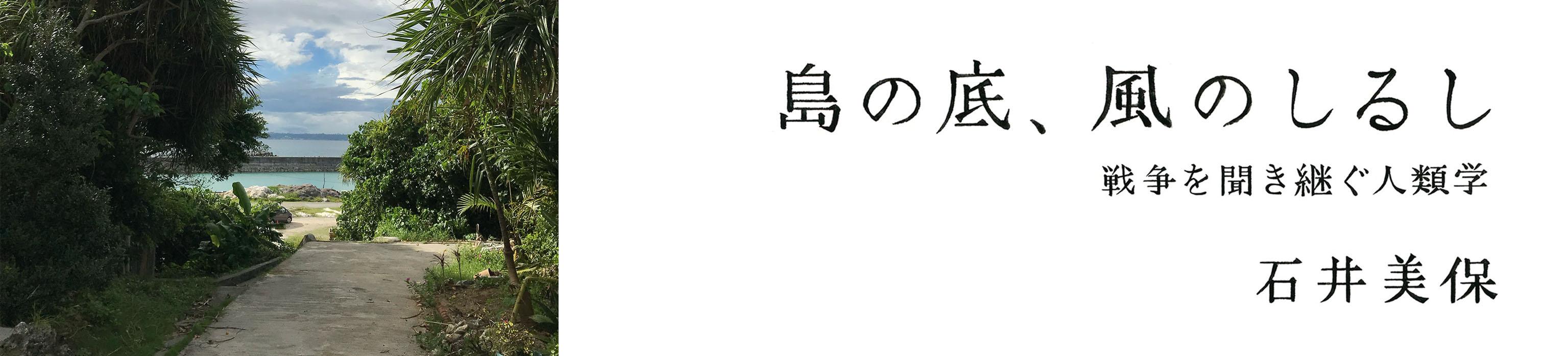



-thumb-800xauto-15803.jpg)


