第6回
砂糖小屋のリズム(1)
2025.07.23更新
戦前の暮らしについて話しているとき、二人の表情は晴れて、口元はほころぶ。それぞれに思い出をたどり、互いに補足しあうやりとりを通して、当時の船越と前川の景色が浮かんでくる。それらは互いに相似ていながら、対照的な特徴をもった集落だ。
前川集落の中央部、
戦前のランドマークを記した地図を片手に一帯を歩いてみると、昔の集落の構造がよくわかる。もっとも標高の高い、集落の北端には
興味深いのは集落の西端だ。そこにはクムイと呼ばれる池があり、そのほとりには村芝居のかかる
――この芝居場っていうのはどんな?
ユキさん ここは、そばにちょっとおうちがあって。テントが。
――ここで芝居をやってたんですか。
ユキさん うん。昔はね、こんなにしているから、〔土手の〕下で踊って、みんなこうして、お客さんに観えやすいように。それでバンク〔舞台〕と。〔...〕そこで村芝居とか何かを。
このあたりの集落では年に一度、葉月の十五夜に
――へえー、面白い!
ユキさん そこにね、池が掘られていたわけ。〔...〕戦争前には、この池のそばにはね、松が植えられてからに、あれだった。そこは斜めになっているからよ、子どもたちの遊び場になっているわけ。滑って。
――ここに松があったんですね。
ユキさん 滑り台の代わりに滑りに行きよった(笑)。遊びに。〔...〕松がよ、この池のほとりはみんな植えられてるの。ムルマーチ〔全部の松〕。
して、兵隊が、死んだ人がいたわけ。そこでね、焼いていた。アンサーニ〔そんなことがあって〕からよ、ウマナーデージ〔ここは大変だから〕といって、子どもたちも遊ばなくなったよ。人を焼いてるの。――怖いからですか。
ユキさん キブヤープープー〔煙がぼうぼう〕して、人を焼いて、兵隊さん焼いているわけよ。
――それ、ここですか。このバンクのそばの池で?
ユキさん そう、そこで。それからもう、そこで子どもは。
その芝居場から南に少し下ったところには、
ユキさん ハカチモーと言って、名があるわけ。だからうちのおばあちゃんが、「この道からあっち側に、絶対におうち造らせてはいかんよ、子孫には」と言って、私に言われていたわけ。〔...〕ここがね、みんなお墓だったはず。
いまでは空き地になっているハカチモーの跡を通り過ぎて坂道を下っていくと、県道十七号線に出る。ここは集落の南西の端で、道路の向こうには畑が広がっている。その畑と道路の境目に、かつてこの場所にあった
県道を越えた農地の、さらに西側にはカーヤマと呼ばれる崖があり、亜熱帯の樹々に覆われた急斜面の崖の底には北から南へと蛇行しながら
こうした前川の地理的な環境――太平洋を望む高地の斜面につくられた集落と、近くを流れる雄樋川、カーヤマの崖とヒージャーガー――は、やがて戦争が激しくなってきたとき、前川の人びとと日本軍の両方にとって重要な意味をもつことになる。
ありし日の芝居場について語るユキさんの言葉には、松林の土手を滑り降りて遊んだ思い出の中に、異質で不穏な光景の記憶が顔を覗かせていた。戦前、集落の人びとが村芝居を愉しみ、子どもたちの遊び場になっていた池のほとりは、一九四四年の夏以降にこの地域に駐屯した日本軍によって火葬場に転用された(6)。ユキさんよりも一歳年上の勲さんの記憶に残っているのは、すでに様変わりしてしまったバンクの風景だ(7)。
勲さん 戦前はね、ここに大きな松が五本あって、その下に池があって、その松を後ろに舞台を作って、そこで村芝居したという話は聞いた。だけど、もう戦前の、私たちの記憶はないね。〔...〕ここはね、昭和十八年くらいからもうね、村芝居どころじゃないですよ。もう戦時が。〔...〕
ここでね......日本軍はここで火葬もしたんですよ、この松の下で。あの、亡くなった兵隊をここで火葬してね。憶えているよ。私はまた家が近いからね、見に行って。日本兵がこう銃を持って立って、「向こうに行くな」と言って。変な匂いがしよったわけさ。――それは、病気で亡くなったんですか。
勲さん そうでしょう、〔まだ〕戦争ではないから。病死だと思いますよ。
そんな風に、軍の存在はやがて集落のあらゆる場所に入り込み、子どもたちもそれと無縁ではいられなかった。でもそれは、まだ少し先の話だ。
(1)前川集落は、中央部の仲地原、西部の石川原と屋繰原、東部の長田原と大道原をはじめとする複数の地区からなるが、集落の家のほとんどは仲地原に位置している。この地区は、一七三六年頃に首里王府の認可を受けて構築された、「碁盤の目」型の構造をもつ集落である(玉城村前川誌編集委員会 一九八六:三−四、二六−三二、山元 二〇一九:一三一−一三三)。
(2)戦前の前川は、集落の北側から東側を取り巻く丘陵と、それに連なるように南東から南側に植えられた松林からなる
(3)以下に引用した徳田ユキさんの語りは、二〇二四年三月三日に南城市玉城字前川にて行った聞き取りに基づいている。
(4)村遊びは元来、集落に祀られた神々に五穀豊穣を祈願する奉納芸能としての意味をもっていた。一方、組踊は台詞と音楽、舞踊からなる琉球の古典劇であり、中国の
(5)前川と船越の村遊びについてはそれぞれ、玉城村前川誌編集委員会(一九八六:二五二−三〇三)、船越誌編集委員会(二〇〇二:二八一、三〇〇-三〇一)参照。
(6)一九四四年の夏頃から一九四五年の春にかけて、前川には複数の部隊が次々に駐屯した。一九四四年の七月より、玉城村には第九師団(武部隊)第十九連隊第一大隊が駐屯し、前川には一個中隊が配置された。一九四四年の十二月以降に第九師団が台湾に転出すると、玉城村には第六十二師団(石部隊)歩兵第六十四旅団独立歩兵第十五大隊が駐屯し、前川には第四中隊が配置された。さらに一九四五年の二月初旬にこの部隊が浦添村・那覇方面に移駐すると、玉城村には同年の四月まで独立混成第四十四旅団第十五連隊(球部隊)が駐屯し、前川には第三大隊が配置された(玉城村史編集委員会 二〇〇四:八七-八、九八−九九、沖縄県立埋蔵文化財センター 二〇一五:二五七、『南城市の沖縄戦 資料編』専門委員会 二〇二〇:二三六)。玉城村前川誌編集委員会(一九八六:四一八)によると、前川に駐屯していた武部隊の一般兵はハカチモーの広場にテントを張って野営していたという。このことから、ハカチモーと隣り合ったバンクを火葬場として使用していたのは武部隊の兵士であったと思われる。
(7)以下に引用した大城勲さんの語りは、二〇二五年七月一七日に前川で行った聞き取りに基づいている。
参照文献
沖縄県立埋蔵文化財センター 二〇一五『沖縄県立埋蔵文化財センター調査報告書 第75集 沖縄県の戦争遺跡――平成22〜26年度戦争遺跡詳細確認調査報告書』沖縄県立埋蔵文化財センター。
玉城村史編集委員会 二〇〇四『玉城村史 第六巻 戦時記録編』玉城村役場。
玉城村前川誌編集委員会 一九八六『玉城村 前川誌』玉城村前川誌編集委員会。
當間一郎 n.d. 「組踊」『日本大百科全書(ニッポニカ)』(二〇二五年七月二十一日閲覧)。
『南城市の沖縄戦 資料編』専門委員会 二〇二〇『南城市の沖縄戦 資料編』南城市教育委員会。
船越誌編集委員会 二〇〇二『玉城村 船越誌』玉城村船越公民館。
矢野輝雄 二〇〇一『組踊への招待』琉球新報社。
山元貴継 二〇一九「沖縄本島・玉城前川の村落構造と「抱護」」鎌田誠史ほか編『「抱護」と沖縄の村落空間――伝統的地理思想の環境景観学』風響社、一二九--一五〇頁。


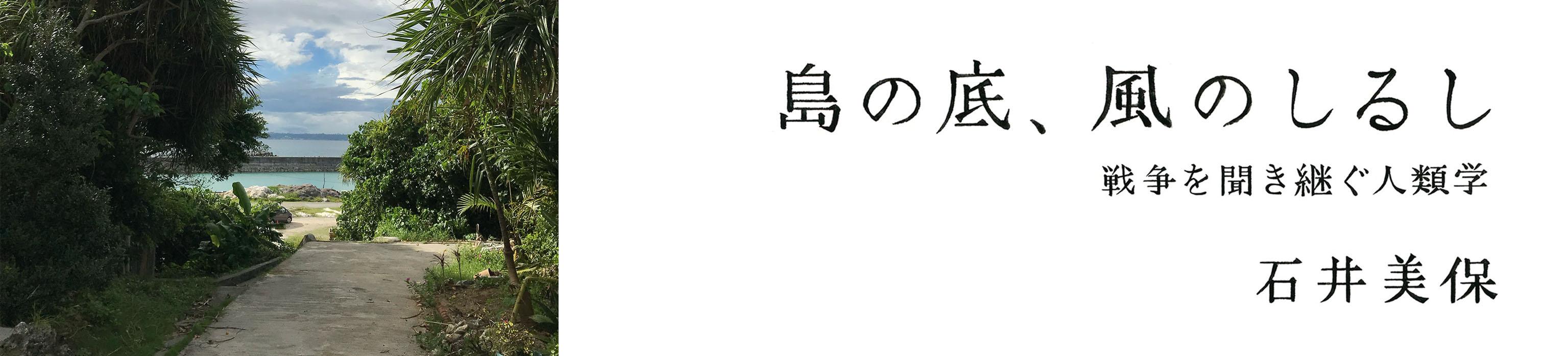



-thumb-800xauto-15803.jpg)


