第9回
西の果て、黄泉の国(2)
2025.10.21更新
死者の名前と命日を墨書した白旗が風にはためき、前卓持ちの運ぶ白位牌に差し掛けられた黒い傘が、空中を揺れながら動いていく。縁者や参列者たちの後を、棺箱を乗せた龕がしずしずと進み、頭に芭蕉衣を被った女性たちがそれに続く。行列の最後尾に、人びとから少し離れて、一人の男が鉦鼓を打ち鳴らしながらゆっくりと歩いていく(1)。念仏者だ。
湧上さんは戦前、船越の葬式に来ていたニンブチャーのことを憶えている(2)。
湧上さん ニンブチャーというのはですね、ある意味では......。その集落であんまり働きのない人が〔なる〕、ニンブチャーというのは、みんなからあんまりよく言われてない。
――普段はちょっと差別されているような感じの?
湧上さん うん、そういう人たちですからね、それは限られていたんですかね。
鉦鼓というのがあってですね、これを叩くんです。「ケン、ケン、ケン」というんですけどね。〔年中行事の〕綱引きでもケンゲン、ケンゲン。これが綱引きの中心になるものです。ケンタンケレレン、ケンタンケレレンとかいう。ただ、葬式の場合はそういうにぎやかな音じゃなくて、ケン――ケン――と、なんとなく物哀しいような感じで、ケン、とやる人なんです。
それで、普通の人からちょっとあんまりいい感じで見られてない人が、それをやって。結局、それをやることによって、お金がもらえるわけですね。――船越にはいなかったですよね、ニンブチャーは。
湧上さん いました。
――船越に住んでる人で、いたんですか。
湧上さん はい。でも、ほとんどがよそから来ましたですね。たまにおったわけです。
ニンブチャーというのは、首里のアンニャ村だったかな、向こうに物乞いみたいな集団があってですね。そこのグループの人が、龕と一緒に来よったんです。〔...〕
ニンブチャーはですね、龕、死者を乗せる籠の後ろについて、最後尾で、ケン、ケン、してゆっくり動く。なんとなく哀しいような感じがするんです。
湧上さんの話に出てくる首里郊外のアンニャ村は、遅くとも十八世紀初頭から戦前に至るまで、ニンブチャーたちの根拠地とされていた場所だ。彼らは、あちこちの村の葬式で鉦鼓を叩き、墓前で念仏歌をうたい、僧侶の代わりに経文を唱えることもあった(3)。
興味深いのは、このアンニャ村にはニンブチャーだけでなく、チョンダラーと呼ばれる門付け芸人たちも住んでいたということだ。彼らはほうぼうの村に出かけてゆき、祝儀や法事のある家々をめぐっては祝い歌や念仏歌をうたい、仏と呼ばれる人形を使った人形芝居を演じて、心付けを乞うていたという(4)。
首里の町外れに住み、村から村へと移動しながら芸を披露し、歌をうたう。してみると、ニンブチャーとチョンダラーの役割の間には、ほとんど違いがないようにみえる――というより、実のところ、この二つは別々の集団ではなく、アンニャ村に住む同じ人びとに対する異なる呼び名であったらしい。葬式に呼ばれて鉦鼓を叩くときにはニンブチャー、家々をまわって門付け芸を行うときにはチョンダラー、というわけだ(5)。
いずれにしても、ニンブチャー、またはチョンダラーと呼ばれていた人びとは、特殊なわざと力をもつとされる宗教的な職能民であり、芸能集団だった。儀礼におけるその役割は、神仏の聖性と死の穢れの両方にふれるような、境界的な領域にかかわっている。だからこそ彼らは、一般の人びとから離れて暮らし、ふだんは人びとから忌避され、畏れられ、ときに蔑視されてもいたのではないだろうか。
死者を黄泉の国へと運ぶ龕。その行列の最後について鉦鼓を叩いていた人は、よそ者であり、逸れ者であり、境界に住まう者だった。前川の龕屋はかつて、集落を野から隔てる道の向こう側に立っていたけれど、それも故のないことではないのだろう。死者たちの力と、穢れへの畏れ。村の地理的な中心と周辺は、社会的で観念的なそれらと重なりあっている。
大城勲さんの記憶にあるのは、その前川で戦後、まだ龕が活用されていた頃のことだ(6)。
――きのう湧上さんが、船越で昔、葬列の最後で鉦鼓を叩いていた人〔ニンブチャー〕のことをおっしゃっていて。前川にもいたんですか、そういう人って。
勲さん 専門にする人ではないが、〔集落の〕各班で葬儀をするんだから、各班の誰かがやるわけ。前川の者では、一人に決まった人というのはなかったみたいですね。
村のウッチュー〔小使い〕と言ってね、識名グヮーのおじいと言ってね、独り者のおじいがいたから、戦後はあの人がやりよったけど。昔はニンブチャーという、その職業があったみたいですね。〔...〕だけど、前川では誰それがその職業だということは、聞いたことはないね。湧上さん 前川の場合は龕があるから、それと一緒になっておるんですよ。船越には龕がないわけですよね。〔だから〕前川から借りたり、大城から借りたりする。大城から借りる場合は、ニンブチャーといって、その人もあの辺からついてきてね、やっていた。
――龕を借りる時には、そういう人が呼ばれて来るんですね。
勲さん 前川も、〔龕を貸したときに〕ついていく人はいるよ。だけど、この人が向こうで、ニンブチャーとして鉦を打つわけではない。龕も、物だから壊したりするさーね。だから、龕佐事という人がいたんですよ。部落のウッチュー。ウッチューといったら、いまの用務員。年配のおじいさんだったが、この人が、〔たとえば〕船越で亡くなった人がいて、〔前川の〕龕を貸すということになれば、ついていくんですよ。で、船越に行ったり、目取真とか湧稲国とか〔に行ったり〕。あの辺は龕がないから、前川から借りよったんですよ。
――ちゃんと壊さないように、その人が見ているわけですか。
勲さん はい、ちゃんと。あれ、部品がいっぱいあるんですよ。あれ一つでもなくなっていたら、もう、まさに大変だった。
龕は人が葬式で担いでいるときと、普通の、龕屋に置かれているときとは違うんですよ。人が入るときは全部バラして、あれ〔部品〕を組み立てて、高くして。普通はもう、低くてね。で、人が入るときは棺箱があるから、柱が四本か五本、六本ぐらいあったかな。その上に屋根が載っかるんですよ。だから、部品が何個かあるから、これ一つでもなくしたら、もう大変なことになる。それをちゃんと管理するには、付き人がいないと。
獅子頭と引き換えに糸数の龕を手に入れたという明治の中期以降、前川の集落には龕があった。一方で、龕をもたない集落からすれば、ムラで誰かが亡くなったとき、死者を墓地へ、また黄泉の国へと運んでくれる龕が、付き人やニンブチャーとともに共同体の外部からやってくるということは、それ自体が意味深いことだったのではないだろうか。
集落の外からやってくる特別な乗りものに乗って、故人は馴染み深い土地を離れ、二度と戻ることのない旅に出る。死者を運んでゆく龕は、それ自体がムラとムラ、此岸と彼岸の往還の中にあり、わけてもそれが高く組み上げられているときには、いつも旅の途上にあった。その外部性と移動性、異界との近しさは、ニンブチャーやチョンダラーと呼ばれた人びとのそれと似ている。
正月の月中にChundarāなるものが、シマの長者を訪れて祝福して立去った。今から二十四五年来は彼等は絶えて来なくなった。
彼等は長者の家の庭で小鼓を打ち歌を歌いながら、箱の中で人形を躍らせた。島の老幼男女は長者の家の庭に集って之を見物した。歌舞がすんでから長者の家では、彼等を二番座(仏間の隣室)に招じて御馳走(豚料理)し、米を与えて帰した(7)。
民俗学者の佐喜眞興英が一九二五年に上梓した『シマの話』には、二十世紀初頭の沖縄本島中部、新城におけるチョンダラーの来訪と長者による歓待の様子が、そのように描かれている。
この記述を読んで思いだすのは、長らく調査をしていた南インドの村のことだ。
トゥルナードゥと呼ばれるこの地域では、「ブータ」と総称される土着の神霊が古くから祭祀されていた。村の祭りでは、パンバダやナリケといった特定のカーストの男性たちが神霊になりかわって踊り、領主たちに祝福を与え、人びとからの供物を受けとる。彼らは神霊の憑坐として、村人と神霊のやりとりを媒介する役割を担う一方で、ひと昔前までは村の中で周辺的な立場におかれていた。当時、彼らはほかの村人たちと共食することも許されず、集落から離れた場所に暮らしていたという。
そしてまた、思いだされるのはスッバという名の一人の老人のことだ。彼は独り者で、定職をもたず、よく昼間から酔っ払っては村の通りをぶらついていた。そんな彼はしかし、年に一度だけ催される「カンブラ」と呼ばれる農耕儀礼では、その中心となる司祭の役割を担っていた。儀礼の前夜、スッバはたった一人で山に登り、その頂上に立って野生のスイギュウの神霊を呼びだす。そして翌日、里に戻ってきた彼は生身のスイギュウを駆って代田の中に走り込み、領主たちの前で踊りを披露するのである(8)。
彼らに共通しているのは、人間を含むあらゆる生きものを生かし、また死に至らしめるような豊饒で危険な野生の力に、ほかの人びとの代わりにふれる役割を担っているということだ。生命を育む豊饒な力の現れを祝福として人びとに分け与える一方で、死にかかわる危険な力の現れは、共同体の外部に運び去る。人の世の外からやって来てはまた去りゆく、人間にとっては不可知の力をその身に引き受け、人びとの眼前にいっとき顕現させ、その流れを方向づける。
神霊の憑坐として、その力の容れものとなり、乗りものともなる彼らは、ニンブチャーやチョンダラーと呼ばれていた人びとと同じように、常ならぬ力を帯びた存在として畏れられ、隔てられ、周辺化されてもいた。
やがてこの島を襲った戦火によって首里の都が壊滅したとき、アンニャ村も焼失し、二度と再建されることはなかった(9)。
アンニャ村の消滅は、その住民たちの体現していた世界、両義的な野生の力が村々の底を流れ、浸していた古来の世界の終焉を意味していたのだろうか。ときに差別や迫害を受けながら島の各地を漂泊していた彼らにとって、それは一面において、旧い身分からの解放としての意味をもちうるものだったのだろうか。それともそれは彼らにとって、居場所と生業と縁のすべてを喪失し、社会の底辺からさえも追放されることを意味していたのだろうか――もしも彼らのうちのいくたりかが、戦火を越えて生き永らえていたとしても。
そのことを確かめるすべを、私はもっていない。けれども彼らの存在を知ったいま、野辺送りの行列のしんがりで、もの哀しげな音色で鉦鼓を打ち鳴らしていたその人の姿は、南インドの村で出会った小柄な老人、いまは亡きスッバの面影と重なりあっている。
(1)船越における伝統的な野辺送りの様子については、船越誌編集委員会(二〇〇二:三一六−八)参照。
(2)以下に引用した湧上洋さんの語りは、二〇二四年十月十八日に南城市玉城船越で行った聞き取りに基づいている。
(3)島尻(一九八三:一四二)、玉城村前川誌編集委員会(一九八六:三四一−三四二)、知名(二〇〇八:三七八−三八二、二〇二一:二〇三−二〇九)、那覇市歴史博物館(二〇二五)参照。
(4)宮良(一九八〇)、当間(一九八三:八〇一−二)参照。
(5)池宮(一九九〇)、島村(二〇二三)参照。「チョンダラー」という呼び名について、方言学者の宮良當壯(一九八〇[初版一九二五]:十二)は「京太郎」が転訛したものと解釈し、それが通説となっている。だが、この集団が仏教にかかわることや、彼らの職能の特徴と社会における周辺性を考慮すると、チョンダラーという呼称は仏教経典に登場する
(6)以下に引用した大城勲さんと湧上洋さんの語りは、二〇二四年十月十九日に南城市玉城前川で行った聞き取りに基づいている。
(7)佐喜眞(一九二五:五六−七)参照。引用にあたり、原文の旧字体・旧仮名遣いは新字体・新仮名遣いに改めている。
(8)ブータ祭祀とカンブラ儀礼については、石井(二〇一七、二〇二二)参照。
(9)宮良(一九八〇:一二三)参照。
参照文献
池宮正治 一九九〇『沖縄の遊行芸――チョンダラーとニンブチャー』ひるぎ社。
石井美保 二〇一七『環世界の人類学――南インドにおける野生・近代・神霊祭祀』京都大学学術出版会。
―― 二〇二二『たまふりの人類学』青土社。
佐喜眞興英 一九二五『シマの話』郷土研究社。
島尻勝太郎 一九八三「ニンブチャー〔念仏者〕」沖繩大百科事典刊行事務局編『沖繩大百科事典 下』、一四二頁、沖縄タイムス社。
島村恭則 二〇二三「迷宮都市・那覇を歩く 第20回 ジュリ馬とチョンダラー」『太陽WEB』(二〇二五年九月十四日閲覧)
玉城村前川誌編集委員会 一九八六『玉城村 前川誌』玉城村前川誌編集委員会。
知名定寛 二〇〇八『琉球仏教史の研究』榕樹書林。
―― 二〇二一『琉球弧叢書35 琉球沖縄仏教史』榕樹書林。
当間一郎 一九八三「京太郎 チョンダラー」沖繩大百科事典刊行事務局編『沖繩大百科事典 中』八〇一−二頁、沖縄タイムス社。
那覇市歴史博物館 二〇二五「行脚村跡(アンニャムラアト)」(二〇二五年九月十四日閲覧)
日本史広辞典編集委員会 二〇一六「旃陀羅 せんだら」『山川 日本史小辞典 改訂新版』山川出版社。(二〇二五年九月十四日閲覧)
船越誌編集委員会 二〇〇二『玉城村 船越誌』玉城村船越公民館。
宮良當壯 一九八〇『沖縄の人形芝居 芸能・文学論考 琉球文学資料篇(宮良當壯全集十二)』第一書房。
山崎元一 二〇〇七「チャンダーラ Caṇḍāla」『改訂新版 世界大百科事典』平凡社。(二〇二五年九月十四日閲覧)


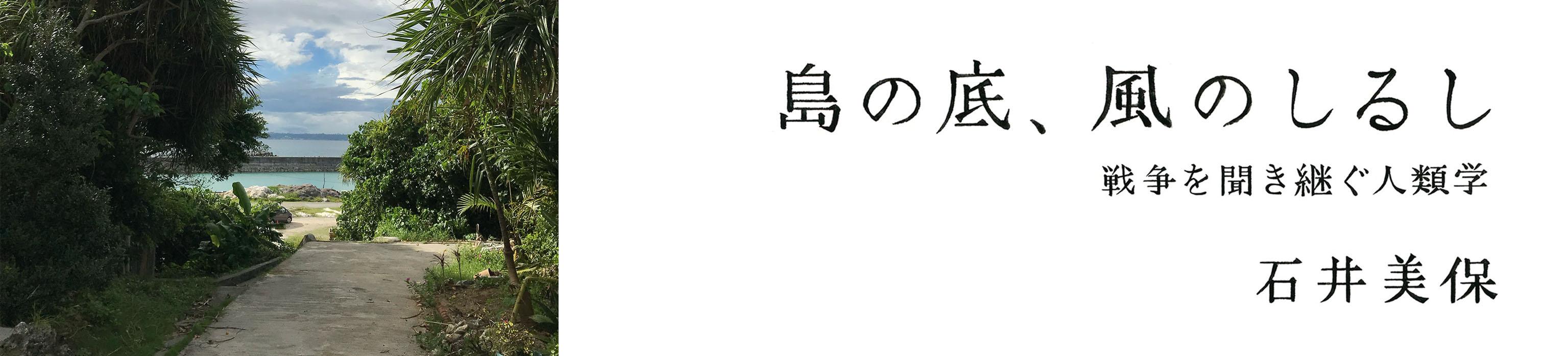



-thumb-800xauto-15803.jpg)


