第8回
西の果て、黄泉の国(1)
2025.09.18更新
前川集落の南西の端、県道と畑地の境には
石碑を建てるほどに大切なものだった龕は、でも、この辺りのすべての集落にあったわけではない。たとえば船越には龕がなく、葬式のたびに近隣の前川や大城の集落から借りていたという。
それは結構、不便なことではないのか。そう思うけれど、ある集落が龕をもつか、もたないかということは、そうした利便性
一九三四年生まれの泉スミ子さんは、小柄で溌剌とした女性だ。彼女は船越のしきたりを
龕をもつ前川と、もたない船越の違いについて、彼女はこんな風に説明してくれた。
船越の場合はカミバンだから、神様。前川はグソーバンですよ、龕があるから。船越は獅子、
獅 子 頭 の人が入って、踊りをする獅子頭(1)。
〔船越で獅子舞をやっていたのは〕あれは何世紀かね。
世 立て始まりだはずよ、獅子さんがいたのは。〔...〕
この獅子のあるところは、十五夜にはこの獅子舞しないと、ちょうどいま、綱引かんと五穀豊穣〔が叶わず〕、畦払い しないと虫が発生〔するように〕、魔除けであるわけさ。[...]十五夜は、お月さまに感謝するさ。で、この踊りして、回すわけ、踊りさせるわけよ、この獅子を(2)。
綱引きも畦払いも、この地域の集落の伝統的な年中行事だ。なかでも稲作が盛んだった船越では、五穀豊穣を祈願する農耕儀礼として、綱引きが重要な意味をもっていた。いまも続けられている綱引きでは、その年に収穫された稲藁で作った
――そんな大事な獅子舞なのに、なんでなくなったんですか。禁止されたとか?
スミ子さん これはまた、事情があるせ。あの......糸数の龕、霊柩車とこの
獅子 加 那 志 や、魔除けだのに、みんなお金が困るから、換えてしまって、祟りが出たわけよ、この集落 に。――獅子を売っちゃったんですか。
スミ子さん いえ、龕と交換。
あるとき船越の人びとは、その獅子頭を隣の糸数集落にあった龕と交換し、
集落にとっての宝物であったはずの獅子頭を、なぜ、よその龕と交換することになったのか。スミ子さんによれば、それは当時の船越の長たちが、龕を隣近所の集落に貸すことで得られる賃料に目をつけて、龕の保有によるムラの収入増を目論んだからだ。だが、そうやってせっかく手に入れた龕も、やがてこの島を襲った台風の大水で流され、消失してしまったという。
スミ子さんの語ってくれたような、「獅子頭と龕の交換」というエピソードは、じつはあちこちの集落に残されていて、その経緯や真偽のほどははっきりしない。スミ子さんの話の中で「グソーバン」とされる前川も、もとは獅子頭をもっていたが、明治の中頃に糸数集落の龕と交換したともいわれている(4)。遠い昔にあったという船越と糸数の間の交換と、明治期における前川と糸数の間の交換。それに、他にもあったかもしれないムラ同士の何度かの交換を経て、それぞれの龕や獅子頭がどこからどこへ受け渡され、どんな運命を辿ったのかは謎のままだ。
これらの伝承において重要なのは、たぶん、史実としてどうだったのかということよりも、かつて集落同士の間で、龕と獅子頭が「交換されていた」ということの方なのだろう。
つまり、まずもってこの地域の集落は、カミバンとグソーバンという役割分担と、それに伴う龕の貸し借りによって互いに関係づけられていた。けれども、その役割分担は不変のものではなく、獅子頭と龕を交換することで
神々の世界と先祖の世界。そうした異界的で、超越的なものとのかかわりにおいて定められる集落の役割と立ち位置や、よその集落との関係性を、それを象徴するものを交換することで――あるいは、過去に交換があったのだと語ることで――入れ替え、創り変え、操作しようとする、それは先人たちの知恵だったのかもしれない。
糸数との交換ののち、早々に龕を失ったとされる船越に対して、前川では龕を受けとったとされる明治の中期から、昭和の戦争による焼失と戦後の再建を経て、この地域に火葬が普及して葬送の習俗が変化するまでの長い間、龕が保有され、活用されてきた。
興味深いことに、これらの古墓の主だったのは、カーヤマに一番近い場所にあり、前川の本部落とされる仲地原の住民たちではなく、隣の字である船越や、前川の
ともあれ、こんな風に仲地原の西の果てを歩いてみると、なぜほかでもなくこの場所に龕屋が建てられたのか、その所以がわかるような気がする。バンクにハカチモーに龕屋、そして墓所でもある崖。集落の西側のラインに沿って、どことはなしにあの世的な、異界につながる場所が配置されているようだ。
人がこの世からあの世へと旅立つとき、龕はその乗りものになる。他方で獅子頭は、人びとが神に捧げる舞を舞うとき、みずから獅子に変身し、神々の世界に近づくための乗りものになる。
龕も獅子頭も、そんな風にこの世と異界の間をつなぎ、こちら側からあちら側へと人を運ぶ媒体である。異界への旅はとても危険なものだから、それを媒介する乗りもの自体が畏れられ、常とは異なる力をもつものとして祀られていても不思議ではない。
危険な旅をつつがなく行うためには、慎重に手順を踏み、乗りものを軌道にのせ、異界に由来する力をいなしつつ、それと交流せねばならない。神事にも、葬儀にも、そのための独特な手順があり、知識が要り、手段がある。そのひとつが、
(1)この泉スミ子さんの語りは、二〇二四年三月八日、湧上洋さん、堀川輝之さんとともに南城市玉城船越で行った聞き取りに基づいている。
(2)このスミ子さんの語りは、二〇二五年七月十七日、湧上洋さん、堀川輝之さんとともに南城市玉城船越で行った聞き取りに基づいている。
(3)船越における綱引きと畦払いについては、船越誌編集委員会(二〇〇二:三〇一、三〇六)参照。
(4)前川と糸数の間の獅子頭と龕の交換については、玉城村前川誌編集委員会(一九八六:三四三)、糸数字誌編集委員会(二〇一二:二八九)参照。
(5)屋取集落とは、十八世紀初頭以降、生活に困窮して首里から農村地域に移住した元士族らが寄り集まって形成した集落を指す。とりわけ一八七九年の廃藩置県(琉球処分)以降、凋落した士族らの移住によって多くの屋取集落が形成された。田里(一九六八、一九八三:七三〇)、琉球新報社(二〇〇三)参照。石川屋取は一八七〇年、首里王府の命によって
参照文献
糸数字誌編集委員会 二〇一二『糸数字誌』糸数公民館。
田里友哲 一九六八「沖縄における屋取集落の研究と課題」『歴史地理学紀要』十号、七九−九五頁。
―― 一九八三「屋取集落」沖縄大百科事典刊行事務局編『沖縄大百科事典 下』、沖縄タイムス社、七三〇頁。
玉城村前川誌編集委員会 一九八六『玉城村 前川誌』玉城村前川誌編集委員会。
船越誌編集委員会 二〇〇二『玉城村 船越誌』玉城村船越公民館。
琉球新報社 二〇〇三「屋取(やーどぅい)」『最新版 沖縄コンパクト事典』琉球新報社(二〇二五年八月三十一日閲覧)。


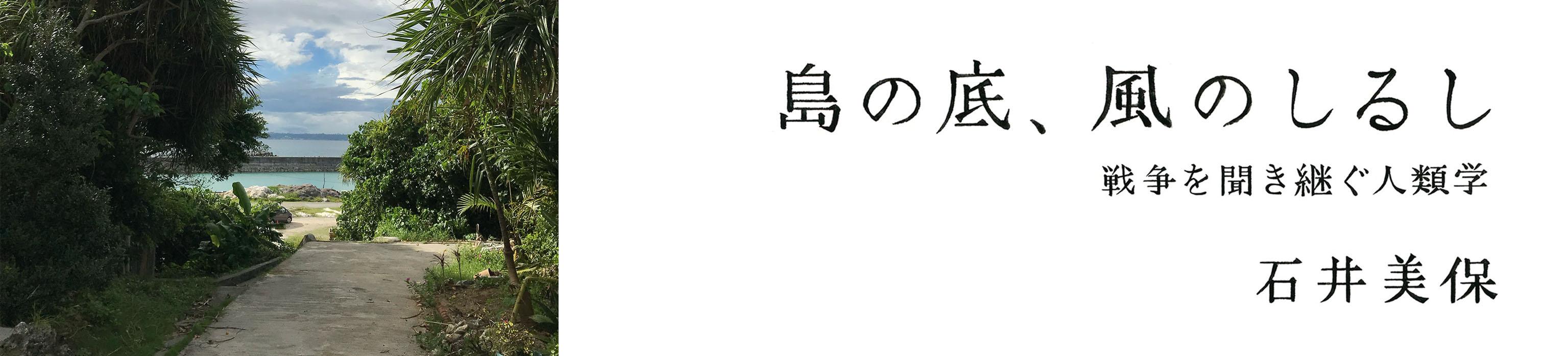



-thumb-800xauto-15803.jpg)


