第7回
砂糖小屋のリズム(2)
2025.08.20更新
船越と前川の集落を結ぶ道路沿いには、サトウキビ畑が広がっている。保水力の高い
一九三〇年代の半ばに前川で生まれた大城勲さんの子ども時代、サトウキビはありふれた、けれども大切な作物だった(2)。
勲さん 〔子どもの頃は〕朝起きて〔...〕隣近所の子どもたちと遊んだりして、妹も何名かいたから、弟も。最後の妹は〔自分が〕子守をさせられて。何歳くらいだったかな......。親たちは、農家だから畑へ行って。で、十時頃になったらおんぶしている赤ん坊を、〔母親の〕おっぱい飲ませに畑まで行きよった。そういうことも憶えてますね。〔...〕
沖縄というところはキビが主体で、十二月になったらキビの収穫、黒砂糖の製糖期が来て。うちの村には三機の砂糖工場があって、発動機でした。その昔は馬グルマといって、馬が引っ張って(3)。〔...〕もう、効率の悪い仕事だったようですが、私たちが子どもの時から発動機になって。もう十二月頃から、村では発動機の音がポンポンポンポンして、村がとっても活気づいて。
勲さんの言うように、戦前の前川には
その頃、
勲さん 製糖工場というところは、たくさんの人が集まって砂糖を圧搾機で絞って、サトウキビを炊いて砂糖にするから。そして、炊いて黒砂糖ができるまでには、大きな鍋があって。沖縄ではシンメーナービといっていますが。
――シンメー鍋?
湧上さん
四枚鍋 という。五枚鍋 とかですね、大型鍋。勲さん それに炊かれたお砂糖を、柄杓で汲んで入れてかき混ぜて、冷ましたらもうこれ、固くなって砂糖になるんですよ。それが柔らかい時に、鍋の縁についている薄いのがあって、それをヘラでこう剝いで、子どもたちはこれを伸ばして(笑)。ああいうような、砂糖。〔...〕だけど、〔子どもは〕頻繁には入れないですよ、危ないから。
――たまーに入れてもらえるんですか。
勲さん 親戚とか、自分のおうちの砂糖を炊く時は自分のものだから入れるが、それでも来るなと親たちは言う。だけども〔製糖場に〕行って、ムチャー剝いでね、食べた。
湧上さん 前川の場合はですね、発動機を使う製糖場が一番早いんですよ。船越の場合は、一箇所、二箇所ぐらいしかなかったですね。〔...〕それ以外は馬グルマですから。馬グルマというのは、大量には〔砂糖を〕作れないわけですよ。だから、〔製糖場に〕来ても少ないもんですからね。よく鍋のそばについている、ムチャーというんですが、あれを剝いでね。
学校から帰ってから、〔馬グルマの〕馬追いを手伝って、その手伝いのたびに、親たちが剝いであげよったんですね。
鍋の側面にくっついた黒砂糖の甘い滓を楽しみに、曳き木につながれた馬を真面目な面持ちで追っている少年の日の湧上さんと、発動機の騒音と蒸気、大人たちの活気に満ちた製糖場の入り口で、妹の手をひいて中の様子を窺っている勲少年の姿が目に浮かぶ。
勲さん 馬追いは、子どもがしよったさーね。
湧上さん 前川は、そういうのは少なかったです。発動機になっているもんですから。
――それはディーゼルですか。ディーゼルエンジン?
湧上さん そうです。ヤンマーディーゼル、それでやってたよね。
勲さん あの、ブーッと音がする、昔の。
湧上さん ポンポン、ポンポン。
勲さん ポンポン
船 といって、昔はありました。焼玉エンジンで、ポンポンポンポンポンポンと音がするんですよ、発動機でも。その音が聞こえたら、ああ、もう動いているなと。朝、もう暗い時から、一時、二時からもう発動機は回転して、サトウキビを圧搾しているんですよ。
そんな風に前川では、リズミカルな発動機の音が冬の風物詩だったのに対して、機械化の進んでいなかった頃の船越では、馬グルマを曳く馬の蹄の音とともに、作業にあたっている若い男女の歌う
いずれにしても、サトウキビ農家が自分たちの手で製糖まで行うという当時の黒糖生産のしくみの中で、集落の世帯同士がつくる組合は大きな役割を担っていた。
――機械を使うにも、順番があるんですか。「うちから使う」とか。
勲さん ありますよ。あれは、番組が組まれて。〔...〕生産の多い農家の人たちは、月に三回当たる人もいるし、生産高の少ない人は月に一回とか。
――その順番は誰が決めてたんでしょうか。
勲さん それは委員といって、その人たちがみんな、〔各世帯に〕いくらサトウキビがあるということを出して、それで番組を作るんですよ。いまでもそれはやりますよ。
――その発動機の維持にかかるお金は、みんなが均等に出すんですか。それかやっぱり、よく使う人が多く?
勲さん 生産量の多い人は多く出す。維持費、管理費は、多いほど多いように......。
湧上さん 負担するんです。
勲さん 三つの組合があって〔...〕そこでいろんなやりくりしたり、家〔砂糖小屋〕の修理をしたり、釜の修理をしたり。やっぱり鍋がまた穴開いたりして、そういった修理も、製糖期前に全部するんです。製糖期が始まってから壊れたら、もう大変なことになるから(笑)。
湧上さん サーター組っていうんですね。釜や発動機、
砂糖小屋 を利用する人たちということで。〔...〕――できた砂糖は那覇に売りに行かれてたんですか。
勲さん ううん、それはまた那覇に、砂糖を売る中間的な商売をしている人がいて。〔...〕その人たちが買い集めて、値上がりするのを待ったりして。〔...〕
ほんで、お金もそこから前借りもさせよったんでしょう、戦前は。現金収入がないから、キビの〔時期が〕終わって、しばらくしたら現金が途絶え。その頃、砂糖委託会社と言っていました。その砂糖委託会社から前借りして、砂糖を納めて借りたお金を払うというような、そういうことだったみたいですね。うちの親の時代は。
勲さんと湧上さんの語りから断片的に浮かび上がってくるのは、一九三〇年代から四〇年代の初頭にかけての、沖縄における黒糖の生産をめぐる状況とその変遷だ。
前川に初めて発動機が導入されたのは一九三〇年のことだけれど、それは沖縄県において、発動機を使った改良式製糖場が増えはじめた時期にあたる(5)。この増加を後押ししたのは、一九三三年から実施された沖縄県振興十五カ年計画だった。一九一九年に一時高騰した砂糖の市価は翌年には暴落し、サトウキビ栽培を基幹産業としていた沖縄の経済は、その後十数年間にわたって「ソテツ地獄」と呼ばれる大不況に陥った。沖縄県振興計画は、この不況を打破するために策定された事業だったが、その要とされたのが製糖業の振興だった(6)。
さらに一九三七年に日中戦争が始まると、食料の増産を図る戦時統制経済の本格化に伴って、この振興事業における糖業費の割合が急増する(7)。一九四一年の一月には農林省によって黒糖集荷統制規則が施行され、それまで糖商や委託業者を介して流通していた黒糖は、沖縄県産業組合連合会に一括して集荷され、その流通が一元的に管理されることになった(8)。
こうした黒糖の流通の統制は、その生産を担ってきた個々の農家に国策への対応と従属を迫るものだったが、それは同時に、さまざまな経路で砂糖の売買を行ってきた委託業者や糖商の活動に打撃を与えるものでもあった。勲さんの語りにあるように、それまでは委託業者が砂糖を買い付けるだけでなく、生産物をカタに農家に金を貸し付ける、いわゆる「砂糖前貸し」が横行していたが、そうした慣行も徐々に廃れていったに違いない(9)。
こうしてみると、戦前の前川と船越ののどかな風景は、すでに着実に、戦時体制に向かっていく国家の政策の中に組み込まれていたことがわかる。湧上さんや勲さんの父母の世代にあたる人びとは、そうした時代の趨勢の中で畑を耕し、サトウキビを育て、仲買人と交渉し、組合を作って機械化に対応しつつ、自分たちの手で黒糖を製造していたのである。
けれども、一九四五年の春以降にこの地域を襲った戦火によって、そうした彼らの日々の努力と営みは――砂糖小屋も、サトウキビも、新式の機械も、馬たちも――すべてが灰燼に帰すことになる。
でもそれは、まだ少し先のことだ。
あの頃、戦争が始まる前に少年たちの目に映っていたのは、森も畑も作物も、馬も機械もよく手入れされ、日ごと繰り返されるリズムの中に調和した、親しみぶかい世界だった。
(1)船越と前川の製糖業について、詳しくは船越誌編集委員会(二〇〇二:一七六−一八三)、玉城村前川誌編集委員会(一九八六:一五六−一五九)参照。
(2)以下に抜粋した大城勲さんと湧上洋さんの語りは、二〇二四年十月十九日、前川にて行った聞き取りに基づいている。
(3)『玉城村 船越誌』によれば、馬グルマを使った砂糖小屋にはサトウキビを絞るための
(4)船越誌編集委員会(二〇〇二:一八一)参照。
(5)久保(二〇一九:七七、八一)参照。
(6)沖縄県教育庁文化財課史料編集班(二〇一七:一四−一五)、沖縄県教育委員会・琉球王国交流史・近代沖縄史料デジタルアーカイブ参照(二〇二五年八月十二日閲覧)。一九一四年から一九二〇年にかけての砂糖価格の変動については、大澤(二〇一七:四八)参照。
(7)川平(一九九六:二八九−二九四、一九九八:八〇)参照。
(8)渋谷(二〇〇八:九)、川平(一九九八:八二−八三)参照。
(9)砂糖前貸しについて、詳しくは渋谷(二〇〇八:九)、金岡(二〇二一:一七四−一七七)参照。
参照文献
大澤篤 二〇一七「第一次大戦期日本における砂糖産業の展開――台南製糖の事例にそくして」『経済研究』(明治学院大学)第一五四号、四五−六六頁。
沖縄県教育庁文化財課史料編集班 二〇一七『沖縄県史 各論編6 沖縄戦』沖縄県教育委員会。
金岡克文 二〇二一「明治・大正期の沖縄庶民金融の検討」『高岡法科大学紀要』三二号、一六五−一八九頁。
川平成雄 一九九六「戦時統制経済下における沖縄経済の変容――日中戦争期を中心に」『琉球大学経済研究』第五二号、二八七−三一二頁。
―― 一九九八「戦時統制下の沖縄糖業」『琉球大学経済研究』第五六号、七七−九一頁。
久保文克 二〇一九「黒糖から見た戦前沖縄糖業――沖縄糖業の概観と八重山糖業の黎明期」『商学論纂』(中央大学)第六一巻第一・二号、七三−一一七頁。
渋谷義夫 二〇〇八「近代沖縄における糖商資本による黒糖流通支配について」『農業史研究』第四二号、三−一三頁。
玉城村前川誌編集委員会 一九八六『玉城村 前川誌』玉城村前川誌編集委員会。
船越誌編集委員会 二〇〇二『玉城村 船越誌』玉城村船越公民館。


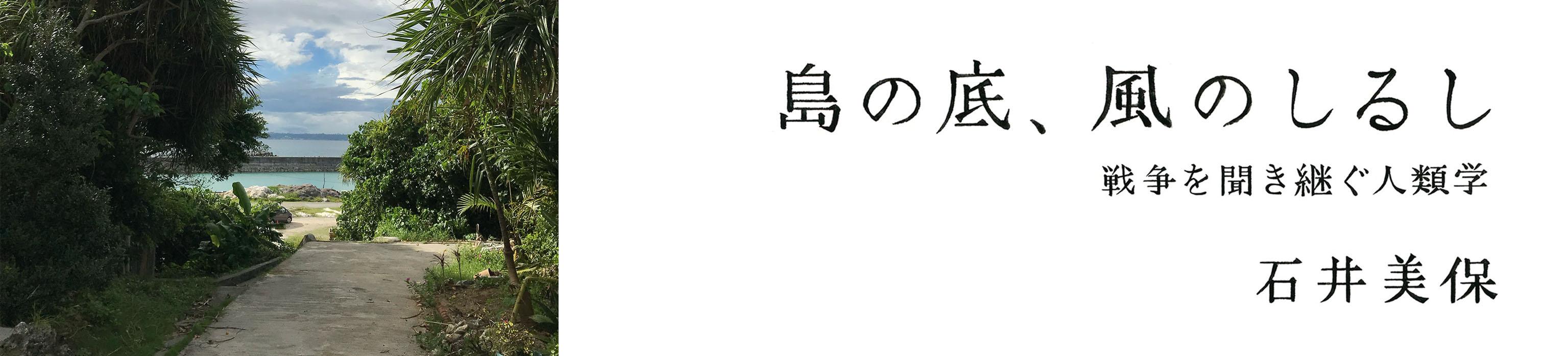



-thumb-800xauto-15803.jpg)


